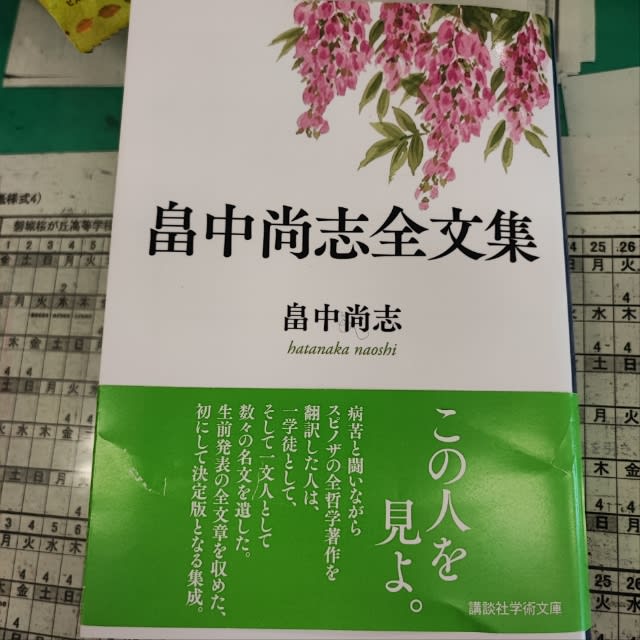2022年8月28日(日)、フォーラム福島で、
映画『さとにきたらええやん』を観てきた。
大阪の西成地区釜ヶ崎で40年ほど続く「こどもの里」が舞台のドキュメンタリー(2h弱)だったが、グイグイ引き込まれた。
西成の釜ヶ崎といえば日雇い労働者の町、そして正直「怖い街」という漠然とした印象しかなかった。
そして、その場所で40年も子どもたちの生を支え続けてきた子ども園「こどもの里」のドキュメンタリーといえば、ついついいわゆる「社会派」の立ち位置を想像してしまう。
そして映画はもちろん、なんか、そういう話じゃない。まったくそういう撮られ方はしていない。そこにまず驚いた。
勝手に想像しておいて、勝手にズレに驚くレトリックも大概だと自分でも思うが、この映画は、そういう観る者をまっすぐ覗き込む瞳に満ちているのだった。
上映に引き続き開催されたトークショーもすごかった。
「こどもの里」を設立前から営んできた代表の荘保共子さん、
西成で研究を続けている哲学者村上靖彦さん、
北海道大学アイヌ・先住民センター准教授の石原真衣さん、
の3人という超豪華メンバー。
いや、至福でした。
まず瞳の話だ。
荘保さんが会場のの質問に答えて、
子どもたちの生き生きとした瞳こそこの営みを始めそして続けた理由だ
と言っていたことに関わる。
もちろん、西成の大人たちは生活に様々な困難をかかえている。そこでせいかつする子どもたちは当然、その、親の困難の中で生きることを余儀なくされている。
その、西成の子どもたちの瞳がめっちゃ魅力的だ、輝いている、それが荘保さんをして、この営みにダイブさせた原因だ、というのだ。
その言葉を聴きながら映画を振り返りつつ、私はまた泣きそうになった。
映画の内容自体は、検索してもらえば分かる。
まず今ここではあくまで個人的な感想を書いておきたい。
その瞳を、私も見たことがある、と思った。
大学四年の頃、小学校教師の免許取得のために、6週間の教育実習に行ったことがある。
動き続けて止まない小動物の群のような子どもたちのカオス、その中で本当に輝く瞳たち、それらに出会って、私は小学校教師を断念したのだ。
私はその単純明晰で動きに満ちた、クルクルとめまぐるしく輝きながら動き続けるその瞳の力に圧倒された。
とても太刀打ちできない、と思った。
自分がそんな子どもの一人にすぎないというのに、どうやって彼らを「教育」し「導く」ことができるのか。
オレにできるはずがない、と思った。
それで私は、小学校から逃避し、高校へと逃避したわけだ。
教育学部に入った当初は、その瞳の輝きをこそ、求めていたのかもしれないというのに。
ちょうど22才、荘保さんは私より10才ほど上だが、同じ年齢で私は逃亡し、荘保さんはそこにダイブしていったことになる。
40年高校の国語教師をやってきても、逃避癖は治らなかった、いや直らなかった、か。
水平軸が苦手なんだと思う。
自分の中の「GPS」のようなものを使って、なんとか平面上に世界をプロットしようとつとめてはいても、所詮、社会のポリフォニックな響きの中に身をゆだねることはできなかった。
だからスピノザが好きなのかもしれない。
そんな自分にとって「こどもの里」は衝撃であり、いーなーと思った。
岡惚れするというのではない。
もしかすると身近にあるのかも、と思えた。
自分が探し続け、逃避し続けたことがここにある、そんな思いを抱いた。
映画を見ながらいっぱい泣いた。そして、トークを聴いて深くうなずいた。
今週から、どんな授業をしようか。
中身についてはまた後で書ければいいのだが。