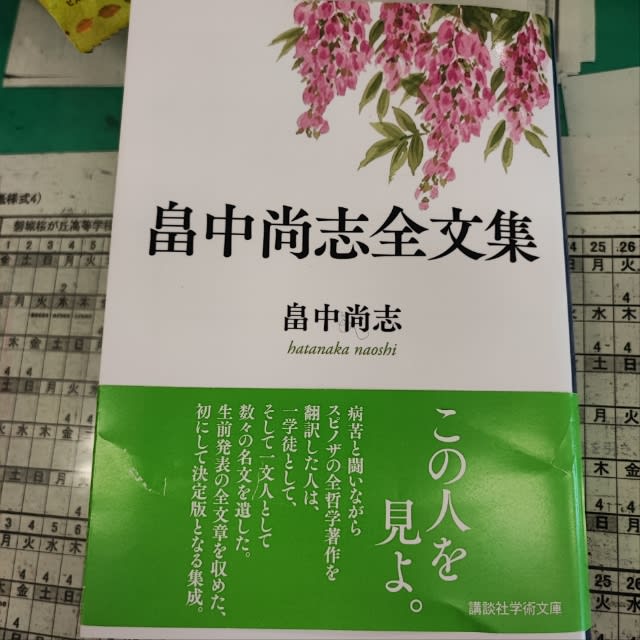いわきFC×藤枝MYFC、開幕戦に行ってきました。
改修されたいわき市湯本のグリーンスタジアム。
駅から20分はそんなものでしょうけれど、何もない、そして最後の急な坂はけっこうツラいです(笑)。
途中にお店とかあるとほっとするんだけどなー。
それから、駐車場の絶対量が足りないきもします。
(後日、2/26に水戸のケーズデンキスタジアムにアウェーの応援に行ったのですが、広大な駐車場があってとてもうれしかったです)
去年の試合(今治?)以来だから、久しぶり。席数も増え、大型スクリーンも出来、夜間の照明も整って、いよいよプロの匂いが濃くなってきます。いわき市のサポート、ありがたいです。
正直、J3の時は、アマチュア用か練習用の場所という感じが拭えませんでした。Jビレッジも、21世紀の森のここもプロの試合を見に行くぞ的なスタジアムという感じは希薄。今年は大画面のスクリーンを見ているだけでも、気分は高まってきます。
いわき市長&市議会のみなさん、ありがとうございます!
この集客を生かすには、サッカー開催に合わせたイベントとか、お店とか、無料駐車場を生かした商店群とか、いろいろ進めていってほしいです。
ただ、ほかのスタジアムはまだ沼津しか見たことがないのでなんともいえませんが、これからJ2(できればJ1)の試合を戦っていく上では、さらなる改修(もしくは新築?)が必要になるのだろうな、という印象。
さて、試合の話です。
正直、対戦が組まれた時に、J2初戦が藤枝MYFCというのは、ちょっと残念な気がしました。
せっかくだったら昇格組同士でやるのではなく、それぞれJ2組(J1からの降格組でも!)とやれればいいのに、と。
だって、いわきは藤枝に直近の試合3-0で勝ってますからね。
でも、いざ試合が始まってみると、元来攻撃的という意味ではいわきも藤枝もJ3トップクラスのチームなわけで、藤枝はガンガン攻めてきます。
ところが、です!
対するいわきは立ち上がりから自分たちのサッカーができていません。
中盤でボールを握ったら素早く突破して、CBの上がりを含めて前への推進力で圧倒してゴール……という昨年後半の戦闘的な戦いは影を潜めてしまいました。
有田、嵯峨も突破するまえにきちんとマークされ、中盤でも数を優位に保てず、山下のところでも球が収まらず、強い向かい風もあってか、多く自陣ちかくでもみ合ったあと、両サイド深く切り込まれる、という展開が続きました。セカンドボールもなかなか回収できません。
あのパワフルで戦闘的ないわきはどこへいった?
と思っているうちに、サイド深くゴール近くに入り込んだところからおもしろいように点を決められ、あっと言う間に3-0にされてしまいます。
3点はいくらなんでも取られすぎだろう、と思いますが、攻撃的なチームに押し込まれるとこうなるという見本のようなものでしょうか。藤枝もそうですが、考えてみれば、いわきが大勝するときもこんな感じ(後半得点が多かったけれど)、スタイルは異なれど相手を圧倒する攻撃力の前には、こうなってしまうという見本のような状況でした。
どうした、いわき?
GK、左側の二人、右側と、4人の新人がスターティングラインアップに加わりましたが、去年の中盤でボールを奪ったら、みんなでゴールに走り出し速度ある攻撃で加点していく(そこには両サイドバックの素早いオーバーラップも!)感じは、ここからはまったく感じられませんでした。
サッカー変わったの?
とすら感じてしまいます。
J3からファンクラブ会員になって、初めての1試合3失点。どういう気持ちになればいいのか戸惑いすらありました。
しかし、このままでは終わりませんでした(よかった)。
後半、
鏑木→永井
石田→宮崎
有田→近藤
と左側を変え、
右も
加藤→江川
ときちんと交代を仕掛けていきます。
こういうのって、応援する側にとってもフィールドの選手にとっても「切り替え」のサインとして重要だなあ、とスタジアムで直にみていると強く感じます。
このままでは終わらないよ、っていう監督の意思表示を感じました。
個人的には日高のいなくなった左側をどのようにしていくかは試行錯誤中なのかな、と思っています(素人の印象にすぎませんが)。
初戦前半で3-0になり、交代させられるというのは、新しい人にとってはちょっと残念な展開かもしれませんが、ぜひ次回は悔しさをバネに、より戦闘的に戦ってほしいです。
鏑木、加藤、石田各選手、応援してます!
後半になるとギアが上がり、相手陣内でサッカーをする時間帯が増えていきます。これは、次戦の水戸相手にも感じたことですが、後半になると速度で相手に勝てるシーンが増えてくる印象があります。あきらめない、パワーを出し続けるいわきのサッカーの鼓動は感じるといったところでしょうか。スタミナでは負けませんね!
3点を跳ね返すのはさすがに厳しかったですが、
「開幕戦、去年勝ってた相手にこのまま終わったらどうすんだい?!」
という危惧は払拭されました。
有田→近藤
の交代も効いていたかな?
素人の私見では、山下、有田、嵯峨のあたりには、藤枝の選手も意識して数で迫っていた印象があります。
近藤選手は、有田選手とはタイプが違いますが、ゴール前である種の体の強さを持った選手という印象を持ちました。この試合ではこの交代が効果あり、だったと思います。
ただ、友人とも話をしたのですが、4-4-2の2のフォワードのところ、有田は鉄板だとして、もう一人を谷村でいくのか?近藤なのか?(近藤選手は前に素早く動くタイプではない?)
ここは2列目の鈴木、岩淵とは違った整理が必要なのかもしれません。
(ディフェンス側は家泉、遠藤を中心にそう大きく変わらないとしても)
嵯峨は、マークされていても相変わらずの活躍をしてくれています。ただ、嵯峨はマークされるとかされないじゃなくて、素早く後ろからあがっていくあの感じが欲しいですよねえ。これは右側だけの問題ではなく、反対側のサイドをどう動かすかということも関わってくるのでしょうか?
左側のやり方が見えてくると、どう応援したらいいのか、もわかってくると思います。しばらくは待ちながら応援のツボを探すことになりそうですかね。
「中盤真ん中を固めて両サイドに圧縮し、人数かけて取ったら全員ダッシュ!」
これ、続けてほしいなあ、と友人とも話しをしています。
素人ファンではあっても、もいろいろ考えながら「点が入ればよい」というだけではない応援をしていきたいですね。
「午前中は働き、午後は釣りをして、夕方は酒を飲みながら批評家になる」
マルクスも言ってるそうですし、のが理想だって(本当かい?<笑>)。
自分の知っている教養の範囲でも、
文字がなくてもお店の小僧たちが歌舞伎のディープな魅力に心を奪われる話は落語の「七段目」でしたっけ?
ありましたよね。
サッカーなんて全然したことがない輩でも、批評家にはなれる。むしろそういう好きな対象に対する愛を批評で示せるようになればいいなあ。
サッカー道は奥が深いから、当分は無理ですけれど。10年ぐらいかかるかな?