
この本は言わずと知れた超B級映画と名高い『ブレードランナー』の原作本。
私は、学生時代に映画化される以前に読んでいて、映画を見たときは「ずいぶん内容が変わっちゃったなぁ~」と思ったものです。
それでも、『ブレードランナー』は好きな映画のひとつですが。
レイチェルは美しかった。。。
そういえば、ギブスンはこの映画の街の外観を見て映画館を飛び出したとか。
心中お察しします。
そんなことはどうでもよいですね。
初めて読んだのは、もう、ウン十年も遠い彼方。
この本の記憶といいますと、レイチェルが山羊を屋上から突き落とすシーンと
砂漠のヒキガエルのシーン。
レイチェルもカエルも本物ではありませんね。
そうか、このころから、人間よりも人工生命体のほうに感情移入していたわけか。
で、再読してみた。
なんだろうね、この胸苦しい感じは。
大戦後ということで、死の灰やらなにやら閉塞的な空気だけれど、死に取り囲まれているというより、ゴミに囲まれていて、生きていないもの、使われていないものはゴミになる、そんな感じ。
小説中では、それらをキップルと呼んでいて、ちょっとでも目を離していれば、
どんどんキップル化が進んでいく。
地球も、移住できる人間は宇宙に出て行き、それができない人間は取り残され、
やがてキップル化するに違いない。
これは再生不可能という意味だろう。
ゴミ再生リサイクル法もなければ、生命のサイクルもない。
胸苦しさの原因はその迫りくる塵芥にもあるけれど、
それ以上に感じる境界線のあいまいさにあるような気がします。
この物語は、たくさんの二項対立がみられますね。
人間とアンドロイド
アンドロイドとスペシャル
スペシャルとレギュラー
他の惑星に移民していく人と地球に残る人
アンドロイドを作る人と狩る人
動物と模造動物
共感ボックスと感情移入度テスト
まだまだあるでしょう。
有機人工生命体であるアンドロイドは、外見では人間と区別がつかないけれど、感情移入ということが苦手で、情動的に欠陥がある。
8本あるくもの足を、4本でも歩けるかと嬉々として切ってみたり。
ちょっと考えれば、情動的に欠落のある人なんて、大勢いることに気がつきますね。
感情移入度検査法、すなわちフォークト・ガンプラテストを受けたら、アンドロイドと判断される人が少なからずいるだろうことは想像に難くありません。
また、情調オルガンや共感ボックスに不健康さや、嫌悪感を感じます。
共感ボックスは、マーサーを介し、マーサーの痛みや苦しみを通して、共感ボックスと接触している人すべてと融合を果たすという代物。
共感ボックスで得られる共感と感情移入との差はどこにあるのか。
それは、気づかずに行うことと自ら共感を得ようとする行為にあるのか。
う~ん、よくわからん。(もっと考える余地あり)
ところで、マーサーは、さまよえるユダヤ人のようですね。
死に向かっていつまでも歩き続ける。
主人公のリックは自分をマーサー自身だと言います。
先日読んだ『キリスト教文学を学ぶ人のために』という本の中に、
さまよえるユダヤ人に関する記述がありました。
「裏切る相手が神でなくとも、友や仲間、親、祖国を裏切って罪意識に苦しみさまよう罪人が私たちの本質的な姿かもしれない」
リックはアンドロイドを処分したことを殺したと感じます。
アンドロイドに人間性を認め、人間の中にアンドロイド性を認めます。
デッィクが描きたかったのは、人間そのものだったのではないでしょうか。
アンドロイドは電気羊の夢を見るか?
キリスト教文学を学ぶ人のために

いつの間にか投稿記事数が増えていました。
この記事もブログルポに参加させてみよう。
というわけで、評価してくださる方はポチッとお願いします。
この記事を評価する
ブログルポに関して、詳しくお知りになりたい方は、バナーをクリックしてみてね。
私は、学生時代に映画化される以前に読んでいて、映画を見たときは「ずいぶん内容が変わっちゃったなぁ~」と思ったものです。
それでも、『ブレードランナー』は好きな映画のひとつですが。
レイチェルは美しかった。。。
そういえば、ギブスンはこの映画の街の外観を見て映画館を飛び出したとか。
心中お察しします。
そんなことはどうでもよいですね。
初めて読んだのは、もう、ウン十年も遠い彼方。
この本の記憶といいますと、レイチェルが山羊を屋上から突き落とすシーンと
砂漠のヒキガエルのシーン。
レイチェルもカエルも本物ではありませんね。
そうか、このころから、人間よりも人工生命体のほうに感情移入していたわけか。
で、再読してみた。
なんだろうね、この胸苦しい感じは。
大戦後ということで、死の灰やらなにやら閉塞的な空気だけれど、死に取り囲まれているというより、ゴミに囲まれていて、生きていないもの、使われていないものはゴミになる、そんな感じ。
小説中では、それらをキップルと呼んでいて、ちょっとでも目を離していれば、
どんどんキップル化が進んでいく。
地球も、移住できる人間は宇宙に出て行き、それができない人間は取り残され、
やがてキップル化するに違いない。
これは再生不可能という意味だろう。
ゴミ再生リサイクル法もなければ、生命のサイクルもない。
胸苦しさの原因はその迫りくる塵芥にもあるけれど、
それ以上に感じる境界線のあいまいさにあるような気がします。
この物語は、たくさんの二項対立がみられますね。
人間とアンドロイド
アンドロイドとスペシャル
スペシャルとレギュラー
他の惑星に移民していく人と地球に残る人
アンドロイドを作る人と狩る人
動物と模造動物
共感ボックスと感情移入度テスト
まだまだあるでしょう。
有機人工生命体であるアンドロイドは、外見では人間と区別がつかないけれど、感情移入ということが苦手で、情動的に欠陥がある。
8本あるくもの足を、4本でも歩けるかと嬉々として切ってみたり。
ちょっと考えれば、情動的に欠落のある人なんて、大勢いることに気がつきますね。
感情移入度検査法、すなわちフォークト・ガンプラテストを受けたら、アンドロイドと判断される人が少なからずいるだろうことは想像に難くありません。
また、情調オルガンや共感ボックスに不健康さや、嫌悪感を感じます。
共感ボックスは、マーサーを介し、マーサーの痛みや苦しみを通して、共感ボックスと接触している人すべてと融合を果たすという代物。
共感ボックスで得られる共感と感情移入との差はどこにあるのか。
それは、気づかずに行うことと自ら共感を得ようとする行為にあるのか。
う~ん、よくわからん。(もっと考える余地あり)
ところで、マーサーは、さまよえるユダヤ人のようですね。
死に向かっていつまでも歩き続ける。
主人公のリックは自分をマーサー自身だと言います。
先日読んだ『キリスト教文学を学ぶ人のために』という本の中に、
さまよえるユダヤ人に関する記述がありました。
「裏切る相手が神でなくとも、友や仲間、親、祖国を裏切って罪意識に苦しみさまよう罪人が私たちの本質的な姿かもしれない」
リックはアンドロイドを処分したことを殺したと感じます。
アンドロイドに人間性を認め、人間の中にアンドロイド性を認めます。
デッィクが描きたかったのは、人間そのものだったのではないでしょうか。
アンドロイドは電気羊の夢を見るか?
キリスト教文学を学ぶ人のために

いつの間にか投稿記事数が増えていました。
この記事もブログルポに参加させてみよう。
というわけで、評価してくださる方はポチッとお願いします。
この記事を評価する
ブログルポに関して、詳しくお知りになりたい方は、バナーをクリックしてみてね。










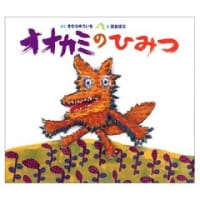
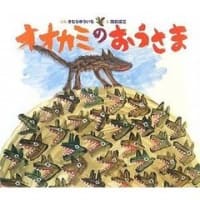
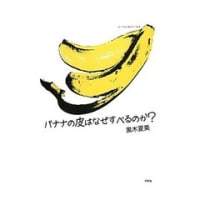
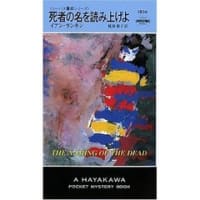
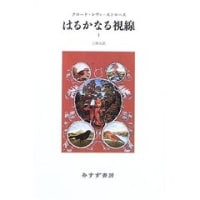
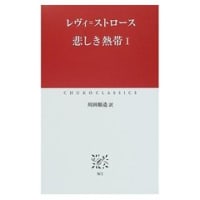
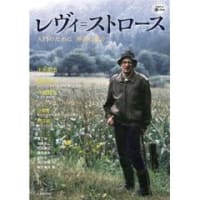
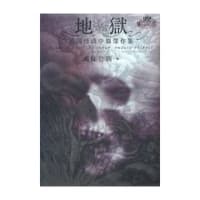
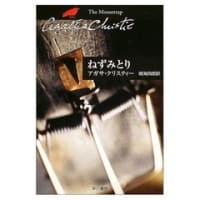
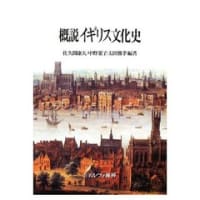
「スキャナー・ダークリイ」も映画化されるとのこと。ディックの作品には,映画人を引き付ける魅力があるのでしょう。
個人的には,お蔵入りになっているらしい「ユービック」なんか,映画化に向いているような気がするのですが。
この作品だけは、ディックのなかでも群を抜いて完成度が高い気がします。マーサーはさまよえるユダヤ人、というイメージはそのとおりだと思います。と同時にジジフォスの神話も思い出しました。
と考えていくと、この本の主要な主題の内の多くは映画には現れませんね(笑)映画も好きなんですが・・・
お恥ずかしい。。。
でも、これから読もうかと思って「火星のタイム・スリップ」を図書館から借りています。
ディックは、確かに映画化されている作品が多いですね。
58歳という若さで夭逝されたことが惜しい作家です。
「ユービック」はお蔵入りになっちゃったんですか。
もったいないですね。
あれも報われない話ですね。
私も映画は何度も観たくちです。
読み返してみて、やっぱり映画とは違うなぁとあらためて思いました。
小説は小説でしか伝えれない奥深さがありました。
リックは嫌なやつでしたけど、だんだん変わってきて人間らしく悩んだりして。
そんなわけで、遅まきながらディックをこれから読みますよ~。
つまり、そういった抽象的な精神活動をするのかという意味になりますね。
人間の胎からでなく、科学技術によって作られた身体に、魂はあるのか、そこに宿る精神活動は見せかけではないのか、まやかしであっても、そこに生命を感じるのが、人間ではないか。
そんな問題が頭をよぎりますが、私はこの物語をアンドロイドという非人間性を用いながらも、アンドロイドを人間として用いていると思います。
だから、この物語は人間そのものを描いたものであって、救いのない物語であると考えます。
ディックは、アル中でヤク中であったとか。
納得。
フクロウは、知恵の象徴でしたっけ?
森の賢者とか、「ミネルヴァのふくろうは黄昏とともに飛びはじめる」とか。
デイヴィッド・アーモンド「肩胛骨は翼のなごり」のスケリグにエサを運んでいたのはフクロウでしたね。
象徴的な意味合いを感じますね。
アンドロイドもの第2弾といたしまして、現在「未来のイヴ」を読書中。
これはディックよりさらに古い。
面白く読んでいますが、借りた本が旧仮名で、漢字がむずかし~。
おもしろかったです。
「未来のイヴ」の感想も教えてね。
ところで、B級映画とA級映画の違いってなんなのでしょう。恥ずかしくってだれにもきけなかったのですが……。
だれか、教えてください。
私が超B級映画と書いたのは、そーとー昔に読んだ映画雑誌に「ブレードランナー」のことがそういう書かれ方をしていて、確かにそうだなぁと思ったからです。
オタクチックな固定ファンがつきそうなそんな映画だし。
SFものはとかくB級といわれがち。
というか万人受けしないところですでにB級ですね。
私一押しのこれぞB級って映画はティム・バートン「マーズ・アタック!」。
あれ、ぜったいマクロスのパクリ。
「未来のイヴ」読み終わりました!
これからレビュー書きますが、これも万人受けする作品でないことは間違いなし。
「マーズ・アタック!」は私も大好きな映画なんですが、あれは何気に豪華キャストな映画でしたね。ラストでトム・ジョーンズが歌い出したときには大笑いしました。
A級映画・B級映画の区別ってのは予算の違いだと言うことを聞いたことがあります。昔は低予算映画をB級映画と呼んでいたとか。
ちょっとグロくないか~?と思ったんですが、子供は全然お構いなしで。
まあ、私も大笑いしましたけど。
そういえば、007の人とか出てましたね。
豪華キャストにあのB級感、たまんない。
予算の違いというのは、私も聞いたことありますね。
ああ、昔はそうだったのか。
ありがとうございます。