
私が「沈黙」を最初に目にしたのは中学生のころで、
小説の一部が教科書に載っていたからです。
教科書に載っていたのがどこの部分なのかは、今ではもうさっぱり思い出せませんが、<神の沈黙>に、なにかとても不条理なものを感じた記憶があります。
その後、「沈黙」を通して読んだのですが、記憶に残っているのは、やはり<神の沈黙>、「神よ、何故、あなたは黙ったままなのですか?」という悲痛な訴えでありました。
まあ、中学生ですから、「沈黙」をそのように誤解してしまっていたのも無理はないでしょう。
大人になり、もうちょっと人生についての経験値が上がってくれば、昔は見えてこなかったことも、今度ははっきりと浮かび上がっていくるというものです。
それが、再読する楽しみであるといえるでしょう。
一般的な日本人である私は、とりあえず仏教徒ということになってはいますが、お正月には三嶋大社に初詣に出かけ、道端の地蔵さんに手を合わせ、クリスマスにはツリーやリースを飾り、ローストチキンやケーキを料理して食する、などというとんでもない宗教のごちゃ混ぜを平気でやってのけています。
つまり、どの宗教も真剣に信じてはいないということですね。
だからといって、全く神も仏も認めないとか、拒絶しているとかといったことではなくて、どれも少しづつ、それなりに信じるに足るところがあると感じているゆえんではないかと思います。
ですから、一つの宗教を心から信じる人々を、時には羨ましく思いながらも、その論理に一抹の不安を感じてしまうこともまた事実です。
「沈黙」を再読し始めたとき、先ず最初に感じたのは、
パードレたちの宗教の内側にいる人たちの論理に対する困惑でした。
宗教への情熱が純粋であるだけに、読んでいるこちらは、
葛藤を覚えずにはいられないといいましょうか。
日本にいる迷える信者たちを勇気づけるため、さらには棄教したと噂されるフェレイラ神父の消息とその真偽を知るため、日本に渡ることを決行したパードレ、ガルペとロドリゴ。
「沈黙」は、まえがきとロドリゴの書簡から、日本に渡る事情とその行程、
日本の信者の様子が描かれ、百姓がキリスト教を信仰する根底にあるのは、その貧しさ、苦しさであることを匂わせます。
そして、転んだ信者であるキチジロー。
キチジローの裏切りによって、ロドリゴは捕らえられてしまいます。
まるで、ユダに裏切られたキリストのように。
ロドリゴはその後、キリストと自分を重ね合わせていきますが、結果的には、キチジローと同じように、ユダやペトロの如く裏切ります。
本書では、裏切りが大きなテーマであるといえるでしょう。
厳しい迫害を受け、拷問され、みじめで辛い殉教を見せつけられた信者たちが、
心とは裏腹に踏み絵を踏む。
踏み絵を踏むことが、果たして裏切りなのか。
裏切った弱きものを誰が責められるでしょうか。
殉教していくことが正しいなどと誰が言えるでしょうか。
ロドリゴは、吊るされた信者のうめき声を鼾として嗤っていました。
信者の苦しみを救うはずのパードレであるロドリゴが、その苦しみに少しも気がつかないとは、どういうことなのか。
本当の信仰とは、いったい何なのか。
さて、最後に<神の沈黙>について、少し触れておきましょう。
本書では、度々、自然の永遠性と<神の沈黙>が同列に置かれています。
これは、世界が在ると同じように、神もただ在るものだということではないでしょうか。
沈黙

小説の一部が教科書に載っていたからです。
教科書に載っていたのがどこの部分なのかは、今ではもうさっぱり思い出せませんが、<神の沈黙>に、なにかとても不条理なものを感じた記憶があります。
その後、「沈黙」を通して読んだのですが、記憶に残っているのは、やはり<神の沈黙>、「神よ、何故、あなたは黙ったままなのですか?」という悲痛な訴えでありました。
まあ、中学生ですから、「沈黙」をそのように誤解してしまっていたのも無理はないでしょう。
大人になり、もうちょっと人生についての経験値が上がってくれば、昔は見えてこなかったことも、今度ははっきりと浮かび上がっていくるというものです。
それが、再読する楽しみであるといえるでしょう。
一般的な日本人である私は、とりあえず仏教徒ということになってはいますが、お正月には三嶋大社に初詣に出かけ、道端の地蔵さんに手を合わせ、クリスマスにはツリーやリースを飾り、ローストチキンやケーキを料理して食する、などというとんでもない宗教のごちゃ混ぜを平気でやってのけています。
つまり、どの宗教も真剣に信じてはいないということですね。
だからといって、全く神も仏も認めないとか、拒絶しているとかといったことではなくて、どれも少しづつ、それなりに信じるに足るところがあると感じているゆえんではないかと思います。
ですから、一つの宗教を心から信じる人々を、時には羨ましく思いながらも、その論理に一抹の不安を感じてしまうこともまた事実です。
「沈黙」を再読し始めたとき、先ず最初に感じたのは、
パードレたちの宗教の内側にいる人たちの論理に対する困惑でした。
宗教への情熱が純粋であるだけに、読んでいるこちらは、
葛藤を覚えずにはいられないといいましょうか。
日本にいる迷える信者たちを勇気づけるため、さらには棄教したと噂されるフェレイラ神父の消息とその真偽を知るため、日本に渡ることを決行したパードレ、ガルペとロドリゴ。
「沈黙」は、まえがきとロドリゴの書簡から、日本に渡る事情とその行程、
日本の信者の様子が描かれ、百姓がキリスト教を信仰する根底にあるのは、その貧しさ、苦しさであることを匂わせます。
そして、転んだ信者であるキチジロー。
キチジローの裏切りによって、ロドリゴは捕らえられてしまいます。
まるで、ユダに裏切られたキリストのように。
ロドリゴはその後、キリストと自分を重ね合わせていきますが、結果的には、キチジローと同じように、ユダやペトロの如く裏切ります。
本書では、裏切りが大きなテーマであるといえるでしょう。
厳しい迫害を受け、拷問され、みじめで辛い殉教を見せつけられた信者たちが、
心とは裏腹に踏み絵を踏む。
踏み絵を踏むことが、果たして裏切りなのか。
裏切った弱きものを誰が責められるでしょうか。
殉教していくことが正しいなどと誰が言えるでしょうか。
ロドリゴは、吊るされた信者のうめき声を鼾として嗤っていました。
信者の苦しみを救うはずのパードレであるロドリゴが、その苦しみに少しも気がつかないとは、どういうことなのか。
本当の信仰とは、いったい何なのか。
さて、最後に<神の沈黙>について、少し触れておきましょう。
本書では、度々、自然の永遠性と<神の沈黙>が同列に置かれています。
これは、世界が在ると同じように、神もただ在るものだということではないでしょうか。
沈黙










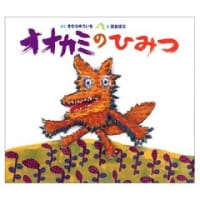
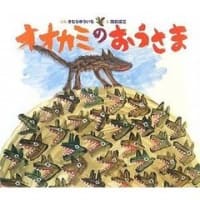
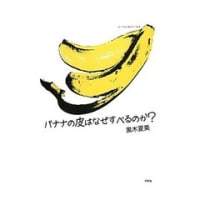
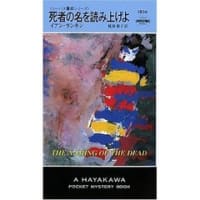
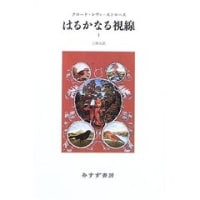
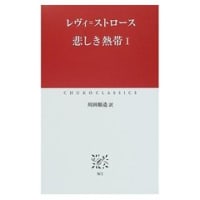
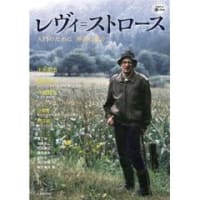
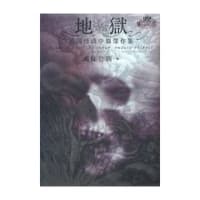
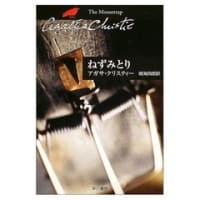
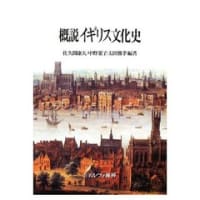
「沈黙」は面白く読みました。映画もみたかな。性悪とか性善の問題ではなく、人間というものは性弱であると思ったものです。神が沈黙しているとは思いませんね。常に語りかけているんじゃないでしょうか。聞こえないのは、耳鼻科的問題か、言語中枢の問題か分かりませんが。オムなら天からではなく地表から、「耳が悪い」と悪態をつくでしょう。ところで、ナショナル・ジェオグラフィック6月号に「ユダの福音書を追う」というのがあり、文藝春秋7月号に「21世紀の最大発見 ユダの福音書」が載ってます。ダヴィンチ・コードの比ではない面白さです。宗教を面白がってはいけないんでしょうが。小田晋著「宗教の時代2 神様は、あなたの頭の”強精剤”?!」、はまの出版、は意外に説得力がありました。まあ、わたしにとって、宗教は教養としての知識でしかありませんが。
神が万能であるのなら、現に困窮している人々をどうして助けようとされないのか? なぜあなたはいま、奇跡を示してはくださらないのですか? 私はそう読みました。
『イエスの生涯』を読んでみて、的はずれではなかった、と思っております。
”神の黙示”という概念は昔から格好いいなあと感じてきました。キリスト教の奇跡は仏教の”方便”のような気もするんですが、むしろキリスト教の本質になっていますね。たしか、今でも”奇跡”が公式に認定されて聖人に列することが行われているんですよね。
教科書に載っていたんです。
今思えば、こんな宗教的なものがよく教科書に載ったものです。
私は、教科書に載っていた作品をいくつか今でも覚えていますよ。
同じ中学校の教科書で覚えているのはチェーホフ「賭け」。
部屋に閉じ込められた男性が愛読していたのは福音書ではなかったかしら。
あれ、黙示録だったかな。
小学校の教科書の記憶もあります。
1年生のとき、最初に習った文章は「あかいあかいふうせん」みたいな詩でした。
6年生のときのいぬいとみこ「白いぼうし」は挿絵まで思えています。
自分の子どもの教科書を見てみると、自分が習ったものが載っていたりして懐かしい~と思うこともあります。
朗読は今でもありますよ。
本を読む宿題とかありまして、何度も同じところを聞かされる親はたまったものではありません。
古典の暗誦も昔と変わらずありますね。
今回は再読でしたが、神は語りかけているということが良くわかりませんでした。
オムに怒られそうですね。
怒られてみたい(笑)
↑にも書きましたが、世界と神が同等であることは理解できますが、そこから語りかけられているというよりは、超越した存在のように感じられます。
まだまだ、人生経験が足りないようです。
ナショナル・ジェオグラフィック「ユダの福音書を追う」の噂は私も聞き及んでいました。
面白いようですね。
私も宗教は、教養としての知識から出ることはないでしょう。
ごちゃ混ぜの宗教観をおかしいと思わない日本人というのは、結構貴重な存在じゃないかと私は思います。
興味深く読ませていただきました。
私も、イエスの説く「愛」は、信ずるに足ると思っていますが、奇跡となると話は別です。
「沈黙」の主人公ロドリゴは、奇跡を信じるような信仰を持っていたのですよね。
しかし、殉教に輝かしさはなく、多くの血が流れようとも神は沈黙したまま。
ロドリゴは「自分の心にあるキリシタンの教え」と闘うことを余儀なくされ、教会の神と彼の神とは別なものになりました。
これは、教会では許されないことでしょう。
「私は、この小説を書いたために、いままで私に寛大だった多くの神父たちを悲しませ、多くの信者の怒りを買ってしまった。とくに、留学以来親友だった一人の神父を傷つけ、絶交せねばならなくなったことはまことにつらいが、しかたがない。」
この言葉は、「沈黙」が谷崎潤一郎賞を受賞したときの受賞の言葉の一部です。
遠藤周作が日本人的な感覚の持ち主であることは、私もそう思います。
信仰を自分にあったように作り変えていく、それこそが日本人が宗教に馴染まない原因ではないでしょうか。
『権力と栄光』チェックしておきますね。
奇跡の認定というのは、今でも行われているようですね。
私はキリスト教徒ではありませんから、興味半分にみていますが、宗教の内側にいる人にとっては、大事なことなのでしょう。
確かに、キリスト教にはかっこよさみたいなものがあります。
憧れというか、ファンタジーに近いかな。
人間である限り、人生に迷いを感じるのは当然だと思うんです。で、その迷いに「だいじょうぶだよ」と言って頭をナデナデしてくれるのが宗教だと僕は思うんですね。解決はしてくれないけれどなぐさめてくれるって感じですかね。
ところが絶対に神を信頼しちゃうと、もう、人生に迷いも何もあったもんじゃなくなりますからね。しかも迷いを考えて克服したんじゃなくて、神様に向けてポーンと投げちゃってるふうに見えなくもない。ものすごく失礼な言い方をすれば「善悪の判断は神様任せ」って感じかな。
僕には本書って、その迷いを神様に投げなかった人々の物語だと思います。世の中に「死ね」と命令する宗教はありません。どの宗教も「生きろ」と言います。矛盾を心に持って迷って苦しんでまでもただ生きる姿。これが遠藤氏の言いたかった宗教じゃないのかな。
……なんてふうに僕は無い頭で考えるのですがね(笑)。
難しい話になっちゃってごめんなさい。
私は、宗教って、心の拠所的なものであればいいなと思います。
粉飾されたものではなく、本質を信じたい。
キリスト教であれば、それは「愛」ですよね。
「赦し」でもあるかもしれない。
私は、本書は「赦し」の物語だと思うんです。
「踏みなさい、踏みなさい」という踏み絵のキリスト。
これは、「愛」の本質であり、キチジローでさえ赦されている。
教会から離れようとも、心にその信仰がある限り、決して転んだとしても信仰を失ったことにはならない。
切支丹役人日記にもあるように、ロドリゴは信仰を依然持っていたようですし、キチジローも信仰を捨てたわけではなかったようです。
もちろん、フィクションであるわけですが、実在のモデルがいたことを考えますと、転んだパードレたちの苦悩や、信徒たちの苦痛が偲ばれます。
私も同感です。
一時ノーベル賞候補にも上がった作家なので
海外でもたくさん翻訳があるようですね。
スコセッシが『沈黙』を映画化するという事実自体は
日本人として誇らしく嬉しいものです。
できあがりには、あまり期待できないですが…。
TBさせていただきました。