
遠藤周作『沈黙』を文庫版で読んだわけですが、解説を読んでみると、
単行本にはどうやら著者あとがきが付いているようでした。
文庫本をふってもひっくり返してもあとがきは見つからず、それならと思い新潮社から出版されている『遠藤周作文学全集』の第2集を図書館から借りてきました。
第2集の解説には、あとがきの全文があり、さらには、『フェレイラの影を求めて』なる日記があるということを知り、全集の12巻、13巻をまた図書館へと借りに行き、ようやくこの記事が書けるという次第なのであります。
以下は、関係のありそうな箇所を拾い読みしたところです。
・日記(フェレイラの影を求めて) 12集
・『沈黙』-踏み絵が育てた想像 12集
・横瀬浦、島原、口之津 13集
・弱者の救い 13集
・一枚の踏み絵から 13集
これらは、『沈黙』を書くための取材を中心としたもので、『沈黙』本文中にこの部分が使われているとか、そういったことを知るにはうってつけの材料です。
しかし、私が一番興味を引かれたのは、隠れ切支丹のことでした。
歴史で習う知識として隠れ切支丹は知っていました。
授業では、鎖国と同時にキリスト教の迫害についても習うのですが、
それは過去の出来事であり、歴史の一部でしかありません。
しかし、これらのエッセイを読むことにより、もう少し深く、
生きた歴史として感じることが出来ました。
隠れ切支丹とは、江戸時代、キリスト教が禁教とされたとき、表向きは仏教徒を装いながら、キリスト教を信仰し続けた人々であり、厳しい迫害にあいながら、教会もなく、導く聖職者もいないまま、自分たちなりに教えを守り、継承していった人々です。
しかし、心はどうあれ、彼らは年に一度づつ踏み絵を踏まされる、
転んだ信者であったわけです。
1864年の信徒発見後、変容してしまった信仰からカトリックに復帰する人々がいるなか、復帰することが出来ない人々もおり、彼らは、今なお、その信仰を守っているといいます。
過疎や高齢化から、減少傾向にあるようですが、いまだ存在するということが、いきおい現実味を帯びて、物語のなかから立ち上ってきます。
彼らには、心ならずも裏切ったことにによる苦悩や痛み、
悲しみが付きまとっているのかもしれません。
カトリックの神父たちは、隠れ切支丹の信仰のなかから非基督教的なものを排除しようとしたようですが、必ずしも成功はしなかったようです。
「切支丹時代のパードレと格好が違うから、あいつらはニセもんじゃ」
という隠れ切支丹たちに、それならと切支丹時代の宣教師の服装をして行くと
「似ているようじゃが、どこか違う」
彼らの警戒心は、そんな心情を表しているのではないでしょうか。
先にもあげましたが、信徒発見という出来事には、私は心を打たれずにはいられません。
大浦天主堂は、ぺりー来航によって、各国と通商条約を結ばなければならなかった幕府が、外国人のため横浜天主堂と共に建てたもので、その美しさとものめずらしさから、近隣の住民が大勢見物に訪れていたといいます。
未だ禁教であったなかで、教会の神父プチジャンは隠れ切支丹を探そうとわざと落馬してみせたり、子どもたちにお菓子を与えて聞き出そうとしたり、涙ぐましい努力をしていたにも関わらず、一向に名乗り出るものはありませんでした。
しかし、ついに1865年3月17日12時30分ごろ、12名から15名ほどの信者が現れ、
神父の努力は報われたのです。
彼らは浦上村という地域の隠れ切支丹であり、浦上は遠藤氏が言うように
受難と試練の村にほかなりません。
プチジャン神父と秘密裏に接触していた浦上信徒たちは、次第に大胆になりその信仰をあらわしはじめ、そのために明治政府下の長崎奉行所の襲撃にあい、3千数百人の信徒たちは、捕縛されたのち、日本各地20箇所に流されました。
この信徒追放は、外国公使団を驚愕させ、
これが契機となってやがてキリスト教迫害の歴史に幕が下ろされます。
ところが、村の受難はそれだけにとどまりません。
第2次世界大戦末期、小倉に向うはずのB29が天候の理由から長崎に原爆を落としましたが、その落下地点は浦上村の真上でした。
信徒発見の際、一人の女性が神父にこう尋ねます。
「サンタ・マリアの御像はどこ?」
『沈黙』の中でも、日本の信徒が聖母マリアをキリスト以上に崇拝しているのではないか
という危惧をロドリゴは抱きます。
隠れ切支丹たちは、神のイメージの中に父を感じ、聖母マリアに母を感じたのではあるまいか
と遠藤氏は推察しています。
「許してくれる」存在の母。
上記に挙げたエッセイではありませんが、『ガンジス河とユダの荒野』(13集)のなかで遠藤氏は以下のことを書いています。
東洋人の宗教心理には「母」なるものを求める傾向があって、「父なるもの」だけの宗教にはとても従(つ)いていけぬというのが私の持論である。
ここで言う「父なるもの」は旧約聖書のヤハウェであり、「母」の要素を加えたものが新約聖書なのですが、自然環境を比較してのこの論理は、なかなか説得力があるように思えます。
ただ、私には、この「母」という存在が、あまりにも美化されているようにもうつります。
母性が時として狂気をはらむように、自然も決して優しくはない。
私が、「神は沈黙で語りかけている」ことを理解できないのは、
これが原因なのかもしれません。
遠藤周作文学全集〈13〉評論・エッセイ(2)

単行本にはどうやら著者あとがきが付いているようでした。
文庫本をふってもひっくり返してもあとがきは見つからず、それならと思い新潮社から出版されている『遠藤周作文学全集』の第2集を図書館から借りてきました。
第2集の解説には、あとがきの全文があり、さらには、『フェレイラの影を求めて』なる日記があるということを知り、全集の12巻、13巻をまた図書館へと借りに行き、ようやくこの記事が書けるという次第なのであります。
以下は、関係のありそうな箇所を拾い読みしたところです。
・日記(フェレイラの影を求めて) 12集
・『沈黙』-踏み絵が育てた想像 12集
・横瀬浦、島原、口之津 13集
・弱者の救い 13集
・一枚の踏み絵から 13集
これらは、『沈黙』を書くための取材を中心としたもので、『沈黙』本文中にこの部分が使われているとか、そういったことを知るにはうってつけの材料です。
しかし、私が一番興味を引かれたのは、隠れ切支丹のことでした。
歴史で習う知識として隠れ切支丹は知っていました。
授業では、鎖国と同時にキリスト教の迫害についても習うのですが、
それは過去の出来事であり、歴史の一部でしかありません。
しかし、これらのエッセイを読むことにより、もう少し深く、
生きた歴史として感じることが出来ました。
隠れ切支丹とは、江戸時代、キリスト教が禁教とされたとき、表向きは仏教徒を装いながら、キリスト教を信仰し続けた人々であり、厳しい迫害にあいながら、教会もなく、導く聖職者もいないまま、自分たちなりに教えを守り、継承していった人々です。
しかし、心はどうあれ、彼らは年に一度づつ踏み絵を踏まされる、
転んだ信者であったわけです。
1864年の信徒発見後、変容してしまった信仰からカトリックに復帰する人々がいるなか、復帰することが出来ない人々もおり、彼らは、今なお、その信仰を守っているといいます。
過疎や高齢化から、減少傾向にあるようですが、いまだ存在するということが、いきおい現実味を帯びて、物語のなかから立ち上ってきます。
彼らには、心ならずも裏切ったことにによる苦悩や痛み、
悲しみが付きまとっているのかもしれません。
カトリックの神父たちは、隠れ切支丹の信仰のなかから非基督教的なものを排除しようとしたようですが、必ずしも成功はしなかったようです。
「切支丹時代のパードレと格好が違うから、あいつらはニセもんじゃ」
という隠れ切支丹たちに、それならと切支丹時代の宣教師の服装をして行くと
「似ているようじゃが、どこか違う」
彼らの警戒心は、そんな心情を表しているのではないでしょうか。
先にもあげましたが、信徒発見という出来事には、私は心を打たれずにはいられません。
大浦天主堂は、ぺりー来航によって、各国と通商条約を結ばなければならなかった幕府が、外国人のため横浜天主堂と共に建てたもので、その美しさとものめずらしさから、近隣の住民が大勢見物に訪れていたといいます。
未だ禁教であったなかで、教会の神父プチジャンは隠れ切支丹を探そうとわざと落馬してみせたり、子どもたちにお菓子を与えて聞き出そうとしたり、涙ぐましい努力をしていたにも関わらず、一向に名乗り出るものはありませんでした。
しかし、ついに1865年3月17日12時30分ごろ、12名から15名ほどの信者が現れ、
神父の努力は報われたのです。
彼らは浦上村という地域の隠れ切支丹であり、浦上は遠藤氏が言うように
受難と試練の村にほかなりません。
プチジャン神父と秘密裏に接触していた浦上信徒たちは、次第に大胆になりその信仰をあらわしはじめ、そのために明治政府下の長崎奉行所の襲撃にあい、3千数百人の信徒たちは、捕縛されたのち、日本各地20箇所に流されました。
この信徒追放は、外国公使団を驚愕させ、
これが契機となってやがてキリスト教迫害の歴史に幕が下ろされます。
ところが、村の受難はそれだけにとどまりません。
第2次世界大戦末期、小倉に向うはずのB29が天候の理由から長崎に原爆を落としましたが、その落下地点は浦上村の真上でした。
信徒発見の際、一人の女性が神父にこう尋ねます。
「サンタ・マリアの御像はどこ?」
『沈黙』の中でも、日本の信徒が聖母マリアをキリスト以上に崇拝しているのではないか
という危惧をロドリゴは抱きます。
隠れ切支丹たちは、神のイメージの中に父を感じ、聖母マリアに母を感じたのではあるまいか
と遠藤氏は推察しています。
「許してくれる」存在の母。
上記に挙げたエッセイではありませんが、『ガンジス河とユダの荒野』(13集)のなかで遠藤氏は以下のことを書いています。
東洋人の宗教心理には「母」なるものを求める傾向があって、「父なるもの」だけの宗教にはとても従(つ)いていけぬというのが私の持論である。
ここで言う「父なるもの」は旧約聖書のヤハウェであり、「母」の要素を加えたものが新約聖書なのですが、自然環境を比較してのこの論理は、なかなか説得力があるように思えます。
ただ、私には、この「母」という存在が、あまりにも美化されているようにもうつります。
母性が時として狂気をはらむように、自然も決して優しくはない。
私が、「神は沈黙で語りかけている」ことを理解できないのは、
これが原因なのかもしれません。
遠藤周作文学全集〈13〉評論・エッセイ(2)













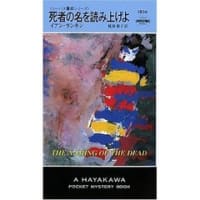





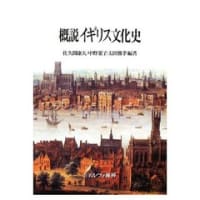
ご紹介の実話を知るといささか不謹慎なような気にもなりますが、”正統”な宗教とされているものもいくつかの教義群間のサバイバルを勝ち抜いてきて現在あるわけですよね。
なぜ勝ち抜くことができたかを考えることこそ興味深い。決して”スーパーナチュラル”な手段で勝ち抜いたわけではないでしょうから。実務的な能力を持った優秀な人材を惹きつける魅力。それはおそらく”論理”ではなかったかと私は思うのです。
勝ち抜いて、生き残っていくためには、それなりに理由があるんでしょう。
宗教についてあまり詳しくはないので、なんとも言えないというのが本音です。
何故、勝ち抜くことができたのかという視点は、私は今まで持ってはいませんでしたが、なるほど、興味深いですね。
私が、今、一番気になるのは、カクレキリシタンたちが、何故、厳しい迫害を受けながらも、キリスト教を信じ続けたのか、いえ、それ以前に、何故キリスト教を自分の宗教として取り入れたのか、です。
現世に苦しみしか見出せないからハライソに幸せを求めたのか、仏教では得られない何があったのか。
この問題には、もう少し時間をかけてみようと思っています。
ちょっとしか話したことなかったんですが、
その人自身は、ずっとキリスト教に
興味がなかったのに、あるとき急に
教会に通うようになったと語っていました。
吉田茂も確か晩年洗礼を受けていたと思います。
洗礼を受け、キリスト教を信仰するきっかけというのは、
もしかしたら、ふっとしたなにげないもので、
それが、年々宿命のように
感じられるのかもしれないなあ
と最近思っています。
実際に会話されたことがあるのですね。
そういうお話を伺うと、歴史という半ば遠い存在であるものが、身近にあることに驚きますね。
歴史というのは、過去起こったことであるとわかってはいても、実際の生活に直接かかわりを持たないので、ついつい物語として捉えがちです。
まったくキリスト教を信仰する土壌がなかった日本において、キリスト教を信仰すること、そのきっかけがいかなるものでも、信仰を捨てることがなかったこと、そういったことに興味があります。
それは、私自身が、確固たる宗教心を持っていないからだと思います。
お正月には神社に行き、クリスマスにはケーキを食べる。
結婚式は教会で、葬式はお寺であげる。
このいい加減さを許容するのは、日本には古来から多くの神がいたせいなのかもしれません。
でも、こういうところが日本のよいところでもあると思うんですよね。