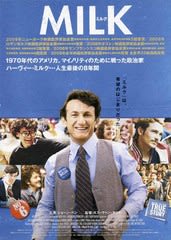去年、UKに行く飛行機の中で、公開されたら観たいなと思っていた映画 『ジュリー&ジュリア』 を観た。
監督・脚本は、映画版 『奥さまは魔女』 のノーラ・エフロン。彼女の作品と言えば、『恋人たちの予感』 や 『めぐり逢えたら』、『ユー・ガット・メール』 と言った王道の恋愛ロマンスが浮かぶが、今回は実話を基にしたコメディ・タッチのテンポのよい作品だ。
これは、料理で人生を変えたふたりの女性の物語。
料理研究家ジュリア・チャイルドが50年前に出版した料理本の全レシピを、1年で制覇しようとする現代のジュリー・パウエル。そのジュリアとジュリーの姿を、第2次大戦後の時代と現代が交差しながら話は進んで行く。実話とは言え、物語の焦点が面白い。
何と言っても、“ボーナペティ!” と大袈裟に言う、ジュリア・チャイルド演じるメリル・ストリープが、とっても可愛らしかった。
外交官の夫の転勤でパリで暮らすことになったジュリアは、フランス料理に魅せられ、好奇心旺盛で食べることが大好きな性格が転じて、名門料理学校コルドン・ブルーのプロ養成クラスに入門する。
その料理修行の過程が面白く、様々な食材に四苦八苦する姿が豪快でユーモアたっぷりに描かれていて、意地になってたまねぎを刻んだりするジュリアの奮闘する姿は、いじらしくて可愛かった。
そして持ち前のバイタリティと理解ある夫に支えられ、見事に料理学校を卒業するジュリア。
その後出版した料理本が話題となり、TVの料理番組で一躍人気を博した。その番組で最後に言うセリフが、“ボーナペティ!”(Bon appetit=フランス語で “召し上がれ”) なのだ。

一方現代のジュリーは、ニューヨークに住む食べることが大好きな働く女性。愛する夫とふたりで幸せな毎日を送っているものの、9.11後の市民相談係の仕事や社会の不満で少々お疲れ気味。何をやっても中途半端の現状から何とか抜け出したいと思っていた時に出会ったのが、半世紀前に出版されたジュリアの料理本。
そこである日、ジュリーは一大決心をした。それは、ジュリアの料理本のレシピに挑戦し、1年で制覇してそれをブログに掲載すること。
何度も失敗しては挫折し、夫に八つ当たりしながらも理解ある夫や応援する友人たちに励まされながら、無謀とも思えるこの挑戦をやり遂げるのだった。

とまあ、あらすじはこんな感じなのだが、ジュリーとジュリアに共通している背景は、ふたりとも素晴らしい夫の献身的な最高の支えがあったということ。
やはり、愛する人からの 「美味しい!」 という言葉は、何事にも変えがたい励みなのだ。

別々の時代で料理に生き甲斐を見出して行くふたりのプロセスが、うまい具合に交互に融合しながら描かれていて、コミカルなスパイスも効かせながら、全く違う時代の違う街での出来事がシンクロして行く映像は、観る側を飽きさせず、とても印象に残っている。
最近は肝っ玉母さん的なイメージが強いメリル・ストリープだが、豪快で無邪気なジュリアのキャラクターにピッタリはまっていた。
偶然にも、同じように “食” が絡む 『恋するベーカリー』 の主演もメリル・ストリープで、パン好きの私にはとても惹かれるタイトルなのだが、予告を観る限りではこの 『ジュリー&ジュリア』 の方が良さそうだった。
さて、そろそろ夕飯にしよう・・・。
Bon Appetit!