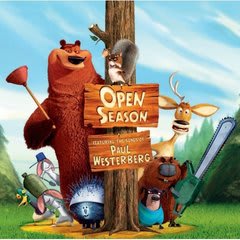特にコレを買おうという目的のものもなかったのだが、今タワーレコードがWスタンプ・キャンペーン中(12/3まで)ということで、久しぶりに行ってきた。
そして、とびっきりのアルバムを見つけてきた。1曲目と2曲目の触りだけ聴いて即買い。
バンド名はLeeland、テキサス州Baytown出身の5人組。
なんと、またまた私には縁がありすぎるくらいの兄弟バンド。
今年8月にリリースされた、彼らのデビュー・アルバム 『Sound of Melodies』。
とにかく煌めくような美しいメロディと、輝きを放つVo.の声に参ってしまった。
若かりし頃のRideのMark Gardener似のそのVo.&GのLeeland Mooringは、なんとまだ若干18歳。(日本のメディアでは17歳となっていたが、本当は18歳)
恐るべし! ティーンエイジャーだ。
しかも自分の名前をバンド名にしているだなんて、Bon Joviみたい。(笑)
それもファースト・ネームの方(Bon Joviはラスト・ネーム)。Key.の兄もいるというのに・・・。
自分=バンドの顔、余程の自信がないとできないであろう・・・。
やはり、恐るべし! ティーンエイジャー。(笑)
もちろん、ソング・ライティングも彼の手による。
彼らのオフィシャル・サイトのバイオによると、彼は相当熱心なクリスチャンのようで、“神が自分たちに与えたメロディが、天国から降りてくる” と表現している。
その歌詞には必ず “God” が出てきて、他にも “saints(聖者)” “praise(賞賛) ” “liberty(自由) ” “salvation(救済)” と言った言葉がたくさん出てくる。
“音楽をプレイしているときはいつでも、メイン・ゴールは自分たちの世代の司祭(神のしもべ)になること” とまで言っている。
なんせ、最も影響を受けたのが “究極のミュージシャン、Jesus” で、読む本は聖書なのだから・・・。
キリストとあまり縁のない私たち日本人には、そういう感覚はなかなかわからないし、ちょっと怖いくらいに不思議な感じがするが、きっと彼の心はとてもとても澄んでいるんだと思う。
その澄みきった心が、この叙情的で美しく透明な音楽に直接表れているのだと思う。
アルバム・タイトル曲のM-1 「Sound of Melodies」 で即ハマったのは、何を隠そう私のイチバン弱いツボ、3連のリズム。
このリズムに乗ってこんなステキなメロディが流れてきたら、もうハマらずにいられない。(笑)
M-3 「Yes You Have」 のAメロのアコースティックなヴァースからぐいぐい引っ張って行くブリッジの展開は、とてもエモーショナルで素晴らしい。
M-6 「Can't Stop」 では、エッジの効いたカッコいいロック・サウンドを聴かせてくれて、アルバムの真ん中で盛り上がりを見せる。
M-8 「Hey」 のピアノとハンド・クラッピングだけの間奏は、とっても楽しくって踊り出したくなる。
美しいメロディと言っても、実はしっとりとしたバラードは最後の曲 「Carried to the Table」 だけ。
この 「Carried to the Table」 の壮大なコーラスがこれまた凄い。
どれもキャッチーで洗練されたメロディの、全11曲、全くの捨て曲なしの完成度の高いデビュー作だ。
情感たっぷりと歌い上げるVo.、そこはかとなく奏でられるピアノ、控えめながらも正確なビートが響くドラム、爽やかな色付けをするアコギetc...。
最初に “熱心なキリスト教信者” をイメージしてしまうことばかり書いてしまったが、人間性に対する偏見や先入観は捨てて是非音楽を聴いてみてほしい。
すごく心が洗われる音楽だし、何と言っても18歳の若者が作り出す楽曲の素晴らしさに脱帽する。
それにしても、私はこういう声が本当に好きだ・・・。
 まずはMySpaceで試聴!
まずはMySpaceで試聴!