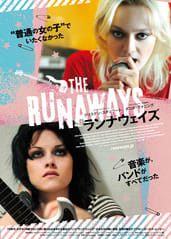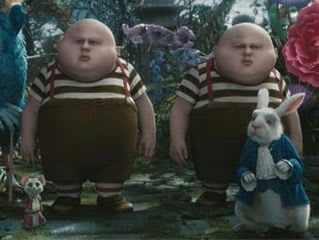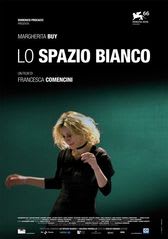ネタはあれど、更新ままならず・・・。
今日は、久しぶりに劇場で観た映画のことでも。
『あしたのパスタはアルデンテ』 って、正直何てタイトルだ!と思った。原題は 『Mine Vaganti』 で、直訳すると “さまよう地雷” だが、ピンと来ない。
では何故パスタが出てきたかというと、主人公の家族がパスタ製造工場を営んでいるところから取ったのだろう。
2010年のイタリア映画で、今年のイタリア映画祭では、『アルデンテな男たち』 というタイトルだったらしい。どっちもどっちかな。
舞台は南イタリア・プーリア州の州都Lecce(レッチェ)。実は、ここではまだ旅行記にもしていないが、レッチェは去年行ってきたところ。
この目で見て感じて、過ごした街のあちこちが出てきて嬉かった。泊ったB&Bの建物まで映り、懐かしくなってまた行きたくなった。
物語は、父親が経営する老舗パスタ会社の社長に長男のアントニオが就任することになり、一族が集まる晩餐会のためにローマに行っている主人公の次男トンマーゾが帰郷するところから始まる。
トンマーゾには家族に内緒にしていたことが三つあった。ひとつ目はローマの大学で経営学を学んでいると嘘を付き、実は文学部を卒業したこと、ふたつ目は稼業を継ぐ意思がなく小説家を目指して執筆中だということ。そしてみっつ目が最大の秘密だった。
【以下ネタバレあり】
その最大の秘密とは・・・自分はゲイであるということ。そのことを、兄アントニオに明かす。
そして稼業を継ぐ意思がなく小説家になりたいトンマーゾは、兄の社長就任パーティの席で家族に自分がゲイであることを明かせば、親から勘当されて自分の好きなことができると企んでいた。
しかし、物事はそう上手くは行かず。さあ、告白するぞ!と決めたその時、アントニオが先にカミングアウトしてしまうのだった。そう、アントニオもゲイだったというわけ。勿論父親はアントニオを勘当、そしてあまりにものショックで倒れてしまう。
自分の秘密を告白するタイミングを逃してしまったトンマーゾは、当然のように工場経営を任され、ローマに戻ることもできずで恋人にも逢えない状態。
トンマーゾの未来はどうなる? 小説家になる夢は? 家族はどうなる? 老舗パスタ会社の経営は?
とまあ全部書いてしまうと面白くなくなるので、この辺にしておこう。
イタリア映画ならではの、家族愛をコミカルに描いた人間ドラマ。
ゲイの兄弟のほかにも実は糖尿病のおばあちゃん、アルコール依存症の叔母さん、婿を親に認めてもらえない長女など、家族それぞれに抱えている悩みがあり、それを笑いと涙で感動させる。王道のパターン的なところがあるが、決してダサくない。個人的にはおばあちゃんがステキで良かった。
ひとつだけ難を言うと、食卓を囲むシーンのカメラワークがずーっと回っているため、観ている方も目が回りそうになってちょっと気持ち悪くなったこと。
ローマにいるトンマーゾの恋人とその仲間達(もちろん全員ゲイ)がトンマーゾを尋ねてレッチェにやってきたところはめちゃくちゃ面白かった。
家族にはゲイであることを隠しているため、彼らもバレないようにしなければならない。その一挙一動が笑いを誘った。
予告編での 「人生いろいろあるけれど、家族だからいつか分かり合える。今日がだめでもあしたになれば・・・」 という言葉がドンピシャの作品で、温かい気持ちになった。
★現在、シネスイッチ銀座で上映中。おすすめ!
★公式サイトはこちら。