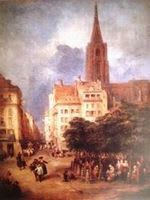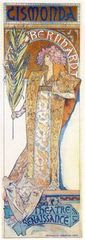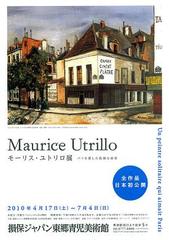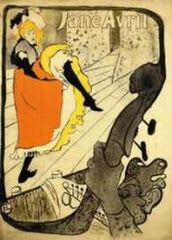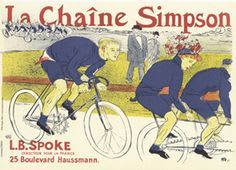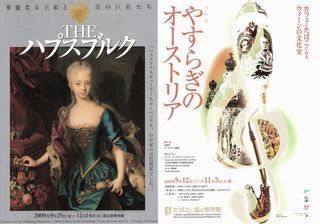9月に入ったというのに、まるで真夏のような毎日。日が暮れるのが早くなり、日に日に秋に近付いているはずなのだが、体感で味わうことができない。
職場では涼しい空間で働けているが、外での仕事の方々には申し訳なく思うほど今年の夏は異常だ。
お休みの日の昼間はすっかり図書館通いが日課になり、お陰でこの夏は読書や勉強がはかどっている。
さて、ここらでちょこっと復活。今日は、既に暑くなっていた7月上旬のお話。
丸の内に新しくオープンした三菱一号館美術館。それは丸の内で最初のオフィス・ビル三菱一号館を復元した建物で、そこが美術館となった。
その開館記念展として開催されたのが、『マネとモダン・パリ』。
戦前の建物を復元しただけあって、レトロな雰囲気の館内。従来の美術館の概念を大きくぶち破った構造となっていた。
2階と3階が展示室になっていて、まず3階から順に廻るようになっていた。窓こそないが廊下や仕切りがあり、大広間があったり暖炉が備え付けられている小部屋なんかもあって、古い大きな洋館を巡っているようだった。
大きく3つの時代に分けられていて、まず最初は “スペイン趣味とレアリスム : 1850-60年代”。この時代は、ベラスケスの影響が大きいらしい。
印象的だったのは、元々はサロン用の大きな絵だったものを、スペイン趣味だの遠近法だのといろんな批判が集まったために結局ふたつに切ったという絵のひとつ、「死せる闘牛士(死せる男)」。黒の色使いがとても心に残った。これはワシントンからの出展だが、もうひとつの 「闘牛のエピソード」 はニューヨークにあるらしい。
 「死せる闘牛士(死せる男)」(1863-64・1865切断と改変)
「死せる闘牛士(死せる男)」(1863-64・1865切断と改変)エミール・ゾラというマネの友人の肖像画のバックには、浮世絵や同じ展示室に飾られていた 「オランピア」 という作品の絵が描かれているのが面白かった。
 「エミール・ゾラ」(1868)
「エミール・ゾラ」(1868)その背景部分と 「オランピア」(1867)


このセクションでいちばん惹かれたのは、この作品。大広間にあったのだが、ひと通り見たあと再び戻って、暫くこの絵の前でじっと眺めていた。なんだか気持ちが安らいだ。
 「街の歌い手」(1862頃)
「街の歌い手」(1862頃)次のテーマは “親密さの中のマネ : 家族と友人たち”。
色使いがだんだん明るくなっていくのが分かる。オランダ旅行やヴェネチア滞在中の制作を機に、インディゴブルーやエメラルドグリーンを確立したのだそうだ。
マネの弟とマネの妻を描いた 「浜辺にて」 の、空0.5、海2.5、砂浜7.0の割合が絶妙なバランスをかもし出す。
 「浜辺にて」(1873)
「浜辺にて」(1873)後に弟の妻となるベルト・モリゾの肖像画が5点あり、弟と結婚する前と後では彼女の表情が違うのが感じ取れるところから、マネとモリゾはお互いに惹かれ合っていたのだろう。きっとお互いにその気持ちを打ち明けないままで・・・。
タイトル写真のチラシの絵は 「すみれの花束をつけたベルト・モリゾ」。私は5点の中では唯一全身の姿が描かれているという 「バラ色のくつ」 が気に入った。
 「バラ色のくつ(ベルト・モリゾ)」(1872)
「バラ色のくつ(ベルト・モリゾ)」(1872)このセクションでいちばん心惹かれたのは、「燕」 という作品。その燕は右側の草の部分に小さく二羽いるだけなのに、作品のタイトルとなっている。
のどかな田園風景の彼方に見える風車や村の様子がほのぼのとしていて、女性ふたりの洋服の色が対照的なのも印象に残った。
 「燕」(1873)
「燕」(1873)2階に下りて、今回のメインでもある3つめのテーマ “マネとパリ生活” では、マネ以外のアーティストの作品もあり、19世紀のパリの街の人々を描いた様々な絵が展示され、その中には聖堂の設計図案やパリのオペラ座の彫像なんかもあった。
この頃は、サロンで認められてこそ価値があると言われていた時代。華やかなパリの人々の生活が見え隠れする作品がたくさんあった。
 「オペラ座の仮面舞踏会」(1867)
「オペラ座の仮面舞踏会」(1867)マネの日本趣味の影響が漂う、エッチングで描かれた猫シリーズはとってもキュートだったし、晩年のマネは静物をたくさん描いていたということを知ることもできた。
 「猫たち」(1868)
「猫たち」(1868)  「レモン」(1880)
「レモン」(1880)なんか美術館で鑑賞したというより、前途したように古い洋館に飾られている絵のコレクションを見て廻ったという印象が強く、とても趣があってアットホームなゆったりとした気分で鑑賞することができた。かの有名な作品 「笛を吹く少年」 はなかったが・・・。
お気に入りの美術館がひとつ増え、この美術館、その中でもひょっとしたらいちばん好きになったかも・・・。