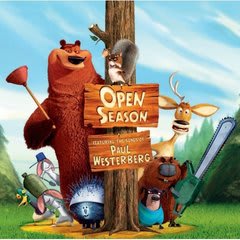それにしても美しい・・・そして儚い。
昨年10月にリリースされたCopelandの3rd 『Eat, Sleep, Repeat』。
まるで哀しいラヴ・ストーリーの映画のサントラのよう・・・。
ジャケのデザインも凝っていて、最初どこから開封していいのか分からなかった。
綺麗なメロディはそのままだが、前2作とはガラッと雰囲気が変わって、本人たちも言っているようにアルバム全体がダークだ。
アルバム・タイトルの “眠って、食べての繰り返し” という日常の普遍的なテーマの中にある様々な形の愛を、音楽だけで描いている。
まるで小さなドラマのような情景を想像させられてしまう。
美しいピアノの音色、ストリングスの壮大なスケールのアレンジ、儚く響くホーン。
なんともドラマティックな、しかし決して派手ではない透明感溢れる珠玉の楽曲が並ぶ。
一度聴いただけではピンと来なかったが、何度も聴いている内にどんどんとその世界観に引き込まれて行ってしまった。
結構ゴツい顔をしているのに、のびのびとしたAaronの歌声は、やはり優しく切なくて胸に沁みる。
前半は少し明るめな楽曲が続き、M-4 「Careful Now」 でだんだんと闇の中に入って行く。
M-5 「Love Affair」 で更に深く閉ざされた闇に沈み、悲しげなサウンドが広がって行く。
しかし、最後には先に見える小さな光の入口を見つけたかのような展開になる。
とても親しみやすいメロディのM-7 「By My Side」 のサビは、日本のTVドラマの主題歌にでも合いそうな感じの曲。
そして、M-9 「Last Time He Saw Dorie」 でのハッとするような輝くサウンド。
淡いベールに包まれた暗い闇の中に、ひとすじの煌く光が差し込む感じの世界観が広がる。
今回のアルバムでは、少しKeaneに似た感じの世界観を感じる。
“暗い” という言葉だけで判断してしまうと間違った解釈をされそうだが、ガラス細工のような儚さの美しいメロディには尊ささえも感じてしまう。
ところで、昨年のサマソニに続き、急遽来日が決まった彼ら。
2005年にはOceanlaneとのカップリング・ツアー。できれば単独で見たいが、今回はAnberlinと一緒だ。
このアルバムの曲が、前2作の曲と交えてどんな展開のライヴになるのかがとても楽しみだ。