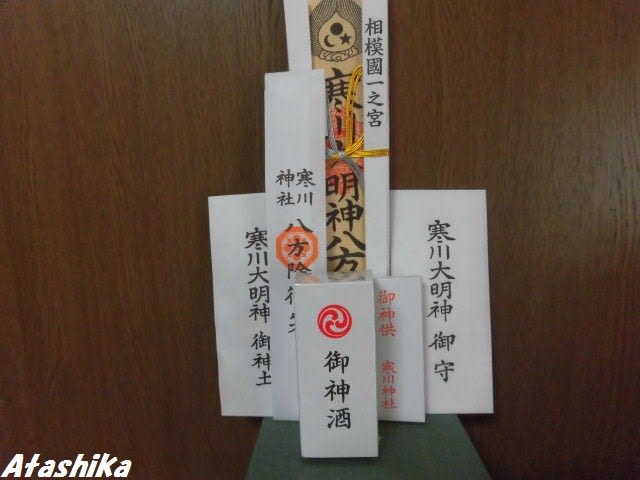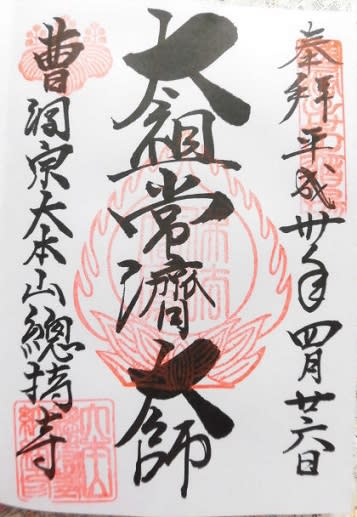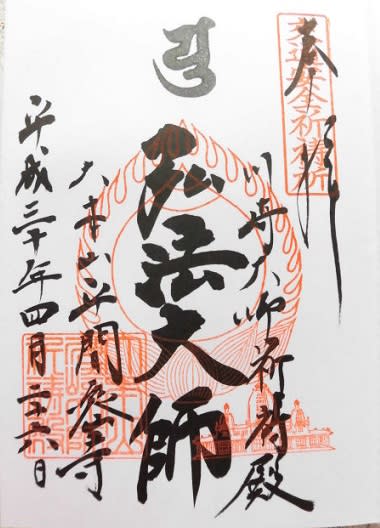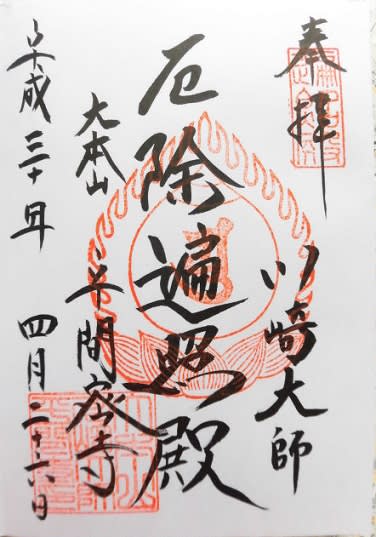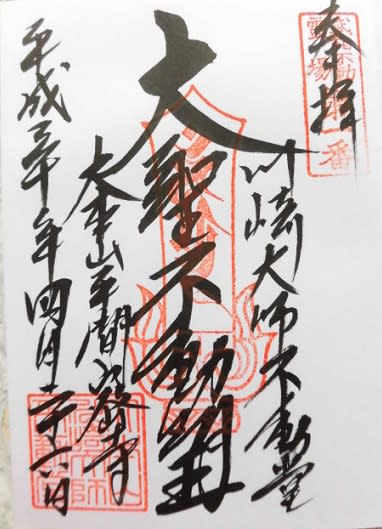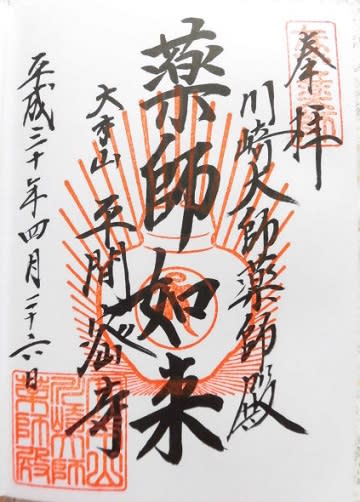毎年恒例にしていた富士山一周浅間神社巡りをやっと昨日行ってきました。全国的の快晴とのこと、狙って出かけたのです。
早朝東名で、サイドを確認しないバカな外車に驚かされましたが、それ以外は順調な旅でした。6時半出発帰宅は17時でした。国道139号で事故がありその後始末で大渋滞が付近で発生、その余韻に巻き込まれたからです。
毎年お詣りしておりますので神社の情報はそれほどありませんが、快晴のため写真を撮った所もありそれを併せて紹介します。
1.富士山本宮浅間大社

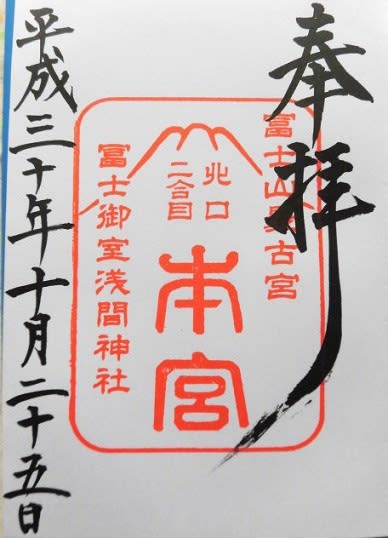
基本的にはお参りに際して撮影はしないのですが、あまりの快晴に誘われていくつか撮影しました。

第2駐車場から三之鳥居を通り楼門を望みます。左手にありますのが立派な手水舎です。

楼門をくぐり拝殿を望みます。拝殿の奥に見えるのが、本殿です。

1604年家康が造営した特殊な浅間造りと言われる2階構造の本殿です。重文です。

ブラタモリでも有名な御手洗橋から富士山を望みました。富士山をすっぽり隠す雲がわいたり消えたりしてました。

偶々頂上を撮影したカットですが、後でこれが貴重な画像となりますか後ほどです。
早朝東名で、サイドを確認しないバカな外車に驚かされましたが、それ以外は順調な旅でした。6時半出発帰宅は17時でした。国道139号で事故がありその後始末で大渋滞が付近で発生、その余韻に巻き込まれたからです。
毎年お詣りしておりますので神社の情報はそれほどありませんが、快晴のため写真を撮った所もありそれを併せて紹介します。
1.富士山本宮浅間大社

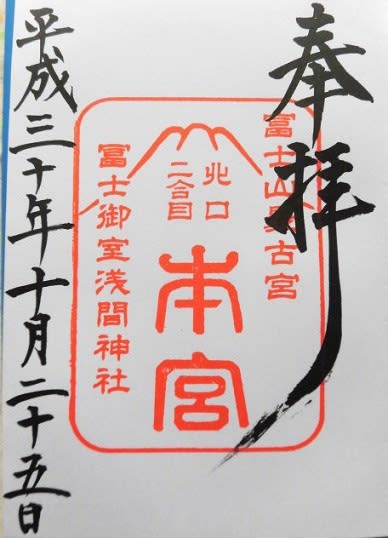
基本的にはお参りに際して撮影はしないのですが、あまりの快晴に誘われていくつか撮影しました。

第2駐車場から三之鳥居を通り楼門を望みます。左手にありますのが立派な手水舎です。

楼門をくぐり拝殿を望みます。拝殿の奥に見えるのが、本殿です。

1604年家康が造営した特殊な浅間造りと言われる2階構造の本殿です。重文です。

ブラタモリでも有名な御手洗橋から富士山を望みました。富士山をすっぽり隠す雲がわいたり消えたりしてました。

偶々頂上を撮影したカットですが、後でこれが貴重な画像となりますか後ほどです。