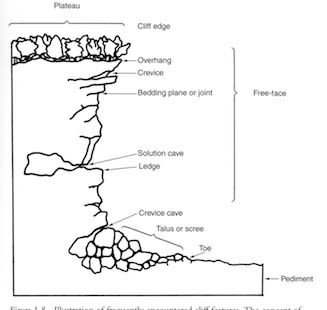ミヒャエル・エンデ(1929-1995年)はドイツの児童文学者ですが、「モモ」や「はてしない物語」など哲学的で文明批判的な作品を多数、世に出しています。「遺産相続ゲームー地獄の喜劇」(丘沢静也訳、岩波書店、1992年)は、1967年にフランクフルトで初演されたエンデの戯曲「ゲームをぶちこわす者たちー五幕の喜劇的な悲劇(Eine konnische Tragodie in funf Akten)」の全訳です。 とある宮殿に10人の遺産相続人が招集され、それぞれ、封筒に入れられた一枚の書き付けが手渡されます。10人が全員、協力しあって、亡き宮殿の主人の全ての言葉を綴り合わせれば遺産の何物かが得られるものを、お互いに疑心暗鬼となり、あるいは独り占めにしようとして協力せず、最後は全員が地獄の業火に焼き尽くされるというストーリーです。 登場人物は、保険会社社長とその家族、将軍、女教師、若い男性、女猛獣使い、前科のあるならず者、盲目の老農夫、家政婦、執事と公証人などです。それぞれの性格や思考パターンは世間で類型化されたもののいずれかに当てはまります。すなわち、読者は登場人物の一人を自分の代理人として投影しながら筋を追う一種の心理劇となっています。
この作品でエンデは、人間の愚かさ、自己破滅性を表現しようとしていますが、特別の主人公がいるわけでなく、登場人物すべてが解決しなければならない課題を均等に共有しています。エンデはその解説で、誰も悪人として登場するのではなく、みんなそれぞれ自分の想像とか行動基準から抜け出せないので、自分の置かれた状況にふさわしい行動を取る事ができない無能者、いいかえれば馬鹿者なのだと述べています。これはまた、現在の日本の社会の状況を言い表しています。一生懸命やっているように見えて、実は自分の利益や自己保身を思考の中心にしているために、目が曇って物事の連環やダイナミズムを理解できないのです。
これが書かれたのは、東西冷戦の真っ最中で、米ソは何百回も人類を死滅させるに足る核兵器を持ってにらみあっていました。すなわち、作品の背景には冷戦下での核戦争の可能性がありました。エンデは、解説でさらに次のように述べています。 「ヒロシマから核時代が出現し、それ以来何事も混沌として常軌を逸し、自殺にすら等しい行為を繰り返しました。そしていま相続人達が魔法の館に集まって、全員の共通の利益のために協力するのか、それとも、ぞっとするやり方で破滅するのか選択を迫られています」 しかし、こういった世界政治的なテーマとしてではなく、この戯曲を今日的に解釈すると、地球という人類が過去から受け継いだ大事な遺産を、相続人がそれぞれエゴを丸出しにして破滅させてしまうという寓話とも言えます。ローマクラブの報告「成長の限界」が出版されたのは1972年で、これの初演の5年後の事ですが、エンデは際限のない生産力とコントロールできない資源乱獲による地球環境の破壊により、人類が破滅の道へと突き進んでいることをすでに予見していたように思えます。この戯曲の悲劇的結末を予言して登場人物の一人は「もしも、この宮殿が破滅すると、その時は私たちも一千万マルクともども一緒に破滅するのよ。私たちは囚われの身なのを忘れないで」と叫んでいます。
このドラマでは舞台となる宮殿が重要な効果を持っています。最初、舞台になる宮殿は明るく輝いて色とりどりの鳥が群れになって自由に飛び回っています。しかし、ストーリーが展開するにつれ、壁や柱は傾き歪んでいき、あらゆる材出はボロボロになり、女人像や肖像画はミイラや骸骨に変容していきます。周りはむんむん照りつけるように暑く、鳥の死体が山となります。魔法にかけられたような宮殿が、地球そのものを暗喩している事は、こういった情景の推移によって分かります。 いずれにせよ、エンデの主張は、現代社会の破滅は多数の個々のプロセスの総和の結果にあるとしています。言い換えると社会の変革や矛盾の解決は、特定の政党や集団によるトップダウン的な操作によるのではなく、市民の個々人の連結を基盤としたボトムアップな力によるものでなければならないと言っていると思います。
追記 1(2021/05/27)
生産力崇拝思想とは?
現代の経済学と政治学は「社会に成長は絶対に不可欠」とする成長力思想にとりつかれている。資本主義も共産主義も生産力思想による経済成長を通じて、この世が天国になると考えており。ただその具体的な手法についてだけ、言い争っていただけだ。その背景には1)人口はこれからも制限無く増え続ける2)生活水準をあげるために必要というものであった。しかし1)人口については工業先進国では減少し始めていること2)生活水準も飽和していることから、この考えの矛盾が指摘されはじめた。一昔前までは、未知の大陸が成長の発展力であったが、現代では科学技術(イノベーション)がそれに替わっている(ユヴァル・ノア・ハラリ 『ホモ・デウス』河出書房 2018)。
追記2(2021/12/02)
資本主義はシャーロックの本姓、すなわち強欲を踏襲したシステムで人間の生活や地球環境にお構いなく利潤を求める。増資、増産、増人口の3つの歯車をフルに連結させ、ひたすら生産力に拍車をかけてきた。さすれば、資本主義の矛盾を弁証法的に止揚した共産主義の未来を予想したマルクスは、生産力思想をどのように分析し批判したのだろうか。それに取り組んだ労作が斎藤幸平の「人新生の資本論」(集英社2021)である。この書のまとまった評論はべつの機会にゆずりたい。この書は問題提議は適格だがマルクスびいきが災いして、本質が見抜けていないように思える。マルクスは労働の歴史的発展については詳しく分析したが、人類の発祥いらい、この種が地球環境とどのようにかかわってきたかを考察し、総括はしなかった(多分その時間がたりなかった)。この欠落が、後にスターリニズムや現代中国の鄧小平路線を生み出す背景になっている。