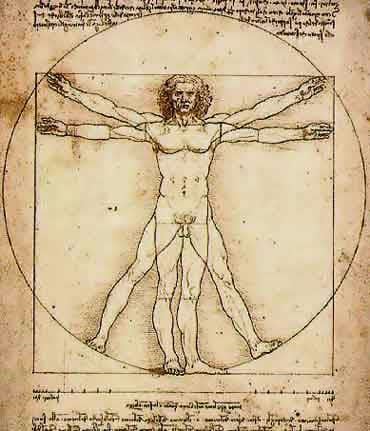GDPはなぜ毎年増加しなければならないとされていたのか?
いままでは、GDPは増え続けなければならないと考えらえていた。この成長神話の背景には、1) 地球のフロンティアは限りなくひろがっているという幻想、2)それと連動して人口も制約なしに増加するという幻想があった。こういった幻想を現実が、木っ端みじんに打ち毀しつつあることを本書はまず指摘する。西部開拓史のように未来が希望にあふれたフロンティアは消滅し、残された宇宙スペースは人類が快適にすめる空間ではない。文明諸国では政府の少子化対策にかかわらず人口は減りつづけている。資源のフロンティアが喪失しただけでなく収奪するべき安価な労働力のフロンティアがなくなりつつある。一時期、中国の膨大な安価な労働力を求めて日本を含めた資本はここに工場を建設したが、そこでの賃金の高騰をうけて、他の東南アジア諸国(ベトナム、タイなど)に移転しつつある。フロンティアが限界に到達したというだけでなく、人類の活動によって地球環境は破綻し、気候変動やパンデミックによって、とんでもない厄災が人々に降り注ごうとしている。それにも関わらず、資本主義と文明社会が、さらなる「発展」をもとめて、いかに悪あがきしているのかを、マルクス主義の立場から本書は批判・告発しようとする。
SDGs運動に象徴される「持続可能的な発展」や「緑の経済成長」は矛盾の外部転嫁にすぎない。外部転嫁には空間的なものと時間的なものがある。EV(電気自動車)や水素燃料自動車は都市部や文明国の局所的環境(都市)を保護し、周辺部の地方や他の国の環境を破壊している。おまけに地方の火力発電所が発生する炭酸ガスや廃棄ガスは回りまわって都市部にも到達した上、地球全体の温度環境を上昇させる。子供でもわかるこんな理屈を無視して成長路線で経済活動をつづける資本主義には、グレタ・テューンベリさんでなくても怒りがわいてくるというものだ。「中核部の廉価で便利な生活の背景には周辺部からの労働力の搾取だけでなく、資源の収奪とそれに伴う環境負荷の押し付けがある」と著者はいう(p33)。それゆえに地方や未開発国の収奪や環境破壊は、ここに棲む若者の離脱・過疎化を促進する。一方、都市はますます過密化し、その自然環境は劣化する。
洪水よ我が亡き後に来たれ!
矛盾の空間的転換だけでなく、時間的転嫁を資本主義は行なおうとしている。「炭酸ガスの排出量を制限して地球温暖化を防ごう」というスローガンはもっともらしが、これがまさに時間的転換である。「10年後に起こるクライシスを20年後までに引き伸ばそう、その間に、賢明なるホモ・サピエンスは科学の力で解決法を考えつく」と説諭するのである。余命宣告1年の末期がん患者に抗がん剤を投与して、生存期間を2~3カ月延ばすようなものだ。その間に魔法の抗がん剤が発明されるよ...。たとえ炭酸ガス問題をクリヤーする方法を発明しても、別の新たな矛盾が出てきて、世界は必ず暗礁にのりあげる。たとえば、低温核融合が完成したとする。これの燃料は水素(重水素H2、トリチュウムH3)なので、エネルギーは無尽蔵に供給される。CO2も出ないし、原子力発電のように危険な核燃料廃棄物も出ない。すなわち無限にクリアーなエネルギーを得ることができる。しかし、エネルギーが、たとえ無尽蔵でも、他の資源は有限なので、文明の律速物質が人類の経済を制約する(このクリティカルな「物」が何かは研究が必要である。おそらくレアーメタルのようなものではないかと著者はいう)。自然のフロンティアは有限かもしれないが、人の英知のフロンティア(イノベション)は無限であるという考えもある。しかし、どんなに工夫しても無から有は生じないし、どの分野にも収穫逓減の法則がある。世界における資源の総消費量は約1000億トンである。2050年には1800億トンがみこまれる。一方、リサイクルされているのはわずか8.6%。これでは持続可能性なんかありえない。ともかく、今が良ければ、未来社会の迷惑などでうでも良いというのが現代文明であり資本主義なのである。マルクスの資本主義分析は資本家でも参考にしているように、著者のグローバル資本主義分析は正鵠を得ている。
弁証法の魂は否定である。
マルクス哲学(思考法の基本)は唯物弁証法である。物と物の発展的な関係が、運動の法則の基盤をなすと考える。発展的な関係のベースには否定があると考える。ある時点でAの状態がBになるのは、Aを否定する力がはたらいてBになるからだ。資本主義では労働者の労働(価値)を否定(搾取)して、その価値を新たな資本に転換する。新たな資本は、そこでまた労働者を搾取する否定の循環が生じる。この資本による「労働の否定」を否定するのがマルクス主義である。否定こそが弁証法の魂であり、否定によってこそ世界は変転し進化する。マルクスはそのように考えた。社会における発展原理は、それぞれの時代で否定の主体である階級(あるクレードの人の集団)が存在したので明確である。
それでは資本主義による自然(地球)の否定(破壊・収奪)についてはどうなるのだろうか。著者(斎藤氏)によると、マルクスは社会と同様に資本主義が地球を収奪していると主張したとしている。はたしてどうか?マルクス自身もそのような事例を散発的に文献引用しているだけで、体系づけてこのテーマを展開していないように思う。そもそも、人類が自然を破壊してきたのは、石器時代、古代メソポタミア、アテネギリシャ時代からのこととされている。近代の産業革命以降になって規模が拡大した。ひょっとすると、原始人類が火を発明したあたりから自然破壊は始まったかも知れない。自然対資本主義ではなく、自然対人類とすれば、考え方は根本的に違ってくる。自然と人社会の矛盾を、一羽ひとからげに資本主義のせいにできないとすると、話が全然ちがってしまう。
エコロジストとしてのマルクス
斎藤氏によると対自然(地球)に対するマルクスの思想は生産力至上主義(1840-1850)、エコ社会主義(18860年代)、脱成長コミュニズム(1870-1880)と変遷(発展?)したとしている。最後の脱成長コミュニズムについては著者による新説である(多分)。ゴータ綱領批判の一節を引用するなどして、論じているが牽強付会の感をまのがれない。
この説と労働者の解放との関係についても何も述べていない。資本主義からの労働者と地球の解放はカプリングしたものであるはずだ。社会における資本による人の収奪にたいしてのマルクスの姿勢は明確である。教科書的には「共産党宣言」を読めばよい。労働者は団結して資本家を打倒することになる。それでは資本主義を廃止すればおのずと、地球に対する収奪はなくなるのだろうか? 著者によると、マルクスの書き物やノートで本としてまとめらえている部分はごく一部だそうだ。膨大な未収集の資料を編集して、欠落した思想を完成させる必要があるとすると大変な努力がいる。きっとマルクスAとマルクスBとか、いろいろなマルクス思想が出てくるだろう。なんとも気の滅入る話である。
著者はマルクスを引用して「否定の否定は、生産者の私的所有を再建することはkせず、協業と、地球と労働によって生産された生産手段をコモンとして占有することを基礎とする個人的所有をつくりだすのである」としている。著者は、さすがにこれではまずいと考えたのか、この後で、「コミュニズムはアソシエーション(相互扶助)に支えらえたコモン主義である」という論を展開している。環境学に出てくる「コモンズの悲劇」は、誰でも利用できる共有資源の適切な管理がされず、過剰摂取によって資源が枯渇してしまい、回復できないダメージを受けてしまうことを指摘した経済学における法則のことである。著者は分別のあったゲルマン民族のマルク協同体やロシアのミールを規範としているが、中世やロシア封建制の頃の生産システムや意識が、近代や現代にどのように適応できるのだろうか?
<労働と資本>の矛盾、<生産と自然>との矛盾の相互関係およびそれの超克の方法が、この書では明示されていない。これらは一元化されて解決できるのか、2元的に扱われのかといった問題が取りあつかえわれるべきテーマといえる。これは残念ながらどこにも見当たらない。
階級はどこにいったのか?
著者は矛盾の超克の具体的な方法として、ワーカーズ・コープ(労働者協同組織)というものを提唱する。これは労働の自治、自律に向けたもので、組合員が出資し経営し労働を営むものである。しかし資本主義と並行して、このようなシステムがあったとしても、競争に勝てるわけがない。これは資本の徹底廃棄の上で可能なものである。しかし資本家が、やすやすとそれを許すはずがなく必然的に厳しい階級闘争が起こる。「否定の否定」には断固とした意思としての階級が登場する必要がある。しかし、本書はマルクスを論じた著書にもかかわらず、階級という用語はほとんど出てこない(ケア階級という意味不明な言葉は出てくる)。階級闘争という言葉は、もうしわけ程度に一度出てくる (p214)。ここではバスターニの民主社会主義的コミュニズム批判がなされ階級闘争の視点が抜けていると批判しているが、著者の文脈にも総体として、それが抜けているのだ。その意味でも不思議な「資本論本」である。
感染症についての考察
コロナ禍を人新生の産物としている。しかし、中世のペストをはじめ古代からエピデミックやパンデミックの歴史は数しれない。近代資本主義のパンデミックは、スペイン風邪からと思えるが、それ以前のものとの質的・構造的な違いを明らかにしてほしかった。規模と速度の問題以外に、むしろ、その影響の質的な違いがあるはずである。さらに、余計な注文をつけると、ウイルス感染から「思想の実効再生産数R」についても考察してほしかった。起源ウイルスはたとえ一匹でRが2でも、短期間にパンデミックになる。一人の革命思想家ー共鳴グループー階級意思へと「思想感染」がおこる道筋(おそらくローマ時代のキリスト教の拡大に似た)のダイナミックスを疫学が提示してくれている。
分業による疎外の問題
資本主義労働による人間疎外は分業の徹底によっておこっている。生産手段や土地を共有するだけでは解決しない問題である。著者は個人の趣味(全体作業)によってそれが補完されるというが(p267)、それではあまりに寂しい。マルクスは「経済学・哲学草稿」において、労働によって人々が没落し貧困化するのは、労働と生産の間の直接的な関係における「労働の本質における疎外」にあるとしている。これはフォイエルバッハの人間主義的で自然主義的を基準にしたものである。資本主義的労働のもつ矛盾を自ら工場に入って経験したシモーヌ・ヴェイユは、それはまさに奴隷労働であるとのべた。ITの完備したモダンな事務所での労働もその本質は変わらない。彼女は人間は何によって偉大なのかを希求した。
総合評価
総合していうと、この本の著者は博覧強記の若手社会学者で様々な視点で問題提議してくれているが、マルクス思想の「筋」(疎外された労働、階級の問題)から外れているように思える。
参考文献
鈴木直 「マルクス思想の核心」NHKBOOKS 1237 NHK出版 2016
座小田豊 「マルクスー経済学・哲学草稿」(哲学の古典101) 親書館 1998
鎌田慧「自動車絶望工場」(講談社文庫2005)
片岡美里「シモーヌ・ヴェイユ ー真理への献身」(講談社1972)
追記:「マルクスは人間が自然に働きかける外に生きる道のないのをさとった。自然に働きかけるのが労働である。自然のもっている物質をとってこれを生産手段とした瞬間に人間は動物から分かれて人となった」と向坂逸郎は書いている(「マルクス伝」(新潮社1962)。そうならば道具の発明から人と自然の対立関係が発生していたのかもしれない。