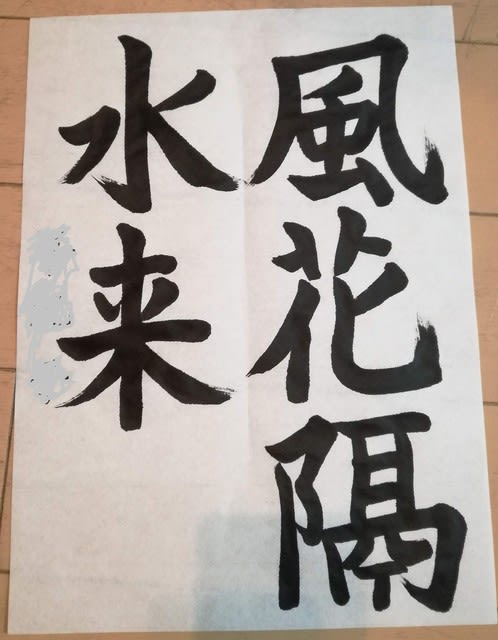書道の先生に、臨書について聞いている中で、臨書にどういう順番で取り組むかという話があった。
 ←ピアノでも、作曲家固定の人と、いろいろ弾く人がいますね。
←ピアノでも、作曲家固定の人と、いろいろ弾く人がいますね。
昔の中国の有名な書家というのは、もちろん王羲之だけでなくいろいろいるのですが、比較的初心者が取り組みやすい字体とそうでないもの、というのがあります。そして、取り組みやすいと思われる中にもいろいろいるけれど、
一人の書家の字をじっくり勉強してから次に移るのがよい
と
いろんな書家の字を併行して勉強していくのがよい
という両方の考え方があり、決着していない状態だとか。
ピアノでいうと、昭和のころはよく、ずーっとハイドンモーツァルトベートーベンばかり長い間やらせて、ショパンはあとから、ドビュッシーやラヴェルはもっとあとから、というのがありましたね…
今は「4期のピアノ」とかいって、毛色(時代)の違うものをいろいろバランスよく学んでいこうというのが主流でしょうか。
私の場合、「どう学ぶべきか」はさておき自分の好きなもの弾きたいものを弾く方針で、その結果いろいろ併行して(というか混ざりすぎ?)手をつけているわけですが、それで行くと「この書家はどんな感じなのかやっぱり書いてみたい」とかいっていろいろ手を広げていく未来が水晶玉に映っています(^^;;
おとといの書道教室で同じ時間帯に来ていた大人の生徒さんは、ひとりの書家の臨書をずーっと好きで続けている状態だそうなのですが、ちょうどそのとき、先生から「説得」されて昇段試験で出ている課題の「楷書」を書いていました。ふだんは「昇段しなくていいので」といって昇段試験はすっとばして好きな臨書をずっとやってるんだとか(笑)
それで久々に書いた「楷書」なのですが、先生も驚いたことにとても上達していたそうです。古典の「真似」を続けていることで、一般的な書体で書くのもちゃんとうまくなっていたのですね。
現代にも素晴らしい書家がたくさんいて、展覧会などで見てみんなが感嘆するような作品をつくっているはずですが、あえて古典(実物は見られず印刷したものを見るだけであっても)の真似をひたすら重ねる意義はどこにあるのでしょうか?
古典であるということは、長い時代を生き残ってきたということで、たとえば、モーツァルトとサリエリがどちらもその時代にあっては良い作曲家とされていたはずなのだけど、現在に至るまでのどこかで片方の作品は忘れ去られてしまっていて、なんか物好きな人がサリエリのピアノ協奏曲を演奏してYouTubeにアップしていたのを聞いたけどなんかつまんない曲…
これほんとに、その時代の人はモーツァルトくらいいいと思ったのかしらん?? 全然違うじゃない??
そういえば、ベートーベンとかショパンとか、そういった本物の大物というのは、田舎から出てくるのだという説を聞いたことはないですか?(今、それを誰から聞いたのか思い出そうとして思い出せない)
もっと「都会」であれば最新流行の曲がいっぱいあったはずなんだけれど、田舎には「時代遅れ」のものしかなくて、ショパンとかはバッハあたりをしっかり学んで育ったのだとか…ネットもなく出版物も今ほど手軽じゃない時代、情報弱者のはずのところからかえって大作曲家が育ってくる。
昨日、artomr先生から教えてもらったブーレーズの言葉:
「歴史的傑作というのは、その後の歴史に影響を与えたものだ」
からすれば、ショパンという新たな「歴史」に影響を与えたバッハは間違いなく歴史的傑作であった、と。
まぁ私は新たな歴史を作るわけじゃないんだけど、自分の楽しみを深める意味では十分「古典から学べ」は正しいと思います。そういえばベネットとか吉松隆とかはまだ古典じゃないよねぇ…私的にはかなりいい線いってるような気がするのですが。23世紀くらいの人から「なんであれがいいと思ったの?」とか言われてたりして。
あ、関係ないんですが、ベネット「スキップとセイディ」の録音があまりに悪かったので、shigさん撮影の動画と差し替えました。動画です。猫耳がうつってます…ただし逆光につき顔はわかりませんw
にほんブログ村 ピアノ ←ぽちっと応援お願いします
にほんブログ村 ヴァイオリン ←こちらでも
にほんブログ村 中高一貫教育

「はじめての中学受験 第一志望合格のためにやってよかった5つのこと~アンダンテのだんだんと中受日記完結編」ダイヤモンド社 ←またろうがイラストを描いた本(^^)
←またろうがイラストを描いた本(^^)

「発達障害グレーゾーン まったり息子の成長日記」ダイヤモンド社
昔の中国の有名な書家というのは、もちろん王羲之だけでなくいろいろいるのですが、比較的初心者が取り組みやすい字体とそうでないもの、というのがあります。そして、取り組みやすいと思われる中にもいろいろいるけれど、
一人の書家の字をじっくり勉強してから次に移るのがよい
と
いろんな書家の字を併行して勉強していくのがよい
という両方の考え方があり、決着していない状態だとか。
ピアノでいうと、昭和のころはよく、ずーっとハイドンモーツァルトベートーベンばかり長い間やらせて、ショパンはあとから、ドビュッシーやラヴェルはもっとあとから、というのがありましたね…
今は「4期のピアノ」とかいって、毛色(時代)の違うものをいろいろバランスよく学んでいこうというのが主流でしょうか。
私の場合、「どう学ぶべきか」はさておき自分の好きなもの弾きたいものを弾く方針で、その結果いろいろ併行して(というか混ざりすぎ?)手をつけているわけですが、それで行くと「この書家はどんな感じなのかやっぱり書いてみたい」とかいっていろいろ手を広げていく未来が水晶玉に映っています(^^;;
おとといの書道教室で同じ時間帯に来ていた大人の生徒さんは、ひとりの書家の臨書をずーっと好きで続けている状態だそうなのですが、ちょうどそのとき、先生から「説得」されて昇段試験で出ている課題の「楷書」を書いていました。ふだんは「昇段しなくていいので」といって昇段試験はすっとばして好きな臨書をずっとやってるんだとか(笑)
それで久々に書いた「楷書」なのですが、先生も驚いたことにとても上達していたそうです。古典の「真似」を続けていることで、一般的な書体で書くのもちゃんとうまくなっていたのですね。
現代にも素晴らしい書家がたくさんいて、展覧会などで見てみんなが感嘆するような作品をつくっているはずですが、あえて古典(実物は見られず印刷したものを見るだけであっても)の真似をひたすら重ねる意義はどこにあるのでしょうか?
古典であるということは、長い時代を生き残ってきたということで、たとえば、モーツァルトとサリエリがどちらもその時代にあっては良い作曲家とされていたはずなのだけど、現在に至るまでのどこかで片方の作品は忘れ去られてしまっていて、なんか物好きな人がサリエリのピアノ協奏曲を演奏してYouTubeにアップしていたのを聞いたけどなんかつまんない曲…
これほんとに、その時代の人はモーツァルトくらいいいと思ったのかしらん?? 全然違うじゃない??
そういえば、ベートーベンとかショパンとか、そういった本物の大物というのは、田舎から出てくるのだという説を聞いたことはないですか?(今、それを誰から聞いたのか思い出そうとして思い出せない)
もっと「都会」であれば最新流行の曲がいっぱいあったはずなんだけれど、田舎には「時代遅れ」のものしかなくて、ショパンとかはバッハあたりをしっかり学んで育ったのだとか…ネットもなく出版物も今ほど手軽じゃない時代、情報弱者のはずのところからかえって大作曲家が育ってくる。
昨日、artomr先生から教えてもらったブーレーズの言葉:
「歴史的傑作というのは、その後の歴史に影響を与えたものだ」
からすれば、ショパンという新たな「歴史」に影響を与えたバッハは間違いなく歴史的傑作であった、と。
まぁ私は新たな歴史を作るわけじゃないんだけど、自分の楽しみを深める意味では十分「古典から学べ」は正しいと思います。そういえばベネットとか吉松隆とかはまだ古典じゃないよねぇ…私的にはかなりいい線いってるような気がするのですが。23世紀くらいの人から「なんであれがいいと思ったの?」とか言われてたりして。
あ、関係ないんですが、ベネット「スキップとセイディ」の録音があまりに悪かったので、shigさん撮影の動画と差し替えました。動画です。猫耳がうつってます…ただし逆光につき顔はわかりませんw
にほんブログ村 ピアノ ←ぽちっと応援お願いします
にほんブログ村 ヴァイオリン ←こちらでも
にほんブログ村 中高一貫教育

「はじめての中学受験 第一志望合格のためにやってよかった5つのこと~アンダンテのだんだんと中受日記完結編」ダイヤモンド社

「発達障害グレーゾーン まったり息子の成長日記」ダイヤモンド社