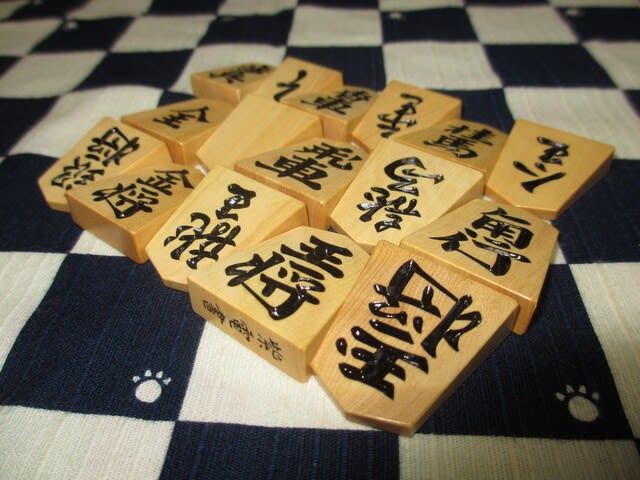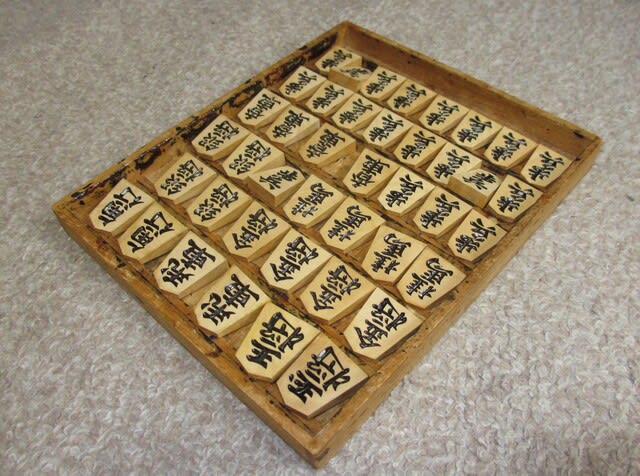木村名人の一字書です。
後戻りできないように、
玉将から彫り始めました。
直感なのですが、
いままで木村名人書が上手く作れなかった原因は複数あり、
その原因の一つがこの玉将のような気がしています。
何処とは言えないのですが、
字母紙どおりではなく、
ちょっと変えて彫っています。
文字の「座り」が良くなった気がしますが、
他の駒とのバランスを見て、
また直すかも知れません。
後戻りできないように、
玉将から彫り始めました。
直感なのですが、
いままで木村名人書が上手く作れなかった原因は複数あり、
その原因の一つがこの玉将のような気がしています。
何処とは言えないのですが、
字母紙どおりではなく、
ちょっと変えて彫っています。
文字の「座り」が良くなった気がしますが、
他の駒とのバランスを見て、
また直すかも知れません。
自宅に戻っております三田玉枝です。
作り直した駒が意外と馴染まず、
まだ白っぽいです。
隷書を見慣れている方は少なく、
使いにくいので出番が少ないのかも知れませんね。
あっ、手前の「と金」、
目止めが残っているので反射してますね。
後で直します。
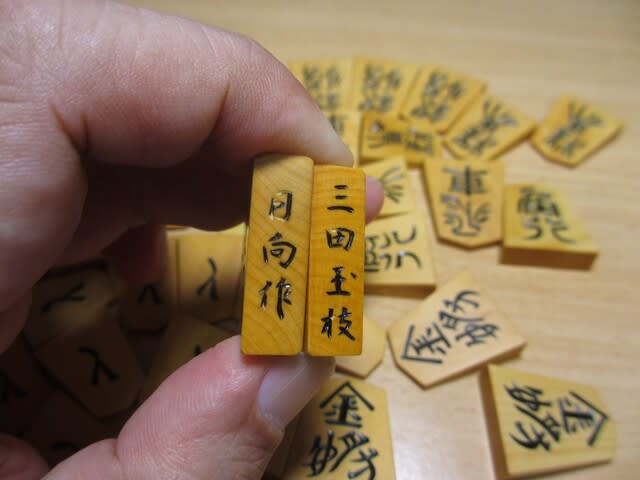
ついでに銘もやり直します。
作り直した駒が意外と馴染まず、
まだ白っぽいです。
隷書を見慣れている方は少なく、
使いにくいので出番が少ないのかも知れませんね。
あっ、手前の「と金」、
目止めが残っているので反射してますね。
後で直します。
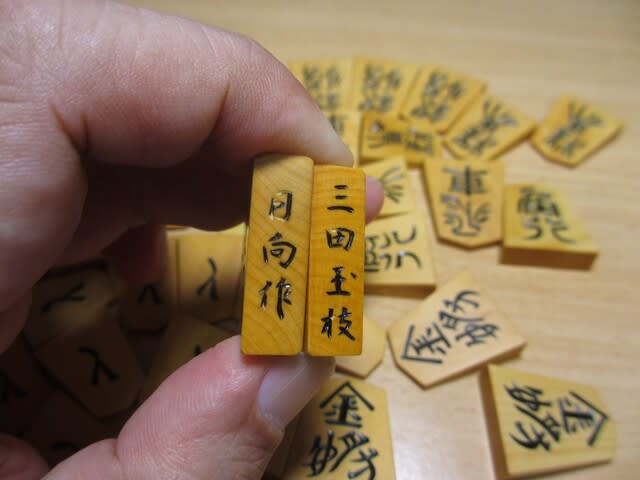
ついでに銘もやり直します。
十四世名人木村書です。
過去二回作ってますが、
どちらも不満が残ってしまった、
私にとっては苦手な書体です。
出来がかなり悪かった一回目の作品は、
戒めとして今でも手元に残しています。
木村文俊調の面長な木地を充て、
字母は一字に変更しました。
気合入れて作ります。
過去二回作ってますが、
どちらも不満が残ってしまった、
私にとっては苦手な書体です。
出来がかなり悪かった一回目の作品は、
戒めとして今でも手元に残しています。
木村文俊調の面長な木地を充て、
字母は一字に変更しました。
気合入れて作ります。
篁輝をメンテしています。
彫り埋め駒は、盤と接する面積が一番大きいので、
その分汚れやすいのが難点ですね。
ちょっとしか使ってないのに、
結構汚れていました。

あんまり上手く彫れていなかった、
駒尻の銘をついでに直します。
彫り埋め駒は、盤と接する面積が一番大きいので、
その分汚れやすいのが難点ですね。
ちょっとしか使ってないのに、
結構汚れていました。

あんまり上手く彫れていなかった、
駒尻の銘をついでに直します。
蜀紅です、彫り始めました。
完成した作品の数からして、
最も多く彫っているのが、
この蜀紅の歩兵かも知れません。
そのせいでしょうか、
滑らかにスタートできました。
蜀紅は故・八代目駒権師を代表する書体、
彫駒が最も似合う書体です。
完成した作品の数からして、
最も多く彫っているのが、
この蜀紅の歩兵かも知れません。
そのせいでしょうか、
滑らかにスタートできました。
蜀紅は故・八代目駒権師を代表する書体、
彫駒が最も似合う書体です。
紫電です。
水研ぎをして、乾燥させているところです。
この段階では、余分な漆がまだ残ってますので、
ちゃんと出来ているか否かは、
まだ分かりません。
ただ、一番怖がっていた漆の滲みは無い様です。
完全に乾いたら、研磨の作業に入ります。
水研ぎをして、乾燥させているところです。
この段階では、余分な漆がまだ残ってますので、
ちゃんと出来ているか否かは、
まだ分かりません。
ただ、一番怖がっていた漆の滲みは無い様です。
完全に乾いたら、研磨の作業に入ります。
次の作品の準備に入ります。
こちらもお客様からご支給頂きました、
御蔵島黄楊斑入りの柾目で作る、
蜀紅(しょっこう)です。
蜀紅を作るのは6回目になりますが、
前回作った時から一年半も経っているので、
気持ちは新鮮です。
書体と木地のバランスは良いと思います。
こちらもお客様からご支給頂きました、
御蔵島黄楊斑入りの柾目で作る、
蜀紅(しょっこう)です。
蜀紅を作るのは6回目になりますが、
前回作った時から一年半も経っているので、
気持ちは新鮮です。
書体と木地のバランスは良いと思います。