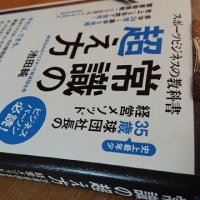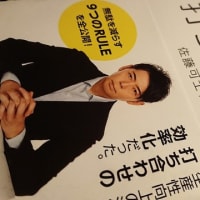この本を評価できるほどファイナンスの知識があるわけではないが、学者による入門書というより実務家による「チャート式」のような感じの本である。理論が展開されるよりも、実際のケースに応用する際には何に留意すべきかについて詳しく書かれている。この本を読んでいるときは本当にわかったような気持ちになる。
ファイナンスは、事業・企業の現在価値を求めることが基本である。
事業・企業価値=Σ(p期間のFCF/(1+WACC)のP乗)
この式でフリーキャッシュフローをもとめ(分子部分)、リターンとリスクが織り込まれたWACCで割り引く(分母部分)。
この分子部分の説明では、第7章の「DCF法」がとてもわかりやすい。キャッシュフローの算定方法やNPV法、IRR法の説明はこの本が一番よい。
実際のWACCの計算は第8章の「投資の意思決定におけるリスク分析」が参考になる。余計なことは考えずにこうすればよいというような書き方ではあるが。
実務で財務などに携わっていない者にとってファイナンスは本当に難しいと思う。
入門者には『ざっくりわかるファイナンス』→『道具としてのファイナンス』→『MBAファイナンス』→『ファイナンシャル・マネジメント』→『コーポレート・ファイナンス』という順序で本を読むのがよいと思う。
しかし、覚えても数ヶ月でファイナンスの知識は忘れてしまっている。
その度に上の順序で本を読んで思い出すことにしている。というよりいつも『ざっくりわかるファイナンス』のレベルで止まっているようにも思う。
ファイナンス音痴の悩みは深い。
ファイナンスは、事業・企業の現在価値を求めることが基本である。
事業・企業価値=Σ(p期間のFCF/(1+WACC)のP乗)
この式でフリーキャッシュフローをもとめ(分子部分)、リターンとリスクが織り込まれたWACCで割り引く(分母部分)。
この分子部分の説明では、第7章の「DCF法」がとてもわかりやすい。キャッシュフローの算定方法やNPV法、IRR法の説明はこの本が一番よい。
実際のWACCの計算は第8章の「投資の意思決定におけるリスク分析」が参考になる。余計なことは考えずにこうすればよいというような書き方ではあるが。
実務で財務などに携わっていない者にとってファイナンスは本当に難しいと思う。
入門者には『ざっくりわかるファイナンス』→『道具としてのファイナンス』→『MBAファイナンス』→『ファイナンシャル・マネジメント』→『コーポレート・ファイナンス』という順序で本を読むのがよいと思う。
しかし、覚えても数ヶ月でファイナンスの知識は忘れてしまっている。
その度に上の順序で本を読んで思い出すことにしている。というよりいつも『ざっくりわかるファイナンス』のレベルで止まっているようにも思う。
ファイナンス音痴の悩みは深い。