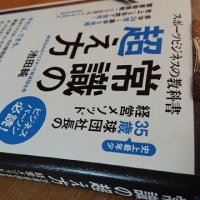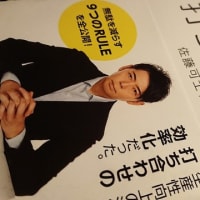人間には二種類の脳(大脳辺縁系と大脳新皮質または扁桃核と前頭前野)、二種類の知性(考える知性と感じる知性)があり、人生をうまく生きられるかどうかは、両方の知性のバランスで決まる(p.64)という考え方は、実感としてよくわかる。
けれど自分の日常生活を振り返ると、人を見るとき、無意識に考える知性としてのIQ的な側面を重視しがちだと思う。感じる知性としてのEQは意識していないと本当に相手の行動や自分の行動を理解できないだろう。
EQの定義は、(1)自分自身の情動を知る (2)感情を制御する (3)自分を動機づける (4)他人の感情を認識する (5)人間関係をうまく処理する という知能のこと (p.85~87) 。これらの知能は生理学的には大脳辺縁系や扁桃核の働きが重要になっている。
この本を読んでから、人を見るときに脳の周辺を見るのではなく、「この人の頭の中心部は今どうなっているんだろう」という眼で気持ちや感情との関係で見るようになった。
EQ(こころの知能指数:Emotional Intelligence Quotient)が提唱された背景は、IQ(知能指数:Intelligence Quotient)が偏重される社会への批判だということはよくわかる。
ただ、IQを測る知能検査はもともと、児童や成人に知的発達の遅れの問題がないかどうかを調べるためのものであり、IQはその測定のために便利な表記法として編み出されたものだった(大学時代、一応心理学専攻でした)。それが健常者に普及して学習指導などに応用されるようになってから、社会的にIQという尺度で人間の資質を比較できるかのようなおかしな価値観が根付いてしまったのだと思う。
訳者あとがきにも触れられている以上にいまやEQテストが大学生の就職指導や企業人事で広く使われている。こういう現象をどう理解してよいのかわからない。EQを数値化して他人と比べることは社会の価値観として正しいことなのだろうか。EQがIQと同じように人間の資質を比較できるかのようなおかしな尺度として根付かないようにすべきだと思う。
EQは意識的に変えることが可能だと著者は言っている。とくに発達過程においてのほうが変容しやすいのはよくわかる。
大人になってから、感情のコントロールをどのように行うのかは難しい課題だ。
怒りを抑えることも難しいが、自分を鼓舞することも難しい。
生理学的には、脳の中核あたりは下等動物の方が比重が大きい。
人間は野性から離れていくにつれて、脳の外側が発達してきた。脳の中核は野性的なものが残っているのだ。しかし、この野性的な部分がないと喜怒哀楽も動機づけられることもない。
知性と野性のバランスは難しい。
スタートレックのミスター・スポックの悩みはよくわかる。
けれど自分の日常生活を振り返ると、人を見るとき、無意識に考える知性としてのIQ的な側面を重視しがちだと思う。感じる知性としてのEQは意識していないと本当に相手の行動や自分の行動を理解できないだろう。
EQの定義は、(1)自分自身の情動を知る (2)感情を制御する (3)自分を動機づける (4)他人の感情を認識する (5)人間関係をうまく処理する という知能のこと (p.85~87) 。これらの知能は生理学的には大脳辺縁系や扁桃核の働きが重要になっている。
この本を読んでから、人を見るときに脳の周辺を見るのではなく、「この人の頭の中心部は今どうなっているんだろう」という眼で気持ちや感情との関係で見るようになった。
EQ(こころの知能指数:Emotional Intelligence Quotient)が提唱された背景は、IQ(知能指数:Intelligence Quotient)が偏重される社会への批判だということはよくわかる。
ただ、IQを測る知能検査はもともと、児童や成人に知的発達の遅れの問題がないかどうかを調べるためのものであり、IQはその測定のために便利な表記法として編み出されたものだった(大学時代、一応心理学専攻でした)。それが健常者に普及して学習指導などに応用されるようになってから、社会的にIQという尺度で人間の資質を比較できるかのようなおかしな価値観が根付いてしまったのだと思う。
訳者あとがきにも触れられている以上にいまやEQテストが大学生の就職指導や企業人事で広く使われている。こういう現象をどう理解してよいのかわからない。EQを数値化して他人と比べることは社会の価値観として正しいことなのだろうか。EQがIQと同じように人間の資質を比較できるかのようなおかしな尺度として根付かないようにすべきだと思う。
EQは意識的に変えることが可能だと著者は言っている。とくに発達過程においてのほうが変容しやすいのはよくわかる。
大人になってから、感情のコントロールをどのように行うのかは難しい課題だ。
怒りを抑えることも難しいが、自分を鼓舞することも難しい。
生理学的には、脳の中核あたりは下等動物の方が比重が大きい。
人間は野性から離れていくにつれて、脳の外側が発達してきた。脳の中核は野性的なものが残っているのだ。しかし、この野性的な部分がないと喜怒哀楽も動機づけられることもない。
知性と野性のバランスは難しい。
スタートレックのミスター・スポックの悩みはよくわかる。