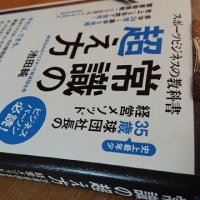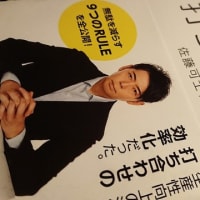経営学者らによる現代の戦争の分析からその戦略論を構築した意欲的な書。
こんなに素晴らしい着想による、吐き気がする本も珍しい。
戦争は科学技術や文化人類学などを変化させてきた。一般にはそれが科学や学問の「発展」と呼ばれている。
この本では戦争を戦うための戦略論自身が古くは孫子の時代から二度に渡る世界大戦、中東、朝鮮、ベトナムなどの戦争で「発展」してきたことを理論化している。
経営における戦略論の進化のために、実際の戦争における戦略論を分析するという着想は素晴らしい。ストレートをど真ん中に投げ込む小気味よさがある。しかし、経営における戦略論と戦争における戦略論とは根本的に違うように思える。
大きな違いは、「人を殺すこと」を手段として肯定するかどうだ。経営戦略の失敗により、公害などで人が死亡する場合がある。これはあくまで失敗である。しかし、戦争では人を殺すことも手段として肯定され、ときに手段が目的に変わることもある。
ベトナム戦争中期ではアメリカ、北ベトナムともにお互いに相手の士気を削ぐためにより多くの人を殺すことを目指していた。こういう戦記の記述を読むのは比喩ではなく本当に吐き気がする。
しかし、この本の戦略論としての面白さは、「転機・逆転」がテーマに据えられていることにもある。中国の国民政府軍に対抗した毛沢東の反「包囲討伐」戦、第2次世界大戦下でドイツ軍の侵攻をソ連軍が食い止め反撃に転じたスターリングラードの攻防戦、「小国」が「大国」を退ける結果となったベトナム戦争など戦略によって「逆転の契機」が生まれたことがわかる。
戦争における戦略とは何か。
戦略には、大戦略、軍事戦略、作戦戦略、戦術、技術、の5つのレベルがある。各レベルには独自の解決すべき課題があり、固有の文脈を持っている。
一方、戦略は、各々独立した意図を持つ主体間の相互作用である。それぞれ主体が互いに戦闘意志を持つ場合、我の行為に対して相手(敵)が反応し、それに対して我が対抗する、という作用-反作用が繰り返される。(p.393)
クラウゼヴィッツは戦争を「拡大された決闘」であり「政治の延長」と捉えた。その後、戦争における戦略論はより科学的、分析的アプローチをとり、とくにアメリカで発展する。一方、<作用-反作用>概念を独自に解釈した毛沢東は「弁証法」への適用により、ゲリラ戦の組織化という新たな戦略論の発展に寄与したらしい。これがベトナム解放軍によりさらに発展する。
ベトナム戦争を指揮したマクナマラはこう言っている。
「われわれは正しいことをしようと努めたのですが、そして正しいことをしていると信じていたのですが、われわれが間違っていたことは歴史が証明している」
これはミンツバーグが批判するように、マクナマラがハーバード・ビジネススクール出身かどうか以前の問題である。
経営における戦略と戦争における戦略をつなぐのは難しい、と思う。
しかしこの本の著者ら経営学者が戦争から引き出した10の戦略の本質だけ見れば、経営によく当てはまる。
弁証法、目的、場の創造、人、信頼、言葉、本質洞察、社会的に創造される、義、賢慮。
孫子が古代中国の兵法から得た教訓を経営に当てはめるのはまだ可愛い。しかし、朝鮮戦争やベトナム戦争の兵法から得た教訓を経営に当てはめるのはあまりにも生々しすぎるのではないか。
この本が経営の現場で引用されないことを祈る。
こんなに素晴らしい着想による、吐き気がする本も珍しい。
戦争は科学技術や文化人類学などを変化させてきた。一般にはそれが科学や学問の「発展」と呼ばれている。
この本では戦争を戦うための戦略論自身が古くは孫子の時代から二度に渡る世界大戦、中東、朝鮮、ベトナムなどの戦争で「発展」してきたことを理論化している。
経営における戦略論の進化のために、実際の戦争における戦略論を分析するという着想は素晴らしい。ストレートをど真ん中に投げ込む小気味よさがある。しかし、経営における戦略論と戦争における戦略論とは根本的に違うように思える。
大きな違いは、「人を殺すこと」を手段として肯定するかどうだ。経営戦略の失敗により、公害などで人が死亡する場合がある。これはあくまで失敗である。しかし、戦争では人を殺すことも手段として肯定され、ときに手段が目的に変わることもある。
ベトナム戦争中期ではアメリカ、北ベトナムともにお互いに相手の士気を削ぐためにより多くの人を殺すことを目指していた。こういう戦記の記述を読むのは比喩ではなく本当に吐き気がする。
しかし、この本の戦略論としての面白さは、「転機・逆転」がテーマに据えられていることにもある。中国の国民政府軍に対抗した毛沢東の反「包囲討伐」戦、第2次世界大戦下でドイツ軍の侵攻をソ連軍が食い止め反撃に転じたスターリングラードの攻防戦、「小国」が「大国」を退ける結果となったベトナム戦争など戦略によって「逆転の契機」が生まれたことがわかる。
戦争における戦略とは何か。
戦略には、大戦略、軍事戦略、作戦戦略、戦術、技術、の5つのレベルがある。各レベルには独自の解決すべき課題があり、固有の文脈を持っている。
一方、戦略は、各々独立した意図を持つ主体間の相互作用である。それぞれ主体が互いに戦闘意志を持つ場合、我の行為に対して相手(敵)が反応し、それに対して我が対抗する、という作用-反作用が繰り返される。(p.393)
クラウゼヴィッツは戦争を「拡大された決闘」であり「政治の延長」と捉えた。その後、戦争における戦略論はより科学的、分析的アプローチをとり、とくにアメリカで発展する。一方、<作用-反作用>概念を独自に解釈した毛沢東は「弁証法」への適用により、ゲリラ戦の組織化という新たな戦略論の発展に寄与したらしい。これがベトナム解放軍によりさらに発展する。
ベトナム戦争を指揮したマクナマラはこう言っている。
「われわれは正しいことをしようと努めたのですが、そして正しいことをしていると信じていたのですが、われわれが間違っていたことは歴史が証明している」
これはミンツバーグが批判するように、マクナマラがハーバード・ビジネススクール出身かどうか以前の問題である。
経営における戦略と戦争における戦略をつなぐのは難しい、と思う。
しかしこの本の著者ら経営学者が戦争から引き出した10の戦略の本質だけ見れば、経営によく当てはまる。
弁証法、目的、場の創造、人、信頼、言葉、本質洞察、社会的に創造される、義、賢慮。
孫子が古代中国の兵法から得た教訓を経営に当てはめるのはまだ可愛い。しかし、朝鮮戦争やベトナム戦争の兵法から得た教訓を経営に当てはめるのはあまりにも生々しすぎるのではないか。
この本が経営の現場で引用されないことを祈る。