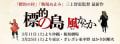[※ ↑「世界を照らす日本国憲法/次世代につなげる願い」「裏金議員に送る言葉は「汚れた手で憲法にさわるな」」(週刊金曜日 1470号、2024年4月26日・05月03月合併号)](https://twitter.com/ActSludge/status/1783821873312411852) (2025年05月02日[金])
(2025年05月02日[金])
《ミサイルよりコメを!》(社民党の参院選公約)。
軍事費倍増って、バカなのか? 鈴木宣弘さん《食料と農業を守ることが安全保障》。《兵糧攻め》に対して、兵器でも喰うのかね? 《コメの生産量が圧倒的に不足していることが露呈している。すべての国民にとって直接的で最重要課題である「食」の危機が可視化》(長周新聞)…カルト協会とヅボヅボな「利権」「裏金」「脱税」党や下駄の雪党、お維、コミに投票するからこうなる。自民党政権の無能ぶりが露呈し、可視化された訳で、それでも、自公お維コミに投票し続けるというのならば、最早、言葉も無い。《減反政策によるコメの生産調整》、転作奨励…これのどこが食料安全保障になるのか。ニッポンの《有事》は少子化(浜田敬子さん)問題も放置しっぱなしの無能ぶり。支持者や投票者も含めて、彼ら、彼女らは、トンチンカンな国・ニッポンが消滅することを願っているのでしょうか?
この農家の言葉をどう思いますか? ―――――― 《私の場合、大まかに計算すると収穫した米のうち250俵分を備蓄用米として1万円で売り、400俵分を通常の買取価格2万円で売るという計算になる。だが、このたび国が放出した備蓄米の落札価格は1俵2万円以上もしたというニュースを見て、驚くと同時に本当に怒りが湧いた。農家から通常の半値の1万円で買い上げた備蓄米を、「価格の高騰を解消する」といいながら、倍の値段で売りつけるのだ。政府がやっていることは、政府自身が犯人扱いする転売ヤーと何ら変わりないではないか》(長周新聞)。ブログ主も、激しい怒りしか湧かない。
『●「令和の百姓一揆」…《実質自給率は9・2%…おそるべき数字》《食料と農業
を守ることが安全保障》だというのに、借金という〝禁じ手〟で軍事費倍増』
『●【こちら特報部/「時給10円」の衝撃…農家は「令和の百姓一揆」を決意
した…】…社民党の参院選公約「がんこに平和 ミサイルよりコメを!」』
長周新聞の記事【食料安全保障めぐり熱い論議 福井・富山で「ごはん会議」 コメと乳製品の市場開放狙う米国 “食の危機転換するのは今”】(https://www.chosyu-journal.jp/shakai/34703)によると、《れいわ新選組が鈴木宣弘氏(東京大学大学院特任教授)を講師に迎え、全国各地でおこなっている「ごはん会議」が11日と12日、福井県福井市と富山県富山市で開催された。福井県はコメの大産地であり、コシヒカリを産んだ県でもある。また富山県は米騒動発祥の地であり、現在は水稲種もみの生産量と県外出荷量が日本一の「種もみ王国」として全国のコメ生産を支えている。全国的なコメ不足により価格が高騰し高止まりするなか、政府の備蓄米放出も「焼け石に水」の状態で、コメの生産量が圧倒的に不足していることが露呈している。すべての国民にとって直接的で最重要課題である「食」の危機が可視化されるなかで、多くの人々が日本の食料安全保障の問題について関心を高めている。全国のごはん会議では、そうした消費者の問題意識と、生産に従事する農家の問題意識が響き合い、熱い議論が交わされている》。
《ミサイルよりコメを!》…《日本の食料安全保障を強化するために農政を転換するのは今しかない》(長周新聞)。
長周新聞の記事【コメ農家から見た「令和のコメ騒動」 減反政策で農業潰してきた国 富山県の米農家に聞く】(https://www.chosyu-journal.jp/shakai/34722)によると、《本紙は11日と12日、れいわ新選組が東京大学大学院特任教授の鈴木宣弘氏を講師に招き、全国各地で開催している「ごはん会議」(全国21カ所で開催を予定)を取材した。会場では、日本の食料安全保障をめぐり真剣な議論が続いており、地元の生産者も多数参加している。そのなかで、富山県内で長年コメを生産してきた稲作農家から、現在大問題になっている「令和の米騒動」で明るみになった日本の農政の問題や、農業生産現場の実情について話を聞いた。以下、インタビューで農家が語った内容を紹介する。(文責・編集部)》。
『●食料と農業を守らないニッポン『乳牛をしぼればしぼるほど赤字になる。
まったく希望が持てない』…《兵糧攻め》に対して、兵器でも喰うのかね?』
(文化放送)【大竹まこと「日本の食料自給率は38%しかない」
防衛費が増えても”兵糧攻め”されれば……】
『●問題解決はとっても簡単だと思いますよ、軍事費倍増を止めればよいのです。
その分の税金を子供たちのため、教育のため、市民のために使えばよいだけ』
『●《誰もが豊かに生きていける社会にたどり着くまでに…未来はそのように
して変化を恐れずに、その時代を生きている人間が作っていくもの…》』
『●カネがない? 軍事費倍増を止めよ! 《突きつけられているのは、食料、
種、肥料、飼料などを海外に過度に依存していては国民の命を守れない…現実》』
(長周新聞)【「世界で最初に飢えるのは日本――食の安全保障を
どう守るか」 東京大学大学院農学生命科学研究科特任教授・
鈴木宣弘氏が下関市で講演】《鶏卵の国産率は97%というが、
エサが止まれば自給率は12%。ヒナが止まれば今でもほぼ0%だ。
それも含めて日本の食料自給率を計算し直す必要がある。現在の
食料自給率は38%ぐらいといっているが、
肥料や種の話は入っていない。さらに化学肥料原料の調達が
できなければ収量が半分になる。実質自給率はそれだけで22%だ。
さらに野菜の種の9割が輸入であることを考慮すれば
実質自給率は9・2%だ。おそるべき数字だ》
『●軍事費倍増して軍事国家となり下がり、やたらに戦争したがる一方で、
増税し、社会保障費を削りまくり、そんなにも狭量なニッポンにしたいのかね?』
『●軍事費倍増して軍事国家になり下がるというトンチンカンな国…ニッポンの
《有事》は少子化であり、食料と農業を守ることが安全保障である』
『●軍事費倍増して軍事国家になりたいニッポン…《なにか海外で事があれば食べ物
を手に入れることすらできない…脆い構造のうえに“食”が成り立っている》』
『●「令和の百姓一揆」…《実質自給率は9・2%…おそるべき数字》《食料と農業
を守ることが安全保障》だというのに、借金という〝禁じ手〟で軍事費倍増』
『●【こちら特報部/「時給10円」の衝撃…農家は「令和の百姓一揆」を決意
した…】…社民党の参院選公約「がんこに平和 ミサイルよりコメを!」』
=====================================================
【https://www.chosyu-journal.jp/shakai/34722】
コメ農家から見た「令和のコメ騒動」 減反政策で農業潰してきた国 富山県の米農家に聞く
2025年4月22日 (2025年4月16日付掲載)
(全国各地から集まった30台のトラックが都心を行進した
「令和の百姓一揆」(3月30日、東京都港区))
本紙は11日と12日、れいわ新選組が東京大学大学院特任教授の鈴木宣弘氏を講師に招き、全国各地で開催している「ごはん会議」(全国21カ所で開催を予定)を取材した。会場では、日本の食料安全保障をめぐり真剣な議論が続いており、地元の生産者も多数参加している。そのなかで、富山県内で長年コメを生産してきた稲作農家から、現在大問題になっている「令和の米騒動」で明るみになった日本の農政の問題や、農業生産現場の実情について話を聞いた。以下、インタビューで農家が語った内容を紹介する。(文責・編集部)
◇ ◇
私が住んでいる地域には、営農組合、大規模農家(10町以上)、小規模農家(10町未満)などさまざまな形態・規模の農家がおり、稲作をしている。
私は40年以上稲作をやってきた。現在は個人で7町の田を持っており、その他数人の仲間と営農組合を立ち上げ計13町の田で稲作をしている。今は高齢化が進み、私も70代後半にさしかかっており、後継者問題なども含め、この地域で稲作を受け継いでいけるかどうかはあと4~5年が勝負だ。
今、日本の農家のほとんどが年金をもらいながら稲作をしており、若手で専業農家をしながら生活していくのはかなり厳しい条件になっている。また近年は、年金の支給開始が65歳に引き上げられ、今後は70歳にまで引き上げられるともいわれている。「農家をするなら年金をもらいながらでないと難しい」といわれるが、一方で年金の支給が開始される65歳、70歳になってから農業を始めようと思ってもその頃には体力も衰えている。そのため、今後は農業を始める人はさらに少なくなっていくだろう。今以上に担い手不足が加速していくことは目に見えている。
コメ不足の根本的原因
今から50年以上前の1970年から、政府は「コメの生産が過剰だから消費量に合わせる」ということで、日本国内のコメの生産量を抑えるための食料安全保障を始めた。約50年にわたって続けられてきた減反政策によるコメの生産調整=減産が、現在のコメ不足の根本的な原因であり、減反はまちがった政策だったと思う。
減反政策では、政府はコメの生産をやめたり転作に協力する農家に補助金を出した。最初の頃の減反率は10%くらいで、富山ではコメの生産をやめる代わりに、所有している農地の10%分で大豆と大麦を作る農家が多かった。10%というごくわずかな量なので、機械も必要なく、手作業で刈りとりできたため農家の負担も少なかった。
だが、次第に減反率が増えていき、それにともない大豆や大麦の生産量も増えていった。収穫のために地域で大豆刈りとり専用のコンバインまで購入して減反に協力してきた。だが、大豆など作っていてももうからなくなり、次第に赤字生産の状態になっていった。
2017年に減反政策は終了したことになっている。たしかに国は農家に対する「生産数量目標」の通知はやめたが、一方で飼料用米や麦などへの転作補助金は支給しており、実質的な「生産調整」は続いている。富山県では減反政策当時の減反率が引き継がれており、大豆や大麦にかわって加工米、備蓄米、飼料米の生産が農家に勧められるようになった。
私は備蓄米と加工用米を作って毎年農協に出荷している。加工用米とは、味噌などの加工品のために安く流通するもので、農協から加工業者へと売られている。出荷したコメを備蓄用にするか加工用にするかは農協が調整して用途を決めている。
備蓄米放出にいいたい
こうして農家の作るコメを減産させながら備蓄米を集めてきた政府は、このたび「米価を抑える」といって放出を決めた。この備蓄米放出について、コメ農家としてどうしてもいいたいことがある。
私は、国が求める減反に協力するという名目で、耕地面積に対して約四割もの減反率を当てはめて、その分だけ備蓄米を作ってきた。
備蓄米の買取価格は、2023年産で1俵当り1万円、2024年産が1万1000円だった。これは政府からの補助も含めた金額だ。一方昨年のコメの価格は、概算金と追加支払いを合わせて2万円だったので、通常の半値で国に備蓄米を納めていることになる。私の場合、大まかに計算すると収穫した米のうち250俵分を備蓄用米として1万円で売り、400俵分を通常の買取価格2万円で売るという計算になる。
だが、このたび国が放出した備蓄米の落札価格は1俵2万円以上もしたというニュースを見て、驚くと同時に本当に怒りが湧いた。農家から通常の半値の1万円で買い上げた備蓄米を、「価格の高騰を解消する」といいながら、倍の値段で売りつけるのだ。政府がやっていることは、政府自身が犯人扱いする転売ヤーと何ら変わりないではないか。今回の備蓄米放出のやり方はあまりにもひどいし農家をバカにしている。私と同じように納得がいかず怒っている農家はたくさんいるはずだ。
これではコメの値段なんて下がるわけがない。日本政府は農家のことをなんだと思っているのか。一生懸命育てたコメを、政府の投機の具としてだましとられたような気がして、はらわたが煮えくりかえる思いだ。
本来なら、毎年この時期にはすでに農協から備蓄米の買取価格が通知されているはずだが、今年はまだ通知が来ていない。あの備蓄米の落札価格を見て、農家がどれだけ怒っているかは国も農協もよくわかっているはずだし、そんななかで農家に「今年も1万円で買いとります」なんて恐ろしくてとてもいえないのだろう。
結局、不足分に対してわずかな備蓄米の放出ではなんの効果もなく、価格は下がるどころか上がっている。これから先、放出を何度もくり返して果たして本当に米価が下がるのか。むしろ国は本気で米価を下げるつもりなどなく、「また次も放出してひともうけしてやろう」くらいのつもりなのではないか。それでいて、国会では「物価高対策」などといって、気休めの5万円給付で国民をだまそうとしている。
とにかく農家に対しても、国民に対しても無責任だ。誰もが「備蓄米を放出したのになぜ米価が下がらないのか」と疑問を抱いているはずだ。農家から預かったコメを「米価を下げる」といって放出したのなら、なぜ下がらないのか、放出したコメはどこへいったのか、責任を持って調査して国民に説明すべきだと思う。このままでは国民も農家も納得がいかないし、この矛盾と怒りは全国で拡大していくだろう。
もう一点、今回政府が放出した備蓄米のほぼすべてをJA全農が落札して買い上げ、そこから業者へ引き渡された。私は、今まで米価が低く抑えられてきたのは大手卸が安く買いたたいていたからだと思っていた。だが今回の備蓄米の入札を見てみると、他が太刀打ちできないほどの圧倒的な資金力で全農が買い占めており、今までの米価の低迷は何だったのかと思うと同時に、米価を安く抑えるという政府の方向性と足並みを揃え、全農そのものが米価を安く抑えていたのではないかと思えてならない。
国の生産見込み量と実際
(田植え作業に精を出す農家(山口県))
今、政府が確保している備蓄米がどれほど残っているのかは未知数だ。また、私の個人的な考えだが、政府が把握しているコメの生産量見込みと実際の生産量にはずれがある(実際よりも少ない)のではないかと思っている。
稲作農家ではコメを収穫した後に玄米の粒選別作業をおこなう。粒選別作業では、選別機で規定の粒径よりも大きい「良品」と、それよりも小さい「くず米」とに選別する。この選別機のふるいの網目の規格が10年ほど前から変わり、網目が少し大きくなってより多くのくず米が出るようになっている。
だいたい1反当り9俵の良品がとれていたが、現在は8・5俵くらいに減っている。そうしたギャップも少なからず影響しているのではないかと思っている。
また、農協にコメを出さずに消費者個人と直接取引する農家が増えているなかで、政府や農協が収量や流通を把握できないコメの割合も増えている。過去に比べて国のコントロールが効かなくなっているのは事実で、このままではその傾向はさらに進んでいくだろう。
機械の更新がネックに
物価高騰の影響で機械の値段も高くなっている。さらに大型化も進むなかで、少し故障しただけで多額の修理代がかかるようになっている。トラクターや田植機などは、1年のうち限られたごくわずかな時間しか使わないが、それでもなくてはならない機械だ。だが一度壊れると、多いときは500万~600万という修理代がかかる。だから機械が壊れたら「もういいや」といってやめていく高齢農家も増えている。また、今は続けられていても、「次に機械が壊れたときが辞め時だ」という農家も少なくない。
やはりどの農家にとっても、機械の更新が大きなネックになっている。営農組合では、集落にいるいくつかの農家が一つの組合を作り、最初は国の補助を受けて機械を購入して組合の皆で共同で使えるという利点がある。農家が一軒ごとにすべての農機具を揃える必要がなく、負担も少ない。
だが、やはり機械はだいたい15年くらいの周期で壊れてしまう。次の新しい機械に更新しなければならないのだが、そこに対する国の支援策が薄い。だから農業を続けることが難しくなる。そうして営農組合が解散した場合、規模を縮小して個人で農業を続けることは難しいため離農はさらに加速し、一気に放棄田が増えるだろう。
営農組合が全国で増えだしたのは今から約20年くらい前だと記憶している。今後はそうした組合が所有している機械が寿命を迎えることになり、新たに機械を更新して続けられるのかどうかという大きな壁に直面することになる。ここに対して国はなんとしても支援策を打ち出してほしい。
規模拡大がもつ問題点
政府は農業を経営的にとらえ、規模を拡大して生産コストを下げることで農業経営が成り立つと考えているようだ。富山県内では規模拡大のために、田の畔を改修して田1枚ごとの面積を広げる「基盤整備」が進められてきた。
たしかに作業効率は上がり、メリットもある。だが、実は大規模化すると一反当りのコメの収量は落ちる。
本来小さな田では、植え付ける前に撒く「元肥」と、出穂直前に穂の籾を充実させるために撒く「穂肥」の2回に分けて肥料を撒いていた。しかし大規模化して田の面積が大きくなると、2回に分けて肥料を撒くのは大変なので、最初にまとめて1回で済ませてしまう「一発肥料」にせざるをえなくなる。コメというのは手を掛ければ掛けるほどよく実るものだが、大規模化すると、稲の状態を見ながら細やかに対応するのが難しくなる。
また、田を大きくすると、畔を回って肥料を撒いたりすることもなくなるので、畔の草を刈らないケースもある。そのため、虫や病気の被害も受けやすくなるというリスクもある。
小さな田でこまめに手を入れると1反当たり9俵くらいのコメが収穫できるのに対し、大規模化するとそれが7~8俵へと収量が落ちる。
大規模化することで、たしかに農地や地域単位で見れば効率的に大量に収穫できるかもしれない。だが、日本の国土は限られている。そのため大規模農場ばかりを全国に拡大させるだけでは、日本全体で見れば必ずしも「効率的」に収量を確保できるということにはならない。だからこそ国は、中山間地をはじめ小さな田でも一生懸命稲作を続けているコメ農家のことも大事にして、稲作を続けられるように支えなければならないと思う。
若い担い手増やすには
7町の田で稲作をして、年収は150万~200万円。これで生活はぎりぎりだ。2町、3町とかの小さな田では完全に赤字経営になる。「農家の時給は10円」といわれているが、これは冗談ではない。現実だ。
集落営農で主力として頑張っている若手の農家に対しても、労働に見合った給料を手渡すことは難しく、この環境で農業に若い担い手を増やすことなどできるはずがない。私が暮らす市内では、約五割の農家が営農組合に所属し、地域の皆が共同で農業をしている。国はこうした農家をもっとしっかり支援してほしい。
そして、カロリーベースの食料自給率は38%と低いなか、主食のコメをはじめ、大豆や麦などの穀物の増産を本格的に進めていかなければ日本の食料自給率は今以上に低迷する。
対策としては、稲作が休みの時期に、国が農家に大豆や麦を作らせてそれをしっかり買い上げること。さらに機械の更新にかかる費用なども補助をすることで、国内全体の増産と、農家の所得向上を担保する政策を打ち出すべきだ。他国にできるのなら、日本にもできるはずだ。
今ならまだギリギリ間に合う。だが今の農政の方向性がこのまま続くのなら、高齢化と離農はさらに深刻化し、増産しようと思ったときにはもう働き手はいないだろう。これまで、「自由競争で勝つためには仕方がない」といって、「先祖代々の農地を守りたい」という農家の良心をも利用してタダ同然でコメが生産されてきた。そのなかで、続けたくても続けられなくなってやめていった農家もたくさんいたはずだ。これが今のコメ不足と価格高騰の根本原因だ。ようやく少しずつ問題が浮き彫りになりつつあるなかで、日本の食料安全保障を強化するために農政を転換するのは今しかない。
=====================================================
[↑ 雑誌「TIME」(2023.5.22・29)… (TBS NEWS DIG)《「日本を軍事大国に変えようとしている」との見出しは政府の申し入れのあと、変更》(https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/481736?display=1)] (2023年09月17日[日])
(2023年09月17日[日])
これもまた、10月下旬になってしまって、「6月ジャーナリズム」「8月ジャーナリズム」を語る…。アベ様とカースーオジサンによって敷かれた、そして、キシダメ政権によっても、いまも続く《メディアコントロール》下…そのジャーナリズムの重要性。最「低」裁を頂点とした司法も役立たずで、三権分立は何処に?
『●《どんな政権であろうと、新聞は権力監視の役割を放棄してはならない》
(東京新聞社説)…下足番新聞やアベ様広報紙に言っても詮無いこと』
『●《「現実離れしている」と叱責…マンネリ化が指摘》? でも、《戦争の
悲惨さと平和の大切さを伝え続ける意味は増している》<ぎろんの森>』
『●軍事国家となり軍事費を《増やせば日本が守れるというのは幻想》…
社説「関東防空大演習を嗤ふ」での桐生悠々の予見・予言に学ぶべきこと』
《新聞が言わなくなった先にあるのは、内外で多大な犠牲者を出した戦争であり、それが歴史の教訓》、《悠々の批判の矛先は、政府や軍部にとどまらず、権力におもねる新聞にも向けられていました》、《新聞を「輿論(よろん)を代表せずして、政府の提灯(ちょうちん)を持っているだけである」「今日の新聞は全然その存在理由を失いつつある」と批判》、《新聞は権力におもねらず、読者の期待に応えているか、常に自問自答する必要を感じざるを得ません》、《「言いたいこと」ではなく、権力者に対して「言わねばならないこと」を言い続けることが新聞など言論の役割》、《悠々が残した一連の言論は、権力と向き合う覚悟を、現代に生きる私たちにも問うています》。
2023年9月10日の東京新聞の【<社説>週のはじめに考える 桐生悠々が問う覚悟】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/276435?rct=editorial)によると、《きょう10日は、反戦、反軍の記者、桐生悠々=写真=が1941(昭和16)年、太平洋戦争の開戦直前に亡くなった命日です。今年で生誕150年。明治から大正、戦前の昭和にかけて藩閥政治家や官僚、軍部の横暴を痛烈に批判し続けた報道姿勢は今も、言論にたずさわる者のお手本です》。
『●政権交代の意義が完全に消えた日』
《▼「听う」は口を大きく開けてわらうことで、「莞う」は感じよく
ほほえむこと、「嗤う」はあざけりわらうことだ。軍国主義が台頭し、
言論弾圧が厳しさを増していた一九三三年、軍の空襲への備えを
嗤った新聞人がいた▼その人、桐生悠々が書いた
「関東防空大演習を嗤ふ」は日本の新聞史上、特筆すべき名論説
として、記憶される。首都上空で敵機を迎え撃つ作戦など滑稽極まる。
数機撃ち漏らせば、木造家屋の多い東京は炎上すると、彼は書いた
▼<阿鼻叫喚(あびきょうかん)の一大修羅場を演じ、
関東地方大震災当時と同様の惨状を呈するだらう…しかも、
かうした空撃は幾たびも繰返へされる可能性がある>。
この指摘が現実のものとなり、大空襲で東京の下町が壊滅、
十万の犠牲者を出したのは、四五年三月十日のことだ》
『●自公支持者を「嗤う」、あれで「採決」「可決」!?:
自公支持者も「听う」ことが出来なくなる日は近い』
「先の『読売』や『産経』、『アベ様の犬HK』などの
「アベ様の広報機関」とは違う、『東京新聞』の新聞人の矜持を
示す社説をご覧ください。2番目の記事の、つまり、
《桐生悠々の言葉。…「言いたい事」と「言わねばならない事」は
区別すべきだとし「言いたい事を言うのは権利の行使」だが、
「言わねばならない事を言うのは義務の履行」で「多くの場合、
犠牲を伴う」と書き残している》
……の部分を受け、社説の末尾には、《憲法を再び国民の手に
取り戻すまで、「言わねばならないこと」を言い続ける責任を
自らに課したい。それは私たちの新聞にとって
「権利の行使」ではなく「義務の履行」だからである》と
〆ています」
『●阿部岳記者「桐生悠々は訓練よりも
「実戦が、将来決してあってはならない」ことを訴えた…先見の明は…」』
「《桐生悠々は訓練よりも「実戦が、将来決してあってはならない」ことを
訴えた。…先見の明は、その後の空襲被害が証明している》訳です。
壊憲が進み、戦争できる国、戦争したい国へとひた走るニッポン。
ジャーナリズムの劣化もそれに拍車をかける」
『●Jアラート狂想曲: 「かつて関東上空での防空演習を
嗤った桐生悠々なら何と評するでしょうか」』
《北朝鮮が弾道ミサイル発射を繰り返し、国内では避難訓練も
行われています。かつて関東上空での防空演習を嗤(わら)った
桐生悠々なら何と評するでしょうか》
『●阿部岳さん、《基地問題への見解の違いも…
デマで攻撃された因縁も関係ない。今回は…産経の側に立つ》』
「東京新聞の社説【週のはじめに考える 権力と向き合う覚悟】…
によると、《◆全米の新聞、一斉に社説…◆言論の自由への危機感
…◆桐生悠々の奮闘を偲ぶ…あす九月十日は、四一年に亡くなった
悠々を偲(しの)ぶ命日です。百年という時を隔て、また日米という
太平洋を挟んだ国で同じように、新聞が連帯して時の政権に毅然(きぜん)
と向き合ったことは、民主主義社会の中で新聞が果たすべき使命を
あらためて教えてくれます。私たちは今、政権に批判的な新聞との
対決姿勢を強める安倍晋三政権と向き合います。悠々ら先輩記者や
米国の新聞社で働く仲間たちの奮闘は、私たちを奮い立たせ、
権力と向き合う覚悟を問い掛けているのです》。
《権力と向き合う覚悟》…無しなニッポンのマスコミではなかろうか…」
『●東京新聞《桐生悠々…にとって一連の言論は、
犠牲も覚悟の上で、言うべきことを言う義務の履行だった》』
「《「言いたいことを言うのは、権利の行使」だが
「言わねばならないことを言うのは、義務の履行」であり、
「義務の履行は、多くの場合、犠牲を伴う」》と。《桐生悠々…に
とって一連の言論は、犠牲も覚悟の上で、言うべきことを言う
義務の履行だった》。この度、アノ高市早苗氏が総務相に復活。
アベ様の政で〝唯一うまく行っている〟メディアコントロールの下、
《権力と向き合う覚悟》がマスメディアにはあるのだろうか?
《義務の履行》を果たしているか?」
『●《国会を開かなければ、それもできない。これを政治空白と言わず
して、何と言う。…国権の最高機関である国会の軽視も甚だしい》…』
『●「自民党総裁選を嗤(わら)う」新聞求む…《明治から大正、戦前期の
昭和まで、藩閥政治家や官僚、軍部の横暴を筆鋒鋭く批判し続けました》』
『●武田砂鉄さん《忘却に加担するのか、しっかり掘り返して問うのか、
メディアが問われている。またいつもの感じでやっているの…》』
『●桐生悠々に《ちなんだ社説の掲載に至ったのも、どんな政権であろうと、
新聞は権力監視の役割を放棄してはならないという決意を》読者に』
《社説「桐生悠々を偲(しの)んで」…。安倍、菅両政権の九年近くの
間、独善的な政治運営が続き、政治は私たちの望む、あるべき方向とは
全く違う道を進んでしまいました。でも、それを止める力が新聞には
まだある、義務を履行せずしてどうするのか、と読者の皆さんに
教えられた思いです。きのう始まった自民党総裁選後には衆院選が
あります。どんな政権ができようとも、私たちは
「言わねばならないこと」を堂々と言う新聞でありたいと考えます》
『●《どんな政権であろうと、新聞は権力監視の役割を放棄してはならない》
(東京新聞社説)…下足番新聞やアベ様広報紙に言っても詮無いこと』
=====================================================
【https://www.tokyo-np.co.jp/article/276435?rct=editorial】
<社説>週のはじめに考える 桐生悠々が問う覚悟
2023年9月10日 07時21分
きょう10日は、反戦、反軍の記者、桐生悠々=写真=が1941(昭和16)年、太平洋戦争の開戦直前に亡くなった命日です。今年で生誕150年。明治から大正、戦前の昭和にかけて藩閥政治家や官僚、軍部の横暴を痛烈に批判し続けた報道姿勢は今も、言論にたずさわる者のお手本です。
◇
本紙読者にはすっかりおなじみだと思いますが、桐生悠々について、おさらいをしてみます。
悠々は、本紙を発行する中日新聞社の前身の一つ「新愛知」新聞や長野県の「信濃毎日新聞」などで編集、論説の総責任者である主筆を務めた言論人です。
新愛知時代の18(大正7)年に起きた米騒動では、米価暴騰という政府の無策を、新聞に責任転嫁して騒動の報道を禁じた寺内正毅内閣を厳しく批判。社説「新聞紙の食糧攻め 起(た)てよ全国の新聞紙!」の筆を執り、内閣打倒、言論擁護運動の先頭に立って寺内内閣を総辞職に追い込みました。
信毎時代の33(昭和8)年の論説「関東防空大演習を嗤(わら)ふ」では敵機を東京上空で迎え撃つ想定の無意味さを指摘します。日本全国が焦土と化した歴史を振り返れば正鵠(せいこく)を射る内容でした。
しかし、在郷軍人会の抵抗に新聞社が抗しきれず、悠々は信州を離れて新愛知時代に住んでいた今の名古屋市守山区に戻り、34(同9)年から個人誌「他山の石」を発行して言論活動を続けます。
◆軍部台頭を厳しく批判
新聞社を辞めても、悠々の筆鋒(ひっぽう)(筆の勢い)が衰えることはありませんでした。他山の石は厳しい検閲で、しばしば発売禁止や削除の処分を受けながらも、軍部の台頭を厳しく批判し続けます。
例えば36(同11)年、旧陸軍の青年将校ら反乱部隊が首相官邸などを襲撃。当時の高橋是清蔵相らを殺害し、軍部の影響力が強まる契機となった二・二六事件です。
悠々は「だから、言ったではないか」との書き出しで「五・一五事件の犯人に対して一部国民が余りに盲目(もうもく)的、雷同的の讃辞(さんじ)を呈すれば、これが模倣を防ぎ能(あた)わないと」「軍部よ、今目ざめたる国民の声を聞け。今度こそ、国民は断じて彼等(かれら)の罪を看過しないであろう」と断罪しました。
しかし、その後の歴史を見ると悠々の警告むなしく、日本は破滅的な戦争へと突き進みます。
悠々は米国との戦争を避けるべきだと考えていました。他山の石ではニューヨーク・タイムズなどで編集者を務めたE・J・ヤング氏の著作を紹介し、米国とは「日本が今これを敵として戦うことは無謀の極(きわみ)であって」「倍旧の友情を温めるのが賢策である」と記しています。
日米の国力差はもちろん、当時の中国大陸や旧ソ連、さらに欧州にまで視野を広げて、国際情勢を冷静に見ていたのです。
こうした分析力は、海外の文献を丹念に読み込むことで磨かれていきます。悠々は名古屋で洋書を取り扱う丸善で当時、大学教授らをしのぐ最大の顧客でした。
悠々の批判の矛先は、政府や軍部にとどまらず、権力におもねる新聞にも向けられていました。
他山の石では当時の新聞を「輿論(よろん)を代表せずして、政府の提灯(ちょうちん)を持っているだけである」「今日の新聞は全然その存在理由を失いつつある」と批判しています。
今、新聞にたずさわる私たちにも耳の痛い指摘です。新聞は権力におもねらず、読者の期待に応えているか、常に自問自答する必要を感じざるを得ません。
◆言わねばならないこと
悠々は「言いたいこと」と「言わねばならないこと」とを明確に区別すべきだと考えていました。
「言いたいことを言うのは、権利の行使」だが、「言わねばならないことを言うのは、義務の履行」であり、「義務の履行は、多くの場合、犠牲を伴う」と、他山の石に書き残しています。
「言いたいこと」ではなく、権力者に対して「言わねばならないこと」を言い続けることが新聞など言論の役割なのです。
新聞が言わなくなった先にあるのは、内外で多大な犠牲者を出した戦争であり、それが歴史の教訓です。当時とは状況が違うとはいえ、岸田文雄内閣が進める防衛力の抜本的強化が、かつての軍備増強に重なります。
<蟋蟀(こおろぎ)は鳴き続けたり嵐の夜>
悠々が遺(のこ)した句です。もし今が再び<嵐の夜>であるならば、私たち新聞は<蟋蟀>のように鳴き続けなければなりません。
悠々が残した一連の言論は、権力と向き合う覚悟を、現代に生きる私たちにも問うています。
=====================================================
 (2022年09月15日[木])
(2022年09月15日[木])
《どんな政権であろうと、新聞は権力監視の役割を放棄してはならない》…下足番新聞やアベ様広報紙に言っても詮無いこと。毎日新聞や朝日新聞には《権力監視の役割を放棄》しないでもらいたい。
『●桐生悠々に《ちなんだ社説の掲載に至ったのも、どんな政権であろうと、
新聞は権力監視の役割を放棄してはならないという決意を》読者に』
《社説「桐生悠々を偲(しの)んで」…。安倍、菅両政権の九年近くの
間、独善的な政治運営が続き、政治は私たちの望む、あるべき方向とは
全く違う道を進んでしまいました。でも、それを止める力が新聞には
まだある、義務を履行せずしてどうするのか、と読者の皆さんに
教えられた思いです。きのう始まった自民党総裁選後には衆院選が
あります。どんな政権ができようとも、私たちは
「言わねばならないこと」を堂々と言う新聞でありたいと考えます》
東京新聞の【<社説>桐生悠々を偲んで 言論の覚悟を新たに】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/202017?rct=editorial)によると、《新聞が言わなくなった先にあるのは、内外で多大な犠牲者を出した戦争であり、それが歴史の教訓です。言論や報道に携わる私たちに「言わねばならないこと」を言い続ける覚悟があるのか。悠々の生き方は、そう問い掛けます》。
『●『学校が教えないほんとうの政治の話』(斎藤美奈子著)読了
…《あなたの政治的ポジションを見つけて…》』
《だいたいみんな、このごろ、まちがえてんのよね。
「偏らないことがいいことだ」「メディアは中立公正、
不偏不党であるべきだ」「両論を併記しないのは
不公平だ」。そういう寝言をいっているから、
政治音痴になるのよ、みんな。》
《あのね、政治を考えるのに「中立」はないの。メディアの役目は
「中立公正、不偏不党な報道」ではなく「権力の監視」なんです。
それ、常識。》
《党派性をもたずに政治参加は無理である。》
『●『国民のしつけ方』(斎藤貴男著)読了…
《それは調査報道…「番犬(ウォッチ・ドッグ)」としての役割》』
《ジャーナリズムの最大の存在意義は「権力のチェック機能」である。
…専門的には「番犬(ウォッチ・ドッグ)ジャーナリズム」理論という》
《「番犬ジャーナリズム」は、純粋培養の環境下にあるよりも、
一人ひとりのジャーナリストがもがき、苦悩しながら遂行していってこそ
成長し、民主主義社会に貢献できるのではないか》
1年前、… ―――――― 「自民党総裁選を嗤 (わら) う」新聞求む…アベ様およびカースーオジサンによる9年近くの《メディアコントロール》の頚木の打破を。―――――― と訴えたのですが、結果は惨憺たるものでした。それを継いだキシダメ氏の酷いこと…。
これも1年前…(東京新聞)《新聞などメディアは社会に寄り添い、世論を代表しているか。政府の言い分を垂れ流し、報道を規制されても公益のためと思考停止に陥っていないか》。…桐生《悠々は個人誌「他山の石」の発行で糊口(ここう)をしのぎます》…箕部幹事長の言う「他山の石」ならぬ、「自」山での「石」だらけ。例えば、腐敗した政権や数多のアベ様案件の責任をとらせてほしい。また、《平和憲法の下、歴代内閣が憲法違反としてきた「集団的自衛権の行使」は、安倍晋三前政権によって容認に転じました。防衛費の増額も続きます。新聞などのメディアが声を上げ続けなければ、平和主義は一瞬にして骨抜きにされるのは歴史の教訓です》…。状況は悪化しています。
『●政権交代の意義が完全に消えた日』
《▼「听う」は口を大きく開けてわらうことで、「莞う」は感じよく
ほほえむこと、「嗤う」はあざけりわらうことだ。軍国主義が台頭し、
言論弾圧が厳しさを増していた一九三三年、軍の空襲への備えを
嗤った新聞人がいた▼その人、桐生悠々が書いた
「関東防空大演習を嗤ふ」は日本の新聞史上、特筆すべき名論説
として、記憶される。首都上空で敵機を迎え撃つ作戦など滑稽極まる。
数機撃ち漏らせば、木造家屋の多い東京は炎上すると、彼は書いた
▼<阿鼻叫喚(あびきょうかん)の一大修羅場を演じ、
関東地方大震災当時と同様の惨状を呈するだらう…しかも、
かうした空撃は幾たびも繰返へされる可能性がある>。
この指摘が現実のものとなり、大空襲で東京の下町が壊滅、
十万の犠牲者を出したのは、四五年三月十日のことだ》
『●自公支持者を「嗤う」、あれで「採決」「可決」!?:
自公支持者も「听う」ことが出来なくなる日は近い』
「先の『読売』や『産経』、『アベ様の犬HK』などの
「アベ様の広報機関」とは違う、『東京新聞』の新聞人の矜持を
示す社説をご覧ください。2番目の記事の、つまり、
《桐生悠々の言葉。…「言いたい事」と「言わねばならない事」は
区別すべきだとし「言いたい事を言うのは権利の行使」だが、
「言わねばならない事を言うのは義務の履行」で「多くの場合、
犠牲を伴う」と書き残している》
……の部分を受け、社説の末尾には、《憲法を再び国民の手に
取り戻すまで、「言わねばならないこと」を言い続ける責任を
自らに課したい。それは私たちの新聞にとって
「権利の行使」ではなく「義務の履行」だからである》と
〆ています」
『●阿部岳記者「桐生悠々は訓練よりも
「実戦が、将来決してあってはならない」ことを訴えた…先見の明は…」』
「《桐生悠々は訓練よりも「実戦が、将来決してあってはならない」ことを
訴えた。…先見の明は、その後の空襲被害が証明している》訳です。
壊憲が進み、戦争できる国、戦争したい国へとひた走るニッポン。
ジャーナリズムの劣化もそれに拍車をかける」
『●Jアラート狂想曲: 「かつて関東上空での防空演習を
嗤った桐生悠々なら何と評するでしょうか」』
《北朝鮮が弾道ミサイル発射を繰り返し、国内では避難訓練も
行われています。かつて関東上空での防空演習を嗤(わら)った
桐生悠々なら何と評するでしょうか》
『●阿部岳さん、《基地問題への見解の違いも…
デマで攻撃された因縁も関係ない。今回は…産経の側に立つ》』
「東京新聞の社説【週のはじめに考える 権力と向き合う覚悟】…
によると、《◆全米の新聞、一斉に社説…◆言論の自由への危機感
…◆桐生悠々の奮闘を偲ぶ…あす九月十日は、四一年に亡くなった
悠々を偲(しの)ぶ命日です。百年という時を隔て、また日米という
太平洋を挟んだ国で同じように、新聞が連帯して時の政権に毅然(きぜん)
と向き合ったことは、民主主義社会の中で新聞が果たすべき使命を
あらためて教えてくれます。私たちは今、政権に批判的な新聞との
対決姿勢を強める安倍晋三政権と向き合います。悠々ら先輩記者や
米国の新聞社で働く仲間たちの奮闘は、私たちを奮い立たせ、
権力と向き合う覚悟を問い掛けているのです》。
《権力と向き合う覚悟》…無しなニッポンのマスコミではなかろうか…」
『●東京新聞《桐生悠々…にとって一連の言論は、
犠牲も覚悟の上で、言うべきことを言う義務の履行だった》』
「《「言いたいことを言うのは、権利の行使」だが
「言わねばならないことを言うのは、義務の履行」であり、
「義務の履行は、多くの場合、犠牲を伴う」》と。《桐生悠々…に
とって一連の言論は、犠牲も覚悟の上で、言うべきことを言う
義務の履行だった》。この度、アノ高市早苗氏が総務相に復活。
アベ様の政で〝唯一うまく行っている〟メディアコントロールの下、
《権力と向き合う覚悟》がマスメディアにはあるのだろうか?
《義務の履行》を果たしているか?」
『●《国会を開かなければ、それもできない。これを政治空白と言わず
して、何と言う。…国権の最高機関である国会の軽視も甚だしい》…』
『●「自民党総裁選を嗤(わら)う」新聞求む…《明治から大正、戦前期の
昭和まで、藩閥政治家や官僚、軍部の横暴を筆鋒鋭く批判し続けました》』
『●武田砂鉄さん《忘却に加担するのか、しっかり掘り返して問うのか、
メディアが問われている。またいつもの感じでやっているの…》』
=====================================================
【https://www.tokyo-np.co.jp/article/202017?rct=editorial】
<社説>桐生悠々を偲んで 言論の覚悟を新たに
2022年9月14日 06時56分
(桐生悠々)
九月十日は私たち記者の大先輩で反軍、抵抗のジャーナリスト、桐生悠々(きりゅうゆうゆう)=写真=を偲(しの)ぶ命日でした。世界を見回すと、悠々が活動していた時代同様、戦禍が絶えず、新たな戦争も始まりました。戦争の犠牲者はいつも、何の罪もない「無辜(むこ)の民」です。こんな時代だからこそ、悠々の命懸けの警鐘に耳を傾け、言論の覚悟を新たにしなければなりません。
◇
本紙読者にはおなじみだと思いますが、桐生悠々について、おさらいをしてみます。
悠々は、本紙を発行する中日新聞社の前身の一つ「新愛知」新聞や長野県の「信濃毎日新聞」などで編集、論説の総責任者である主筆を務めた言論人です。
明治から大正、戦前期の昭和まで、藩閥政治家や官僚、軍部の横暴を痛烈に批判し続けました。
新愛知時代の一九一八(大正七)年に起きた米騒動では、米価暴騰という政府の無策を新聞に責任転嫁し、騒動の報道を禁じた寺内正毅内閣を厳しく批判。社説「新聞紙の食糧攻め 起(た)てよ全国の新聞紙!」の筆を執り、内閣打倒、言論擁護運動の先頭に立ち、寺内内閣を総辞職に追い込みました。
信毎時代の三三(昭和八)年の論説「関東防空大演習を嗤(わら)ふ」では、敵機を東京上空で迎え撃つ想定の無意味さを指摘しました。日本全国が焦土と化した歴史を振り返れば正鵠(せいこく)を射たものですが、在郷軍人会の抵抗に新聞社が抗しきれず、悠々は信州を離れます。
(桐生悠々の遺族から寄託された「他山の石」
=金沢市の金沢ふるさと偉人館で)
◆発禁処分を乗り越えて
それでも悠々は、新愛知時代に住んでいた今の名古屋市守山区に移り、三四(同九)年から個人誌「他山の石」=写真=を月二回発行します。当局からたびたび発売禁止や削除の処分を受けながらも、四一(同十六)年に病で亡くなる直前まで、軍部や政権への厳しい批判を続けたのです。
他山の石が最初に発禁となったのは三五(同十)年の「広田外相の平和保障」という論文です。
当時の広田弘毅外相による「我在任中には戦争なし」との議会答弁を「私たちの意見が裏書きされた」と評価しつつ、アメリカやロシアとの戦争は「国運を賭する戦争」であり「一部階級の職業意識や、名誉心のため」「一大戦争を敢(あ)えてすることは、暴虎馮河(ぼうこひょうが)(無謀な行為)の類である」「戦争の馬鹿(ばか)も、休み休み言ってもらいたいものだ」と軍部の好戦論を批判しました。
これが反戦を宣伝扇動したとして発禁処分になったのです。
悠々の研究者、太田雅夫さんの著書によると他山の石の発禁・削除処分は二十七回に上ります。このうち二十五回は三五〜三八年の四年間ですから、この間に発行された四分の一以上が発禁・削除処分を受けたことになります。
その後、悠々は発行継続のため不本意ながらも愛知県特高課による「事前検閲」を受ける方針に切り替え、指摘された箇所を自主的に削除することで発禁を免れました。ただ、その筆勢は衰えず、政権や軍部批判を続けました。
◆言わねばならないこと
それらは悠々にとって「言いたいこと」ではなく「言わねばならないこと」でした。他山の石にはこう書き残しています。
「私は言いたいことを言っているのではない」「この非常時に際して、しかも国家の将来に対して、真正なる愛国者の一人として、同時に人類として言わねばならないことを言っているのだ」
そして「言いたいことを言うのは、権利の行使」だが「言わねばならないことを言うのは、義務の履行」であり「義務の履行は、多くの場合、犠牲を伴う」とも。
悠々が残した記者としての心構えは古びるどころか、今の時代にも通じる、いや、今だからこそ胸に刻むべき至言なのです。
今、新聞にとって「言わねばならないこと」があふれています。
法的根拠を欠く国葬実施や旧統一教会と政治との深い関係、平和憲法を軽視する安全保障政策への転換や防衛費の増額などです。
国外に目を転じれば、国際法無視のロシアの振る舞いや、核兵器使用の可能性も看過できません。
新聞が言わなくなった先にあるのは、内外で多大な犠牲者を出した戦争であり、それが歴史の教訓です。言論や報道に携わる私たちに「言わねばならないこと」を言い続ける覚悟があるのか。悠々の生き方は、そう問い掛けます。
=====================================================

2020年5月21日放送。NHK【セレクション (3)「地の底の声筑豊・炭鉱に生きた女たち」】(https://www.nhk.jp/p/ts/X83KJR6973/episode/te/Q615RY32YK/)。
炭鉱王一族の末裔ウルトラ差別主義者・麻生財閥もその一つ。
『●炭坑王一族の末裔による凄まじいまでの暴言・差別意識』
上野英信さんと筑豊文庫。《筑豊よ 日本を根底から変革するエネルギーの ルツボであれ 火床であれ 上野英信》。
『●「「慰安婦」問題と言論弾圧」
『週刊金曜日』(2014年11月14日、1016号)について』
「三木健氏【本 推理小説さながら心の闇に挑んだ労作/
『上野英信・萬人一人坑 筑豊のかたほとりから』河内美穂=著
現代書館】…《「筑豊の炭住長屋を改造して施設の「筑豊文庫」を設立
…「英信は過去を忘れた訳ではない。…葬り去ったわけでもない。
…過去を背負ったまま、天皇制のゴウカキ(業担き)として生きる。
…その罪業を担い続けていく覚悟だったのだ」と》。上野英信さんは
「「侵略する側」にいた過去に戦後、どう向き合った」のか?」
『●『キジバトの記』読了(1/3)』
『●『追われゆく坑夫たち』読了(1/3)』
『●『追われゆく坑夫たち』読了(2/3)』
『●『追われゆく坑夫たち』読了(3/3)』
「暗い地の底」で。
『●『松下竜一未刊行著作集2/出会いの風』読了(7/9)』
「田中さんや、「筑豊の地に蟠踞 (ばんきょ) して〈地の底の人々〉を
記録しつづけた上野英信」に見られるように、「どんなに赤字であれ
書かずにおれぬ業 (ごう) を負っている者が、
ノンフィクションライターとして生き残っていくのだろう」」
『●『松下竜一未刊行著作集2/出会いの風』読了(3/9)』
「筑豊の泥くさき「ドロキツイスト」上野英信。『暗闇の思想を』
は僭称であり、「…筑豊の地の底の闇を知らぬ私に「暗闇の思想」を
名乗る資格は、もとよりないのであった」。晴子さんや朱さんのことも。
町立病院での最後のやり取り。また、センセの書いた書評に対して、
上野さんは「…いま、ぼくは泣いていました」。このエピソードは
「筑豊を掘り進む 上野英信著『出ニッポン記』解説」(pp.199-204) にも」
『●記憶遺産その後 ~山本作兵衛翁のスケッチブック見つかる~』
《▼筑豊地方などに数多くあったボタ山は、炭鉱の閉山とともに姿を
消した。明治から戦後にかけての日本のエネルギーを支えた労働の
記憶は、六十六歳でツルハシを絵筆に持ち替えた作兵衛の存在に
よって、後世に伝わった▼出水やガス爆発、逃亡者へのリンチ、
米騒動を鎮圧する軍隊…。その絵はまるで人間扱いされなかった
地の底での過酷な労働の実態を詳細に描き出す。それだけではない。
ヤマで暮らしていた労働者たちのたくましさも同時に伝えているのだ》
『●追われゆく坑夫と脇に追いやられた原発人災』
《まだ貧しかった戦後の時代、這(は)い上がる日本を地の底から支えた
のがヤマの人たちだった▼国が豊かになるのと入れ違いに炭鉱はさびれていく》
『●『坑道の記憶~炭坑絵師・山本作兵衛~』:
「歴史はあらゆる側面から語られる必要がある」』
《熱く暗い地の底で石炭を掘る男と女の姿、道具、共同風呂、
子どもたちの遊び、縁起や迷信》
そして、やはり、山本作兵衛さん。
『●山本作兵衛翁の作品がユネスコ世界記憶遺産に!!』
『●記憶遺産その後 ~山本作兵衛翁のスケッチブック見つかる~』
『●「筑豊よ 日本を根底から
変革するエネルギーの ルツボであれ 火床であれ 上野英信」』
『●筑豊の炭鉱記録画家山本作兵衛翁の記憶遺産、ユネスコが展示打診』
『●上野英信さんは「「侵略する側」に
いた過去に戦後、どう向き合った」のか?』
『●山本作兵衛翁のヤマの「記憶の記録」と
アベ様の「アメリカのために戦争できる国」へ』
『●『坑道の記憶~炭坑絵師・山本作兵衛~』:
「歴史はあらゆる側面から語られる必要がある」』
「「一国の首相が歴史修正主義者なんて恥ずかしいし、…
…羞恥心の無さと自覚の無さという救いの無さ」なニッポン国。
教科書に載っている歴史さえも矮小化させようといつも画策。ましてや、
歴史をあらゆる側面から考える頭も無しなアベ様達。
歴史から教訓を得ることもない」
『●熊谷博子監督《当時の炭鉱の姿ではあるが、私には、そのまま
現代に思えた…労働、貧困、差別…戦争…今と同じだ》』
=====================================================
【https://www.nhk.jp/p/ts/X83KJR6973/episode/te/Q615RY32YK/】
セレクション (3)「地の底の声筑豊・炭鉱に生きた女たち」
コロナ禍で生活や社会に脅威や制限が加わる中、今こそ見つめ直したい問題を過去の番組から厳選して届けるシリーズ。第3回は、筑豊の炭鉱で命がけで働いた女性たちの記録。
【「地方の時代」映像祭2017選奨】井手川泰子さんの手元に残る100本に上るカセットテープ。そこには大正から昭和、炭鉱で働いた女性たちの声が記録されている。暗い地の底で腰巻き一つの姿で石炭を掘った女性たち。死と隣り合わせの肉体労働、炭鉱住宅での共助、女ならではの所帯の苦労と喜びが、泣いたり、笑ったり、ときには歌ったりしながら語られる。働くこと、生きること、女であることの真実をつく言葉に耳を傾ける
=====================================================

東京新聞の社説【週のはじめに考える 桐生悠々と言論の覚悟】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2019090802000159.html)。
《戦前、藩閥政治家や官僚、軍部の横暴を痛烈に批判し続けた言論人、桐生悠々。その生きざまは、言論や報道に携わる私たちに、覚悟を問うています。…信毎時代の一九三三(昭和八)年、「関東防空大演習を嗤(わら)ふ」と題した論説が在郷軍人会の怒りに触れ、信毎を追われます。…大先輩を偲(しの)ぶとともに、業績や遺訓を思い起こし、私たち新聞のなすべきことを考え続けたいと思います》。
『●政権交代の意義が完全に消えた日』
《▼「听う」は口を大きく開けてわらうことで、「莞う」は感じよく
ほほえむこと、「嗤う」はあざけりわらうことだ。軍国主義が台頭し、
言論弾圧が厳しさを増していた一九三三年、軍の空襲への備えを
嗤った新聞人がいた▼その人、桐生悠々が書いた
「関東防空大演習を嗤ふ」は日本の新聞史上、特筆すべき名論説
として、記憶される。首都上空で敵機を迎え撃つ作戦など滑稽極まる。
数機撃ち漏らせば、木造家屋の多い東京は炎上すると、彼は書いた
▼<阿鼻叫喚(あびきょうかん)の一大修羅場を演じ、
関東地方大震災当時と同様の惨状を呈するだらう…しかも、
かうした空撃は幾たびも繰返へされる可能性がある>。
この指摘が現実のものとなり、大空襲で東京の下町が壊滅、
十万の犠牲者を出したのは、四五年三月十日のことだ》
『●自公支持者を「嗤う」、あれで「採決」「可決」!?:
自公支持者も「听う」ことが出来なくなる日は近い』
「先の『読売』や『産経』、『アベ様の犬HK』などの
「アベ様の広報機関」とは違う、『東京新聞』の新聞人の矜持を
示す社説をご覧ください。2番目の記事の、つまり、
《桐生悠々の言葉。…「言いたい事」と「言わねばならない事」は
区別すべきだとし「言いたい事を言うのは権利の行使」だが、
「言わねばならない事を言うのは義務の履行」で「多くの場合、
犠牲を伴う」と書き残している》
……の部分を受け、社説の末尾には、《憲法を再び国民の手に
取り戻すまで、「言わねばならないこと」を言い続ける責任を
自らに課したい。それは私たちの新聞にとって
「権利の行使」ではなく「義務の履行」だからである》と〆ています」
『●阿部岳記者「桐生悠々は訓練よりも
「実戦が、将来決してあってはならない」ことを訴えた…先見の明は…」』
「《桐生悠々は訓練よりも「実戦が、将来決してあってはならない」ことを
訴えた。…先見の明は、その後の空襲被害が証明している》訳です。
壊憲が進み、戦争できる国、戦争したい国へとひた走るニッポン。
ジャーナリズムの劣化もそれに拍車をかける」
『●Jアラート狂想曲: 「かつて関東上空での防空演習を
嗤った桐生悠々なら何と評するでしょうか」』
《北朝鮮が弾道ミサイル発射を繰り返し、国内では避難訓練も
行われています。かつて関東上空での防空演習を嗤(わら)った
桐生悠々なら何と評するでしょうか》
『●阿部岳さん、《基地問題への見解の違いも…
デマで攻撃された因縁も関係ない。今回は…産経の側に立つ》』
「東京新聞の社説【週のはじめに考える 権力と向き合う覚悟】…
によると、《◆全米の新聞、一斉に社説…◆言論の自由への危機感
…◆桐生悠々の奮闘を偲ぶ…あす九月十日は、四一年に亡くなった
悠々を偲(しの)ぶ命日です。百年という時を隔て、また日米という
太平洋を挟んだ国で同じように、新聞が連帯して時の政権に毅然(きぜん)
と向き合ったことは、民主主義社会の中で新聞が果たすべき使命を
あらためて教えてくれます。私たちは今、政権に批判的な新聞との
対決姿勢を強める安倍晋三政権と向き合います。悠々ら先輩記者や
米国の新聞社で働く仲間たちの奮闘は、私たちを奮い立たせ、
権力と向き合う覚悟を問い掛けているのです》。
《権力と向き合う覚悟》…無しなニッポンのマスコミではなかろうか…」
どんどんと《飛翔体》が発射されていますが、あのJアラート狂騒曲は何だったでしょうね…。諸外国からは《「嗤…」…あざけりわら》われている。
《「言いたいことを言うのは、権利の行使」だが「言わねばならないことを言うのは、義務の履行」であり、「義務の履行は、多くの場合、犠牲を伴う」》と。《桐生悠々…にとって一連の言論は、犠牲も覚悟の上で、言うべきことを言う義務の履行だった》。この度、アノ高市早苗氏が総務相に復活。アベ様の政で〝唯一うまく行っている〟メディアコントロールの下、 《権力と向き合う覚悟》がマスメディアにはあるのだろうか? 《義務の履行》を果たしているか?
=====================================================
【https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2019090802000159.html】
【社説】
週のはじめに考える 桐生悠々と言論の覚悟
2019年9月8日
戦前、藩閥政治家や官僚、軍部の横暴を痛烈に批判し続けた言論人、桐生悠々。その生きざまは、言論や報道に携わる私たちに、覚悟を問うています。
桐生悠々は本紙を発行する中日新聞社の前身の一つ、新愛知新聞や、長野県の信濃毎日新聞などで編集、論説の総責任者である主筆を務めた、私たちの大先輩です。
信毎時代の一九三三(昭和八)年、「関東防空大演習を嗤(わら)ふ」と題した論説が在郷軍人会の怒りに触れ、信毎を追われます。
その後、新愛知時代に住んでいた今の名古屋市守山区に戻った悠々は、三四(同九)年から個人誌「他山の石」の発行を始めます。
◆日米開戦は「無謀の極」
悠々が亡くなったのは四一(同十六)年九月十日でした。その三カ月後、悠々が「無謀の極(きわみ)」とした米国との戦争が始まります。
戦後、悠々が再び注目されるきっかけは五一(同二十六)年、信毎が紙齢二万五千号を記念し、悠々ら同紙で活躍した言論人を紹介した特別紙面でした。
これを小説家で文芸評論家の正宗白鳥が読み、東京新聞(現在は中日新聞社が発行)に寄せた「人生如何(いか)に生くべきか」と題する随筆で、信毎の論説や「他山の石」などの悠々の言論活動を振り返りながら、こう評したのです。
「彼はいかに生くべきか、いかに死すべきかを、身を以(も)つて考慮した世に稀(ま)れな人のやうに、私には感銘された。これに比べると、今日のさまざまな知識人の賢明なる所論も、たゞの遊戯文学のやうに思はれないでもない」
それは、戦後間もない時期の知識人たちの言論活動が、悠々の覚悟に比べれば、いかに腰の据わっていない浅薄なものか、と正宗は問いたかったのでしょう。
悠々の言論活動は海外にも視野を広げた豊富な知識に基づいて、過去の習慣や時流に流されない、開明的かつ激越なものでした。
◆言わねばならないこと
まずは一二(大正元)年、明治天皇の死去に伴う陸軍大将、乃木希典の殉死に対してです。
信毎主筆として書いた社説「陋習(ろうしゅう)打破論-乃木将軍の殉死」では「殉死もしくは自殺は、封建の遺習である」「野蛮の遺風である。此(こ)の如(ごと)き陋習は、一刻も早く之(これ)を打破せねばならぬ」と指摘しました。自刃をたたえるものが目立つ中、異色の社説です。
新愛知時代の一八(同七)年に起きた米騒動では米価暴騰という政府の無策を新聞に責任転嫁し、騒動の報道を禁じた当時の寺内正毅内閣を厳しく批判します。
悠々は新愛知社説「新聞紙の食糧攻め 起(た)てよ全国の新聞紙!」の筆を執り、内閣打倒、言論擁護運動の先頭に立ちます。批判はやがて全国に広がり、寺内内閣は総辞職に追い込まれました。
そして信毎論説「関東防空大演習を嗤ふ」です。敵機を東京上空で迎え撃つ想定の無意味さを指摘したことは、日本全国が焦土と化した戦史をひもとけば正鵠(せいこく)を射たものですが、軍部の台頭著しい時代です。新聞社は圧力に抗しきれず、悠々は信州を離れます。
それでも悠々は名古屋に拠点を移して言論活動を続けました。軍部や政権を厳しく批判する「他山の石」は当局からたびたび発禁や削除処分を受けながらも、亡くなる直前まで発行が続きました。
悠々は「他山の石」に「言いたいこと」と「言わねばならないこと」は区別すべきだとして「言いたいことを言うのは、権利の行使」だが「言わねばならないことを言うのは、義務の履行」であり、「義務の履行は、多くの場合、犠牲を伴う」と書き残しています。
悠々にとって一連の言論は、犠牲も覚悟の上で、言うべきことを言う義務の履行だったのです。
正宗が言う「いかに生くべきか、いかに死すべきかを、身を以つて考慮した」悠々の命懸けの言論は戦争への流れの中では顧みられることはありませんでしたが、戦後再評価され、今では私たち言論、報道活動に携わる者にとって進むべき方向を指し示す、極北に輝く星のような存在です。
◆嵐に鳴く蟋蟀のように
<蟋蟀(こおろぎ)は鳴き続けたり嵐の夜>
悠々のこの句作が世に出た三五(昭和十)年は、昭和六年の満州事変、七年の五・一五事件、八年の国際連盟脱退と続く、きなくさい時代の真っただ中です。翌十一年には二・二六事件が起き、破滅的な戦争への道を突き進みます。
もし今が再び<嵐の夜>であるならば、私たちの新聞は<蟋蟀>のように鳴き続けなければなりません。それは新聞にとって権利の行使ではなく、義務の履行です。
来る十日は悠々の没後七十八年の命日です。大先輩を偲(しの)ぶとともに、業績や遺訓を思い起こし、私たち新聞のなすべきことを考え続けたいと思います。
=====================================================
[三上智恵監督『標的の島 風かたか』公式ページ(http://hyotekinoshima.com)より↑]

東京新聞の社説【週のはじめに考える 桐生悠々と防空演習】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2017091002000138.html)。
《北朝鮮が弾道ミサイル発射を繰り返し、国内では避難訓練も行われています。かつて関東上空での防空演習を嗤(わら)った桐生悠々なら何と評するでしょうか》。
『●「軍事的対応ではなく、緊張緩和に知恵を絞り、
外交努力を重ねることこそが平和国家を掲げる日本の役割」』
『●番犬様を諌めることもなく「海自、米空母と訓練検討」…
「あくまでも非軍事的解決の道を探るべきである」』
『●高畑勲監督より三上智恵監督へ、
「あなたがつくっているような映画が、次の戦争を止める」』
『●山内康一氏「『米国の軍事力行使を日本は支持する』
…戦争を積極的に肯定…重大かつ危険な発言」』
『●阿部岳記者「桐生悠々は訓練よりも
「実戦が、将来決してあってはならない」ことを訴えた…先見の明は…」』
『●「平和憲法」が風前の灯火: 壊憲の坂道を転げ落ち、
アベ政権と与党自公は戦争へと火に油を注いでいる』
『●戦争法なんて要らない! 「武力による威嚇や武力の行使を
…永久に放棄した日本の役割」を見失っている』
『●「我が軍」的自衛隊の「違憲」状態を「合憲」へと改めず、
憲法を「壊憲」して「違憲」を解消する!?』
『●戦争で唯一得た平和憲法を壊憲…「日本は自由と民主主義を
失うだけで、代わりに得るものは何もない」』
『●立憲主義も理解できず…「行政の長である総理大臣が
具体的な改憲日程を口にするのは完全に憲法違反」』
『●アベ様による血税4億円のトンチンカン・トンデモ
「ミサイル避難CM広告」によるメディア買収!?』
《この国から倫理観が失われつつある。なにしろ、倫理観ゼロの
安倍さんが総理だしな。…内容はミサイルが飛んで来たら
「屋内に避難」「物陰に隠れる」というトンデモだ。そんなに緊急に
ミサイルの心配をしなくてはならないのなら、まず全国にある原発を
どうにかしなくていいのか? が、そういうことじゃない、きっと。
このCMには4億円もの金をかけている。…そんな中、メディアに
4億円という金が配られる。それはいったい、どういうことを意味するのか?》
『●「「危機が迫っている」とあおり、時の政権の求心力を高める手法」
…メディア買収と国内に向けての圧力』
北朝鮮による核実験やミサイル乱射、それに対する「国内に向けての圧力」としてのCMや「避難訓練」、Jアラート狂想曲。《かつて関東上空での防空演習を嗤(わら)った桐生悠々なら何と評するでしょうか》? 《悠々の評論の核心は、非現実的な想定は無意味なばかりか、有害ですらある、という点にある》。
『●ガジュマル:瀬長亀次郎さん「不屈」の精神…
「忖度政治を危ぶむ全国の多くの人々の心に響くに違いない」』
『●ささやかな核兵器廃絶の願い…高校生の言論封殺:
アベ様のメンツを守るための外務省の横やりという大愚』
『●石破茂氏「日本への核拡散」発言と山尾氏「私事」による離党の
事の軽重…マスコミはわきまえているか?』
『●トランプ氏、「私は、日本と韓国に対して、
アメリカの高性能の軍事装備を大量に購入することを認める…」』
『●《差別の歴史、力の差を無視して「どっちもどっち」論に
持ち込む》(阿部岳さん)低民度…抗い続けねば』
『●人治主義国家ニッポンの人事考査: 証拠隠滅で国税庁長官、
犯罪揉消しで警察庁組織犯罪対策部長…』
『●「戦死を美化」することではなく、いま必要なことは
「同じことを二度と繰り返さないという誓い」』
『●「日米の軍事一体化はますますエスカレート」し「兵站」
=「イージス艦に給油」…「自衛隊は格好の餌食」』
「裸の王様」や自公政権、「我が軍」がやっていることを「嗤う」《反骨のジャーナリスト》や《気骨の新聞人》が少な過ぎやしまいか…。下足番新聞読売や最早新聞と呼べない広報紙サンケイが幅をきかせているようではね。
阿部岳記者は、《桐生悠々は訓練よりも「実戦が、将来決してあってはならない」ことを訴えた》と言います。いま、日米朝、《頭を冷やせ》と言いたい。そして、志位和夫さんの言う通り、ニッポンは《平和的努力こそ政府がすべきことだ》。挑発するな、挑発に乗るな…決して戦争の泥沼に足を踏み込んではいけない。朝韓日、いずこも《一挙に焦土たらしめるだろう》し、お互いに《阿鼻叫喚の一大修羅場》が待っているだけだ。本社説も、《外交努力を惜しんではなりません。軍事的な対応は憎悪が憎悪を呼び、問題の根本的な解決にならないからです》…と。
『●政権交代の意義が完全に消えた日』
《▼「听う」は口を大きく開けてわらうことで、「莞う」は感じよく
ほほえむこと、「嗤う」はあざけりわらうことだ。軍国主義が台頭し、
言論弾圧が厳しさを増していた一九三三年、軍の空襲への備えを
嗤った新聞人がいた▼その人、桐生悠々が書いた
「関東防空大演習を嗤ふ」は日本の新聞史上、特筆すべき名論説
として、記憶される。首都上空で敵機を迎え撃つ作戦など滑稽極まる。
数機撃ち漏らせば、木造家屋の多い東京は炎上すると、彼は書いた
▼<阿鼻叫喚(あびきょうかん)の一大修羅場を演じ、
関東地方大震災当時と同様の惨状を呈するだらう…しかも、
かうした空撃は幾たびも繰返へされる可能性がある>。
この指摘が現実のものとなり、大空襲で東京の下町が壊滅、
十万の犠牲者を出したのは、四五年三月十日のことだ》
『●自公支持者を「嗤う」、あれで「採決」「可決」!?:
自公支持者も「听う」ことが出来なくなる日は近い』
「先の『読売』や『産経』、『アベ様の犬HK』などの
「アベ様の広報機関」とは違う、『東京新聞』の新聞人の矜持を
示す社説をご覧ください。2番目の記事の、つまり、
《桐生悠々の言葉。…「言いたい事」と「言わねばならない事」は
区別すべきだとし「言いたい事を言うのは権利の行使」だが、
「言わねばならない事を言うのは義務の履行」で「多くの場合、
犠牲を伴う」と書き残している》
……の部分を受け、社説の末尾には、《憲法を再び国民の手に
取り戻すまで、「言わねばならないこと」を言い続ける責任を
自らに課したい。それは私たちの新聞にとって
「権利の行使」ではなく「義務の履行」だからである》と〆ています」
『●阿部岳記者「桐生悠々は訓練よりも
「実戦が、将来決してあってはならない」ことを訴えた…先見の明は…」』
「《桐生悠々は訓練よりも「実戦が、将来決してあってはならない」ことを
訴えた。…先見の明は、その後の空襲被害が証明している》訳です。
壊憲が進み、戦争できる国、戦争したい国へとひた走るニッポン。
ジャーナリズムの劣化もそれに拍車をかける」
==================================================================================
【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2017091002000138.html】
【社説】
週のはじめに考える 桐生悠々と防空演習
2017年9月10日
北朝鮮が弾道ミサイル発射を繰り返し、国内では避難訓練も行われています。かつて関東上空での防空演習を嗤(わら)った桐生悠々なら何と評するでしょうか。
きょう九月十日は明治後期から昭和初期にかけて健筆を振るった反骨のジャーナリスト、桐生悠々の命日です。太平洋戦争の開戦直前、一九四一(昭和十六)年に亡くなり、七十六年がたちます。
本紙を発行する中日新聞社の前身の一つである新愛知新聞や、長野県の信濃毎日新聞などで編集、論説の総責任者である主筆を務めた、われわれの大先輩です。
◆非現実の想定「嗤う」
新愛知時代には、全国に広がった米騒動の責任を新聞に押し付けようとした寺内正毅(まさたけ)内閣を厳しく批判する社説の筆を執り、総辞職に追い込んだ気骨の新聞人です。
その筆鋒(ひっぽう)は軍部にも向けられます。信毎時代の三三(同八)年八月十一日付の評論「関東防空大演習を嗤う」です。
掲載の前々日から行われていた陸軍の防空演習は、敵機を東京上空で迎え撃つことを想定していました。悠々は、すべてを撃ち落とすことはできず、攻撃を免れた敵機が爆弾を投下し、木造家屋が多い東京を「一挙に焦土たらしめるだろう」と指摘します。
「嗤う」との表現が刺激したのか、軍部の怒りや在郷軍人会の新聞不買運動を招き、悠々は信毎を追われますが、悠々の見立ての正しさは、その後、東京をはじめとする主要都市が焦土化した太平洋戦争の惨禍を見れば明らかです。
悠々の評論の核心は、非現実的な想定は無意味なばかりか、有害ですらある、という点にあるのではないでしょうか。
その観点から、国内の各所で行われつつある、北朝鮮の弾道ミサイル発射に備えた住民の避難訓練を見るとどうなるのか。
◆ミサイルは暴挙だが
まず大前提は、北朝鮮が繰り返すミサイル発射や核実験は、日朝平壌宣言や国連安保理決議などに違反し、アジア・太平洋地域の安全保障上、重大な脅威となる許し難い暴挙だということです。
今、国連を主な舞台にして、北朝鮮に自制を促すさまざまな話し合いが続いています。日本を含む関係各国が「対話と圧力」を駆使して外交努力を惜しんではなりません。軍事的な対応は憎悪が憎悪を呼び、問題の根本的な解決にならないからです。
その上で、北朝鮮のミサイル発射にどう備えるべきなのか。
政府は日本に飛来する可能性があると判断すれば、全国瞬時警報システム(Jアラート)を使って避難を呼び掛けます。八月二十九日早朝の場合、発射から四分後に北海道から関東信越までの十二道県に警報を出しました。
とはいえ、日本の領域内に着弾する場合、発射から数分しかありません。政府は、屋外にいる場合は近くの頑丈な建物や地下への避難を呼び掛けていますが、そうしたものが身近にない地方の都市や町村では、短時間では避難のしようがないのが現実です。
八月の発射でも「どこに逃げるか、どのように身を隠せばいいか。どうしていいか分からない」との声が多く出ています。
住民の避難訓練も同様です。ミサイル発射を想定した国と自治体による合同の避難訓練が今年三月以降、すでに全国の十四カ所で行われていますが、専門家からは訓練の想定や有効性を疑問視する声が出ています。
北朝鮮は、在日米軍基地を攻撃目標にしていることを公言していますし、稼働中であるか否かを問わず、原発にミサイルが着弾すれば、放射線被害は甚大です。
しかし、政府は米軍基地や原発、標的となる可能性の高い大都市へのミサイル着弾を想定した住民の避難訓練を行っているわけではありません。有効な避難場所とされる地下シェルターも、ほとんど整備されていないのが現状です。
訓練の想定が現実から遊離するなら、悠々は防空大演習と同様、論難するのではないでしょうか。
◆原発稼働なぜ止めぬ
戦力不保持の憲法九条改正を政治目標に掲げる安倍晋三首相の政権です。軍備増強と改憲の世論を盛り上げるために、北朝鮮の脅威をことさらあおるようなことがあっては、断じてなりません。
国民の命と暮らしを守るのは政府の役目です。軍事的な脅威をあおるよりも、ミサイル発射や核実験をやめさせるよう外交努力を尽くすのが先決のはずです。そもそもミサイルが現実の脅威なら、なぜ原発を直ちに停止し、原発ゼロに政策転換しないのでしょう。
万が一の事態に備える心構えは必要だとしても、政府の言い分をうのみにせず、自ら考えて行動しなければならない。悠々の残した数々の言説は、今を生きる私たちに呼び掛けているようです。
==================================================================================


CMLの記事(http://list.jca.apc.org/public/cml/2013-August/025626.html)。
ナチスの「あの手口を学んではどうか」の麻生太郎氏。極めつけの暴言・差別意識について以下に再掲。
『●『創 (12月号)』読了 (2/2)』
「雨宮処凛さん、「45年間にわたり一着45万円のスーツを年間10着仕立てる
おしゃれな首相。・・・敷地だけで6200000000円。・・・『華麗なる一族』の
東京宅を見に行きましょう」。で、ゆでダコ坊主主導によるコウボウ
(「防」でなく「暴」)。」
『●『追われゆく坑夫たち』読了(2/3)』
「『日刊ゲンダイ = 連日の高級ホテル通いが非難を浴び、
「私は幸い、お金があります」と言い放った麻生首相。なるほど
福岡の炭鉱王と呼ばれた一族で、公開された資産は歴代首相では
ダントツだ。それにしたって財力を鼻にかけて自慢するなんて、一国の
トップがやることか。成り金じゃあるまいし、本当の金持ちはもっと謙虚だし、
人前では金のことを話さないのが大人のたしなみというものだ。昔、
大コンツェルンの御曹司から自民党の代議士に担ぎ出され、財産すべてを
政治につぎ込んで「井戸塀」と呼ばれても国家のために働いた藤山愛一郎
という政治家がいた。麻生マンガ太郎首相は同じ御曹司でもこの人物とは
品格が違う。「ボクは金持ちです。だから嫌われます」と吹聴する人物が
最高指導者では国中のモラルが乱れるのも当然。』(赤太字はブログ主)
(「井戸」か・・・。)
「・・・北部を縦走して玄海灘にそそぐ遠賀川の流域一帯、七市四郡にわたる
筑豊炭田は、ほぼ一世紀にちかい年月にわたって全国総出炭量の
おおよそ半分におよぶ量の石炭を産出しつづけ、日本最大の火床として
繁栄をほこってきた。・・・資本主義化と軍国主義化を推し進め
・・・三井・三菱・・・財閥がこの地底から富をすくいあげ・・・」(p.iii)。
「・・・麻生・伊藤とともに「筑豊御三家」のひとつに数えられる貝島・・・」(p.2)。
「・・・ヤマのつぶれるまで労働者を奴隷としてつないでおくための鎖が、
ほかならぬ肩入れ金である・・・」(p.49)。」
『●『差別と日本人』読了(3/4)』
「やはり〝メインイベント〟は麻生太郎のすさまじいまでの暴言・
差別意識でしょう。「麻生氏は、植民地支配で財を築いた麻生財閥の
中でぬくぬく育って、首相にまで上り詰めた。/・・・麻生鉱業は、
・・・消耗品の労働力として、その命を紙くずのように扱った。一九四五年まで
に麻生系の炭鉱に連行された朝鮮人は一万人を超える・・・。また、
・・・民を・・・奴隷のように酷使した」(pp.162-163)。
「辛 私は麻生さんの顔を見ると背筋が寒くなるんです。/とくに彼の中に
あるひどい差別意識には、ぞっとさせられる。/野中 ・・・ある新聞社の記者が
僕に手紙をくれたんです。・・・〈麻生太郎が、・・・「野中やら・・・の人間だ。
だからあんなのが総理になってどうするんだい。ワッハッハッハ」と笑っていた。
これは聞き捨てならん話だ・・・〉/・・・を死ぬほどこき使って、金儲けしてきた
人間だから。/・・・不幸な人だ。一国のトップに立つべき人じゃない。
/・・・/辛 麻生さんは差別意識が体の中に染み込んでるんだと思う」
(pp.163-165)。
「彼には、吉田茂の孫であり、また麻生セメントに代表される麻生財閥の
末裔ということ以外に、政治的資源は何もない。能力もない。
だから出自で人を見下す」(p.166)。「「麻生太郎」とは、日本社会が
生み出した差別の結晶であり、差別による旨みが骨の髄まで染み付いた
人間の典型なのだろう」(p。169)。」
『●『野中広務 差別と権力』読了(2/3)』
「「永田町ほど差別意識の強い世界」(※2) はなく、「総裁選の最中に
ある有力代議士は・・・「・・・総理になれるような種類の人間じゃないんだ」
(p.385) と言ったそう。さらに、最近、ネット上で話題になっていた部分。
当時、「総裁選に立候補した元経企庁長官」 (であり現総理) の
「麻生太郎は・・・「あんな・・・を日本の総理にはできないわなあ」と言い放った」
(p.385) そうである。2003年9月、野中は、最後の自民党総務会に臨み、
当時の小泉総裁や麻生政調会長を前に発言を求めた。「・・・私の最後の発言と
肝に銘じて申し上げます・・・政調会長。あなたは『野中のような・・・を総理には
できないわなあ』とおっしゃった。君のような人間がわが党の政策をやり、
これから大臣ポストについていく。こんなことで人権啓発なんてできよう
はずがないんだ。私は絶対に許さん!」、野中の激しい言葉に総務会の空気は
凍りついた。麻生は何も答えず、顔を真っ赤にしてうつむいたままだった」
(pp.391-392)。」
================================================================================
【http://list.jca.apc.org/public/cml/2013-August/025626.html】
[CML 025706] 麻生はいかにしてセレブになったか
・・・・・・・・・
2013年 8月 2日 (金) 15:58:12 JST
・・・・・・です。
麻生太郎財務大臣のナチス発言が大きな波紋を呼んでいます。
これは失言や誤解ではありません。
日本には、ヒトラーやナチスを高く評価する人が大勢います。ヒトラーの著書
『我が闘争』を人生や経営の指南書として熱心に読む人がたくさんういます。
麻生はヒトラーやナチスの「やり口」を高く評価していることは明らかです。
彼は歴史を学んでいない、学ぼうとはしない政治家です。
これは今から十年前、の2005年10月、麻生太郎財務大臣が小泉純一郎内
閣の外務大臣に就任した時に、私が[aml]というメーリングリストに送った文章で
す。
当時、多くの福岡県民が麻生の外相就任を祝いました。それで私も福岡県民の
一人として以下の文を書いて「祝い」ました。
元々は福岡の豪農地主に過ぎなかった麻生家が、どうやってセレブになったの
かを書きました。
彼の足下には、韓国・朝鮮人と被差別の人々の屍があります。
(ここから)
昨日(10月31日)の内閣改造で、
麻生太郎氏(福岡8区)http://www.aso-taro.jp/index2.html
が、外務大臣に就任しました。ポスト小泉の一人として将来の首相候補になった
とマスコミから大きく取り上げれられています。
福岡県内からは、将来の首相候補として、そして冷え切った日韓・日中関係の
改善に手腕を発揮すると期待の声が上がっています。
福岡県内のテレビニュースの街頭インタビューでは、麻生外相就任を祝う声が
数多く聞かれました。もちろん、広田弘毅(1978年~1948年)以来の福
岡県出身の首相誕生を期待する声もです。
(広田弘毅は外交官として活躍し、外相も務めました。そしてA級戦犯として東
京裁判にかけられ、処刑されました)
福岡県民の一人として、私は外相就任おめでとうございますと言うべきでしょ
うが、そのかわり、次のことを言います。
麻生外相は、韓国・朝鮮人と被差別の人々の生き血をすすってのし上がっ
た一族の出身です、と。
麻生外相は、政界に入る前は麻生セメント(現在は麻生ラファージュセメント)
の社長でした。この会社の前身は、かつて福岡県・筑豊地方に数多くあった炭鉱
を経営していた麻生鉱業です。この麻生鉱業(創立当初は麻生商店)は、福岡県
のみならず日本有数の石炭産業会社として「日本の近代化・産業化に貢献した」
と評されています。炭鉱経営で得た利益をもとに鉄道・電力・病院、そしてセメ
ント会社を設立し、財閥を形成しました。麻生外相は、その麻生グループの3代
目後継者です。麻生グループは今も福岡県有数の企業グループとして大きな力を
持っています。
麻生一族は炭鉱経営で得た富と影響力で政界にも進出しました。
麻生外相の父、麻生多賀吉(1891年~1980年)は吉田茂首相の3女・
和子と結婚し、衆議院選挙に立候補し当選しました。自民党の実力者として活躍
しました。麻生外相はその政治的地盤を引き継ぎました。
麻生外相は吉田茂の孫です。高祖父は「明治維新の三傑」大久保利通、曾祖父
は昭和天皇の重臣だった牧野伸顕、義父は鈴木善幸首相です。妹・信子は三笠宮
寛仁親王妃です。まさに華麗なる一族です。
さて、もともとは農村の豪農地主にすぎなかった麻生家が、日本有数の名家
(今流行りの言葉で言えばセレブ)になったのは、炭鉱経営で得た富でした。そ
の富は、韓国・朝鮮人労働者と、被差別の人々を搾取することで得たもので
した。
私の手元には、消滅した筑豊の炭鉱の全貌をモノクロ写真で記録した写真集
『写真万葉録筑豊』(全10巻 上野英信・趙根在監修 葦書房 1986年
http://www1.ocn.ne.jp/~ashi/)
があります。経営する側ではなく、そこで働く労働者と地域の人々の視点で炭鉱
を捉えた記念碑的写真集です。その写真集の第9巻「アリラン峠」は、韓国・朝
鮮人炭鉱労働者とその家族の姿が納められています。
この本の53,54ページにハングルで書かれたビラの写真があります。私は
ハングルが読めないので内容が分かりません。しかし、ガリ版刷りで印刷された
ビラの文字から、ただならぬ緊張感が感じられます。「労働者諸君!」・「内地
労働者」・「東京労働総同盟」・「世界労働者」と書かれた漢字から、労働争議
に関する呼びかけであることが推測されます。「麻生」の文字もあります。
ビラの最後には漢字で一回り大きく書いてあります。
「打倒暴力搾取之巨魁麻生財閥 民族的差別待遇絶対反対」
これは、1932年8月14日から9月3日の約1ヶ月間に渡って、韓国・朝
鮮人労働者が戦った麻生炭鉱争議のビラです。日本人労働者よりも2割安い賃金
(この時期は輸入石炭との価格競争を理由に3割値下げ)、首切り、長時間労働、
リンチ、侮辱、厳しい監視に対しての怒りが爆発したものでした。
麻生鉱業は日韓併合以前から、いち早く韓国・朝鮮人労働者を雇用していまし
た。その待遇は上記の通りでした。当時、日本の炭鉱の韓国・朝鮮人労働者に対
する労働条件はどこも劣悪でしたけれども、麻生鉱業が経営する炭鉱は、ひとき
わ悪いものでした。「圧制ヤマ」としてその名をとどろかせていました。
立ち上がった韓国・朝鮮人労働者に対して、麻生鉱業は警察とヤクザを使って
潰しにかかりました。多くの血が流されました。その韓国・朝鮮人労働者ととも
に立ち上がって戦ったのが、被差別出身の日本人労働者でした。
豪農地主として、多くの被差別の小作人を支配下においていた麻生家は、
被差別の人々を、経営する炭鉱に送り込みました。また、九州各地や中国・
四国地方から生活の場を求めて流入してきた被差別出身の人々を、積極的に
雇用しました。差別を恐れて声を上げないことにつけ込み、低賃金と劣悪な労働
条件のもとで酷使したのです。人々は「ゲザイニン」と軽蔑され、職種・住居
(炭住)・風呂に至るまで差別されました。しかし、米不足から起こった191
8年の「米騒動」を機に、被差別の人々は立ち上がるようになり、1922
年の全国を結成しました。翌1923年に、九州が結成され、差別
撤廃闘争を展開しました。被差別の人々の多くが炭鉱労働者とその家族であ
った筑豊においては、差別撤廃闘争は労働運動を意味しました。そして、麻生争
議では、同じように差別に苦しんでいた朝鮮人労働者と連帯して、戦いました。
被差別の人々はカンパを集め、米を朝鮮人労働者に送りました。(『日本民
衆の歴史 地域編9 赤いボタ山の火 筑豊三池の人びと』66ページ 新藤東
洋男編 三省堂 1985年)。韓国・朝鮮人と日本人の民衆が連帯した数少な
い例です。
この麻生鉱業争議は、スト参加者263人が解雇されたことで労働者側の敗北
に終わりました。
その後、韓国・朝鮮人の労働運動は厳しい取り締まりで壊滅に追い込まれ、日
本への絶対的服従を強制される協和会運動に飲み込まれました。
運動も、同じように軍国主義体制の強化で、沈黙と政府と政府への協力
を余儀なくされました。
その後麻生鉱業は、賃金や労働条件の改善をあまりしないまま、韓国・朝鮮人
と被差別部出身者を炭鉱に送り続けました。火災や落盤、出水、ガス爆発などの
事故で、多くの人びとが犠牲になりました。それは日中戦争激化と太平洋戦争開
始でさらにひどくなりました。物資不足と人員不足で安全対策がおろそかになっ
たこと、安全を無視した採炭が原因でした。そして、いわば移住で渡ってきた人
びととは別に、強制的に連れられてきた韓国・朝鮮人や中国人も、麻生が経営す
る炭鉱に送り込まれました。その人びとが、どのような運命をたどったのかは多
くの書物に述べられています。また、本土へ疎開した沖縄県出身者も炭鉱に入り
ました。
太平洋戦争敗北後、労働運動が自由になったことで、炭鉱労働者は激しい労働
運動を行い、めざましい成果を上げました。韓国・朝鮮人労働者も祖国分断の苦
難にあいながらも、活発な運動を展開しました。被差別解放運動も活発に行
われました。
しかし、1950年代半ばから始まった石炭から石油への「エネルギー革命」
によって、石炭産業は崩壊しました。生活の基盤であった炭鉱は次々に閉山した
ました。廃墟が広がり、多くの人びとが筑豊から去りました。その多くが高度経
済成長に沸く太平洋ベルト地帯に移りましたけれども、中には農業移民としてブ
ラジルやアルゼンチンなどの南米に移住した人もいました。また、北朝鮮に「帰
国」した韓国・朝鮮人労働者とその家族もかなりいました。
筑豊に残った人びとは、その多くが失業に苦しみ、生活保護と失業対策事業、
日雇いの仕事でかろうじて生活しました。
一方、麻生家は2代目総帥麻生多賀吉が、吉田茂首相の娘婿になったことで政
界に進出し、「華麗なる一族」への道を進みました。グループの主力事業を石炭
からセメントに転換したことで、生き残ることができました。
麻生太郎氏外相就任おめでとう、次は首相か、という声があふれています。
しかし私は、政界で華麗な活躍をしている麻生氏の足下には、踏みつけにされ
た韓国・朝鮮人と被差別の人びとの屍があることを指摘します。そして彼は
踏みつけにされた人びとの叫びが、全く聞こえていないことが、「創氏改名」や
「一民族」発言で明らかです。
ですから私は祝いません。
(ここまで)
・・・
======================================
「郵政民営化は構造改革の本丸」(小泉純一郎前首相)
その現実がここに書かれています・
『伝送便』
http://densobin.ubin-net.jp/
私も編集委員をしています(^^;)
定期購読をお願いします!
購読料は送料込みで1年間4320円です。
================================================================================

asahi.comから(http://www.asahi.com/national/update/0914/SEB201109140062.html)。
地元以外では、山本作兵衛翁の世界記憶遺産の記憶は既になくなりつつあるのでしょうかね。上野英信さんの筑豊文庫も記憶の果てになって久しい。炭鉱の記憶は失われていく。
==========================================
【http://www.asahi.com/national/update/0914/SEB201109140062.html】
2011年9月15日3時4分
作兵衛「超一級」の17枚 1冊目のスケッチブック発見
ユネスコの世界記憶遺産に登録された炭鉱記録画を描いた山本作兵衛(1892~1984)が、本格的に絵筆を握った1958年当時に描きためたスケッチブックが、福岡県田川市の民家から見つかった。作兵衛の1冊目の作品と見られ、関係者は「作兵衛研究のうえで超一級の資料」と話している。
水彩と墨絵で、画用紙に1千点以上の作品を残した作兵衛は57年に日記の余白や広告の裏に絵を描き始め、58(昭和33)年から本格的にスケッチブックに多くの絵を描いた。1冊目と見られるスケッチブックは縦24センチ、横30センチで計17枚。表紙左上に「NO1 位登炭坑」、表紙の裏には「33年秋」と記されている。
すべて墨絵で、うち8枚は仲間が犠牲になった1940年の炭鉱水没事故の様子だ。10日目に奇跡的に生還した仲間との再会や、遺体の搬送などが時系列で描かれている。
==========================================
もう一つ関連した記事(http://www.asahi.com/national/update/0917/SEB201109170014.html)。
==========================================
【http://www.asahi.com/national/update/0917/SEB201109170014.html】
2011年9月17日17時36分
山本作兵衛展、同時開催 ユネスコ遺産の過酷な炭鉱記録
ユネスコの世界記憶遺産に登録された炭鉱記録画や文書を集めた「山本作兵衛コレクション展」が17日、福岡県田川市の市石炭・歴史博物館で始まった。墨絵10点、水彩画20点のほか、日記や写真、ユネスコの認定証など約90点を展示する。
開館の前、作兵衛の遺族や小川洋・福岡県知事らがテープカットをした。伊藤信勝市長は「貴重な未来への遺産として、後世に残していきたい」とあいさつした。訪れた福岡県水巻町の男性(78)は「炭鉱労働の過酷さがよくわかる貴重な記録だ」と話した。
同じ田川市内の中村美術館でもサテライト展示「山本作兵衛原画特別展」が17日から始まった。作兵衛が生前友人らに贈った原画約30点を展示し、絵筆を本格的に握ったとされる1958年に描きためたスケッチブックも公開されている。
開催期間は市石炭・歴史博物館が来年1月9日まで、中村美術館は来年1月10日まで。(小川裕介)
==========================================
お~、なんと東京新聞の「筆洗」(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/hissen/CK2011091802000029.html)にも取り上げられている!
==========================================
【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/hissen/CK2011091802000029.html】
筆洗
2011年9月18日
国内で初めてユネスコの「記憶遺産」に登録された山本作兵衛の炭鉱画五百八十四点を収蔵している福岡県田川市の石炭・歴史博物館を先日訪ねてきた▼♪あんまり煙突が、高いので、さぞやお月さん、煙たかろ…の「炭坑節」の歌詞で有名な二本の巨大な煙突が往時の面影を残している。展示室に作兵衛の言葉が飾ってあった。<ボタ山よ汝人生の如し 盛んなるときは肥えふとり ヤマ止んで日日痩せほそり 或いは姿を消すもあり あゝ哀れ悲しきかぎりなり>▼筑豊地方などに数多くあったボタ山は、炭鉱の閉山とともに姿を消した。明治から戦後にかけての日本のエネルギーを支えた労働の記憶は、六十六歳でツルハシを絵筆に持ち替えた作兵衛の存在によって、後世に伝わった▼出水やガス爆発、逃亡者へのリンチ、米騒動を鎮圧する軍隊…。その絵はまるで人間扱いされなかった地の底での過酷な労働の実態を詳細に描き出す。それだけではない。ヤマで暮らしていた労働者たちのたくましさも同時に伝えているのだ▼戦後、原子力発電の時代が到来すると、かつて全国各地の炭鉱を放浪したように、多くの下請け労働者が原発を渡り歩くようになる。福島第一原発の事故の収束を支えているのもこの人たちだ▼炭鉱は負の遺産を残しながらも、炭坑節や作兵衛の絵を生んだ。原発はなにを残したのだろうか。
==========================================