
【まくら】
長い噺なので寄席などでは前半「花見小僧」と後半「刀屋」に分けて演じられている。
前半は、お嬢さんのおせつと奉公人の徳三郎があやしいと番頭に言われた旦那が、小僧を呼び出し花見に行った時の経緯を飴と鞭を使い分けながら訊き出すという滑稽噺。
後半の「刀屋」は、お店を首になった徳三郎がお嬢さんの婚礼があることを知り、頭に血が上って契りを交わしたのに裏切ったと刀屋に駆け込んで刀を買おうとするが怪しまれ事情を話したところ、店の主人に「不義理な女を殺してもしようがない、懸命に働いて立派なお店の主人となって見返してやれ」と諭しているところへ、お嬢さんが婚礼の席からいなくなったと頭が駆け込んでくる。
人情噺の傑作、客は息付く暇もなく噺の世界に引き込まれていく。
【あらすじ】
御店のお嬢さん”おせつ”さんの婿取りの婚礼が行われると聞いた”徳三郎”。
御店に奉公している時は、二人は将来を約束したいい仲であった。
あれだけ約束したのに婿を取るのかと思ったとたん、カーッとなって刀屋が並んだ日本橋村松町に飛んで行った。
夕方、一軒の刀屋に入って「望みはないが、とにかく切れる刀を譲ってほしい」と見つくろって貰う。
素晴らしい刀であったが高価であったので、もっと安価な刀で二人だけ切れればいいだけの刀をと頼んだ。
主人は事の裏を読んで徳三郎の気持ちを聞き出し説教をした。
友人の事だとすり替えて、二人の仲を裂いて婚礼をあげるので、式に斬り込んで彼女と婿さんを切り殺してしまう。
「貴方は?」、「それを手伝うのです」、「それでは主人殺しで大変な事になりますよ」。
それだったら、”入水”と言ういい方法がある、がどうか。
と冗談半分に言ったが徳三郎は本気になってしまった。
その時、迷子捜しの一行が入ってきた。
十八になるお嬢さんが迷子になった、と言うより足袋裸足で家から逃げ出した。
それを探している、と言う。
それを聞いて、おせつさんの事だとわかり、徳三郎はあわてて店から飛び出して、新大橋を渡って叔父さんの住まい深川佐賀町に来てみると、人とぶつかってしまった。
暗いので分からなかったが、おせつさんであった。二人はしっかりと抱擁した。
ホウヨウと言っても仏の法要ではないですよ。(^_-) と、志ん朝。
「迷子や~い、迷子や~い」の声に追われて、手に手を取って二人は仙台堀から中木場辺りに出てきた。
木場の材木の影に隠れて、やり過ごした。
「二人で死んでしまいたいが、初めてなもんで分からないがどうすればいいかね」、「お嬢さん、それでは川に飛び込みましょう」、と言う事で「南無妙法蓮華経」とお題目を唱えながら、手と手を取って川に飛び込んだ。
しかし川には筏がぎっしり繋いであったので、その上に「ドスン」と落ちてしまった。
迷子捜しがその音に気付いて探し当てた。
「良く助かったね」「助かったのはご主人様の日頃からの御祖師さまへの信心のお陰だね」「そうかぃ ?」「 そーだとも、御材木(お題目)のお陰で助かりました」
出典:落語の舞台を歩く
【オチ・サゲ】
地口落ち(地口とは駄洒落。同じ音を持った別の言葉と結びついて終わるもの。)
【語句豆辞典】
【南無妙法蓮華経】
日蓮系・法華経系の宗教団体などにおいて勤行の際に用いられる南無妙法蓮華経(なんみょうほうれんげきょう、なむみょうほうれんげきょう)の文句のことである。お題目とも言う。妙法蓮華経(法華経)の法{御教え(みおしえ)}に帰依(きえ)することである。
【噺の中の川柳・譬(たとえ)】
『世の中で 金と女は かたきなり 早く仇に巡り会いたい』
『外面如菩薩 内面如夜叉』(女性を指して、外見は美しい顔をしていても、内に恐ろしく凶悪な心を秘めていること。お釈迦様の言葉とされている。)
『宗論は誰が負けても、釈迦の恥』
『天上天下唯我独尊』(釈迦が誕生したときに、七歩歩いて右手で天を指し、左手で地をさしてと言った、という逸話から出てきたものであり、しばしば釈迦を崇める言葉として使われる。「この世で最も尊いのは自分である。なぜなら、この世に自分(という存在)は一人だけである」という意味)
【この噺を得意とした落語家】
・六代目 三遊亭園生
・三代目 古今亭志ん朝
・五代目 古今亭志ん生
【落語豆知識】 開口一番
寄席.落語会で最初演じられる物または人おもに前座が勤める。



般若心経 (Han-nya singyou)
長い噺なので寄席などでは前半「花見小僧」と後半「刀屋」に分けて演じられている。
前半は、お嬢さんのおせつと奉公人の徳三郎があやしいと番頭に言われた旦那が、小僧を呼び出し花見に行った時の経緯を飴と鞭を使い分けながら訊き出すという滑稽噺。
後半の「刀屋」は、お店を首になった徳三郎がお嬢さんの婚礼があることを知り、頭に血が上って契りを交わしたのに裏切ったと刀屋に駆け込んで刀を買おうとするが怪しまれ事情を話したところ、店の主人に「不義理な女を殺してもしようがない、懸命に働いて立派なお店の主人となって見返してやれ」と諭しているところへ、お嬢さんが婚礼の席からいなくなったと頭が駆け込んでくる。
人情噺の傑作、客は息付く暇もなく噺の世界に引き込まれていく。
【あらすじ】
御店のお嬢さん”おせつ”さんの婿取りの婚礼が行われると聞いた”徳三郎”。
御店に奉公している時は、二人は将来を約束したいい仲であった。
あれだけ約束したのに婿を取るのかと思ったとたん、カーッとなって刀屋が並んだ日本橋村松町に飛んで行った。
夕方、一軒の刀屋に入って「望みはないが、とにかく切れる刀を譲ってほしい」と見つくろって貰う。
素晴らしい刀であったが高価であったので、もっと安価な刀で二人だけ切れればいいだけの刀をと頼んだ。
主人は事の裏を読んで徳三郎の気持ちを聞き出し説教をした。
友人の事だとすり替えて、二人の仲を裂いて婚礼をあげるので、式に斬り込んで彼女と婿さんを切り殺してしまう。
「貴方は?」、「それを手伝うのです」、「それでは主人殺しで大変な事になりますよ」。
それだったら、”入水”と言ういい方法がある、がどうか。
と冗談半分に言ったが徳三郎は本気になってしまった。
その時、迷子捜しの一行が入ってきた。
十八になるお嬢さんが迷子になった、と言うより足袋裸足で家から逃げ出した。
それを探している、と言う。
それを聞いて、おせつさんの事だとわかり、徳三郎はあわてて店から飛び出して、新大橋を渡って叔父さんの住まい深川佐賀町に来てみると、人とぶつかってしまった。
暗いので分からなかったが、おせつさんであった。二人はしっかりと抱擁した。
ホウヨウと言っても仏の法要ではないですよ。(^_-) と、志ん朝。
「迷子や~い、迷子や~い」の声に追われて、手に手を取って二人は仙台堀から中木場辺りに出てきた。
木場の材木の影に隠れて、やり過ごした。
「二人で死んでしまいたいが、初めてなもんで分からないがどうすればいいかね」、「お嬢さん、それでは川に飛び込みましょう」、と言う事で「南無妙法蓮華経」とお題目を唱えながら、手と手を取って川に飛び込んだ。
しかし川には筏がぎっしり繋いであったので、その上に「ドスン」と落ちてしまった。
迷子捜しがその音に気付いて探し当てた。
「良く助かったね」「助かったのはご主人様の日頃からの御祖師さまへの信心のお陰だね」「そうかぃ ?」「 そーだとも、御材木(お題目)のお陰で助かりました」
出典:落語の舞台を歩く
【オチ・サゲ】
地口落ち(地口とは駄洒落。同じ音を持った別の言葉と結びついて終わるもの。)
【語句豆辞典】
【南無妙法蓮華経】
日蓮系・法華経系の宗教団体などにおいて勤行の際に用いられる南無妙法蓮華経(なんみょうほうれんげきょう、なむみょうほうれんげきょう)の文句のことである。お題目とも言う。妙法蓮華経(法華経)の法{御教え(みおしえ)}に帰依(きえ)することである。
【噺の中の川柳・譬(たとえ)】
『世の中で 金と女は かたきなり 早く仇に巡り会いたい』
『外面如菩薩 内面如夜叉』(女性を指して、外見は美しい顔をしていても、内に恐ろしく凶悪な心を秘めていること。お釈迦様の言葉とされている。)
『宗論は誰が負けても、釈迦の恥』
『天上天下唯我独尊』(釈迦が誕生したときに、七歩歩いて右手で天を指し、左手で地をさしてと言った、という逸話から出てきたものであり、しばしば釈迦を崇める言葉として使われる。「この世で最も尊いのは自分である。なぜなら、この世に自分(という存在)は一人だけである」という意味)
【この噺を得意とした落語家】
・六代目 三遊亭園生
・三代目 古今亭志ん朝
・五代目 古今亭志ん生
【落語豆知識】 開口一番
寄席.落語会で最初演じられる物または人おもに前座が勤める。



般若心経 (Han-nya singyou)











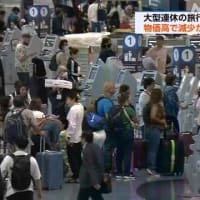
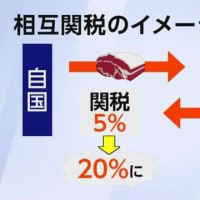







コメントありがとうございます。
寄席の入場料、末広亭で3000円程度でしょうか。
私も東京に住んでいた頃は同じ思いをしたことがあります。
若い頃、約三十年前の新婚時代、川越市に住んでいました。的場という所で、駅は霞ヶ関でした。懐かしいですね。休みの日には川越の「丸広」というデパートに買い物に行っていました。