都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「作品のない展示室」 世田谷美術館
世田谷美術館
「作品のない展示室」
2020/7/4~8/27

新型コロナウイルス感染症の影響により、展覧会スケジュールの変更を余儀なくされた世田谷美術館が、一切の作品を展示せずに、美術館の空間のみを公開する「作品のない展示室」を開催しています。
1986年、建築家の内井昭蔵の設計によって建てられた世田谷美術館は、数多くの展覧会を企画し続けながら、音楽会やダンスの公演などの様々なプログラムを行ってきました。
内井が美術館の設計に際して重要だと考えたのが、「生活空間としての美術館」、「オープンシステムとしての美術館」、「公園美術館としての美術館」の3つのコンセプトで、砧公園の自然環境と一体化すべく、窓を多く取り入れるなど、開放的な建物として築かれました。

実際に受付から展示室内へのアプローチは、左右がガラスに覆われていて、光が降り注ぐとともに、屋外の緑を目にすることもできました。しかし展示室に関しては、絵画などの作品を光から守るため、多くの窓がふさがれるなど、公園と一体となった環境は感じられませんでした。

よって今回の「作品のない展示室」では、多くの窓を覆う壁を取り放っていて、外の光を感じながら、公園の緑を見やることができました。

私自身もこれほど多くの窓が開けられた展示室を見たのは初めてでしたが、いかに美術館が自然に囲まれた恵まれた環境であるのかがよく分かりました。

それこそ窓をフレームとして捉えれば、屋外の緑は絵画の一場面のようで、驚くほどに美しい空間が広がっていることを見て取れました。
また展示室の随所には内井の言葉も紹介されていて、それぞれのテキストを通し、言わば建築設計を支えたの根本的な思想の一端についても触れることができました。
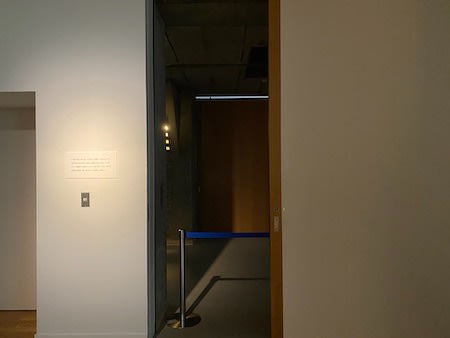
さらに搬入のための開口部も特別に開けられていて、普段は意識することの少ない美術館の機能についての知見も得られました。
最後のスペースでは、特集「建築と自然とパフォーマンス」と題し、開館以来行われてきたパフォーマンスの記録写真や映像、それにチラシのアーカイブなども紹介されていました。

ぼんやりと窓の外の景色を眺めながら、展示室を行き来していると、扇型から長方形へと前後で変化する空間の面白さと、力強いまでの建物の量感を覚えてなりませんでした。

いわゆるコロナ禍に伴う企画ではありますが、世田谷美術館の魅力を再発見できるような展覧会と言えるかもしれません。

なお同館の2階展示室では、「ミュージアム コレクションⅠ気になる、こんどの収蔵品―作品がつれてきた物語」と題した所蔵作品展を開催中です。(コレクション展は有料)
ここでは、近年収蔵された版画や洋画、それに彫刻などの作品、約120点が紹介されていて、とりわけ和紙にバレンで山の木立を表したジョルジュ・ヴェンガーの版画と、ヨーロッパ遊学先で見た人々を大津絵風に描いた小川千甕の着彩の木版などに目を引かれました。
最後に新型コロナウイルス感染症対策についての情報です。入館時はマスク着用の上、消毒、及び検温、また名前などの連絡先を記入する必要があります。マスクを着用していなかったり、37.5度以上の体温がある際は入館できません。一方でレストランやカフェ、ショップは通常通り営業していました。

私が出向いた日は、いかにも梅雨らしい雨混じりの曇天でしたが、これから夏の強い日差しが照る季節に入ると、また違った景色に映るのかもしれません。

一部を除き、会場内の撮影も可能でした。8月27日まで開催されています。
「作品のない展示室」 世田谷美術館(@setabi_official)
会期:2020年7月4日(土)~8月27日(木)
休館:毎週月曜日。(祝・休日の場合は開館、翌平日休館)
*8月10日(月・祝)は開館、翌8月11日(火)は休館。
時間:10:00~18:00
料金:無料
*コレクション展は一般200円、65歳以上、大高生150円、中小生100円。
住所:世田谷区砧公園1-2
交通:東急田園都市線用賀駅より徒歩17分。美術館行バス「美術館」下車徒歩3分。
「作品のない展示室」
2020/7/4~8/27

新型コロナウイルス感染症の影響により、展覧会スケジュールの変更を余儀なくされた世田谷美術館が、一切の作品を展示せずに、美術館の空間のみを公開する「作品のない展示室」を開催しています。
1986年、建築家の内井昭蔵の設計によって建てられた世田谷美術館は、数多くの展覧会を企画し続けながら、音楽会やダンスの公演などの様々なプログラムを行ってきました。
内井が美術館の設計に際して重要だと考えたのが、「生活空間としての美術館」、「オープンシステムとしての美術館」、「公園美術館としての美術館」の3つのコンセプトで、砧公園の自然環境と一体化すべく、窓を多く取り入れるなど、開放的な建物として築かれました。

実際に受付から展示室内へのアプローチは、左右がガラスに覆われていて、光が降り注ぐとともに、屋外の緑を目にすることもできました。しかし展示室に関しては、絵画などの作品を光から守るため、多くの窓がふさがれるなど、公園と一体となった環境は感じられませんでした。

よって今回の「作品のない展示室」では、多くの窓を覆う壁を取り放っていて、外の光を感じながら、公園の緑を見やることができました。

私自身もこれほど多くの窓が開けられた展示室を見たのは初めてでしたが、いかに美術館が自然に囲まれた恵まれた環境であるのかがよく分かりました。

それこそ窓をフレームとして捉えれば、屋外の緑は絵画の一場面のようで、驚くほどに美しい空間が広がっていることを見て取れました。
また展示室の随所には内井の言葉も紹介されていて、それぞれのテキストを通し、言わば建築設計を支えたの根本的な思想の一端についても触れることができました。
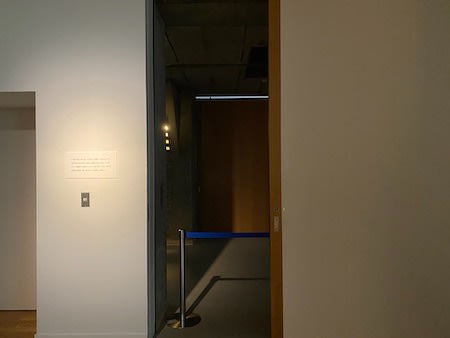
さらに搬入のための開口部も特別に開けられていて、普段は意識することの少ない美術館の機能についての知見も得られました。
最後のスペースでは、特集「建築と自然とパフォーマンス」と題し、開館以来行われてきたパフォーマンスの記録写真や映像、それにチラシのアーカイブなども紹介されていました。

ぼんやりと窓の外の景色を眺めながら、展示室を行き来していると、扇型から長方形へと前後で変化する空間の面白さと、力強いまでの建物の量感を覚えてなりませんでした。

いわゆるコロナ禍に伴う企画ではありますが、世田谷美術館の魅力を再発見できるような展覧会と言えるかもしれません。

なお同館の2階展示室では、「ミュージアム コレクションⅠ気になる、こんどの収蔵品―作品がつれてきた物語」と題した所蔵作品展を開催中です。(コレクション展は有料)
ここでは、近年収蔵された版画や洋画、それに彫刻などの作品、約120点が紹介されていて、とりわけ和紙にバレンで山の木立を表したジョルジュ・ヴェンガーの版画と、ヨーロッパ遊学先で見た人々を大津絵風に描いた小川千甕の着彩の木版などに目を引かれました。
【世田谷美術館HPのお知らせ】7月1日(火)の新着情報「2020年度展覧会スケジュールの変更について」をアップしました。 #世田谷美術館https://t.co/mnACpRPKxK
— 世田谷美術館 (@setabi_official) July 2, 2020
最後に新型コロナウイルス感染症対策についての情報です。入館時はマスク着用の上、消毒、及び検温、また名前などの連絡先を記入する必要があります。マスクを着用していなかったり、37.5度以上の体温がある際は入館できません。一方でレストランやカフェ、ショップは通常通り営業していました。

私が出向いた日は、いかにも梅雨らしい雨混じりの曇天でしたが、これから夏の強い日差しが照る季節に入ると、また違った景色に映るのかもしれません。

一部を除き、会場内の撮影も可能でした。8月27日まで開催されています。
「作品のない展示室」 世田谷美術館(@setabi_official)
会期:2020年7月4日(土)~8月27日(木)
休館:毎週月曜日。(祝・休日の場合は開館、翌平日休館)
*8月10日(月・祝)は開館、翌8月11日(火)は休館。
時間:10:00~18:00
料金:無料
*コレクション展は一般200円、65歳以上、大高生150円、中小生100円。
住所:世田谷区砧公園1-2
交通:東急田園都市線用賀駅より徒歩17分。美術館行バス「美術館」下車徒歩3分。
コメント ( 1 ) | Trackback ( 0 )









