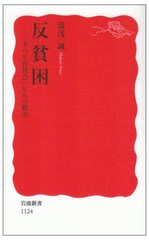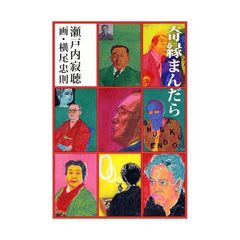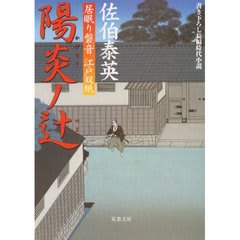湯浅 誠 著、岩波文庫
小泉、安倍政権の新自由主義政策のもと、日本社会の格差は、確実に広がりかつ深刻になった。その事実の、貧困問題の現場からの報告である。
著者は、1969年生まれ。東大大学院博士課程終了中退。95年よりホームレス支援活動に従事。反貧困ネットワーク事務局長、NPO法人自立生活サポートセンターもやい事務局長。
著者の思いは、一度転んだらどん底まですべり落ちていってしまう”すべり台社会”の中で、「このままいったら日本はどうなってしまうのか」という不安が社会全体に充満しており、(中略)「このままではまずい」と「どうせ無駄」の間をつなぐ活動を見つけなければならない、というところにある。
彼が取り上げる事例の一つ一つは、われわれが、ニュース報道でその悲惨さに胸を塞がれた、この数年の出来事ばかりである。にも拘わらず、多くの日本人は、まだ、それほど酷い貧困の中にあるとは実感できていない。それこそが問題なのだと著者は訴える。
的確に提示された研究書や調査統計資料を順に目にした時、今更ながら事の深刻さに愕然とする。身の毛がよだつと言ってもいい。以下若干。
今や全労働者の三分の一(1736万人)が非正規社員であり、若年層では45.9% になる。
国民健康保険料の滞納に背景には、加入者の49.4%が60歳以上、53.83%が無職、61.5%が年収200万円以下とい事情がある。
生活保護費の、必要の無いところへの支給が14669件、本当に必要な人にいきわたっていないのが600万人という事実がある。
日本社会の自殺者は、9年連続で3万人を超す。残された遺書から、1万人が生活苦が理由である。
著者は言う。なぜ政府は貧困と向き合いたがらないのか。貧困はあってはならないからだ。 最低生活費以下で暮らす人が膨大に存在することは憲法25条違反にあたる。国にはその違憲状態を解消する義務が生じる。貧困問題の解決は政治の重要な目的の一つである。しかしこれは小さな政府路線の根本的な修正になるからだ。
’あとがき’から 考えれば考えるほど、この「すべり台社会」には出口がない、と感じる。もはやどこかで微修正を施すだけではとうてい追いつかない。正規労働者も非正規労働者も、自営業者も失業者も、働ける人も働けない人も、闘っている人もそうでない人も、それぞれが大きな転換を迫られていると感じる。問われているのは”国の形”である。ひとつひとつ行動し、仲間を集め、場所を作り、声をあげていこう。あっと驚くウルトラの近道はない。それぞれのやっていることをもう一歩進め、広げることだけが、反貧困の次の展望を可能にし、社会を強くする。貧困と戦争に強い社会を作ろう。今、私たちはその瀬戸際にいる。
当代屈指のブロガー田中宏和は湯浅誠を、「現在の日本で湯浅誠以上の社会科学の説得力は他にない。ようやく出てきた待望の若い理論家。それはやはりと言うか、アカデミーの内ではなく外から出てきた。わたしはそれを待っていた。私を恍惚とさせたもう一人の若い知性、正義のカリスマの本村洋も、裁判所でもなく国会でもなく大学でもなく、市井から出現した。無名の市民から現れて神の存在になった。日本を変えるべき二人目のカリスマ。この男にはコミットできる。日本の救世主だ。知性と理論に間違いがない。不足が無い。欠点がない。冷静であり。政治と行政をよく見ている」と、最大級の讃辞で宣揚している。