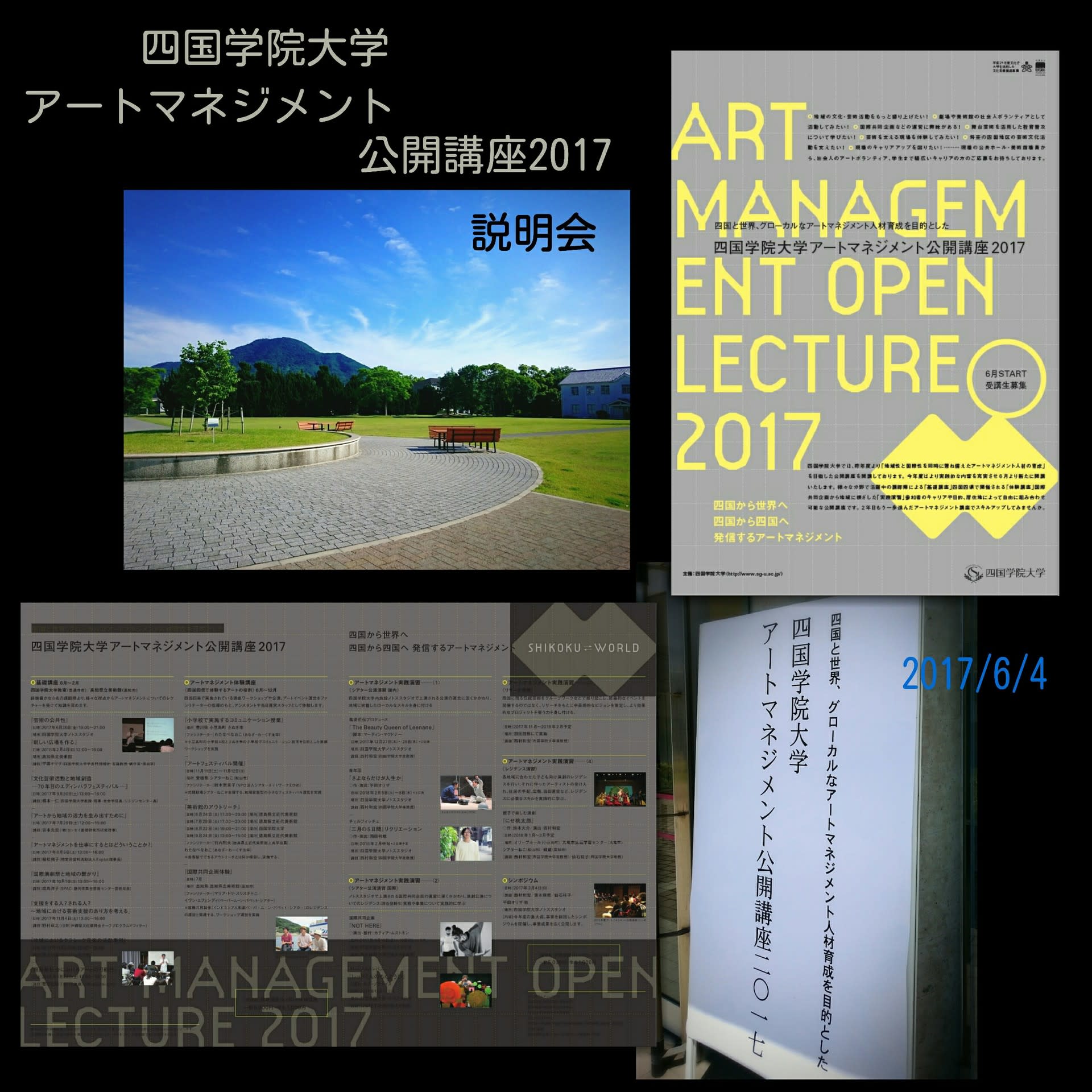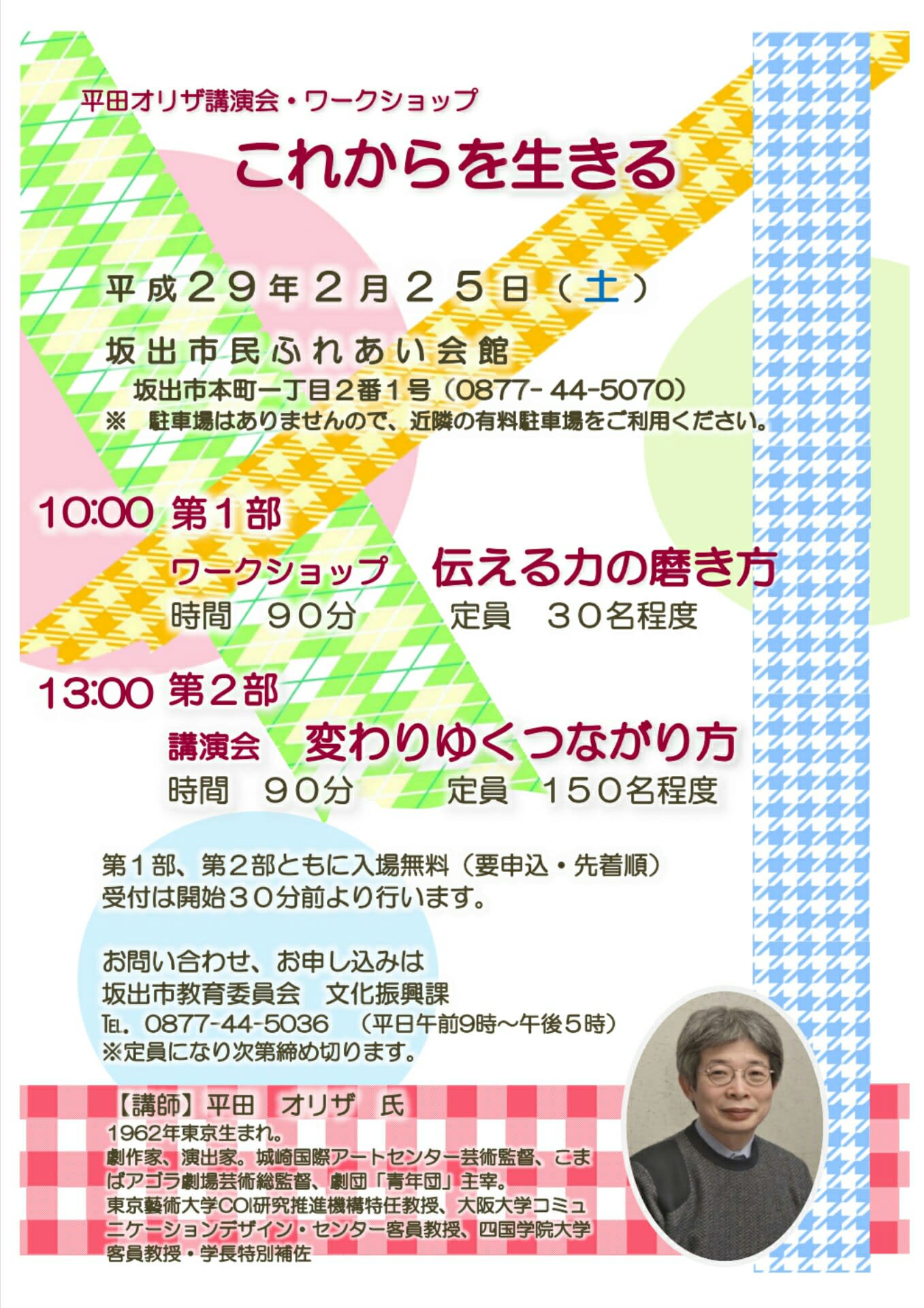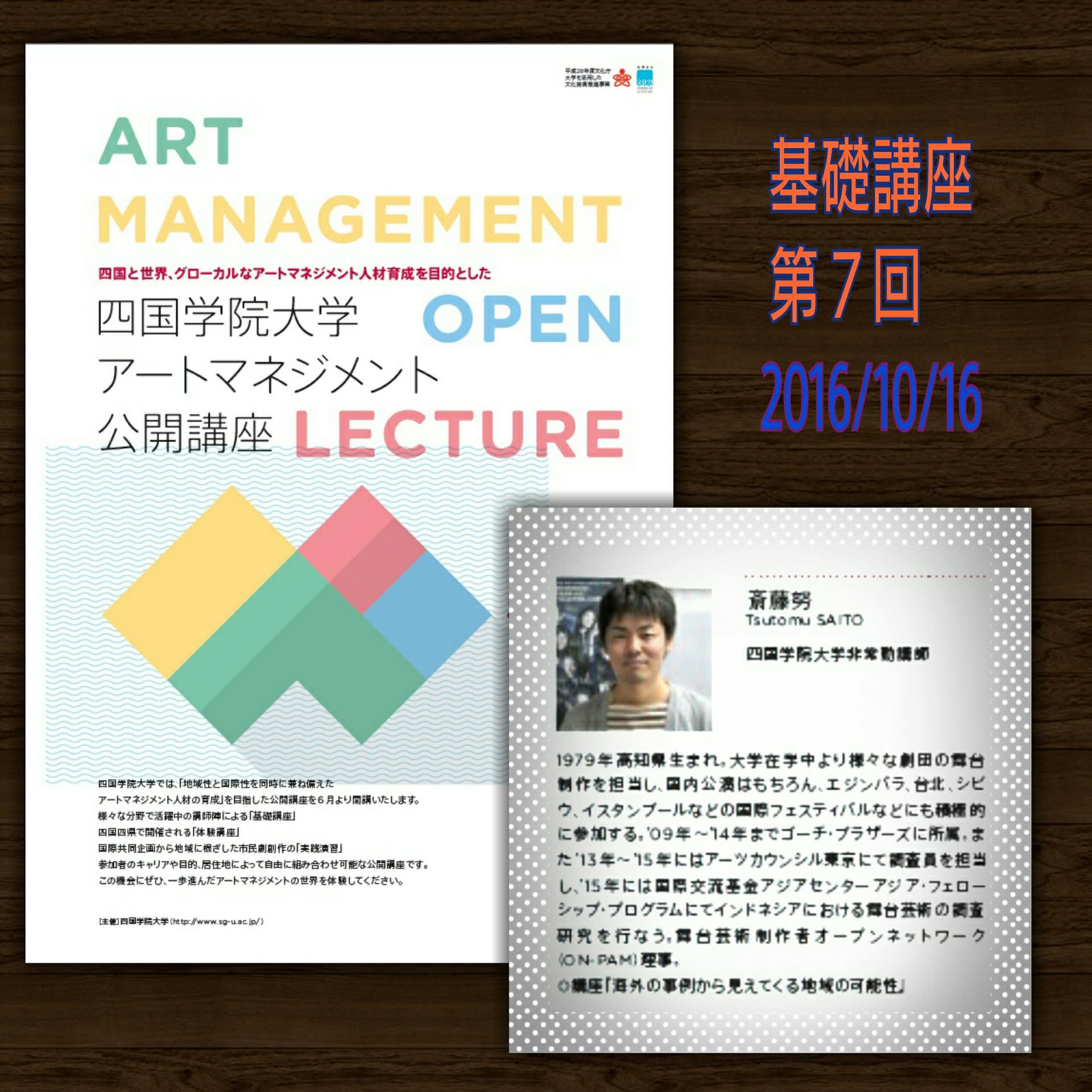7/9(日)
人形作りワークショップ
『Puppetry for all みんなのための人形劇』
http://www.notos-studio.com/contents/event/event/2440.html
アートマネジメント公開講座
体験講座『国際共同企画』のひとつ。
インドネシアの現代人形劇のカンパニー
「ペーパームーン・パペット・シアター」
その公演が、7/27~28
高知県立美術館で開催される。
http://www.kochi-bunkazaidan.or.jp/~museum/contents/hall/hall_event/hall_events2017/ppt/hall_event17papermoon.html
それに関連し、四国学院大学で
人形作りのワークショップが行われた。
受講生は、運営のお手伝い、
ワークショップの見学ができる。
小学生の子どもがいる人は、
一緒にワークショップに参加できる
とのことだったので三女を連れて。
場所はいつものノトススタジオではなく
そこより西、大学の南側。
最近改装された稽古場らしい。
……………………
講師は
インドネシアの現代人形劇のカンパニー、
ペーパームーン・パペット・シアターの
アーティスト。
通訳を介しての挨拶から始まったが、
ご夫婦で 幼いお子さん連れ
ということもあり、一気に和む。
作る人形は自由。
画用紙に作りたいものを
描くところからスタート。
自分も三女も、何も考えてなかったけれど
思い付きで描き始めた。
それをもとに、人形作り。
配られた新聞紙を丸めて固めて、
白い幅広のマスキングテープを巻いて
形を作っていく。
ひとつの見本として人形を見せてくれた。
目やまぶたが立体的になっている!
間近で見たのを思い出して真似てみた。
三女は三角の耳をつけるのに苦戦していた。
平面で描けば三角でも、立体になると
奥行きがどのようになるか
ちょっと悩むのかもしれない。
時間も限られてるので、そこはお手伝い。
三角おにぎりをちょっとアレンジする
要領で新聞紙を丸める。
そんな風に手伝ったり、
どうしたらいいか尋ねられたことに
答えたりしながらも
自分の人形作りに没頭した。
他の方たちの様子を見る余裕は
なかったのが残念だけど、
一参加者として楽しませてもらった。
出来上がった頭、体、両腕を
平たいテープ状の紐で繋げて
動かせるようにしてもらった。
好きな色の和紙をちぎり、
水で溶いたボンドを筆で塗りながら
貼り付けていった。
そこからは、とにかく地道な作業。
そうこうするうち
あっという間の3時間。
未完成の方も多かったけれど終了。
色の和紙を貰って帰り、続きは家で。
最後に、舞台で使われている
実際の人形を動かして見せてくれた。
目の玉のビー玉がキラッと光り
まるで生きているようでドキッとした。
人形の両足のかかとは
足の指で挟んで動かせるようになっていた。
生きている人が乗り移ったような動きが
面白かった。
解散後は、子どもたちにも
その人形を触らせてくれた。
三女は側に寄るのをためらっていたが、
同じテーブルで仲良くなった子が
触っているのを見て近付き
いつの間にか頭を動かすのを
やらせてもらっていた。
とても楽しそうだった。
言葉も分からないのに
子どもは雰囲気で溶け込めるのか。
また、アーティストの方に
引き寄せるものがあるのか。
とにかく、面白かった人形作り。
鼻の頭から汗が垂れるのも
気にならないくらい
没頭できたのは久しぶりだった。
まだ色の和紙を貼る途中なので、
仕上げて完成させたい。