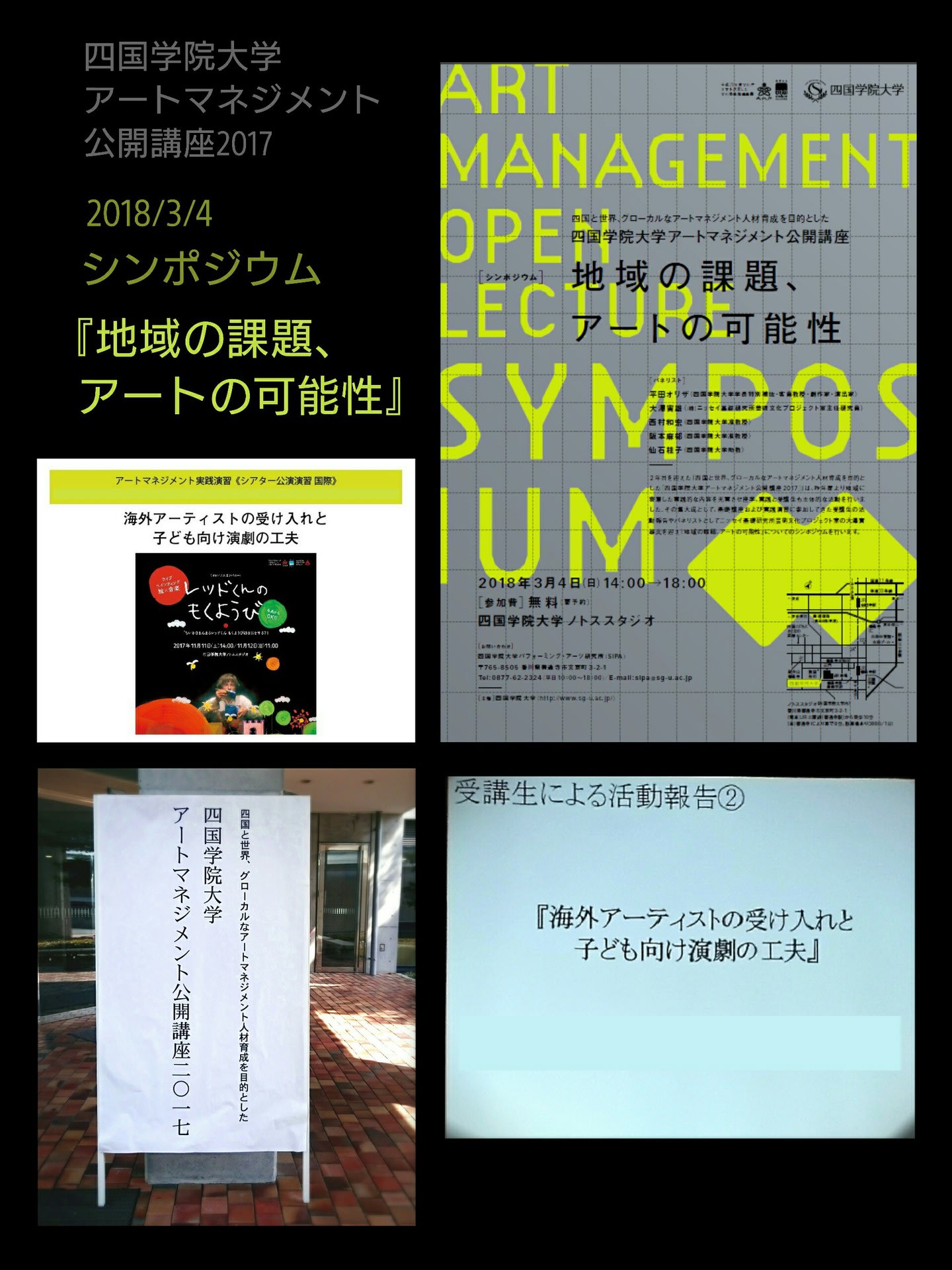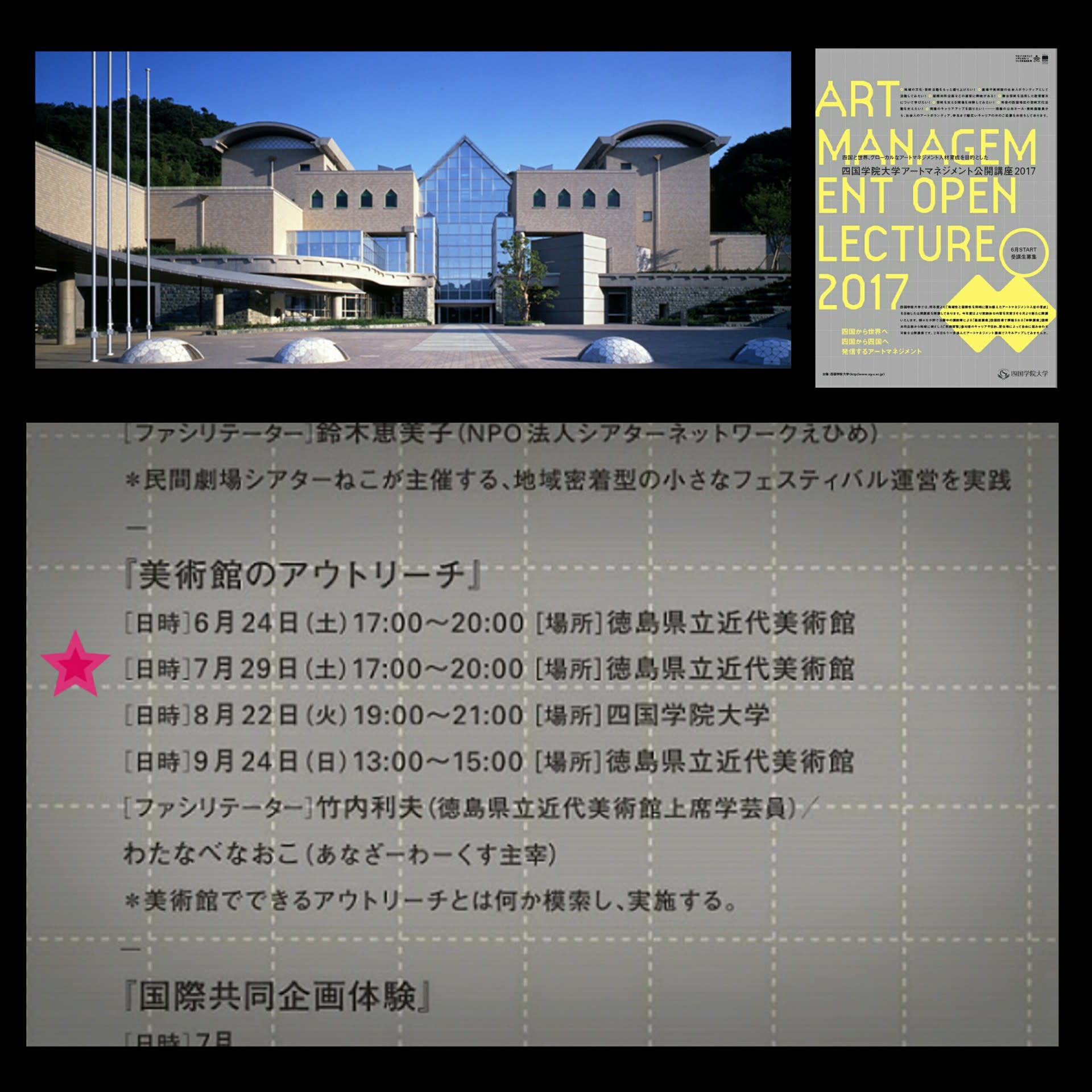8/5(土)
四国学院大学
アートマネジメント公開講座2017
基礎講座
『アートマネジメントを仕事にするとは
どういうことか?』
講師:植松侑子(特定非営利活動法人Explat)
舞台芸術的の現場や海外での活動など
様々な経験をされてきた中で、
アートマネジメントの
具体的な仕事についてのお話があった。
まだ認知が進んでいない現状や
これからの人材育成、課題についても。
ワールドカフェ方式で、3人1組での
リラックスした話し合いもできた。
…………………………
まとまってませんが、内容を
↓
舞台芸術には専門知識は必要だが、
その場で経験しないと分からないものの
割合が高い傾向にあるとのこと。
舞台芸術のアートマネジメントの仕事は
新しい職種で、まだ職業分類に入っておらず
まだ多くの人に認知されていない。
仕事をする上では
セルフプロモーションが重要で、
自分が何を考え 何をやっているかを
伝えられなければならないとのこと。
顧客にとっての価値を高めていく
マーケティング戦略が必要。
また、きちんと値段交渉すること。
単位制を導入したことなどの話があった。
気持ちよく仕事ができなかったり
自分でなくてもいいのなら、
断ることも大切とのこと。
ちなみに、この辺りの話を聞いて
主婦の家事や地域の仕事を思い起こした。
主婦の仕事も
あまり認知されているとは言えず、
考えや、やっていることが
きちんと周囲に伝わっていないことも多い。
際限なく予定外のことが入ってくる割に
断りきれずなし崩しに受けては
無理が生じたり、優先順位を誤ったりする。
仕事量は他と比較にならないかもしれないが
より私生活に入り込んでいる分、
マネジメントは必要なのかもしれない。
話を舞台芸術に戻す。
舞台芸術の強み、演劇の力には
今に必要なものがある。
一般の会社や色々な業界の人たちと
どう接点を持てばいいのか?
社会課題を解決するために
企業、行政、非営利組織、3つ(トライ)の
垣根を超えて活躍する
トライセクター・リーダーという
人材がいるそうだ。
そこに、教育機関が加わった4つに
関わり、それぞれの強みを活かせる
リーダーが必要。
それほど必要性のある仕事でありながら
生涯の仕事として続ける環境が整っていない。
それは社会的認知度が低いからでもある。
美術館、博物館の学芸員や
図書館の司書は知られているが、
劇場、ホールには統一した職業名や資格がない。
これからは、
地域のコミュニティの拠点で
それぞれの場を活かす専門人材が必要。
地元の文化や魅力の集積地にならなければ、
どこに行っても同じような
ショッピングモール以上の魅力を持てない。
植松さんのExplatでの
新しい人材育成プログラムが興味深い。
マネジメント専門員の志向性を
強みや興味関心によって6タイプに分類。
↓
●クリエーション
現場の最前線。
●コミュニティ
地域の人達や特定のコミュニティに対して
何ができるか。
●プラットホーム
その劇場などの組織に どれだけ
色々な人に関わってもらえるか、
器を機能させる。
●サポート
行政、アーティストを支える。
●ネットワーク
遠く離れた人と人を繋ぐ。
●アントレプレナー
この業界にないものを新たに立ち上げていく。
ビジネスモデルとして…
例) 折り込みチラシ専門、など
このようなことについて、
一人が複数の志向性を持っていることが多い。
そして、これまでの経験や現場を踏むことで変わっていくことがある。
そんな適材適所ができるシステムが確立できれば
この業界は活性化できる。
…………………
休憩の後は、参加型。
ワールドカフェという議論の方法で。
できるだけ初対面の3人くらい1組になる。
① 協力的な雰囲気でリラックスして
② お互いに意識を集中
③ 議論ではなく、対話(即否定しない)
④ 知識より 実感、体験を大切に
⑤ 話は短く簡潔に
1人1分ずつ。お題に沿って話す。
1分で声かけがあり、交代する。
↓
① 舞台芸術との出会いは何?(原体験)
② 舞台芸術のマネジメントを
やろうと思ったのはなぜ?
③ 舞台芸術の専門人材として、
今自分に足りてないと思うことは?
④ 今 戸惑っていること、
悩んでいること、困っていることは?
(発表はせず個人で考える)
⑤10~20年後、49%の仕事が
ロボットに代替されると
言われている。マネジメントの仕事は
ロボットに代替される可能性は
高いか低いか?
2011年入学の小学生の65%は大卒時、
今存在しない職に就くだろうと
言われていることをふまえて。
(発表はせず個人で考える)
話し合いは短いながらも色々話せた。
それぞれの話の中から
アートマネジメントの仕事について
考える糸口を見つけていった。
その他、興味深かった、
「没入感」を
高めるためのチェックリスト
① 仕事の難易度……適切に難しい
② 対象への統制感…
やったことがどう変化を起こしたか
感じられる
③ ダイレクトフィードバック…
何かアクションをとった時に
早く反応がある
④ 外乱のシャットアウト…
外から中断されるような要素が
入ってこない
没入できることで
仕事を続けられる、
という話だったと思う。
……………………
強みをいかに仕事に活かしていくか。
日本の教育の傾向では、弱点を
どう克服できるかという考えがち。
自分の弱点にはよく気付くもの。
しかし克服するのは大変で、
頑張ったとしても平均にしかならない。
それよりも、自分の強みを磨き、
誰にも負けない武器にすることが
大切なのではないか。
★強みは4つに分類できる
① 知識
② 技術
③ 才能
*無意識に繰り返される思考、感情、行動のパターン(誰にでもある)
④身体的・体質的ボーナス
①知識②技術は
努力によって誰でも取得可能
後天的なもの
③才能④身体的…は
その人独自のもの
先天的なもの
これに気付いて磨いて武器にしていく
そのために有効なものとして
↓
★VIA 強みの無料診断
才能を見つけるツール
24の強みから5つの組合わせを選んでくれる
悩んでいることは、自分の強みと
マッチングしていないと思われる。
志向性と強みにマッチングしていないと
苦痛になる。
自分にとっても所属している
組織に対しても良くない。
●6つの志向性
●強みのタイプ診断
●悩み
これらから、
自分の方向性が見えてくる。
★資料のプリント
制作マニュアルの一覧表
“舞台芸術制作者の職能をひもとく”
Next 舞台制作塾を通して見えてきた
舞台制作者の職能分類図
初心者な自分にも分かりやすかった!
………………
舞台芸術のマネージメントの
仕事についての話だったが、
どの仕事にも通じることだと思った。
それこそ一介の主婦であっても。
そして「強み」は
特別な人だけでなく
誰もが持っていそうだと思えた。
教育の面では
それぞれの個性を活かすという点でも
大事なことだろう。
皆が平均的に同じようになるよりも
早く強みに気付くために
具体的な糸口が見えた気がした。
それぞれの強みが活かされることは
その人個人にとって良いこと
であると共に
周りにとっても利があることでもある。
物事は損得ではないけれど
どちらも両立できるなら
その方が、
それこそ持続可能な社会といえる。