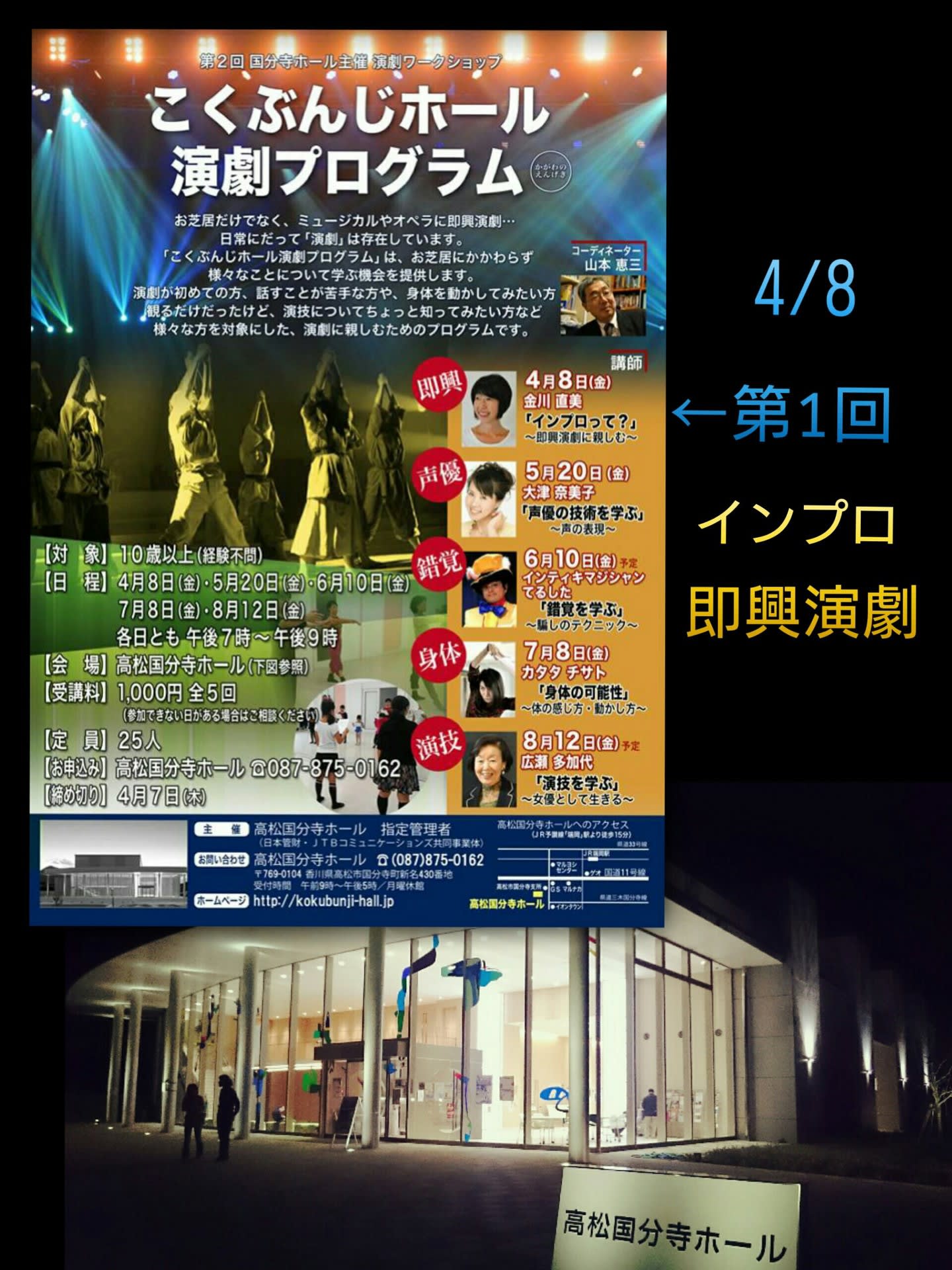8/12
こくぶんじホール
演劇プログラム 第5回
「演技を学ぶ」
~女優として生きる~
講師 広瀬多加代 さん
******
お歳を聞いてびっくり。
そんな昔から!
劇団を立ち上げた頃のお話など、
県内でも昔から演劇活動はあったこと。
子どものいじめや自殺など
問題を受けての舞台作りに
取り組んでいたお話も。
子どものことについては
今も難しい問題がある。
命を粗末に…という感覚よりも
より切羽詰まった心の問題が
広がってきている気がする現在。
それは、子どもに限ったことでなく
世の中全体に広がる大きな問題が
子どもにも影響を与えているのかも。
自分自身、演劇などの芸術で
救われることもある。
そういった意味でも、これからも
どんな人にも演劇の力は
必要なのだと思う。
そして、どんなものが
そうあることができるのか
考えていきたいと思った。
*******
技術面も大切であるとの
お話もあった。
それは基本的なことであるが
そこをクリアするのが難しいのだと。
そのひとつとして
いくつか皆で実際に
声を出してやってみた。
桃太郎の冒頭
“むかしむかし あるところに……”
からの数行。
ただ読むのではなく
その場面が想像できるような読み方。
“ 言葉が言葉として伝わる ”方法
これを聞いてハッとした。
普段そんな大切に
言葉を発しているだろうか。
伝えようという気持ちすらなく
ぞんざいに、乱暴に発している
言葉の数々を思い出して悲しくなった。
お互いにそうであるなら
言葉として間違っていなくても
伝えたいことが伝わるはずもない。
演じる人だけでなく
それを見て受け止める人も
そのことに気付くことが大切だろう。
これは舞台の上だけでなく、
日常を生きる人にとっても
切実な問題であるかもしれない。
また、自分が活動している
おはなし会などでは
絵本の読み聞かせだけでなく
絵本を使わない
素話(語り聞かせ)をすることもある。
そういう時には、
今回教えていただいたことは
おおいに参考になると思った。
言葉の意味が伝わるような
抑揚や間合いや……
自分で考えていく時の手がかりとして。
*****
『雨ニモマケズ』を
母音法(アイウエオだけで)話す練習も。
滑舌を良くするために
効果があるとのこと。
なかなか すらすらとは話せない(笑)。
これも繰り返し、続けていくことで
身に付いていくのだろう。
********
今回でこの講座は終了。
けれど この後も
このホールで学ぶ場を設けて
ゆくゆくは
舞台公演をする構想とのこと。
行き帰りに長時間かかることや
稽古の曜日に家庭の事情が
重なることもあり、
継続的には難しいけれど
せっかくのご縁なので
何らかの形で関わりを
持てたらなとは思っている。
ちょうど帰り際に
声をかけてくれた方と
少しお話することができた。
皆さん演劇を求める気持ちは
同じだなぁと。
自分なりの関わり方を
探していきたいなと思った。
全5回の講座
本当にお世話になりました!