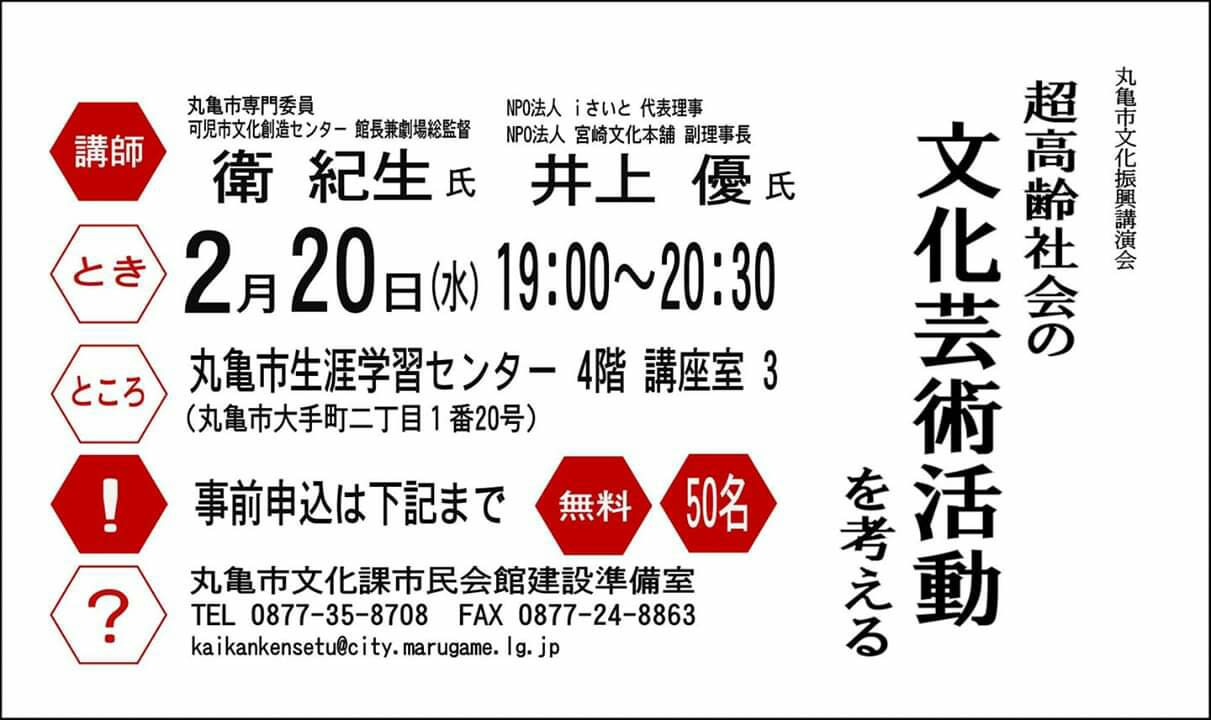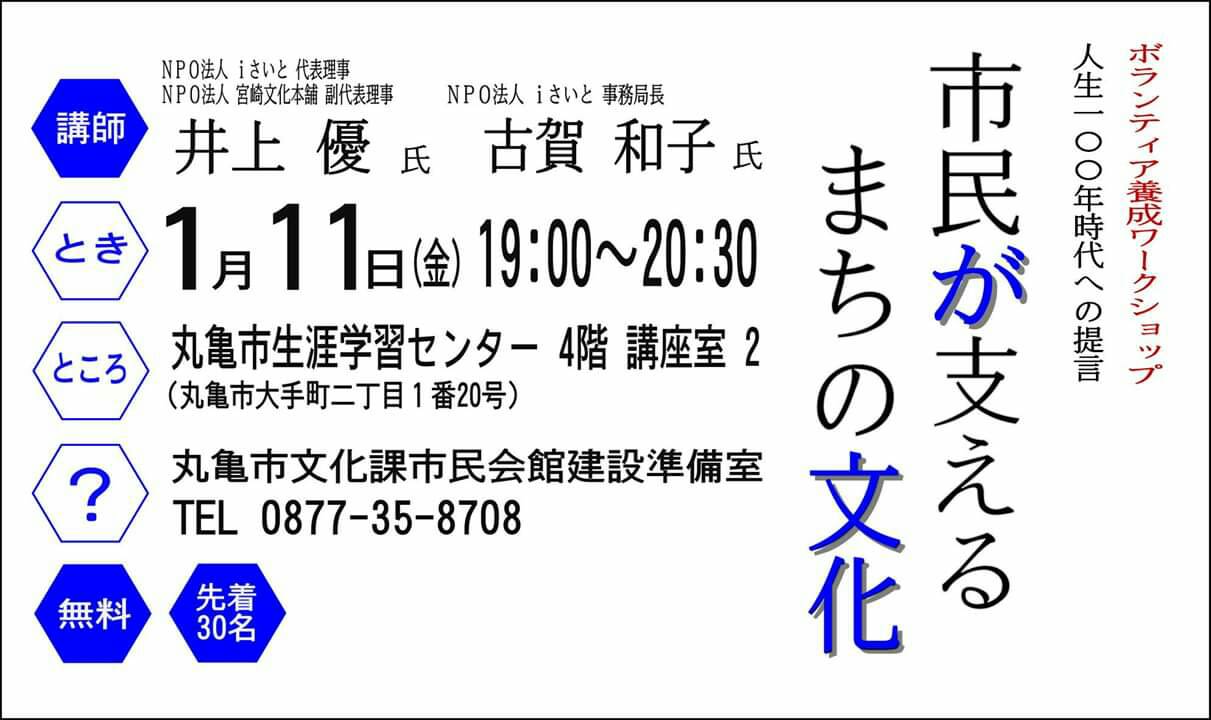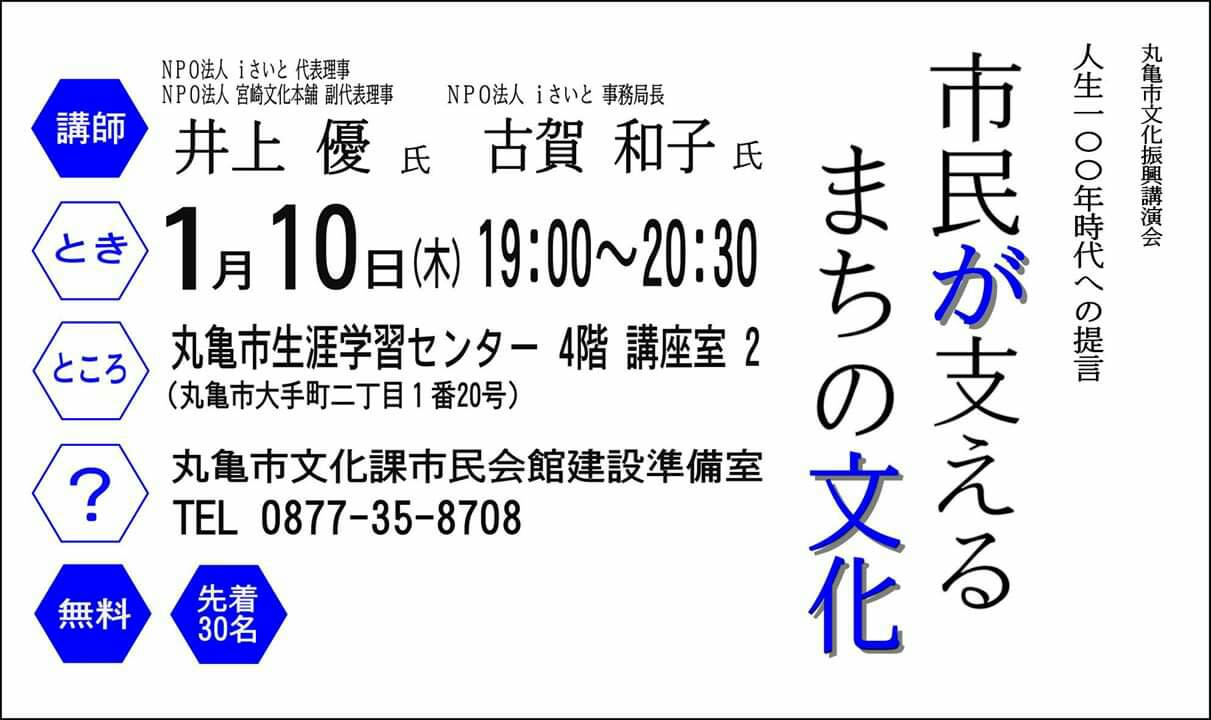アートマネジメント公開講座2018
実践演習『リサーチ演習』
四国の伝統芸能のマネジメントを考える
~徳島県人形浄瑠璃、愛媛県内子座から~
2019/3/7(木) 20:00~21:30
四国学院大学内教室826
講師:
佐藤憲治
(徳島県立阿波十郎兵衛屋敷 館長。徳島県の主要な文化施設の整備・運営や阿波人形浄瑠璃、阿波藍、音楽の振興など、長年にわたり徳島の文化振興に従事。NPO法人阿波農村舞台の会の設立)
徳永高志( 茅野市民館コアアドバイザー、慶應義塾大学大学院アートマネジメントコース非常勤講師。内子座、町立久万美術館、淡路人形座のほか、伊予市、神戸市の文化施設計画や文化政策にもかかわる)
…………………………………
うまくまとめられませんでしたが
忘れないように(笑)
感想を交えつつメモしたものです。
■「伝統芸能」の現在と未来
・伝統芸能とは何か?
古いものだけでなくその様式や手法などを使い
新しいものも作られている。
自分達の生活から遠いものではない。
・四国の伝統芸能
人形浄瑠璃、神楽、歌舞伎
徳島から愛媛に伝播いていった歴史あり
昔は現代のように交通は発達していなかったが
交流があったようだ。
吉野川を利用した水運が発達していた。
・土佐藩の「芝居禁止」と絵金
四国でも藩によって違いあり。
政治的な背景などにより。
・個別の事例から
阿波人形座、内子座など芝居小屋、茂山狂言
・伝統芸能が直面する課題
継承、鑑賞、地域
……………………
藍や農作物などで潤った経済力で
人形の芸能が発展してきた歴史がある。
徳島には農村舞台が沢山残されている。
それを活かすために活動が行われている。
観客を呼ぶための工夫。
周遊の船などのミニツアーやグッズなど。
次の世代へ。
高校の民芸部→卒業生が人形座
学校での指導は、以前の経験者
継続して次の世代に伝える必要はある。
でも、やらされる感があっては
続かないのだろう。
楽しいということが大事。
年上の子が楽しそうにやっている、
その姿がかっこいい、など
身近なモデルも大切なのだろう。
自分の身近なところでは
獅子舞などがあるが
やはり氏子が減っていたり
夜の練習の負担などの問題はあるようだ。
関わりをもつのは
良いことだと思うのだけど
それぞれに合ったやり方など
もっとうまくいく方法はないかな…と思う。
やはり続けることや継いでいくことに
大変さは付き物なのだと思う。
ただ、そこに楽しさや
やりたくなる気持ちがあれば
心が動き、体も動く。
それを大切にしたい。
忠臣蔵を例に、
古いものが若い世代が知られていない現実。
昔なら誰もが知っていたものを通して
楽しさを共有できる機会があった。
世代など色々違う人同士でも
一緒に楽しめていたのだろうか。
最近では娯楽も多様化し
ジャンルが違うと全く話が通じないこともある。
みんな同じである必要はないが
これなら老若男女、多くの人が
親しんでいるものというのが
あってもいいと思う。
ことわざなど、短い言葉を聞いただけで
伝わるようなことがあれば。
人形浄瑠璃について。
神に奉納するという建前もあり
地域の信仰を支える役割を担っている。
地域の人も大事にしてくれて、
生活に密着している。
災害など大変なことがあっても
そんな伝統芸能によって
救われる部分もあるのではないかという話。
↓
えびす舞の
「えびすさん ういた」という言葉の裏に
意味するものがあるのでは。
厳しい自然や現実を受け入れ
芸能によって明日を生きる力を得ている。
人々の生活に根付いて
生活の大切な要素になっている。
これこそ、
誰もが必要としているものではないか。
単に趣味嗜好というだけでなく、
生きるために必要な要素があるのでは。
普段はそんなに
必要性を感じることはないのだが
古いものにはそんな要素があるのかも。
岡本太郎の言葉に、
伝統芸能は
その時代の新しいものと格闘して
勝ち残ってきたもの、
というのがあるとか。
誰にでも必要だったから
残ってきたということなのか。
現代は昔と変わったところもある。
しかし、相変わらず色々な問題はあって
求められているものもある。
そういう視点で
伝統芸能を考えてみるのもいいかもしれない。
とはいえ、固く難しく考えるのではなく
あくまで 楽しいが 基本。
…………………
特にオススメされていた
10/30 津野山神楽 (高知県 梼原町)
気になった。
以前から好きだった絵金の
絵金祭りも、いつか行きたい。
まずは、こんな話を聴けて良かった。
次は機会を見つけて実際に見てみることだ!
その、絵金についても、
子どもの頃、高知の美術館で見た
あの時のゾクッとする感覚が
今でも忘れられない。
体験は大事だ。