初めてアフリカで開催されているワールドカップ。
蜂の大群の羽音のごときブブゼラなるラッパの騒音の中に、時折混じる太鼓の音。
ジェンベ叩きまくってるガーナ・サポーターがいたり、シェケレ振り回すナイジェリア・サポーターがいたり。
アフリカ楽器好きにはたまらん!とかなんとか楽しんでいるうちに、すでに予選リーグも一順。すべての参加国が登場いたしました。
すべての試合をくまなく見ているわけではないので私的な印象論に過ぎませんが、ここまでの試合の中で、なんと言っても驚いたのはスペインの敗戦です。
堅守スイスに対して、これでもか!っていうくらいパスを回し、エリア内に進入してもパスを回しているうちにあれっ?あららら~?っていう感じでカウンターで一発。さらにあわや追加点か?という局面もありました。
やはり、取るべき時に取っておかないと、神様はそっぽ向いてしまうんですね。
一方のスイスは「懸中待、待中懸」という言葉が似つかわしい。
「懸かる=攻撃」の中に「待ち=守備」があり、その逆もまた然り。守る間にも攻撃の糸口を探し、攻める最中にも守備を意識しなくてはいけない、というこの言葉、確か私の中学校の剣道部の部室に貼ってあった言葉でして、いまだに好きな言葉です。
スイスのヒッツフェルト監督自身が「まさか勝つとは思わなかった」と答えているほどの驚きの結果ですが、守備的とか攻撃的とかいうカテゴライズが無意味なほど、どこでどう奪って仕掛けるか?少ないチャンスをどう生かすか?という命題をきっちり理解した選手がチームとして機能した、美しい勝利でした。
美しかったと言えばポルトガルVSコートジボワール、アルゼンチンVSナイジェリア。
いずれの試合も、およそ日本代表がやっている「さっかー」というものと同じ競技とは思えないほどのハイテンポかつダイナミックな内容で見ごたえがありました。
ダイナミックと言えば韓国もそうです。
対戦国であるギリシャはユーロ2004のダークホース的優勝国であり、きっちり守ってカウンターが売りの「お堅い」チームでしたが、朴智星という稀代のタレントを中心に、徹底して自ら仕掛けることで相手の出足を止め、きっちり完封。
すばらしい!
イタリア代表監督のリッピが絶賛していた模様です。
そのリッピが同様に褒めていたのがなんとわが日本。
「組織的でよかった」そうな。
確かに組織的でしたね。だって闘莉王がハーフライン以上上がらなかったし、守備ブロックを固めてゴールキックはすべてカメルーン左サイドバックのアスー・エコトめがけてぶち込み、そのポイントに松井と本田が突っ込む様子はまるでラグビー。モールからパスが出ても駒野・長谷部・阿部がきっちり囲い込んでまたもや右サイドに展開。そしてワンチャンスで得点して勝利。
ちょっとシドニーオリンピックの時のアメリカ代表を思い出しました。
海外では酷評もされているようです。「内容がない」「美しくない」などなど。
たしかに美しくないかな?しかし、スペインの敗戦と同じ、もしくはそれ以上に驚いた試合でもあります。
まずなんと言っても選手の気合、一体感が伝わってきたこと。
全員が肩を組んで国歌斉唱なんて、史上初じゃないですか?
非常に健全なナショナリズムだと思いますし、本田の得点シーンでも同様の光景が!
中村憲剛との約束を思い出してベンチへと走る本田の姿。
日韓大会の稲本と秋田みたいな話、ってか、真似たんだろ、健剛~!
でも、いいの。盛り上がるんだよ、ああいうのって。
若干一名、すかした態度の選手がいましたけど、それはともかく。
そして監督の作戦ですね。
方針がぶれているとかなんとか、いろいろ言われている岡田監督ですが、この本番の大舞台で、中村俊輔が惜しむ「今まで積み上げてきたもの」をあっさり脇に置いて、このような見栄えの悪いサッカーを選択した、という点で、やはりギャンブラーだねぇ、というポジティヴな感想を抱かずにはおれません。
たった一度のチャンスに賭けて得点できたのも、そこまで繰り返し仕掛けたことで生まれたものですから、日本の作戦勝ちです。
勝てば官軍、とまでは言いませんが、弱者・小国のネガティヴなサッカーであっても、日本が展開したのは「懸中待、待中懸」のサッカーであり、「勝ち点3」を至上命題とするならば、この戦法は等身大であり、正しい、と思います。
日本チームの次の命題が、もし一次リーグ突破であるならば、デンマークつぶしを第一に掲げて、そこから逆算して、オランダ戦は控え選手のテストにしちゃう、っていうくらいの勝負師根性を見せてほしいですね。
ただし、カメルーン戦では、「懸中待、待中懸」の「懸」と「待」しか見えませんでした。これがスイスほどのスタイリッシュさに繋がらない要因でしょう。
オランダ戦とデンマーク戦では、「中」の意味を付加してほしいですね。
「中」って、「アタル」とも読むんだそうです。
「中」・・・「気」満ちて、未だ発せざることを「中」(アタル)といふ
これまた剣道の本で読んだ言葉ですけど。
見慣れない言葉ではありますが、この「アタル」という状態の有無、それが相手チームに伝わるか否か?が、それこそ武道で言うところの「位取り」みたいなものに繋がるものだと思いますし、そういったメンタルな強さ、まさに「位」を持てれば、カメルーン戦で展開したサッカーが「つまらん」という評価にはならんでしょうね。
個人的にはそれこそがサッカーの「日本化」だと信じてるんですけど。
蜂の大群の羽音のごときブブゼラなるラッパの騒音の中に、時折混じる太鼓の音。
ジェンベ叩きまくってるガーナ・サポーターがいたり、シェケレ振り回すナイジェリア・サポーターがいたり。
アフリカ楽器好きにはたまらん!とかなんとか楽しんでいるうちに、すでに予選リーグも一順。すべての参加国が登場いたしました。
すべての試合をくまなく見ているわけではないので私的な印象論に過ぎませんが、ここまでの試合の中で、なんと言っても驚いたのはスペインの敗戦です。
堅守スイスに対して、これでもか!っていうくらいパスを回し、エリア内に進入してもパスを回しているうちにあれっ?あららら~?っていう感じでカウンターで一発。さらにあわや追加点か?という局面もありました。
やはり、取るべき時に取っておかないと、神様はそっぽ向いてしまうんですね。
一方のスイスは「懸中待、待中懸」という言葉が似つかわしい。
「懸かる=攻撃」の中に「待ち=守備」があり、その逆もまた然り。守る間にも攻撃の糸口を探し、攻める最中にも守備を意識しなくてはいけない、というこの言葉、確か私の中学校の剣道部の部室に貼ってあった言葉でして、いまだに好きな言葉です。
スイスのヒッツフェルト監督自身が「まさか勝つとは思わなかった」と答えているほどの驚きの結果ですが、守備的とか攻撃的とかいうカテゴライズが無意味なほど、どこでどう奪って仕掛けるか?少ないチャンスをどう生かすか?という命題をきっちり理解した選手がチームとして機能した、美しい勝利でした。
美しかったと言えばポルトガルVSコートジボワール、アルゼンチンVSナイジェリア。
いずれの試合も、およそ日本代表がやっている「さっかー」というものと同じ競技とは思えないほどのハイテンポかつダイナミックな内容で見ごたえがありました。
ダイナミックと言えば韓国もそうです。
対戦国であるギリシャはユーロ2004のダークホース的優勝国であり、きっちり守ってカウンターが売りの「お堅い」チームでしたが、朴智星という稀代のタレントを中心に、徹底して自ら仕掛けることで相手の出足を止め、きっちり完封。
すばらしい!
イタリア代表監督のリッピが絶賛していた模様です。
そのリッピが同様に褒めていたのがなんとわが日本。
「組織的でよかった」そうな。
確かに組織的でしたね。だって闘莉王がハーフライン以上上がらなかったし、守備ブロックを固めてゴールキックはすべてカメルーン左サイドバックのアスー・エコトめがけてぶち込み、そのポイントに松井と本田が突っ込む様子はまるでラグビー。モールからパスが出ても駒野・長谷部・阿部がきっちり囲い込んでまたもや右サイドに展開。そしてワンチャンスで得点して勝利。
ちょっとシドニーオリンピックの時のアメリカ代表を思い出しました。
海外では酷評もされているようです。「内容がない」「美しくない」などなど。
たしかに美しくないかな?しかし、スペインの敗戦と同じ、もしくはそれ以上に驚いた試合でもあります。
まずなんと言っても選手の気合、一体感が伝わってきたこと。
全員が肩を組んで国歌斉唱なんて、史上初じゃないですか?
非常に健全なナショナリズムだと思いますし、本田の得点シーンでも同様の光景が!
中村憲剛との約束を思い出してベンチへと走る本田の姿。
日韓大会の稲本と秋田みたいな話、ってか、真似たんだろ、健剛~!
でも、いいの。盛り上がるんだよ、ああいうのって。
若干一名、すかした態度の選手がいましたけど、それはともかく。
そして監督の作戦ですね。
方針がぶれているとかなんとか、いろいろ言われている岡田監督ですが、この本番の大舞台で、中村俊輔が惜しむ「今まで積み上げてきたもの」をあっさり脇に置いて、このような見栄えの悪いサッカーを選択した、という点で、やはりギャンブラーだねぇ、というポジティヴな感想を抱かずにはおれません。
たった一度のチャンスに賭けて得点できたのも、そこまで繰り返し仕掛けたことで生まれたものですから、日本の作戦勝ちです。
勝てば官軍、とまでは言いませんが、弱者・小国のネガティヴなサッカーであっても、日本が展開したのは「懸中待、待中懸」のサッカーであり、「勝ち点3」を至上命題とするならば、この戦法は等身大であり、正しい、と思います。
日本チームの次の命題が、もし一次リーグ突破であるならば、デンマークつぶしを第一に掲げて、そこから逆算して、オランダ戦は控え選手のテストにしちゃう、っていうくらいの勝負師根性を見せてほしいですね。
ただし、カメルーン戦では、「懸中待、待中懸」の「懸」と「待」しか見えませんでした。これがスイスほどのスタイリッシュさに繋がらない要因でしょう。
オランダ戦とデンマーク戦では、「中」の意味を付加してほしいですね。
「中」って、「アタル」とも読むんだそうです。
「中」・・・「気」満ちて、未だ発せざることを「中」(アタル)といふ
これまた剣道の本で読んだ言葉ですけど。
見慣れない言葉ではありますが、この「アタル」という状態の有無、それが相手チームに伝わるか否か?が、それこそ武道で言うところの「位取り」みたいなものに繋がるものだと思いますし、そういったメンタルな強さ、まさに「位」を持てれば、カメルーン戦で展開したサッカーが「つまらん」という評価にはならんでしょうね。
個人的にはそれこそがサッカーの「日本化」だと信じてるんですけど。
















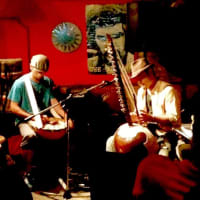



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます