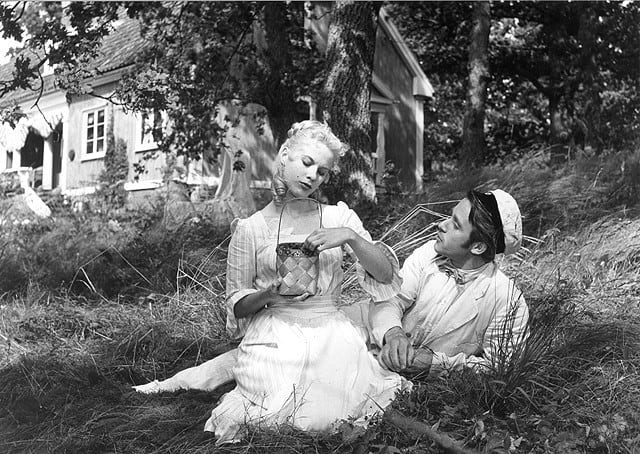映画「残像」は2017年日本公開のポーランド映画である。

「灰とダイヤモンド」「鉄の男」といった不朽の名作をつくったポーランドの巨匠アンジェイ・ワイダ監督の遺作である。神保町の交差点横にある知性の殿堂「岩波ホール」手前の大きな看板に映るじいさん顔をみて、なんか暗いなあとDVDスルーにしてしまう。
二次大戦後というのポーランドはソ連が関与する共産党支配となり、共産党の宣伝にならない作品はブルジョア文化とされて統制されることになる。そこで被害をうけるのがこの主人公である。アメリカの赤狩り映画で共産主義者が弾圧されるのと全く逆の話である。なかなか考えさせられる作品だ。
それにしても救いようのない話だ。最初は大学教授としての権威を持って、官憲たちと渡り合っている姿が映し出される。ただ、一番タチの悪いのはスターリン時代から続く共産主義の粛清だ。気の毒としかいいようにない主人公の落ちぶれ方に、資本主義社会に生まれてきた自分の幸せをつくづく感じる。

第二次大戦後、ソヴィエト連邦の影響下におかれたポーランド。スターリンによる全体主義に脅かされながらも、カンディンスキーやシャガールなどとも交流を持ち、情熱的に創作と美術教育に打ち込む前衛画家ヴワディスワフ・ストゥシェミンスキ(ボグスワフ・リンダ)。しかし、芸術を政治に利用しようとするポーランド政府が要求した社会的リアリズムに真っ向から反発したために、芸術家としての名声も、尊厳も踏みにじられていく。けれども彼は、いかなる境遇に追い込まれても、芸術に希望を失うことはなかったが。。。状況はどんどん悪くなっていく。
1.ソ連のポーランド占領と主人公の落ちぶれ
世界史の教科書では1939年9月にナチスドイツがポーランドに侵攻したことが第二次世界大戦の始まりと主に記述されている。しかし、その前月にヒトラーとスターリンは手を組み、独ソ不可侵条約を締結し世界をあっと言わせた。ポーランドでは戦争中ソ連はドイツ以上にポーランドでむごいことをしたと伝えられている。その流れで、戦後もポーランドで影響力をソ連がもつことになる。本当に悲劇としか言いようにない。

「残像」はポーランドの社会主義化が最も過激な形を取り、社会主義リアリズムが芸術表現に必須の様式となった、1949年から1952年までの重要な4年間を描いている。 アンジェイ・ワイダ監督は、人々の生活のあらゆる面を支配しようと目論む全体主義国家と、一人の威厳ある人間との闘いを描きたかったとしている。
2.ダルトン・トランボとの比較
1947年トルーマン大統領のソ連への封じ込め政策がとられ、マッカーシズムが台頭し赤狩りがはじまる。そのあたりは失脚した脚本家ダルトン・トランボの伝記をはじめとして、いくつかの映画で語られている。しかし、仕事が完全になくなることはなかった。クレジットに名前は出ていないが、オスカー作品「ローマの休日」、「黒い牡牛」の脚本を提供している。映画会社は抜け道を工夫し、ブラックリスト作家を起用できる環境を整えて、結果的に作家たちの自由を守った。
ノーベル経済学賞自由主義の泰斗ミルトン・フリードマン博士の「資本主義と自由」を引用する。
もし、ハリウッドをはじめとする映画産業が国営であったり、作家への発注がBBCのように公営企業にゆだねられていたとしたら、ハリウッドテンに挙げられた作家が仕事にありつくチャンスはほとんどなかったであろう。国が事業主だったら。。。どんな思想の持ち主も雇ってもらえないだろう。
結局彼らを救ったのは市場経済だった。政府から放りだされても、市場で職を見つけることができたのである。(村井訳p59~60)

ここでの主人公は完全に干された。職すらもなくなった。このドツボはやり切れない。知性の殿堂岩波ホールには、最近駅前でビラを配っているのが目立つ共産党系ババアぽい人がいつも多数来ている。学生運動の洗礼を受けたクズババアか?この映画を見て全体主義、共産主義に対してどうおもったんだろう?

「灰とダイヤモンド」「鉄の男」といった不朽の名作をつくったポーランドの巨匠アンジェイ・ワイダ監督の遺作である。神保町の交差点横にある知性の殿堂「岩波ホール」手前の大きな看板に映るじいさん顔をみて、なんか暗いなあとDVDスルーにしてしまう。
二次大戦後というのポーランドはソ連が関与する共産党支配となり、共産党の宣伝にならない作品はブルジョア文化とされて統制されることになる。そこで被害をうけるのがこの主人公である。アメリカの赤狩り映画で共産主義者が弾圧されるのと全く逆の話である。なかなか考えさせられる作品だ。
それにしても救いようのない話だ。最初は大学教授としての権威を持って、官憲たちと渡り合っている姿が映し出される。ただ、一番タチの悪いのはスターリン時代から続く共産主義の粛清だ。気の毒としかいいようにない主人公の落ちぶれ方に、資本主義社会に生まれてきた自分の幸せをつくづく感じる。

第二次大戦後、ソヴィエト連邦の影響下におかれたポーランド。スターリンによる全体主義に脅かされながらも、カンディンスキーやシャガールなどとも交流を持ち、情熱的に創作と美術教育に打ち込む前衛画家ヴワディスワフ・ストゥシェミンスキ(ボグスワフ・リンダ)。しかし、芸術を政治に利用しようとするポーランド政府が要求した社会的リアリズムに真っ向から反発したために、芸術家としての名声も、尊厳も踏みにじられていく。けれども彼は、いかなる境遇に追い込まれても、芸術に希望を失うことはなかったが。。。状況はどんどん悪くなっていく。
1.ソ連のポーランド占領と主人公の落ちぶれ
世界史の教科書では1939年9月にナチスドイツがポーランドに侵攻したことが第二次世界大戦の始まりと主に記述されている。しかし、その前月にヒトラーとスターリンは手を組み、独ソ不可侵条約を締結し世界をあっと言わせた。ポーランドでは戦争中ソ連はドイツ以上にポーランドでむごいことをしたと伝えられている。その流れで、戦後もポーランドで影響力をソ連がもつことになる。本当に悲劇としか言いようにない。

「残像」はポーランドの社会主義化が最も過激な形を取り、社会主義リアリズムが芸術表現に必須の様式となった、1949年から1952年までの重要な4年間を描いている。 アンジェイ・ワイダ監督は、人々の生活のあらゆる面を支配しようと目論む全体主義国家と、一人の威厳ある人間との闘いを描きたかったとしている。
2.ダルトン・トランボとの比較
1947年トルーマン大統領のソ連への封じ込め政策がとられ、マッカーシズムが台頭し赤狩りがはじまる。そのあたりは失脚した脚本家ダルトン・トランボの伝記をはじめとして、いくつかの映画で語られている。しかし、仕事が完全になくなることはなかった。クレジットに名前は出ていないが、オスカー作品「ローマの休日」、「黒い牡牛」の脚本を提供している。映画会社は抜け道を工夫し、ブラックリスト作家を起用できる環境を整えて、結果的に作家たちの自由を守った。
ノーベル経済学賞自由主義の泰斗ミルトン・フリードマン博士の「資本主義と自由」を引用する。
もし、ハリウッドをはじめとする映画産業が国営であったり、作家への発注がBBCのように公営企業にゆだねられていたとしたら、ハリウッドテンに挙げられた作家が仕事にありつくチャンスはほとんどなかったであろう。国が事業主だったら。。。どんな思想の持ち主も雇ってもらえないだろう。
結局彼らを救ったのは市場経済だった。政府から放りだされても、市場で職を見つけることができたのである。(村井訳p59~60)

ここでの主人公は完全に干された。職すらもなくなった。このドツボはやり切れない。知性の殿堂岩波ホールには、最近駅前でビラを配っているのが目立つ共産党系ババアぽい人がいつも多数来ている。学生運動の洗礼を受けたクズババアか?この映画を見て全体主義、共産主義に対してどうおもったんだろう?