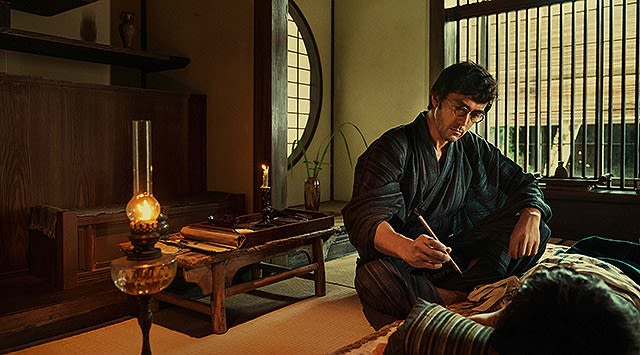映画「私のプリンスエドワード」を映画館で観てきました。

映画「私のプリンスエドワード」は武蔵野館の新世代香港映画特集で「縁路はるばる」に引き続き観た。香港好きの自分としては、現代香港を撮ったこの映画を観ないわけにはいかない。「縁路はるばる」は自分の好みの作品であった。ここでは新鋭女性監督ノリス・ウォンによる偽装結婚も題材に加えた現代香港の結婚事情を覗き込む。
香港のプリンス・エドワード地区(太子)にある金都商場は、結婚式に必要なものすべてが格安で揃えられるショッピングモールだ。ウェディングショップで働くフォン(ステフィー・タン)は、ウェディングフォト専門店のオーナーであるエドワード(ジュー・パクホン)と同棲中。ある日、エドワードからプロポーズを受けたフォンだったが、実は10年前に中国大陸の男性と偽装結婚しており、その婚姻がまだ継続中であることが判明する。それでフォンは偽装結婚の離婚手続きと結婚式の準備を同時に進めるという話だ。

結婚式グッズが揃うショッピングモールで働く男女が、結婚に向かって準備している。でも、女性には大陸の男との偽装結婚の履歴があってそれを打ち消さねばならないという課題を解決せねばならないというわけだ。
現代香港の若者のウェディング事情がよくわかる。
主演のステフィータンを東京の街に放っても誰も中国人だとはわからないだろう。素敵な女性だ。広東語でまくしたてるといかにも気の強い香港人女性ぽくなる。相手役のジュー・パクホンはラブコメデイ的要素を意識させるお笑い系のキャラを持っている。その一方で、クールな主役女性のキャラクターがシリアスに見えてしまう。いかにも香港人女性監督による作品というのがよくわかる。香港人の気質を知っている自分からすると、全く不自然ではない。でも、コメディになりきれないのでのれない日本人もいるのでは?

⒈偽装結婚
主人公が何で偽装結婚しなければならなかったのか?という理由はよくわからない。実家を飛び出して1人暮らしをするためにお金がいるという。たしかに家賃が高い香港に住むのは大変だ。日本から移り住んだ日本人も大手企業の香港駐在員以外はほとんどルームシェアだ。
でも、ほんの少しのお金を得るために戸籍を汚すという心理がよくわからない。逆に大陸の中国人からすると香港の居住権が欲しい。実際にカネで偽装結婚した人がいるから映画の題材になったのであろう。自分には香港人の心理の方が意味不明といった感じがする。
結婚解消するために、偽装結婚した大陸に住む男性と交渉する過程や偽装結婚をそうでないと示す写真を撮ったりする場面に奇異な印象を持つ。相手が住む大陸の福州にまさに遠路はるばるバスで向かう。中国の知らない町を映し出すそれ自体はありがたい。

⒉マザコンの婚約者
女性監督がつくったというのが顕著に出るのは、男性側のマザコンぶりである。母親が結婚式の段取りを一気に仕切る。披露宴をやるつもりはなかったのに、母親が自分の友人を中心に招待客をかき集める。見栄っ張りだ。フィアンセ側があきれた顔をしても、母親が一気に突き進む.。母親の暴走を極端に強調する。いかにも姑を嫌う女性監督がつくったと思わせる構図だ。

実は香港のプリンスエドワード(太子)には行ったことがない。旺角(モンコック)の次の駅だ。今回の舞台の金都商場は典型的な香港の商店モールである。親しみをもつ。「縁路はるばる」の主演のお兄ちゃんがこの映画でも、エドワードのアシスタント役で出演していた。自分には「縁路はるばる」の方がよくできている映画だと感じる。


映画「私のプリンスエドワード」は武蔵野館の新世代香港映画特集で「縁路はるばる」に引き続き観た。香港好きの自分としては、現代香港を撮ったこの映画を観ないわけにはいかない。「縁路はるばる」は自分の好みの作品であった。ここでは新鋭女性監督ノリス・ウォンによる偽装結婚も題材に加えた現代香港の結婚事情を覗き込む。
香港のプリンス・エドワード地区(太子)にある金都商場は、結婚式に必要なものすべてが格安で揃えられるショッピングモールだ。ウェディングショップで働くフォン(ステフィー・タン)は、ウェディングフォト専門店のオーナーであるエドワード(ジュー・パクホン)と同棲中。ある日、エドワードからプロポーズを受けたフォンだったが、実は10年前に中国大陸の男性と偽装結婚しており、その婚姻がまだ継続中であることが判明する。それでフォンは偽装結婚の離婚手続きと結婚式の準備を同時に進めるという話だ。

結婚式グッズが揃うショッピングモールで働く男女が、結婚に向かって準備している。でも、女性には大陸の男との偽装結婚の履歴があってそれを打ち消さねばならないという課題を解決せねばならないというわけだ。
現代香港の若者のウェディング事情がよくわかる。
主演のステフィータンを東京の街に放っても誰も中国人だとはわからないだろう。素敵な女性だ。広東語でまくしたてるといかにも気の強い香港人女性ぽくなる。相手役のジュー・パクホンはラブコメデイ的要素を意識させるお笑い系のキャラを持っている。その一方で、クールな主役女性のキャラクターがシリアスに見えてしまう。いかにも香港人女性監督による作品というのがよくわかる。香港人の気質を知っている自分からすると、全く不自然ではない。でも、コメディになりきれないのでのれない日本人もいるのでは?

⒈偽装結婚
主人公が何で偽装結婚しなければならなかったのか?という理由はよくわからない。実家を飛び出して1人暮らしをするためにお金がいるという。たしかに家賃が高い香港に住むのは大変だ。日本から移り住んだ日本人も大手企業の香港駐在員以外はほとんどルームシェアだ。
でも、ほんの少しのお金を得るために戸籍を汚すという心理がよくわからない。逆に大陸の中国人からすると香港の居住権が欲しい。実際にカネで偽装結婚した人がいるから映画の題材になったのであろう。自分には香港人の心理の方が意味不明といった感じがする。
結婚解消するために、偽装結婚した大陸に住む男性と交渉する過程や偽装結婚をそうでないと示す写真を撮ったりする場面に奇異な印象を持つ。相手が住む大陸の福州にまさに遠路はるばるバスで向かう。中国の知らない町を映し出すそれ自体はありがたい。

⒉マザコンの婚約者
女性監督がつくったというのが顕著に出るのは、男性側のマザコンぶりである。母親が結婚式の段取りを一気に仕切る。披露宴をやるつもりはなかったのに、母親が自分の友人を中心に招待客をかき集める。見栄っ張りだ。フィアンセ側があきれた顔をしても、母親が一気に突き進む.。母親の暴走を極端に強調する。いかにも姑を嫌う女性監督がつくったと思わせる構図だ。

実は香港のプリンスエドワード(太子)には行ったことがない。旺角(モンコック)の次の駅だ。今回の舞台の金都商場は典型的な香港の商店モールである。親しみをもつ。「縁路はるばる」の主演のお兄ちゃんがこの映画でも、エドワードのアシスタント役で出演していた。自分には「縁路はるばる」の方がよくできている映画だと感じる。