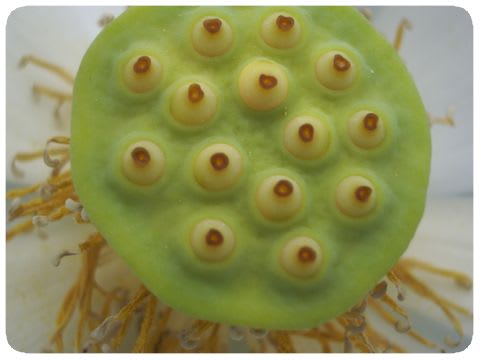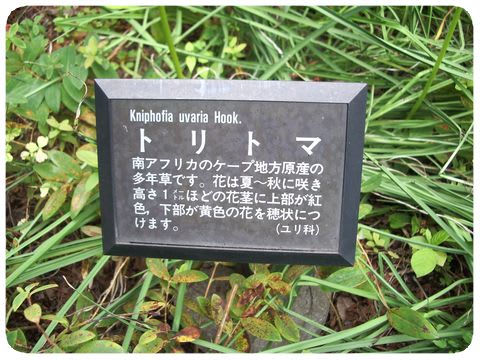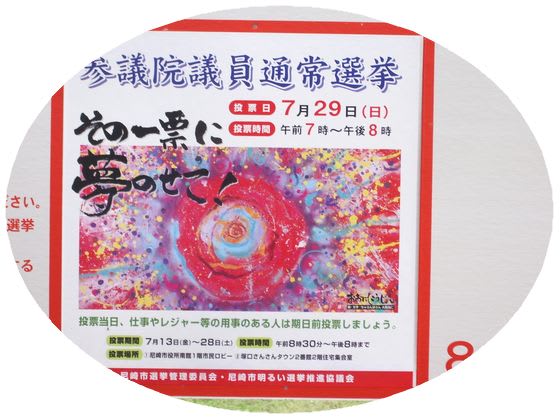車を買い換えました。
未だ山道や川原、海辺を走るのでオフ・ロード仕様、今年2月発売になったクロスロードです。

メーカーもTOYOTAからHONDAに変えました。

前の車がTOYOTAで、10年前に買ってからすぐマイナーチェンジしよった。それってちゃんと説明しておけよなと、トヨタのセールスマンに思ったのでした。
TOYOTAは自社の車の売れ行きに胡坐をかいてると思う。
そんな会社は嫌いだ。
買った10年前は丁度消費税が3%から5%に跳ね上がった4月当初、物を買う時期なんて相当ずれてない限り、売る側の気持ち一つで日付はいつにでも変更出来るのにねぇ。
古い型を新しい制度で売る・・・そんなセールスマンの拙さ、会社の姑息さが気に入らなかったんです。

この車種を決める前にいろいろな人から意見をもらい、本を読み、セレナ・カローラフィルダー・ウィングロード・エクストレイアル・ノア・ステップワゴン・・・いろいろ検討しましたが、巡り巡って買い換えると決めたときに思っていたこの車になったのでした。
決め手は姫の家に楽に出し入れ出来るのかどうか。なんせ道幅が狭いですから。

私的にはこのパールホワイトは個性的でなく否だったのですが、こともあろうに一銭の金も払わない・そしておそらく乗る時間の大部分を占めるあろう三男がこれっ!と譲らないのでした。

未だ乗ってみてほんの僅かな時間なので一概には言えないのですが、スタートダッシュが前のカリブに比べると弱い、そしてアクセルを踏み続けていると急にドッと出るんですよね。スタート時の滑らかな加速が無いという感じを受けました。
前の車の感覚で交差点の右折を行うと危ないかも・・・
カリブより車幅も車長もありますが、回転は前車よりスムーズな感じを受けます。
後はHDDナビをどう使いこなせるか・・・又あと10年この車に乗るのかなぁ?
どこかで見かけたら「オイ、ぼんくら」と、声をかけて下さいネ。
未だ山道や川原、海辺を走るのでオフ・ロード仕様、今年2月発売になったクロスロードです。

メーカーもTOYOTAからHONDAに変えました。

前の車がTOYOTAで、10年前に買ってからすぐマイナーチェンジしよった。それってちゃんと説明しておけよなと、トヨタのセールスマンに思ったのでした。
TOYOTAは自社の車の売れ行きに胡坐をかいてると思う。
そんな会社は嫌いだ。
買った10年前は丁度消費税が3%から5%に跳ね上がった4月当初、物を買う時期なんて相当ずれてない限り、売る側の気持ち一つで日付はいつにでも変更出来るのにねぇ。
古い型を新しい制度で売る・・・そんなセールスマンの拙さ、会社の姑息さが気に入らなかったんです。

この車種を決める前にいろいろな人から意見をもらい、本を読み、セレナ・カローラフィルダー・ウィングロード・エクストレイアル・ノア・ステップワゴン・・・いろいろ検討しましたが、巡り巡って買い換えると決めたときに思っていたこの車になったのでした。
決め手は姫の家に楽に出し入れ出来るのかどうか。なんせ道幅が狭いですから。

私的にはこのパールホワイトは個性的でなく否だったのですが、こともあろうに一銭の金も払わない・そしておそらく乗る時間の大部分を占めるあろう三男がこれっ!と譲らないのでした。

未だ乗ってみてほんの僅かな時間なので一概には言えないのですが、スタートダッシュが前のカリブに比べると弱い、そしてアクセルを踏み続けていると急にドッと出るんですよね。スタート時の滑らかな加速が無いという感じを受けました。
前の車の感覚で交差点の右折を行うと危ないかも・・・
カリブより車幅も車長もありますが、回転は前車よりスムーズな感じを受けます。
後はHDDナビをどう使いこなせるか・・・又あと10年この車に乗るのかなぁ?
どこかで見かけたら「オイ、ぼんくら」と、声をかけて下さいネ。