アマゾンから届きました(^◇^)。
さっそくイッキ読みしました。
プロフェショナル仕事の流儀にも出演、それがマンガ化もされた中村伸一先生の新刊。(→ブログはこちら)。
(次はドラマ化だ・・・。あ、コトーがあるか。)
・自分の中に「寄りそ医」と「究めた医」が存在する。
・そのなかで地域に寄り添いつづけていたら、いつの間にか「支えあ医」も新たに誕生した。
・地域と医療をステキな関係へ
と現場での格闘をつづけてこられた中村先生と名田床の軌跡と奇跡がいっぱいいっぱい語られています。
医学生、研修医時代のエピソードも・・。
まず「大学は社会の縮図だった!」と振り返ります。
狭い栃木の医学部村(自治医大)での勉強と並行してハマったバンド活動。(その名もTIA!)。
ラジオ放送局でDJをし目の前にいない不特定多数の人に「伝える」技術を学び、コンサートで近隣のお店から広告収入を得た代わりに、そのお店を優先的に使うなど「お互い様」の関係を維持する体験から地域社会の方々と「交わる」技術を身につけ、あたってくだけろ方式で道行く人にチケットをうる経験から人を「見抜く」技術をつけたり・・・。
臨床実習でも臨床研修でも行く先々の科でトンチンカンなことをやらかす”ちょっとだけ問題児”だったようで、「語り継がれる研修医」だったようです。(^_^;)
地域の診療所にでてからも現場を知らないで指導してくる社会保険庁あいてに立ち回ったりと大活躍。
わらじ医者、早川一光先生のいらした京都府美山町が実は中村先生のいらっしゃる福井県名田庄村の隣で、早川一光先生が突然訪ねて来たりというエピソードが面白かったです。
中村先生も名田床で20年、そこで実習する医学生や研修をうける若い研修医も増えています。
地域医療を実践したいという研修医ばかりではありません。
でも、他の道に進む研修医も指導医として平等に接することの大切さは自身の外科研修で分かっている中村先生は、
「地域医療の仲間を増やすことも必要ですが、それと同じくらい、地域医療を理解する他の分野の医師を増やすことも大切。」
と訴えます。
それが地域医療の裾野を広げることになると・・。
「ウルトラマンは専門医で”医局”という星から派遣されて活躍する、サッと現れては、さっと去って行くクールな職人的なウルトラマンではなく、アンパンマンはいろんな人たちと連携して患者さんの暮らしを支える、縁の下の力持ち的存在。「ウルトラマンとアンパンマンがうまく連携することで両者の特性が、より活きるぞ!」
大病院の専門医は非日常に対応する。地域の総合医は日常を支える
医療にガイドラインはあっても人生にガイドラインは無い。
幸せの全国統一規格はない。
などヒントがたくさんありました。
本文の中の
「私の大先輩、早川先生や鎌田實先生は多くの著作を出されていますが、今そのお気持ちが少しわかる気がしています。伝えることも、医の一つ。
ただ、それも現場を担ってこそだとおもっています。(129P)」
↑ここに深く共感。(チクリ)
著作を沢山だして講演会に飛び回って有名になるにつれ現場から離れていくという人も多いですもの。
(誰とは言いませんが・・。講演会には中毒性ありますし・・。)
別の現場を持ったのだと言えばそれまでですが、話しが上手になるのに反比例して、だんだんリアリティがなくなるのは悲しいことです。
私がリスペクトするのは50年以上佐久の地でニーズに応じた実践を続けられた若月俊一先生をはじめ、ずっと現場での「実践」にこだわり続けている人です。
自分の現場にこだわり患者さんに「寄りそ医」つづけたいものです。
「寄りそ医」は「かっこい医」ぜっ!
類書はたくさんありますが、著者の考え方のルーツ、現在の地域医療をめぐる社会情勢と、浄土真宗の思想が今も活きる名田床でのローカルな活動がバランスよく紹介されており、だじゃれも含む言葉の使い方が上手く、新たな時代(第3世代)の地域医療のバイブルたる本と思います。
(ちなみに私見ですが第1世代の代表が「村で病気とたたかう」(若月俊一著)、第2世代の代表が「地域医療の冒険」(黒岩 卓夫)と思います。)
さっそくイッキ読みしました。
 | 寄りそ医「逝き方を選べる町」を作った青年医師の20年 |
| 中村伸一 | |
| メディアファクトリー |
プロフェショナル仕事の流儀にも出演、それがマンガ化もされた中村伸一先生の新刊。(→ブログはこちら)。
(次はドラマ化だ・・・。あ、コトーがあるか。)
・自分の中に「寄りそ医」と「究めた医」が存在する。
・そのなかで地域に寄り添いつづけていたら、いつの間にか「支えあ医」も新たに誕生した。
・地域と医療をステキな関係へ
と現場での格闘をつづけてこられた中村先生と名田床の軌跡と奇跡がいっぱいいっぱい語られています。
医学生、研修医時代のエピソードも・・。
まず「大学は社会の縮図だった!」と振り返ります。
狭い栃木の医学部村(自治医大)での勉強と並行してハマったバンド活動。(その名もTIA!)。
ラジオ放送局でDJをし目の前にいない不特定多数の人に「伝える」技術を学び、コンサートで近隣のお店から広告収入を得た代わりに、そのお店を優先的に使うなど「お互い様」の関係を維持する体験から地域社会の方々と「交わる」技術を身につけ、あたってくだけろ方式で道行く人にチケットをうる経験から人を「見抜く」技術をつけたり・・・。
臨床実習でも臨床研修でも行く先々の科でトンチンカンなことをやらかす”ちょっとだけ問題児”だったようで、「語り継がれる研修医」だったようです。(^_^;)
地域の診療所にでてからも現場を知らないで指導してくる社会保険庁あいてに立ち回ったりと大活躍。
わらじ医者、早川一光先生のいらした京都府美山町が実は中村先生のいらっしゃる福井県名田庄村の隣で、早川一光先生が突然訪ねて来たりというエピソードが面白かったです。
中村先生も名田床で20年、そこで実習する医学生や研修をうける若い研修医も増えています。
地域医療を実践したいという研修医ばかりではありません。
でも、他の道に進む研修医も指導医として平等に接することの大切さは自身の外科研修で分かっている中村先生は、
「地域医療の仲間を増やすことも必要ですが、それと同じくらい、地域医療を理解する他の分野の医師を増やすことも大切。」
と訴えます。
それが地域医療の裾野を広げることになると・・。
「ウルトラマンは専門医で”医局”という星から派遣されて活躍する、サッと現れては、さっと去って行くクールな職人的なウルトラマンではなく、アンパンマンはいろんな人たちと連携して患者さんの暮らしを支える、縁の下の力持ち的存在。「ウルトラマンとアンパンマンがうまく連携することで両者の特性が、より活きるぞ!」
大病院の専門医は非日常に対応する。地域の総合医は日常を支える
医療にガイドラインはあっても人生にガイドラインは無い。
幸せの全国統一規格はない。
などヒントがたくさんありました。
本文の中の
「私の大先輩、早川先生や鎌田實先生は多くの著作を出されていますが、今そのお気持ちが少しわかる気がしています。伝えることも、医の一つ。
ただ、それも現場を担ってこそだとおもっています。(129P)」
↑ここに深く共感。(チクリ)
著作を沢山だして講演会に飛び回って有名になるにつれ現場から離れていくという人も多いですもの。
(誰とは言いませんが・・。講演会には中毒性ありますし・・。)
別の現場を持ったのだと言えばそれまでですが、話しが上手になるのに反比例して、だんだんリアリティがなくなるのは悲しいことです。
私がリスペクトするのは50年以上佐久の地でニーズに応じた実践を続けられた若月俊一先生をはじめ、ずっと現場での「実践」にこだわり続けている人です。
自分の現場にこだわり患者さんに「寄りそ医」つづけたいものです。
「寄りそ医」は「かっこい医」ぜっ!
類書はたくさんありますが、著者の考え方のルーツ、現在の地域医療をめぐる社会情勢と、浄土真宗の思想が今も活きる名田床でのローカルな活動がバランスよく紹介されており、だじゃれも含む言葉の使い方が上手く、新たな時代(第3世代)の地域医療のバイブルたる本と思います。
(ちなみに私見ですが第1世代の代表が「村で病気とたたかう」(若月俊一著)、第2世代の代表が「地域医療の冒険」(黒岩 卓夫)と思います。)
 | 自宅で大往生 (中公新書ラクレ) |
| 中村伸一 | |
| 中央公論新社 |










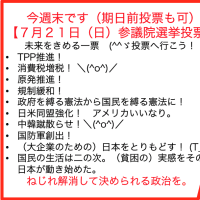
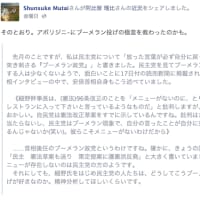




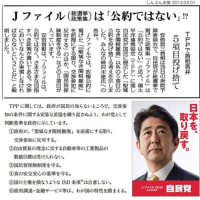

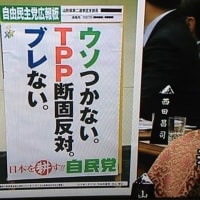

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます