p
天才というのはレンブラントとゴッホのふたりだけという仮説を立て、その立証に力を注ぐ。
なぜ、ふたりを天才と認定しなければならないのか。彼らがいなければ、いた未来より少ない幸福しかもたらさないからか。すると、クレジット・カードというものを作ったり、郵便というもので世界に手紙をとどける仕組みを考えて実行したり、あるいは指紋認証などというシステムを発明したひとたちの方がより天才という名に値するのだろうか。
ならば、アップルという企業の有名なひげを生やした故人が、いちばんの天才なのだろうか。もし、あの道具たちが机のうえの一角や手のひらになかったら。
ぼくにとっては、どれもみな、しっくりとこない。
下町の人間の表現。
「くその役にも立たない」
ふたりの画家が、まさにこの表現に合致するからふさわしく、貴いのだろうか。
天才とは何なのか? ある一種類の技能に秀でたひとなのか。万能の天才、という言葉もあった。思い浮かぶのはレオナルド・ダ・ヴィンチ。彼を凡人という役柄に抑え込むほど、ぼくは愚かではない。
複雑なものが、より簡素になる。
では、天才というのはそもそも必要なのか? なぜ、あこがれを抱くように人々は作られているのか。仮定には答えがはっきりと明示されることも要求されないのか。
みなが楽しむ遊園地とそのキャラクターを生み出したひとこそ天才なのか。天才というのは軽々しく口に出してもよい言葉なのか。
段々と狭めていく。頭のなかにアイデアが先ず浮かぶ。それを実現化することになる。ノウハウと技術と経験が前段階にある。では、訓練の賜物が天才にと通じるのだろうか。それは、職人に過ぎない。同じものをコピーしつづける能力ともまた違う。もっと、開花の期間の短いものを望んでいる。そして、線香花火の終幕のようにぽとりと落ちる。その時点で名声とか、預金額の残高で評価を曇らせてはならない。その落ちた炎は永続性をもつのだ。
するとシステムの更新を要求するもの、新しいアトラクションを創造することは、天才と相容れない。もう既に終了とともに完成していなければならない。完成にはその後の発展も加味されない。努力の余地や、ある種の余力ものこされない。完全燃焼がお似合いだ。麦畑のもとでの銃声が引き裂くような、圧倒的なまでのエンディング。
自分の内面の絶対的な誇らしさを汚すことは誰にもできない。いや、誰も眠る誇りを見抜いていないのだ。あそこに絶対に通じる扉があった。永遠性を忍ばせる秘薬があった。
多くの笑顔を手にする。幸福な気持ちにさせる。その場を提供する。このひとをどう表現したらよいのだろうか。経営者とも違う。エンターティナーとも、芸人とも違う。毎年、通いたくなるような場所。ぼくらは、毎年、オランダに行ってふたりの画家の作品を堪能するほど余裕もないし、切羽つまってもいない。
オルセーにいる。外は雨だった。肌寒い。
画家たちの一室がある。商売の材料にならなかった(存命中と、その後しばらくに限定。輸入や輸出に長けていたオランダ人の伝統を受け継がない)絵の群れが、きちんと部屋を確保していた。壁一面に。自画像。世界をその目で見て、その指で描き、その耳を切り落とす。その世界は生きている間、彼を無視した。麦畑にひそむいっぴきの昆虫ぐらいの価値しか与えずに。
でも、時間を生き延びた芸術作品は、雨の心配もせずに空調の効いた部屋に陣取っている。
片や、目の原則。基本中の基本。両目は絡み合ってものを立体化させる。その自然に備わっている仕組みがある画家にはないと言われている。
しかし、描かれた絵は、光の効果にもよっていっそう立体的に思える。
ぼくの両目は大人になるまで視力が偏っていた。そのことで絵が好きになったのか分からない。現実は、立体であり、生身であり、潤いで、匂いである。絵も、本も平面で、乾燥で、無機質で、より生々しさも表現できる。
レンブラントの、この小さなハンディ・キャップこそ天才へと導いたのだろうか。より先鋭化させるため、より才能をある一点に絞るように。虫メガネで光を一点に集めるように。
これも、美化と誤解の狭間なのだ。サングラスの音楽家や作曲家のトリックのように。
天才とは詐欺師とも呼べるのか。ぼくは自分が誰かを騙した機会を探る。騙すというのは最終的に利益がともないそうだ。あるいは損失や損害の免除。これも、どちらかといえば自分の利益である。ぼく自身がこういう欲求がないため、判断できない。
ゴッホとレンブラントが、自分を大きく見せていることなど想像できない。
しかし、同時代には無名の同じようなふたりが無数にいたのだろう。永続につながるものは何なのだろう。誰かが発掘したからなのか。弟の援助の力なのか。画材にこそ、永続するべき秘密が含まれていたのだろうか。
子どもと手をつなぐ。休日にはどこかに出かけなければならない。教育も施さなければならない。ある親のひとことが美術館のなかで、ぼくの耳に入る。
「こういう絵のことを知っておくと、面接のときに役立つかもしれないから」
それでも、退屈さを隠せない子ども。やはり、夢の国につれていくべきなのだろう。楽しみ方を手のひらの端末で確認し、電車の運行や乗り換えも同じもので調べる。耳のついた帽子を無邪気にかぶる。京葉線に乗り遊び疲れて眠る。新たに付け加えられたキャラクターを生み出す企業にも黒のタートルネックの故人は関与していた。知らなかった。迂闊だった。天才とは、大衆に楽しみを与えること。ぼくは論理の展開に失敗する。敢えて、失敗したかったのだとも思う。
天才というのはレンブラントとゴッホのふたりだけという仮説を立て、その立証に力を注ぐ。
なぜ、ふたりを天才と認定しなければならないのか。彼らがいなければ、いた未来より少ない幸福しかもたらさないからか。すると、クレジット・カードというものを作ったり、郵便というもので世界に手紙をとどける仕組みを考えて実行したり、あるいは指紋認証などというシステムを発明したひとたちの方がより天才という名に値するのだろうか。
ならば、アップルという企業の有名なひげを生やした故人が、いちばんの天才なのだろうか。もし、あの道具たちが机のうえの一角や手のひらになかったら。
ぼくにとっては、どれもみな、しっくりとこない。
下町の人間の表現。
「くその役にも立たない」
ふたりの画家が、まさにこの表現に合致するからふさわしく、貴いのだろうか。
天才とは何なのか? ある一種類の技能に秀でたひとなのか。万能の天才、という言葉もあった。思い浮かぶのはレオナルド・ダ・ヴィンチ。彼を凡人という役柄に抑え込むほど、ぼくは愚かではない。
複雑なものが、より簡素になる。
では、天才というのはそもそも必要なのか? なぜ、あこがれを抱くように人々は作られているのか。仮定には答えがはっきりと明示されることも要求されないのか。
みなが楽しむ遊園地とそのキャラクターを生み出したひとこそ天才なのか。天才というのは軽々しく口に出してもよい言葉なのか。
段々と狭めていく。頭のなかにアイデアが先ず浮かぶ。それを実現化することになる。ノウハウと技術と経験が前段階にある。では、訓練の賜物が天才にと通じるのだろうか。それは、職人に過ぎない。同じものをコピーしつづける能力ともまた違う。もっと、開花の期間の短いものを望んでいる。そして、線香花火の終幕のようにぽとりと落ちる。その時点で名声とか、預金額の残高で評価を曇らせてはならない。その落ちた炎は永続性をもつのだ。
するとシステムの更新を要求するもの、新しいアトラクションを創造することは、天才と相容れない。もう既に終了とともに完成していなければならない。完成にはその後の発展も加味されない。努力の余地や、ある種の余力ものこされない。完全燃焼がお似合いだ。麦畑のもとでの銃声が引き裂くような、圧倒的なまでのエンディング。
自分の内面の絶対的な誇らしさを汚すことは誰にもできない。いや、誰も眠る誇りを見抜いていないのだ。あそこに絶対に通じる扉があった。永遠性を忍ばせる秘薬があった。
多くの笑顔を手にする。幸福な気持ちにさせる。その場を提供する。このひとをどう表現したらよいのだろうか。経営者とも違う。エンターティナーとも、芸人とも違う。毎年、通いたくなるような場所。ぼくらは、毎年、オランダに行ってふたりの画家の作品を堪能するほど余裕もないし、切羽つまってもいない。
オルセーにいる。外は雨だった。肌寒い。
画家たちの一室がある。商売の材料にならなかった(存命中と、その後しばらくに限定。輸入や輸出に長けていたオランダ人の伝統を受け継がない)絵の群れが、きちんと部屋を確保していた。壁一面に。自画像。世界をその目で見て、その指で描き、その耳を切り落とす。その世界は生きている間、彼を無視した。麦畑にひそむいっぴきの昆虫ぐらいの価値しか与えずに。
でも、時間を生き延びた芸術作品は、雨の心配もせずに空調の効いた部屋に陣取っている。
片や、目の原則。基本中の基本。両目は絡み合ってものを立体化させる。その自然に備わっている仕組みがある画家にはないと言われている。
しかし、描かれた絵は、光の効果にもよっていっそう立体的に思える。
ぼくの両目は大人になるまで視力が偏っていた。そのことで絵が好きになったのか分からない。現実は、立体であり、生身であり、潤いで、匂いである。絵も、本も平面で、乾燥で、無機質で、より生々しさも表現できる。
レンブラントの、この小さなハンディ・キャップこそ天才へと導いたのだろうか。より先鋭化させるため、より才能をある一点に絞るように。虫メガネで光を一点に集めるように。
これも、美化と誤解の狭間なのだ。サングラスの音楽家や作曲家のトリックのように。
天才とは詐欺師とも呼べるのか。ぼくは自分が誰かを騙した機会を探る。騙すというのは最終的に利益がともないそうだ。あるいは損失や損害の免除。これも、どちらかといえば自分の利益である。ぼく自身がこういう欲求がないため、判断できない。
ゴッホとレンブラントが、自分を大きく見せていることなど想像できない。
しかし、同時代には無名の同じようなふたりが無数にいたのだろう。永続につながるものは何なのだろう。誰かが発掘したからなのか。弟の援助の力なのか。画材にこそ、永続するべき秘密が含まれていたのだろうか。
子どもと手をつなぐ。休日にはどこかに出かけなければならない。教育も施さなければならない。ある親のひとことが美術館のなかで、ぼくの耳に入る。
「こういう絵のことを知っておくと、面接のときに役立つかもしれないから」
それでも、退屈さを隠せない子ども。やはり、夢の国につれていくべきなのだろう。楽しみ方を手のひらの端末で確認し、電車の運行や乗り換えも同じもので調べる。耳のついた帽子を無邪気にかぶる。京葉線に乗り遊び疲れて眠る。新たに付け加えられたキャラクターを生み出す企業にも黒のタートルネックの故人は関与していた。知らなかった。迂闊だった。天才とは、大衆に楽しみを与えること。ぼくは論理の展開に失敗する。敢えて、失敗したかったのだとも思う。











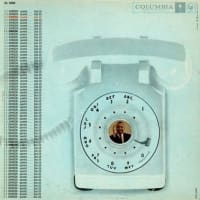







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます