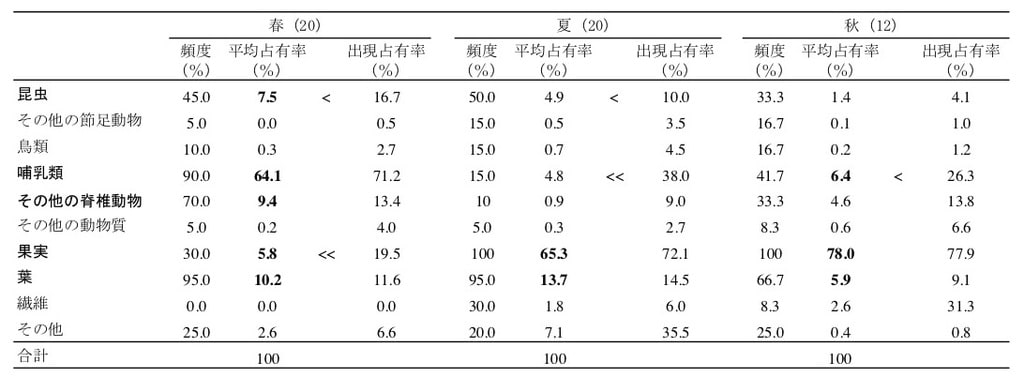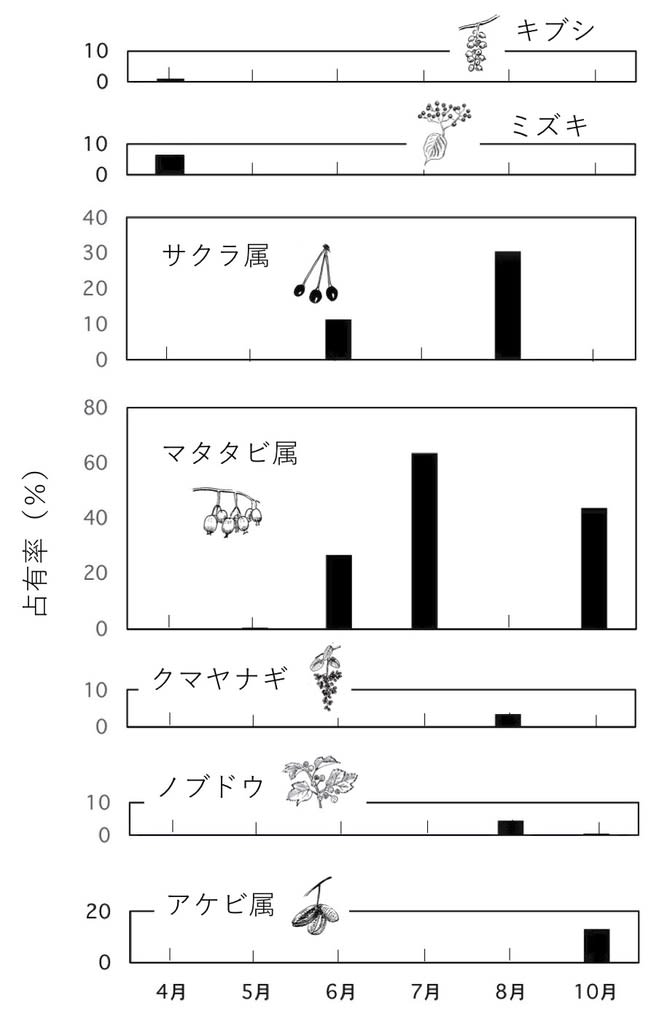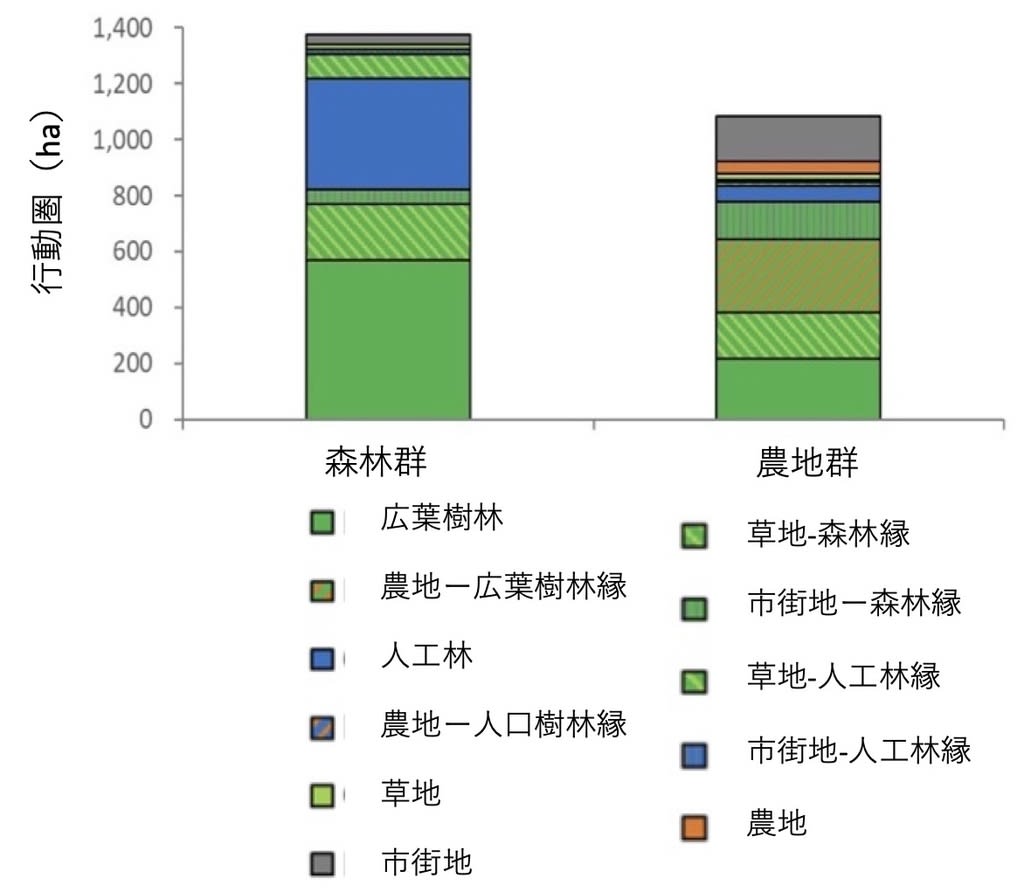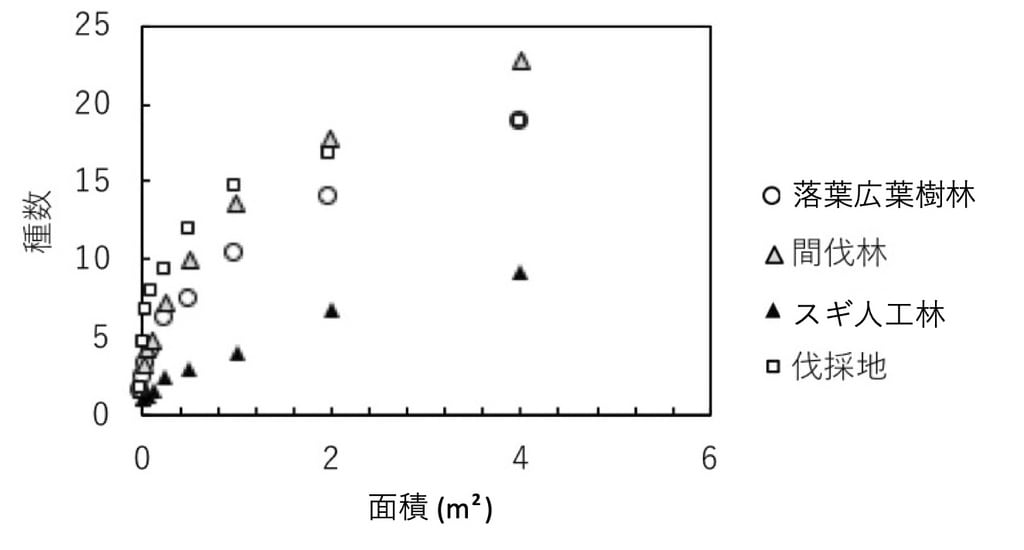<はじめに>
仙川は小金井から始まって南東に流れて野川と合流したあと二子玉川で多摩川に合流する川です。川とはいっても上流部分はいわゆる「三面張り」、つまり自然の川を底も両岸も
人工的にコンクリートにしています。ただし仙川では両岸は鉄板になっています。また水は流れていません。したがって「川」と呼ぶには相当無理がある感じです。
この仙川上流部にタヌキがいるという情報があったので、様子を見にいったところ、ため糞が見つかりました。私は「都会のタヌキ」の食性を調べたことがあります。一つは小平市の津田塾大学のキャンパス、もう一つは明治神宮です。津田塾大は確かに市街地にありますが、キャンパス内には立派なシラカシの林があるために、ムクノキなどの果実や植栽されたものですが、カキノキとイチョウの果実が主要な食物になっていました(こちら)。もう一つの明治神宮の森は津田塾大学以上に立派な林ですから、やはりムクノキやギンナンがタヌキの重要な食物になっていました。だから、都会のタヌキを調べたと言っても、正確には「都会の立派な林に住むタヌキ」しか調べていないことになります。 その意味では仙川のタヌキは文字通り都会の極端に人工化された環境に住むタヌキといえますから、そのタヌキが何を食べているかを知ることは、人と野生動物との共存という意味でも意義のあることです。
<仙川の環境>
仙川の「川底」に降りると、底の部分はコンクリート、両側は鉄の壁で、高さが2メートルあまりもあります。ユニットになっている鉄板は凹凸がありますが、隙間はなく、足がかりになりそうなものもないので、タヌキには上下ができそうもありません。ところどころに鉄の手すりがありますが、もちろんタヌキは使えません。
仙川の「川底」から眺める
しかも川の両側には高さ1メートル余りの金網柵があるので、人も出入りできません。このことはタヌキにとって人はほとんど来ないという意味で、安全性は確保されていると言えます。
仙川を上から見下ろす
<ため糞>
その仙川の一角でタヌキのため糞を見つけました。ここから新しいものを数個拾って分析することにしました。またセンサーカメラをおいておきました。
見つかったため糞
これがタヌキのため糞であるのは間違いないことではありますが、カメラには糞をするタヌキが写っており、確かにタヌキが利用していることが確認できました。
糞をするタヌキ
このため糞場で5月15日から17日、19日、21日と順調に糞を拾うことができましたが、22日
以降、パタリと利用されなくなりました。理由は不明ですが、あるいはセンサーカメラを警戒したのかもしれません。しかしカメラを設置した初めの方で警戒し、次第になれるのが普通なので、1週間ほどしてから使わなくなったのは不思議です。実はこの近くで営巣していることが確認されており、子供の成長に伴い行動圏が変化した可能性もあります。
そのため、糞が集められなくなったのですが、5月31日に別の場所2カ所でため糞を見つけることができました。
<分析結果>
5月に16個の糞を分析しました。分析するには、まず糞を0.5mm間隔のフルイの上で水洗します。そのあとで、特殊なスライドグラスにのせ、顕微鏡でのぞいて多い少ないを評価します。細かいことは略しますが、「有無」ではなく、多い少ないを表現します。
その結果は以下の円グラフの通りです。
仙川のタヌキの糞組成
多かったのは種子(19%)、哺乳類(16%)、昆虫(13%)、無脊椎動物(11%)、貝(11%)などでした。種子のほとんどはサクラの種子で、仙川に落ちていたのはヤマザクラのサクランボでした。
仙川に落ちていたヤマザクラのサクランボ
ただ種子によってヤマザクラとソメイヨシノは区別ができないようです。
サクラ種子 (格子間隔は5mm)
「哺乳類」としたのは毛で、タヌキの毛と思われるものは微量で、多くはネズミの毛を思われる細く、短いものでした。その割には哺乳類の骨が少ししか出てこなかったのは不思議でした。
哺乳類の毛 (格子間隔は5mm)
昆虫は甲虫やアリとわかるものもありましが、多くは細かい断片で、識別できませんでした。
貝としたのは、カタツムリの殻で、これは別の場所ではあまり見かけないものでした。
カタツムリの殻 (格子間隔は5mm)
<まとめ>
全体を見ると、動物と植物がほぼ半々で、文字通り雑食性と言えます。ただし、日本のタヌキは果実依存で、ふつうは植物の方が多いので、このことが仙川のタヌキの食性の特徴かもしれません。食物環境としては、植物が貧弱で、川底にナガバヤブマオなどの方か外来雑草が生えている程度ですが、地上に植えられているサクラ、ヤマグワ、ミカンなどの果実が落ちてくるようです。今後も糞が確保できたら、季節変化を追跡したいと思います。
<タヌキがいなくなった>
その後、調査地からタヌキがいなくなりました。どこに行ったのかわかりません何度も糞を探して歩きましたが、見つからなくなりました、残念ながら調査を停止しました。