服部半蔵というと、「忍者の頭領」のイメージが強いが、彼自身は忍者ではなかった。
半蔵というのは継承された俗称で、幕末まで12人の半蔵が存在した。
黒井宏光氏の説では半蔵の「半」は平家の「平」の分解であり、もともと服部家は平家に仕える武将であったという。
もっとも有名な半蔵は二代目半蔵正成である。
その正成でもっとも有名なエピソードは「伊賀越え」である。
伊賀越えについては詳細は省略するが、要点は次の通りだ。
本能寺の変で信長が斃されたとき、家康は少数の部下を伴って堺にいた。
信長と同盟関係にあった家康は包囲網は潜れないとと自決を決心したが、本多忠勝らの進言もあり、思いとどまり浜松まで戻ろうと決意する。
道中、困難を極めたのが柘植村(伊賀町)、鹿伏兎峠(加太峠)ら伊賀越えであった。
その際、活躍したのが服部半蔵正成や伊賀者・甲賀衆であり、家康はその働きにより、半蔵を長として伊賀者、甲賀衆を召し抱えた。
上記は広く伝わっている半蔵正成の華々しいエピソードだが、正成は岡崎生まれの岡崎育ち。地理に詳しい訳でもなく、実際は活躍したかどうか不明だといえる。
ただし、伊賀者ら土地の者が活躍したのは紛れもない事実で、海音寺潮五郎氏も指摘するように、伊賀越えの活躍云々は別にして、それまで功績もあり伊賀にも所縁のある半蔵が伊賀者の長に選ばれたのであろう。
正成は家康と同年齢で、いまも半蔵門に名を残すほど重用されたが、子供の代になると栄華は続かなかった。
嫡子である三代目半蔵正就{まさなり}は、家康の弟である松平定勝の娘を嫁に貰い、家康とも親戚関係となる。
正就にはもはや忍者の面影はひとかけらもなく、生まれながらの大身旗本としての姿しかない。戸部新十郎氏は「忍びの知識そのものも捨てたいと思ったかも知れず」とまで言っている。
とにかく正就は配下の伊賀同心を奴僕のように使い、指示に従わぬ者は扶持米を減らしたというが、正就は会社でいえば部長職であり、社長は将軍である。社員の給与を決定するのは会社であり社長である。減給処分は部長職の権限を逸脱している。
正就の振る舞いは部下のボイコットを招き、伊賀同心は新たに足軽大将大久保甚右衛門の配下となった。これを恨みに思った正就はボイコットの首謀者と思しき一人を一刀の下に斬り殺しているが、これが人間違い。正就は妻の実家である松平家へお預けとなった。降格だけに留まらず、転勤まで言い渡された訳だ。
再起を期した正就は大坂夏の陣に出陣するが、そこで行方不明になっている。奥瀬平七郎氏は「多分、旧配下の伊賀者に消されたのであろう」と書いているが、黒井宏光氏は、越後長岡に逃れ農民として75歳まで生きたと書いている。
一方、四代目半蔵を襲名した正成の次男・正重も手落ちがあり、旗本の地位を失っている。
正重は結局、松平定綱に召し抱えられ、代々服部半蔵は幕末まで桑名藩の家老職を勤めることとなった。
伊賀では半蔵正成の兄である服部保元の子である千賀地半蔵則直が服部半蔵系統の継承者となる。
則直の子である采女が藤堂姓を許され、伊賀上野城代となった。
服部家では、桑名藩の家老、津藩の出先である伊賀上野の城代を産んだわけである。
桑名藩は周知の通り最後まで西軍に徹底抗戦した藩、かたや藤堂采女は鳥羽伏見の戦いにおいて、山崎砲台で佐幕の立場から一気に倒幕に転じた際の最高指揮官であったのが興味深い。
参考図書:忍者の履歴書(朝日文庫)戸部新十郎
煙の末(伊賀上野観光協会)黒井宏光
忍術の歴史(上野市観光協会)奥瀬平七郎
忍者と忍術(学研)
桑名藩分限帳(桑名市教育委員会)

伊賀上野城
↓ よろしかったら、クリックお願いします!!

人気ブログランキングへ

にほんブログ村


半蔵というのは継承された俗称で、幕末まで12人の半蔵が存在した。
黒井宏光氏の説では半蔵の「半」は平家の「平」の分解であり、もともと服部家は平家に仕える武将であったという。
もっとも有名な半蔵は二代目半蔵正成である。
その正成でもっとも有名なエピソードは「伊賀越え」である。
伊賀越えについては詳細は省略するが、要点は次の通りだ。
本能寺の変で信長が斃されたとき、家康は少数の部下を伴って堺にいた。
信長と同盟関係にあった家康は包囲網は潜れないとと自決を決心したが、本多忠勝らの進言もあり、思いとどまり浜松まで戻ろうと決意する。
道中、困難を極めたのが柘植村(伊賀町)、鹿伏兎峠(加太峠)ら伊賀越えであった。
その際、活躍したのが服部半蔵正成や伊賀者・甲賀衆であり、家康はその働きにより、半蔵を長として伊賀者、甲賀衆を召し抱えた。
上記は広く伝わっている半蔵正成の華々しいエピソードだが、正成は岡崎生まれの岡崎育ち。地理に詳しい訳でもなく、実際は活躍したかどうか不明だといえる。
ただし、伊賀者ら土地の者が活躍したのは紛れもない事実で、海音寺潮五郎氏も指摘するように、伊賀越えの活躍云々は別にして、それまで功績もあり伊賀にも所縁のある半蔵が伊賀者の長に選ばれたのであろう。
正成は家康と同年齢で、いまも半蔵門に名を残すほど重用されたが、子供の代になると栄華は続かなかった。
嫡子である三代目半蔵正就{まさなり}は、家康の弟である松平定勝の娘を嫁に貰い、家康とも親戚関係となる。
正就にはもはや忍者の面影はひとかけらもなく、生まれながらの大身旗本としての姿しかない。戸部新十郎氏は「忍びの知識そのものも捨てたいと思ったかも知れず」とまで言っている。
とにかく正就は配下の伊賀同心を奴僕のように使い、指示に従わぬ者は扶持米を減らしたというが、正就は会社でいえば部長職であり、社長は将軍である。社員の給与を決定するのは会社であり社長である。減給処分は部長職の権限を逸脱している。
正就の振る舞いは部下のボイコットを招き、伊賀同心は新たに足軽大将大久保甚右衛門の配下となった。これを恨みに思った正就はボイコットの首謀者と思しき一人を一刀の下に斬り殺しているが、これが人間違い。正就は妻の実家である松平家へお預けとなった。降格だけに留まらず、転勤まで言い渡された訳だ。
再起を期した正就は大坂夏の陣に出陣するが、そこで行方不明になっている。奥瀬平七郎氏は「多分、旧配下の伊賀者に消されたのであろう」と書いているが、黒井宏光氏は、越後長岡に逃れ農民として75歳まで生きたと書いている。
一方、四代目半蔵を襲名した正成の次男・正重も手落ちがあり、旗本の地位を失っている。
正重は結局、松平定綱に召し抱えられ、代々服部半蔵は幕末まで桑名藩の家老職を勤めることとなった。
伊賀では半蔵正成の兄である服部保元の子である千賀地半蔵則直が服部半蔵系統の継承者となる。
則直の子である采女が藤堂姓を許され、伊賀上野城代となった。
服部家では、桑名藩の家老、津藩の出先である伊賀上野の城代を産んだわけである。
桑名藩は周知の通り最後まで西軍に徹底抗戦した藩、かたや藤堂采女は鳥羽伏見の戦いにおいて、山崎砲台で佐幕の立場から一気に倒幕に転じた際の最高指揮官であったのが興味深い。
参考図書:忍者の履歴書(朝日文庫)戸部新十郎
煙の末(伊賀上野観光協会)黒井宏光
忍術の歴史(上野市観光協会)奥瀬平七郎
忍者と忍術(学研)
桑名藩分限帳(桑名市教育委員会)

伊賀上野城
↓ よろしかったら、クリックお願いします!!

人気ブログランキングへ
にほんブログ村










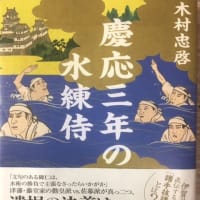
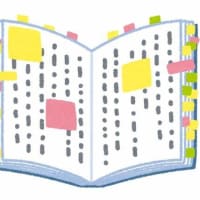
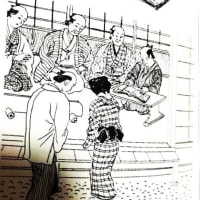
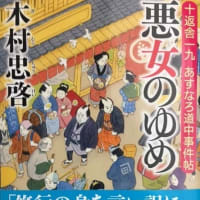
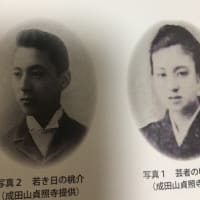

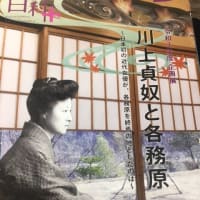
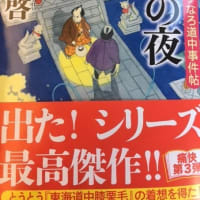
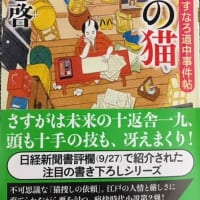
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます