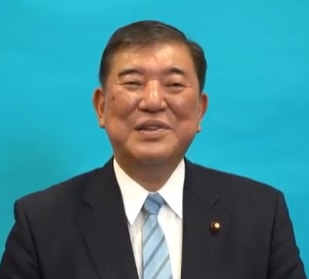【田久保市長】「19.2秒見せた」“卒業証書チラ見せ”否定するも録音を聞くと疑問点が…市長は「東洋大への謝罪」求め市議会に抗議文提出(静岡・伊東市)
まず誰が悪いのか。
この混乱を引き起こしたのは誰か?です。
東洋大学に謝罪しろって?
そもそも卒業していないのに卒業していた、
それがバレて除籍だった。と言ったのは田久保さん。
田久保さんの勘違いなのか、嘘なのかわかりませんが、
悪いのは田久保さんじゃないですか。
それをまあ、よう言うわ。です。
もう言い掛かりです。
ああ言えば、こう言う、もう呆れ果てます。
話題になっている19.2秒。
なんと副議長も抜かりがなかった・・・・
副議長も録音していたとは。
一応、普通は「今から録音します」と言って了解を得て録音するものですが、
お互い、信用ならないと録音していたのです。
いいえ、田久保さんは自分の正当性を示さなければならない場面を想定し、
副議長もまた嘘を付かれたらたまらないとの疑いで。
で、計測したらやっぱり19.2秒だった・・・・
今度は「いいじゃん」の言葉。
普段「いいじゃん」って言葉を使わないので、多分関西圏では言わない言葉。
言うなら「ええやん」? 違う? よくわからないですが。
「はいはい卒業したのがわかりました」「だからもう見せなくていいです」という納得し了解した意味なのか。
それとも「そんな見せ方なら、もう見せてくれなくてもいいです」という意味なのか。
それとも「もっと見せてくれてもいいじゃないか」という意味?
う~ん・・・よくわからないです。
それにちょっと軽い言葉に聞こえるのですが、どうなのでしょう。
とはいえ、論点は違うでしょ。
論点ずらしですよね。
除籍だった事は間違いない。
ですから卒業はあり得ない。
卒業証書も存在しない。
だからチラ見せした卒業証書は偽物、偽造したもの。
何秒見せたかは関係ありません。
だって偽物ですから。
偽物を20秒だろうと、2分だろうと見せられても偽物は偽物。
本物そっくりなら騙されるでしょうが、それでも偽物なのは間違いない。
いやあ、伊東市議会も大変です。
こんな事に時間と労力を使って、肝心の本業が疎かになるって事です。
市民の皆さんは怒らなくてはなりません。
税金で市長、市議の給与が払われているのに肝心の市政が滞っているのですから。
これこそ税金の無駄遣いです。
ま、他所の市の事を言えた義理じゃありませんが。
やっぱり百条委員会を開く時には追及する議員さんは想定問答で質問をよく考えておくべきでしょう。
こう答えられたら、こう反論する。
ああ答えたら、こう反論するってね。いわゆる「上祐論法」です。
若い人は知らないでしょうが、「ああいえば上祐」と言われた人物で、
何でもかんでも反論するのです。ま、ディベートの訓練を受けていたのでしょうが。
あのオウム真理教の広報担当で、問題発覚後記者から色々突っ込まれても屁理屈を並べて言い逃れしていました。
田久保さんも活動家だっただけあって口が達者。
屁理屈の女王ってところでしょうか。
でも、スラスラと誤魔化しを平気で言うのを見ると腹が立ちます。
他市民ですが、ムカつきます。
伊東市民の方々はどう思っておられるのでしょう。
もっと怒ってもいいと思いますが、どうなのでしょうね。