◆田野で干し大根を見た後、都城に『魯山人の宇宙展』を観に行ってきました。最終日で、お昼前に到着したのですが、けっこう人がいっぱい。みなさんギリギリさんが多いのね…。
入るとすぐに、長ーーい年表が…。すごい経歴で斜め読み…。陶芸家、料理家、美食家で知られている彼ですが、もともとは書家だったそうで。その後篆刻や画家も経験している。結婚も6回も‼(皆離婚)びっくりなおじさんだ。何はともあれ、陶器にだけ興味がある私は先を急ぐ…
彼の私の勝手なイメージは、タタラ作りの無骨な器で、織部釉薬をがっつりかけたもの…。でしたが、初めに登場した器たちは、けっこう繊細な染付の器でした。書家らしく、模様もありますが、文字を描いたものが多いです。
次から次へと、日本各地の陶芸の模倣がいっぱい登場します。なので、何でも『○○風』です。一枚目の写真の色絵の器は、『九谷風』といった具合に。全て自分の窯で焼いていたようで、それだけの土や釉薬の材料などをそろえるのは大変だったと思うし、オリジナルを作ってしまうのは器用なんだなー。
赤絵あり、、鉄絵あり、備前風火襷あり、織部、伊羅保、三島手まであってびっくりしました。
織部釉にいたっては、器全体にかけるという大技なのに、嫌みのない美しいものが沢山ありました。もちろん器の美を追求していたとおもうけれど、美食家の彼はきっと、盛られる料理を想像しながら作っているんでしょうね…。戦中終盤は、窯焼きに使う薪がなくなったので、陶器ではなく、漆器も作るという器用さ。たまげた。
自宅の写真には、お風呂や男性用トイレも陶器で作られている写真などもあったり、書や日本画、挿絵などの展示もありました。各ブースには魯山人の名句などが壁に書かれていて、面白い。『美器をつくらんとするものは、美食に通ずべし。』『山鳥のように素直でありたい。太陽が上がって目覚め、日が沈んで眠る山鳥のように…』『道は遠いかもしれない。しかし、その遠い道は、いつもいちばん手近の第一歩からはじまっているのだ。』
この展覧会、珍しくカメラ撮影が許されていました。展示も、和室などに直に器が飾られていたり、料理が盛り付けてある写真があったり、彼の作品は、芸術というより、使ってなんぼの、民藝なんだなーーと思いました。普段づかいの器にこそある美を堪能しました。美術館の外には世界緑茶コンテスト2009で金賞を受賞した「お茶のさかもと」のカフェコーナーがあり、魯山人写しの器でいただくお茶とほうじ茶マカロンでほっこりしました。












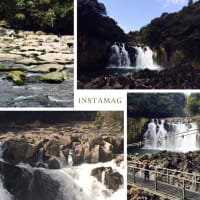







都城には大学時代の友人がいるのですが、これをみた夜、
都城に向かう夢をみました。ところが、行けども行けどもつかないのです。夢ってこんなものですよね。いつもいいところで終わっちゃう。魯山のこともお手紙に書いて送ろうと思いました。
私よりじっくり年表を見て、写真を撮りまくっておりました
面白い夢を見ましたねーー
お手紙書いて、都城まで遊びに行ってみてくださーーい
そして足を延ばして我が家まで