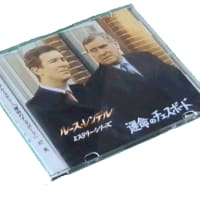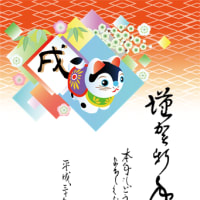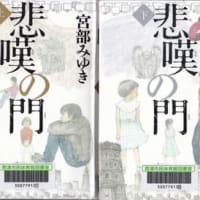| 探偵小説名作集 大下宇陀児集 | ||
|---|---|---|
 |
読了日 | 2010/10/03 |
| 著 者 | 大下宇陀児 | |
| 出版社 | 河出書房 | |
| 形 態 | 単行本 | |
| ページ数 | 307 | |
| 発行日 | 1956/08/15 | |
| ASIN | B000JAWCL6 | |
 の全集が発刊された昭和31年に、僕は高校2年生だった。その頃この全集の中の高木彬光集(刺青殺人事件、能面殺人事件収録)を無理して買って読んだ。
の全集が発刊された昭和31年に、僕は高校2年生だった。その頃この全集の中の高木彬光集(刺青殺人事件、能面殺人事件収録)を無理して買って読んだ。
(前に僕は、「刺青殺人事件」をいつ頃、どのような形で読んだのか忘れた、とここで書いたことがあったが、今更ながらこの本を買ったことで記憶が呼び覚まされた)
箱の後ろに定価240円とあるが、今とは違う貨幣価値がどのくらいだったのかは、全く記憶にないが、その当時の僕には通常の小遣いの範囲で買える値段ではなかったようだ。
こういうことを書いていると、苦い思い出が次々と浮かんで、16-7の僕がいかに子供だったかということからくる、後悔の念が湧くのだが、残りわずかとなった人生の今になって、後悔しても何も生まれない。

50年以上前の読書事情はすっかり忘れていたのだが、yahooのオークションを覗いていて、本書の写真を見た懐かしさから、思わず買ってしまった。当時はこういう箱入りの単行本が普通だったことを思い出して、そういえば同じ頃東京創元社から出ていた世界推理小説全集も箱入りだったと、懐旧の思いが重なる。
NHKのニュース番組で、昨日(10月27日)から一般向けにも始まった神田の古書店祭りの模様を見て、行ってみたいと思うが、交通費だけで何冊かの本がBOOKOFFで買えることを考えると、なかなか足は向かない。若いころは金がなくとも、せっせと古本屋街に通ったのだが・・・。
もっともその頃は今と違い郊外型の書店もなければ、古書店のチェーン店もなかったから、いきおい神田へと足を運ぶしかなかったのだ。
この全集が出た頃は、僕は著者の作品はまだ読んだことがなく、NHKラジオのクイズ番組「二十の扉」の解答者という意識しかなかった。
昭和35年まで続いたラジオ番組はNHKの看板ともいえる人気を誇っていた。僕が聞き始めたのはおそらく小学校高学年になってからだと思うが、なにしろ当時の家庭での娯楽と言えばラジオだけだったから(少なくも僕の所は)、番組の始まるのを心待ちにしていたことを思い出す。
もちろんラジオだから聞こえるのは声だけで、司会のNHKアナウンサー藤倉修一氏や解答者の藤浦洸氏(作詞家)や、柴田早苗氏(女優?)、大下宇陀児氏らの姿を写真で見たのはずっと後になってからだ。


 て、全集の名の通り本書には、2編の長編小説が収録されている。
て、全集の名の通り本書には、2編の長編小説が収録されている。
初めの「鉄の舌」は、頭脳はそれほどでもないが、誠実さを持ち味とする青年を主人公としたサスペンス・ストーリー。
公立の高等学校(旧制)の受験に三度も失敗している下斗米悌一は、今度こそという意気込みはあるのだが、友人たちと行きつけのカフェ「レギイネ」の娘・扶佐子が気になって受験勉強も捗らない。4度目にしてようやく弟の章吉ともども合格して安心したのもつかの間、代議士だったこともある父親は、相場に失敗して、下斗米家は家屋も人手に渡す羽目に陥る。
出来のよい弟だけでも進学させるため、悌一は会社勤めをする決心をする。会社勤めを始めた悌一は、そのまじめさが経営者に気に入られて、アルバイトから正社員へ、さらに経理を任されるまでになるのだが…。
波乱万丈ともいえる下斗米悌一の人生は、これでもかというばかりに不運に見舞われるのだが、誠実一筋の人間を陥れてはならないという教訓か?昭和12年の作品。
「石の下の記録」は、昭和23年から25年にかけて雑誌「宝石」に連載された戦後の作品で、こちらの方が全体の3分の2近くを占めている。
今では全く聞かなくなったアプレゲール(戦後派の新しい思想や態度を表す意味で、少し変わった人間をつかまえてそう呼んだりした)という言葉を使って巻末で、中島河太郎氏の解説があるが、不良学生たちの考え出した金融業は、後の高木彬光作品の、白昼の死角を思い起こさせる。1951年、第4回の日本推理作家協会受賞作だが、この当時はまだ、日本探偵作家クラブ賞だったと思う。
どちらも名探偵が事件を解く、という形ではなくリアリズムを目指したストーリーで、その時代の世相を色濃く反映させて、それでも探偵小説を読んだという読後感を与えてくれた2編だった。