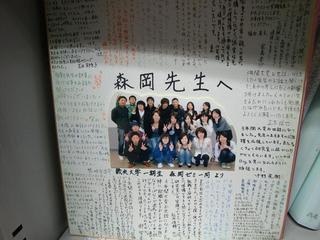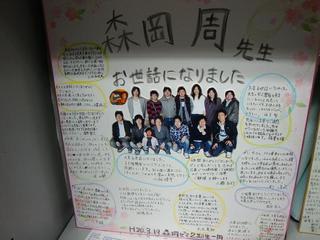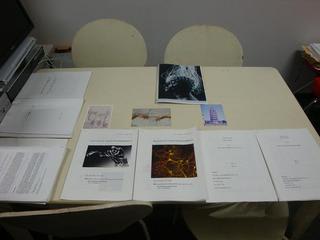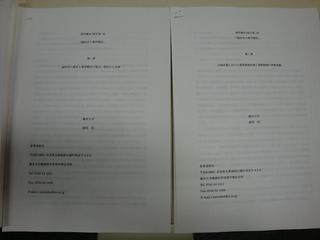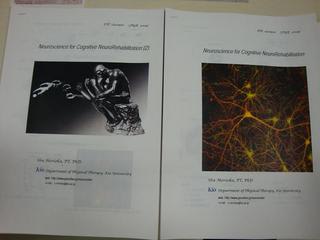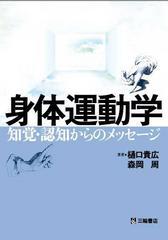今日は早々に大学に来て、
深夜に仕上げた週末の講演の資料を添付で送信する。
もう少し時間があれば、意味ある資料にできたと思うが、
元来、活字は論文もしくは著書で読むべきで、
それを情報として能動的に仕入れるということが、
学問する、のスタートだと臨床1年目から思い、
実践してきた自分にとって、
講習会の資料ですべてがわかるとは思わず、
あくまでも、イントロダクションで良いと思っているために、
図の挿入が中心となる。
これは、恩師である高知大学認知行動神経科学教室の八木教授のスタイルに影響を受けている。
八木先生の系統講義資料「Behavior Neuroscience」は図のみである。
その活字入りが「神経心理学」となった。
今読み返してもこの本は「名著」である。
9時過ぎには今日の試験である「人間発達学」の印刷を行い、
ホッチキスとめを行った。
このような自動化されたいわゆる上肢の周期運動とは?
などと考えながら、とめるとあっという間にすぎた。
10時にはweb magazine siteの
「カラフル・エイジ」の松浦さんが研究室に来られ、取材を受ける。
松浦さんはご近所さんである。
「夜型キッズ」の増加の問題について、
視覚、記憶の視点から話した。
自然の光には自由度があるし、違いがある。
自然を感じるとは、違いに敏感になるということ。
人工光では、それは感じ取れない。
記憶は睡眠時の海馬の機能について話し、
いわゆる「期末試験」でなく、
「受験」という壮大な目標を達成するためには睡眠が必要であることを話した。
また、「ゲームと脳」についても問われ、
ゲームが決して悪いわけでないが、
「対話」の重要性について「共同注意」の視点から話した。
すなわち、子どもと情報を共有することの意味について。
また、遊びの創造性において、
何かに見立てる脳の機能の重要性を問題解決能力から述べた。
以前にこれは地元の小学校のPTAの会報に書いた記事を視点に。
創造力豊かな子どもを育てる。
親としてはとっても魅力あるこの響きに、
現代社会のリアリティ重視の世界観は矛盾が生じている。
人間はいつか人間自身を滅ぼしてしまうのかもしれない。
遠い先の話かもしれないが、
時間は続いている、歴史を作るのは人間だし、自然現象だ。
近々、松浦さんの記事がWEB「カラフル・エイジ」に掲載されるようだ。
顔写真が入るので、ついに5割イメージになるのかもしれない。
写真は年々いやになる。
脳のなかの記憶が更新されない。
「カラフル・エイジ」とはいい響きである。
30~40代の一見自動化されやすい人生に、多様性、柔軟性をもたらすためにも「色どり」を与えるという響きにおいても。
また、「美意識」は人間の脳にとっての究極のもの。
美を意識することは、老いてもなお意識の中心にすえたいものだ。
13時より試験監督に入る。
追って試験問題は公開する。
監督最中、入来先生の主張である「感覚運動に心はいらない」視点を考え、
移動のための動き自体を自覚するには体性感覚のみでよいという神経科学的仮説について、
RizzolattiらのPE領域の機能とPFおよびAIP領域の機能の違いから、
ついにある視点にたどり着く。
合点がいった瞬間にである。
テスト監督中にず~と考えていた。
終了20分前に合点がいったために、「にやけて」しまった。
ついにある理論に到達する。
上肢と下肢機能に対するリハビリテーションは根本的に変えないといけない。
時間を見つけて論文にしたい。
試験監督を終え、残った原稿を半分書き(可塑性の部分)、
明日に半分(ブレイン・リーディングやコーディング)書くという自己約束をして、
17時以降にメールの返事を書き、
書類を書き、
そして、19時に奈良リハの佐藤先生を向かえ、
「脊髄損傷者の身体イメージ」に関する彼の論文を添削する。
彼は来年度から大学院生になる。
自らを追い込む、学者らしさを持っている。
20時過ぎにおえ、腰の痛さがピークになり、
しばらく、研究室内の赤いソファーで横になって、21時過ぎには帰路とした。
荷物には文献を多く入れて家でやるべし、と思ってもって帰ってきたが、
腰痛から、難しそうと判断し、
ただいま、ブログを書いて、明日にゆだねるとする。
今日から書き始めた原稿は、明日にはなんとか終わらせたい。
3月末日刊行に向けてはもうタイムリミットである。

家に帰りつくと、宮崎県士会の忠谷先生から南国フルーツが届いていた。
この場を借りてお礼を申し上げたい。