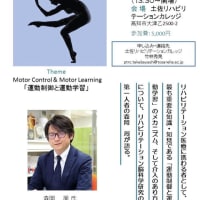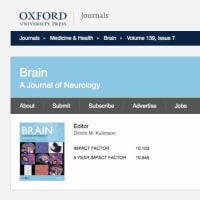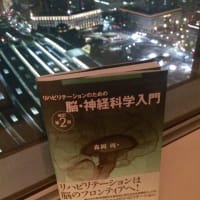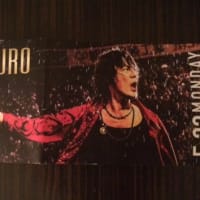昨日は2つの試験監督と大学院の研究計画発表。
試験、お疲れ様。
今日にでもすべて採点しないといけない。
1回が62名、3回が70名とちと多い。
明日は、94名の2回が待っている。
採点すれどもすれども終わらないという「予期」が頭によぎる。
おそらく、手に取り、答案の分厚さを体性感覚で確認する自分がたびたびあるだろう。
試験監督しながら、視覚の情報経路を考えたが、「黒い」と「真っ黒い」の言語の使い方の違いを、「真っ黒い」という比喩から考えた。
「真」とは何なのか?
また、運動と感覚を考えたときに、やはり、感覚の重要性にいきついた。
身体がないという感じは、この世に、そのものが存在しないといくことであるし、自分のoutputを感じられないのであれば、それはoutputが起こったとしても、豊かではないし、ステレオタイプなものになるのは当然である。
やっぱり、「理学療法」っていうのを見直さないといけないな。
環境と相互作用なんていっているわりには、一生懸命動かしている。
五感をもっと意識する、そういうセラピーにせめてかえていただきたい。
とりあえず、アクセサリーになっている「感覚」を復興したい。
「感覚」と分断するのは日ごろしていなく、このようなことは言いたくないが、いずれにしても、それを無視した「理学療法」ばかりだから、まず、はじめの第一歩としてしかたない。
自分のoutputを感じられないと、自分のoutputの×を感じられるとは大違いである。
「~ここち」とうものが生活を豊かにする。
大学院では、固有感覚と注意、目的運動の準備電位、ミラーニューロンシステムと異種・同種感覚統合の3つの計画が報告された。
早め早めに動いてください。
そのまま「博士論文」へといけるものもあります。
「修士」からneuro系の国際誌へ。
いままでにない「修士論文」になるでしょう。
自分を追い込むことです。
M的生活に変えてください。
追い込まれている自分に出会います。
さてさて、研究については、奈良、大阪のセラピストにも波及しているようだ。
経験から、これで軋轢も生まれると思うが、それぞれの立場でやらないといけないことはたくさんある。
若いセラピストが一緒に研究をしたいと、メールなどをいただく。
おそらくであるが、これもいままでの経験から上司が不愉快に感じるかもしれない。
高知でもよくあった。
だが、この際、先入観は捨て、バリアを自ら作らず、自由にやらしてみてはいかがでしょうか?
何がよい(違うという意見はすでに整理した言語による分類)かはわかりません。
その本質は見えないのです。
やってみながら、修正する、それが人生だし、やるまえからわかっていたら、それは人の生き方でなく、機械の生き方になってしまう。
そんなことを若者の不平不満から考えています。
僕自身、その時代、内容はどうであれ、そのとき、研究をしていなかったら、今の自分の生活はないと思う。
研究とは、チャレンジする「こころ」、それがはぐくまれる。
共同研究のみなさん、最近「論文」のペースが遅いですよ。
スピードも大事です。
越境しましょう。
試験、お疲れ様。
今日にでもすべて採点しないといけない。
1回が62名、3回が70名とちと多い。
明日は、94名の2回が待っている。
採点すれどもすれども終わらないという「予期」が頭によぎる。
おそらく、手に取り、答案の分厚さを体性感覚で確認する自分がたびたびあるだろう。
試験監督しながら、視覚の情報経路を考えたが、「黒い」と「真っ黒い」の言語の使い方の違いを、「真っ黒い」という比喩から考えた。
「真」とは何なのか?
また、運動と感覚を考えたときに、やはり、感覚の重要性にいきついた。
身体がないという感じは、この世に、そのものが存在しないといくことであるし、自分のoutputを感じられないのであれば、それはoutputが起こったとしても、豊かではないし、ステレオタイプなものになるのは当然である。
やっぱり、「理学療法」っていうのを見直さないといけないな。
環境と相互作用なんていっているわりには、一生懸命動かしている。
五感をもっと意識する、そういうセラピーにせめてかえていただきたい。
とりあえず、アクセサリーになっている「感覚」を復興したい。
「感覚」と分断するのは日ごろしていなく、このようなことは言いたくないが、いずれにしても、それを無視した「理学療法」ばかりだから、まず、はじめの第一歩としてしかたない。
自分のoutputを感じられないと、自分のoutputの×を感じられるとは大違いである。
「~ここち」とうものが生活を豊かにする。
大学院では、固有感覚と注意、目的運動の準備電位、ミラーニューロンシステムと異種・同種感覚統合の3つの計画が報告された。
早め早めに動いてください。
そのまま「博士論文」へといけるものもあります。
「修士」からneuro系の国際誌へ。
いままでにない「修士論文」になるでしょう。
自分を追い込むことです。
M的生活に変えてください。
追い込まれている自分に出会います。
さてさて、研究については、奈良、大阪のセラピストにも波及しているようだ。
経験から、これで軋轢も生まれると思うが、それぞれの立場でやらないといけないことはたくさんある。
若いセラピストが一緒に研究をしたいと、メールなどをいただく。
おそらくであるが、これもいままでの経験から上司が不愉快に感じるかもしれない。
高知でもよくあった。
だが、この際、先入観は捨て、バリアを自ら作らず、自由にやらしてみてはいかがでしょうか?
何がよい(違うという意見はすでに整理した言語による分類)かはわかりません。
その本質は見えないのです。
やってみながら、修正する、それが人生だし、やるまえからわかっていたら、それは人の生き方でなく、機械の生き方になってしまう。
そんなことを若者の不平不満から考えています。
僕自身、その時代、内容はどうであれ、そのとき、研究をしていなかったら、今の自分の生活はないと思う。
研究とは、チャレンジする「こころ」、それがはぐくまれる。
共同研究のみなさん、最近「論文」のペースが遅いですよ。
スピードも大事です。
越境しましょう。