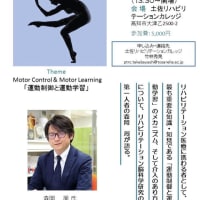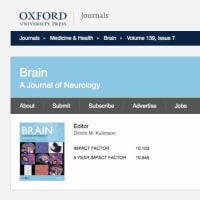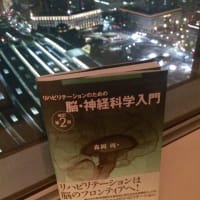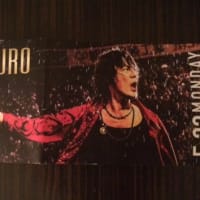昨日は朝早くから、出張講義の準備を何もしていないので、
必死に準備して、AMの11時に奈良を出て、
一路、滋賀県の安曇川まで向かう。
1時間半ほどかかる道のりは昨年以来である。
琵琶湖の湖西を過ぎると、
突然、雪景色に。

雪は降っていないが、
先日の大雪がいまだにとけていないという。
迎えに来ていただいた高校教諭の先生からそううかがった。

13時50分より、
普通科80名の高校生に対して、
脳科学が教える高校生の学習方法という題で、
1時間40分の出張講座をはじめる。
50分授業でも注意がもたない高校生にとって
1時間40分は相当に長かったと思うが、
よく聴いてくれたと思う。
記憶、海馬の話をして、
長期増強モデルから、
反復することが、記憶することの大前提である視点、
脳番地の話をして、
つながる(結合)することが大事である視点、
作業記憶の実行機能を取り上げ、
途中、M1で買ったnon style を取り上げ、
入力された情報を言語化し外に向けることの大事さを話した。
中間、期末試験のサイクルでなく、
日々、出し続けるためには、
どうすべきかをヒントを与えた。
最後に学習は創発現象であり、
その現象に出会うためには結果をすぐ求めるのではなく、
継続し続けることの意味を神経科学から話した。
最後に脳科学の視点から以下の一般的に言われていることの大切さを話した。
① リラックスすること
② 自信を持つこと
③ 対象を好きになること
④ 対象に興味を持つこと
⑤ 強い動機付けや切迫感を持つこと
⑥ イメージ(予期)を活用すること
⑦ 反復すること
⑧ いろんな感覚を利用すること
⑨ 感情を使うこと
⑩ 注意を持続すること
⑪ 対話すること
⑫ 自己スタイルを見つけること
切迫感とは規律から生まれる。
自己に負けて責任を他者や学校や社会だけに向けるというのは、
いかにも自己中心的であり、
屁理屈のみで、先に進めない。
とにかく、自分本位でなく、
ルールを設けることが。
先に進む。
原稿なんかもそうです。
そのときに済ませていないと、
半年後の自分は更新されているから、
結局完成をみないまま終わる。
志向性は常に変化し続けるものだが、
ある面、妥協をして、
完成させることも大切である。
国家試験勉強もそのひとつであるし、
研究発表もそうである。
高校生の目は純粋であり、
それを感じた。
16時17分、安曇川発の新快速にのり、
高槻でおり、
阪急の乗り場にまで重い荷物を持ち、
雨の中、走った。
エスカレーターでつまずきそうになり、
やっとのことで、1分前に電車に乗ることができた。
それに乗り遅れたら飛行機に間に合わないので必死なのである。
切迫感というものは、なりふりかまわず、
がむしゃらに、時に力を発揮する。
一方で、俺はこんなに忙しくして、
走りまくって、何をしたいのだろう、
という弱い部分の心理も生まれる。
しかし、前を向いていこうと思った。
南茨木でモノレールに乗り換え、
伊丹空港へ。
これまた滑り込み、
機内へ。
途中、電話が色々かかってきたが、
出る暇なんかなかった。
高知空港に19時過ぎにつき、
園田先生に迎えにきていただき、
くろそん まで。
小野先生、高橋先生と合流。

とてつもない大きさ(分厚さ)のひらめ、ブリ、サザエの刺身、
そして、これまたものすごい分厚いクエの鍋。

そして、これまた分厚くあたたかいかつおの塩たたき。
焼き切り。
何もつけないで食べる。

すしもついてこれで一人5000円。
料理を堪能し、
体調がよければよいが、
なかなか味覚まで幸福になる、っていうのは、
心身ともにリラックスが必要なのかもしれない。
その後、ヨークで鶴埜先生と合流し、
色々話す。
11時過ぎには体調からホテルに帰り、
最近、ほとんど寝てなかったので、
寝て、5時におき、
今日の講義資料を作成した。
今日の講義テーマは、
高知医療学院1年生~3年生のすべてを対象にした、
「脳からみる動作分析」
皮質間連合、皮質-皮質下連合による運動制御を話したのち、
今日は運動制御の基本的構成である、
前頭-頭頂間結合を話して、
理学療法評価の視点を話した。
脳のなかを評価・分析するためには、
動作学、運動学がある程度わかっているのを前提に、
その運動不全の背景になっている、
どこの連結に問題があるか、
脳の機能から評価していく。
診断ではなく、リハビリテーション評価である。
その視点を近々、
まとめていきたいと思う。
そろそろ、評価も提供しないといけないと、
最近痛感している。
3時間講義したが、
みなさん、純粋な目をしている。
悪く言えば、幼児的だが、
逆に、いろんなことを感じていくのだと思う。
大人は物の見方が、トップダウン解釈してしまい、
時に、自己中心的になってしまう。
他者の意見に反するっていうのもそのひとつ。
知恵が邪魔をするときもある。
いや、それは知恵とはいわないか。
15時前まで学校にいて、
今、休息中である。
この後、内田脳神経外科・もみのき病院で、
「運動学習・運動イメージ」について2時間半の講演を行う。
必死に準備して、AMの11時に奈良を出て、
一路、滋賀県の安曇川まで向かう。
1時間半ほどかかる道のりは昨年以来である。
琵琶湖の湖西を過ぎると、
突然、雪景色に。

雪は降っていないが、
先日の大雪がいまだにとけていないという。
迎えに来ていただいた高校教諭の先生からそううかがった。

13時50分より、
普通科80名の高校生に対して、
脳科学が教える高校生の学習方法という題で、
1時間40分の出張講座をはじめる。
50分授業でも注意がもたない高校生にとって
1時間40分は相当に長かったと思うが、
よく聴いてくれたと思う。
記憶、海馬の話をして、
長期増強モデルから、
反復することが、記憶することの大前提である視点、
脳番地の話をして、
つながる(結合)することが大事である視点、
作業記憶の実行機能を取り上げ、
途中、M1で買ったnon style を取り上げ、
入力された情報を言語化し外に向けることの大事さを話した。
中間、期末試験のサイクルでなく、
日々、出し続けるためには、
どうすべきかをヒントを与えた。
最後に学習は創発現象であり、
その現象に出会うためには結果をすぐ求めるのではなく、
継続し続けることの意味を神経科学から話した。
最後に脳科学の視点から以下の一般的に言われていることの大切さを話した。
① リラックスすること
② 自信を持つこと
③ 対象を好きになること
④ 対象に興味を持つこと
⑤ 強い動機付けや切迫感を持つこと
⑥ イメージ(予期)を活用すること
⑦ 反復すること
⑧ いろんな感覚を利用すること
⑨ 感情を使うこと
⑩ 注意を持続すること
⑪ 対話すること
⑫ 自己スタイルを見つけること
切迫感とは規律から生まれる。
自己に負けて責任を他者や学校や社会だけに向けるというのは、
いかにも自己中心的であり、
屁理屈のみで、先に進めない。
とにかく、自分本位でなく、
ルールを設けることが。
先に進む。
原稿なんかもそうです。
そのときに済ませていないと、
半年後の自分は更新されているから、
結局完成をみないまま終わる。
志向性は常に変化し続けるものだが、
ある面、妥協をして、
完成させることも大切である。
国家試験勉強もそのひとつであるし、
研究発表もそうである。
高校生の目は純粋であり、
それを感じた。
16時17分、安曇川発の新快速にのり、
高槻でおり、
阪急の乗り場にまで重い荷物を持ち、
雨の中、走った。
エスカレーターでつまずきそうになり、
やっとのことで、1分前に電車に乗ることができた。
それに乗り遅れたら飛行機に間に合わないので必死なのである。
切迫感というものは、なりふりかまわず、
がむしゃらに、時に力を発揮する。
一方で、俺はこんなに忙しくして、
走りまくって、何をしたいのだろう、
という弱い部分の心理も生まれる。
しかし、前を向いていこうと思った。
南茨木でモノレールに乗り換え、
伊丹空港へ。
これまた滑り込み、
機内へ。
途中、電話が色々かかってきたが、
出る暇なんかなかった。
高知空港に19時過ぎにつき、
園田先生に迎えにきていただき、
くろそん まで。
小野先生、高橋先生と合流。

とてつもない大きさ(分厚さ)のひらめ、ブリ、サザエの刺身、
そして、これまたものすごい分厚いクエの鍋。

そして、これまた分厚くあたたかいかつおの塩たたき。
焼き切り。
何もつけないで食べる。

すしもついてこれで一人5000円。
料理を堪能し、
体調がよければよいが、
なかなか味覚まで幸福になる、っていうのは、
心身ともにリラックスが必要なのかもしれない。
その後、ヨークで鶴埜先生と合流し、
色々話す。
11時過ぎには体調からホテルに帰り、
最近、ほとんど寝てなかったので、
寝て、5時におき、
今日の講義資料を作成した。
今日の講義テーマは、
高知医療学院1年生~3年生のすべてを対象にした、
「脳からみる動作分析」
皮質間連合、皮質-皮質下連合による運動制御を話したのち、
今日は運動制御の基本的構成である、
前頭-頭頂間結合を話して、
理学療法評価の視点を話した。
脳のなかを評価・分析するためには、
動作学、運動学がある程度わかっているのを前提に、
その運動不全の背景になっている、
どこの連結に問題があるか、
脳の機能から評価していく。
診断ではなく、リハビリテーション評価である。
その視点を近々、
まとめていきたいと思う。
そろそろ、評価も提供しないといけないと、
最近痛感している。
3時間講義したが、
みなさん、純粋な目をしている。
悪く言えば、幼児的だが、
逆に、いろんなことを感じていくのだと思う。
大人は物の見方が、トップダウン解釈してしまい、
時に、自己中心的になってしまう。
他者の意見に反するっていうのもそのひとつ。
知恵が邪魔をするときもある。
いや、それは知恵とはいわないか。
15時前まで学校にいて、
今、休息中である。
この後、内田脳神経外科・もみのき病院で、
「運動学習・運動イメージ」について2時間半の講演を行う。