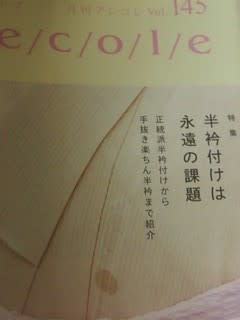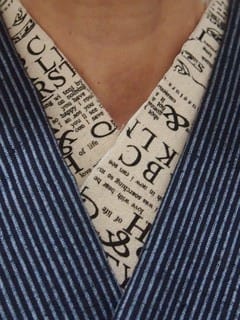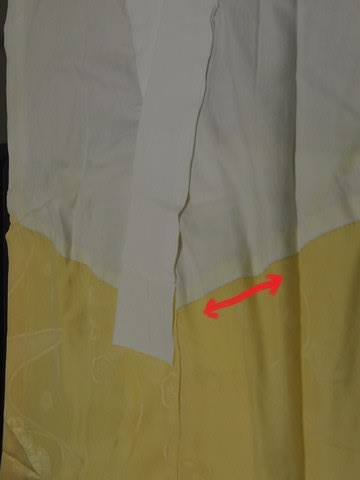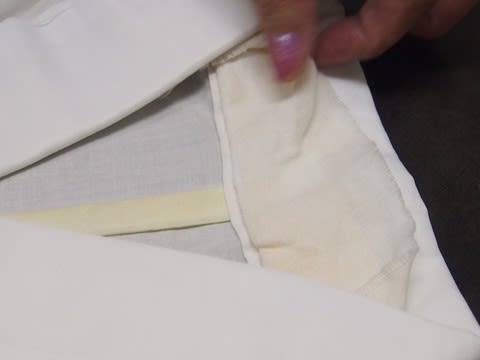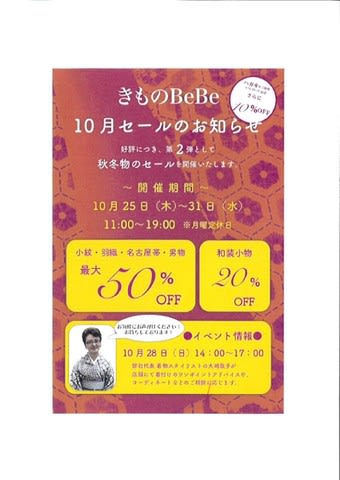捨ておいていた着物関係の記事ですが
アップしておきます。
先の燕コーディ、
最初は縞小紋に合わせるつもりでした。


ちょっと仕事という雰囲気ではないかなと、
お召し替え。
後ろからみるとそうでもないのですが、
前からみると、

ちょっとシドケないかなと。
半襟はこちらのほうが合うなあ。

帯揚げはモノトーン格子。
帯締めは緑系で翡翠でした。
こちらは生紬にカーネーション。
帯締めも同じ緑ながらちょっと違う。
帯同じでも、結構印象変わるなあ、
これも着物着回しの面白さです。

あと、帯結び。
これは前に銀座に行ったとき、

最初に結んだときには、こんな風に
お太鼓大きくてぺたんこ。
気に入らないなあ~~、

そこでふっくら結び。
やはり私はこちらが好き。
帯に通した帯締めを少し上に
持ってくるだけですが。

というわけで、
残りモノきもののアップです。
ブログネタは数々あれど、
アップの時間が~~。

残りものには福がある~~?
ありますように~~。
燕来る母は出かけてをりまする
野中
いつも応援ポチ
ありがとうございます。
励みになっております。





























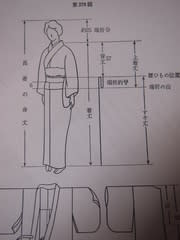















 一
一