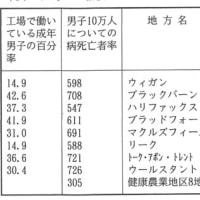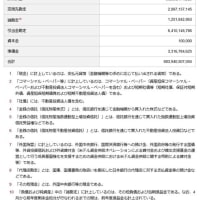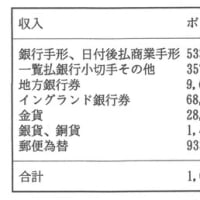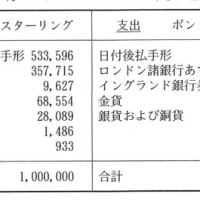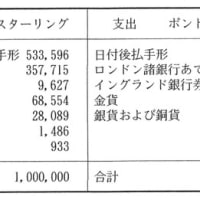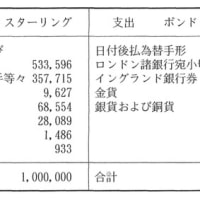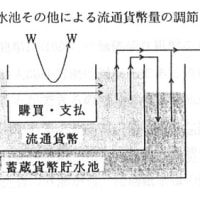『資本論』学習資料No.29(通算第79回)(1)
◎「いかにして、なぜ、なにによって、商品は貨幣であるか」(№6)(大谷新著の紹介の続き)
大谷禎之介著『資本論草稿にマルクスの苦闘を読む』の「Ⅲ 探索の旅路で落ち穂を拾う」の「第12章 貨幣生成論の問題設定とその解明」のなかの「Ⅰ 貨幣生成論の問題設定とその解明--いかにして、なぜ、なによって、商品は貨幣であるか--」の紹介の続きで、その第6回目(最終回)です。
前回は、大谷氏が久留間鮫造氏のシェーマ(=定式、「いかにして、なぜ、何によって、商品は貨幣になるか」)は、あくまでも〈『資本論』における貨幣生成論という観点から見たときに,価値形態論,物神性論,交換過程論のそれぞれの課題がなんであるかを問題にしている〉のであって、例えば価値形態論の場合においても、〈『資本論』第1部第1篇における第3節の課題あるいは『資本論』第1部の商品論における価値形態論の課題を,それ自体として問題にしているのではない〉と強弁しているのに対して、それでは実際問題として、久留間鮫造氏の著書『価値形態論と交換過程論』のなかで氏自身はどのように問題を提起しているのかを検討し、その問題提起のなかで久留間氏が引用している『資本論』第1篇第2章の第15パラグラフで、果たしてマルクスは何を問題にしているのかを問い、それは久留間氏がいうように〈それは第3章の貨幣論の直前のところであり、したがってまた、第3章以前の貨幣に関する考察の最後のところにあたる〉と、あたかもマルクスが貨幣に関する考察を結論的に述べているところであるかに説明していますが、果たしてマルクスにはそうした意図があったのかどうか、を検討するために、第15パラグラフ全体を紹介して、その解説を試みたのでした。しかしその解説はあまりにも長くなりすぎるので、一旦、途中で中断したのでした。今回はその続きです。
やはり、もう一度、第15パラグラフ全体を紹介しておきます。
【15】〈(イ)先に指摘したように、一商品の等価形態はその商品の価値の大きさの量的規定を含んではいない。(ロ)金が貨幣であり、したがって他のすべての商品と直接的に交換されうるものであることを知っても、それだからといって、たとえば10ポンドの金の価値がどれだけであるかはわからない。(ハ)どの商品もそうであるように、貨幣〔*〕はそれ自身の価値の大きさを、ただ相対的に、他の諸商品によってのみ、表現することができる。(ニ)貨幣〔*〕自身の価値は、その生産のために必要とされる労働時間によって規定され、等量の労働時間が凝固した、他の各商品の量で表現される(48)。(ホ)貨幣〔*〕の相対的価値の大きさのこうした確定はその産源地での直接的交換取引の中で行われる。(ヘ)それが貨幣として流通に入る時には、その価値はすでに与えられている。(ト)すでに17世紀の最後の数十年間には、貨幣分析のずっと踏み越えた端緒がなされていて、貨幣が商品であるということが知られていたけれども、それはやはり端緒にすぎなかった。(チ)困難は、貨幣が商品であることを理解する点にあるのではなく、どのようにして、なぜ、何によって、商品が貨幣であるのかを理解する点にある(49)。〉
〔* カウツキー版、ロシア語版では「金」となっている〕
前回は、各文節ごとの解説を試み、《だから、久留間氏が注目した最後の二つの文節((ト)(チ))で述べていることは、このパラグラフ全体でマルクスが中心に言いたいことから見れば、ある意味では、副次的な、あるいはそれを補強するようなものでしかない》ということを確認したのでした。
今回はその上で久留間氏が提起している問題に戻って考えてみようということです。以下、やはり以前の解説からの紹介の続きです。
《さて、その上で、それでは久留間氏の問題提起に戻りましょう。これまでの考察を前提して、最後の文節((チ))の内容をもう一度吟味してみましょう。まず〈貨幣が商品であることを理解する〉ことは、厳密にいえば正しいとはいえなくても、比較的容易なことであって、〈すでに17世紀の最後の数十年間〉に〈貨幣分析〉の〈端緒がなされ〉るなかでも指摘されてきたことです。しかし本当に困難なのは、そうしたことではなく、〈どのようにして、なぜ、何によって、商品が貨幣であるのかを理解する点にある〉とマルクスは言います。
まずここで、〈商品が貨幣である〉とは、一体、どういうことなのでしょうか。フランス語版では,この部分は〈困難は、貨幣が商品であることを理解することにあるのではなく、どのようにして、なぜ、商品が貨幣になるか、を知ることである〉となっており、〈商品が貨幣になる〉と書かれています。また〈どのようにして、なぜ〉としか問われていません。フランス語版の場合は、ドイツ語版の初版や第二版に較べて、平易化する配慮がなされていることを考慮したとしても、ここでマルクスが述べていることは、貨幣は商品であるということより、商品が貨幣になるのはどうしてかを理解することの方が困難であり、またそれこそが貨幣の何であるかを知ることになるのだ、ということではないでしょうか。
だから〈商品が貨幣である〉というのは、フランス語版のように、文字通り商品がどのようにして貨幣になるのかを知ることだということのように思えます。以前、第2章の位置づけや課題について、次のように論じたことがありました。
【「第1篇 商品と貨幣」は「第1章 商品」と「第2章 交換過程」、「第3章 貨幣または商品流通」からなっています。この構成をみれば、第1章では商品とは何かが解明され、第3章では貨幣の諸機能と商品流通における諸法則が解明されることが明らかになり、第2章は、第1章と第3章を媒介する章であることが分かるのです。・・・・
そして第2章が第1章と第3章を媒介する章であるとの位置づけが分かれば、それが短いのに一つの章として第1章と第3章と対等の位置に置かれているという理由も分かると思います。それは例えば第2篇には、一つの章しかなく、しかも分量としては短いものであるのに、第1篇や第3篇と対等の位置にどうして位置づけられているのかという理由と同じ理由なのです。第2篇の表題は「貨幣の資本への転化」ですが、これはまさに第1篇と第3篇を媒介する篇であることをその表題そのものが示しているといえるでしょう。だから同じような位置づけで考えるなら、「第2章 交換過程」は、内容からいえば、いわば「商品の貨幣への転化」とでも言えるような位置にあると考えられるわけです。・・・・〉(第33回報告)
〈だからこの第3節は確かに貨幣に言及し、貨幣形態の発生を立証しているわけですが、しかし、それはあくまでも商品とは何か(それが第1章の課題です)を明らかにする一環としてそうしているのだということ、商品とは何かを明らかにするために、商品にはどうして値札が付いているのかを説明するためのものだという理解が重要なのです。同じように貨幣の発生を説明しているように見える「第2章 交換過程」が、第1章の商品論を前提にして、商品がその現実の交換過程において、如何にして貨幣へと転化するのかを解明するものであり、それによって第1章と第3章とを媒介するものであるという、その役割や位置づけにおける相違も分かってくるのです。〉(第44回報告)
〈(1)まず第1章では商品は、二重の観点で観察され、ある時は使用価値の観点のもとに、他の時は、交換価値の観点のもとに、分析されたのですが、しかし第2章では、商品はひつの全体として、すなわち使用価値と交換価値との直接的な統一物として考察されるということです。つまり第1章では、その限りでは商品は抽象的に取り上げられたのですが、第2章では、商品はより具体的なものとして取り上げられることが分かります。だから諸商品の相互の現実の関係、つまり諸商品の交換過程が考察の対象になるというわけです。
(2)そしてそうすると、商品はそうした使用価値と交換価値との直接的な統一物としては、直接的な矛盾だとも指摘されています。第1章では商品の二要因である使用価値と交換価値(価値)とは、互いに対立するものとして考察されました。これに対して、第2章では、そうした対立物の直接的な統一として商品が考察されるために、諸商品の交換は直接的な矛盾だというのです。矛盾ということは、諸商品が、使用価値として存在する場合、あるいは交換価値として存在する場合、それらは互いに前提し合いながらも、同時に排斥し合う関係にもあるということです。第2章では、現実の諸商品の相互の関係が、こうした直接的な矛盾として分析されることが指摘されています。そしてその矛盾が現実に解決されていく過程こそが、すなわち貨幣の発生過程でもあるというわけです。だから第2章は現実の諸商品の交換過程において、如何にして商品は貨幣へと転化するのかを解明するものでもあるといえるでしょう。
(3)そしてまた商品の現実の関係である交換過程においては、互いに独立した諸個人、すなわち商品所有者が入り込む社会的過程でもあると指摘されています。つまり商品は第1章に比べてより具体的に考察されるわけですが、それは使用価値と交換価値との直接的な統一物として考察されるだけではなく、第1章では捨象されていた、それらの諸商品の所有者が新たに考察の対象に入ってくるということです。〉(第45回報告)
〈しかし、これらの三つの矛盾の相互の関係を論じるまえに、そもそもどうして交換過程では、こうした矛盾が論じられているのでしょうか。まずそれから考えましょう。
それを考えるためには、もう一度、第1章「商品」との関連で、第2章「交換過程」の課題を明確に掴む必要があります。
これについては、一度詳しく論じたことがあります(第44回報告)。そこでは次のように説明しました。第1章「商品」は、商品とは何かを明らかにすることでした。確かに第1章ではリンネルや上着やコーヒーや鉄や金など、さまざまな商品が登場してそれらの関係が考察されたのですが、しかしこれらはあくまでも商品とは何かを明らかにすることが目的なのです。もちろん、商品とは何かを明らかにするということは、その商品がリンネルであろうが、上着であろうが何でも良かったのですが、しかし問題は、あくまでも商品とはそもそも何かを明らかにすることでした。そしてその商品の何たるかを解明するためには、商品は自らの価値を具体的に表す存在でなければならないこと、それを商品は貨幣形態、つまり価格という形で表していることをマルクスは明らかにしたのです。だからリンネルと上着との価値関係やリンネルと他の諸商品との展開された価値形態など、さまざまな諸商品との関係が考察されたのも、そもそも商品にはどうして価格が、すなわち値札が付けられているのか、そうしたことを明らかにするために商品の価値の表現形態としての貨幣の発生を論証したのでした。
しかし重要なことは、そうした一連の諸商品の価値関係や価値形態の考察も、あくまでも、そもそも商品とは何かを解明するためであったということです。だから第1章では、商品はそれ自体として存在するもの、つまりその姿においてだれもが商品として分かる物的存在として、すなわち一つの現存在として把握されたのでした。あとはこの商品が一つの自立的存在として、今度はそれ自身の運動をわれわれは分析するのです・・・・
だから第2章は、第1章で明らかにされた商品をもとに、今度は自立した商品の運動が、すなわちその交換の過程が分析の対象になるのです。・・・・
つまり私たちが第1章で跡づけた価値形態の発展(単純な価値形態→展開された価値形態→一般的価値形態)は、いわば現実の商品交換の発展を前提して、そのうえで、そのそれぞれの発展段階の交換過程から、諸商品の交換を前提した上で、交換される諸商品そのものに注目して、それ以外の現実の商品交換に付随する商品所有者やその欲望等を捨象して、純粋に諸商品の交換関係だけを取り出し、商品の価値関係そのものに潜む、価値の表現形態の発展段階を分析してきたといえるのです。だからこそ、そうした商品の価値形態の発展の前提としてあった交換過程そのものが、今度は、第2章の分析の対象なのですから、諸商品の交換過程の発展が、こうした交換過程の三つの矛盾に対応していると言いうるのではないかと考えられるわけです(だからまた、当然、交換過程の三つの矛盾は、価値形態の三つの発展段階にも対応しているとも言えます)。〉(第46回報告)】
だから〈どのようにして、なぜ、商品が貨幣になるか〉(フランス語版)というマルクスの問いは、自立した現存在として捉え返された諸商品の運動、すなわちそれらの交換過程のなかで、あるいはその歴史的な発展の過程において、〈どのようにして、なぜ、商品が貨幣になるか〉ということであって、それは決して久留間氏が考えたような、第1章の課題ではないのです。 第1章第3節が貨幣の発生を論証しているのは、あくまでも商品形態--つまりその目に見える姿や形だけで、直接、われわれが商品であると認識できるような状態--を説明するために、その貨幣形態(価格形態、すなわち値札、われわれは値札が付いていて、初めてそれが商品であることを知り得るのです)を説明するがためなのです。それは自立した諸商品の運動が、すなわちそれらの交換過程のなかで、如何にして貨幣になるのか、つまり貨幣を生み出すのか、要するに「商品の貨幣への転化」を直接説明するものではありません。それはあくまでも商品の価値の表現形態の発展過程を跡づけることが課題であり、その最終的な完成形態としての貨幣形態を--商品にはどうして値札がついているのかを--説明し論証するがためのものなのです。第1章第3節は、第2章の交換過程が、その歴史的な発展において、どのように貨幣を生み出していくのかというその道程を、ただ諸商品の価値の表現形態という一面だけから、いわばその一面だけを切り取って、抽象的に見ることで、その発展を跡付けたものだといえるものなのです。
だから久留間氏のように、〈どのようにして〉が何処で論じられ、〈なぜ〉は何処で、〈何によって〉は何処だというような詮索の是非はともかく(そんな詮索そのものは本当は何も説明したことにはなっていないと思うのですが)、われわれは、これまでの第2章の展開のなかでそれらは追求され、明らかにされてきたのだと理解されるべきではないかと思います。
いずれにせよ、以前にも指摘したように、この問題での久留間氏の問題意識そのものが最初から正しいものでは無かったといわざるを得ません。むしろ久留間氏の問題提起は、その影響力が極めて大きかったこともあり、マルクスが本来この第2章の第15パラグラフで言いたかったことを正しく理解することを反対に妨げてきたといえるのではなないかとさえ私には思われます。》
以上が、以前説明したものの紹介です。これですでに答えは出ていると思いますので、この問題はこれで打ち切ることにします。
それでは本文テキストの解説に移ります。今回から第3篇「絶対的剰余価値の生産」の第5章「労働過程と価値増殖過程」の第1節「労働過程」を対象にします。しかしその前に、第2篇から第3篇への移行について問題にすることにします。
◎第2篇「貨幣の資本への転化」から第3篇「絶対的剰余価値の生産」への移行について
今回から「第3篇 絶対的剰余価値の生産」に入ります。まず目次を確認しておきましょう。次のようになっています。
〈第3篇 絶対的剰余価値の生産
第5章 労働過程と価値増殖過程
第1節 労働過程〉
さて、私たちは「第1節 労働過程」の各パラグラフの解説に移る前に、「第2篇 貨幣の資本への転化」から「第3篇 絶対的剰余価値の生産」への移行について少し考えてみましょう。以前、第2篇の位置づけについて次のように説明しました。
《だから第2篇第4章「貨幣の資本への転化」は、資本主義的生産様式の内在的諸法則を解明して、それを〈弁証法的形態で叙述する〉ために、貨幣から資本への移行を、すなわち第1篇「商品と貨幣」と第3篇「絶対的剰余価値の生産」とを媒介する篇なのです。それは第2章「交換過程」が、商品から貨幣への移行を、すなわち第1章「商品」と第3章「貨幣または商品流通」とを媒介する章であったのと同じ役割を果たしています。
第2章「交換過程」では、まずは商品の交換過程における矛盾が明らかにされ、その矛盾を解決するために必然的に貨幣が生み出されたように、第4章でも、第3章の結果である貨幣としての貨幣が、資本の最初の現象形態であることが明らかにされ、資本の一般的定式が与えられ、さらにその一般的定式の矛盾が指摘され、その解決のためには、単純流通から資本の生産過程への移行が必然であることが明らかにされるわけです。》
そして第2篇第4章の「第3節 労働力の売買」の第19パラグラフに次のように書かれていました。
〈いま、われわれは、労働力というこの独特な商品の所持者に貨幣所持者から支払われる価値の規定の仕方を知った。この価値と引き換えに貨幣所持者のほうが受け取る使用価値は、現実の使用で、すなわち労働力の消費過程で、はじめて現われる。この過程に必要なすべての物、原料その他を、貨幣所持者は商品市場で買い、それらに十分な価格を支払う。労働力の消費過程は同時に商品の生産過程であり、また剰余価値の生産過程である。労働力の消費は、他のどの商品の消費とも同じに、市場すなわち流通部面の外で行なわれる。そこで、われわれも、このそうぞうしい、表面で大騒ぎをしていてだれの目にもつきやすい部面を、貨幣所持者や労働力所持者といっしょに立ち去って、この二人について、隠れた生産の場所に、無用の者は立ち入るな〔No admittance except on business〕と入り口に書いてあるその場所に、行くことにしよう。ここでは、どのようにして資本が生産するかということだけではなく、どのようにして資本そのものが生産されるかということもわかるであろう。貨殖の秘密もついにあばき出されるにちがいない。〉
こうして私たちはいよいよ『資本論』の第1部の表題「資本の生産過程」を直接対象にし、それを明らかにする門口に立ったことになったわけです。ここに来るまでには何と長い道のりがあったことでしょう。しかしそれらは確かに「資本の生産過程」を直接に対象にしたものではありませんでしたが、しかしそれを背後に隠してその表面に現象している単純な流通過程を対象にしたものでした。それは現実には資本の流通過程であるものをとりあえずはより具体的な資本関係を捨象して、そのなかに一般的に存在している抽象的な関係を取り上げて考察したものだったのです。だから確かに「資本の生産過程」を直接には取り扱いませんでしたが、しかしまぎれもなく資本主義的生産様式そのものを対象にしていたのです。
ところで「労働過程」の解説に移る前にまだ片づけておかねばならないものがあります。
まず第3篇の表題である「絶対的剰余価値の生産」についてです。第1部「資本の生産過程」の本題に入るわけですが、それがどうして「絶対的剰余価値の生産」になっているのかという問題です。
私たちは第2篇の第1節で資本の一般的定式を知りました。それはG-W-G'でした。このG'については次のような説明がありました。
〈すなわちG'は、最初に前貸しされた貨幣額・プラス・ある増加分に等しい。この増加分、または最初の価値を越える超過分を、私は剰余価値(suplus value)と呼ぶ。それゆえ、最初に前貸しされた価値は、流通のなかでただ自分を保存するだけではなく、そのなかで自分の価値量を変え、剰余価値をつけ加えるのであり、言い換えれば自分を価値増殖するのである。そして、この運動がこの価値を資本に転化させるのである。〉
つまり剰余価値を生む運動がその貨幣を資本に転化させるのですから、資本の生産過程というのは剰余価値の生産過程なのです。剰余価値の生産は「第3篇 絶対的剰余価値の生産」と「第4篇 相対的剰余価値の生産」との二つに分けることができます。これは労働者から剰余価値を搾り取るそのやり方の違いです。絶対的なものはとにかく長時間労働を強いて搾り取るか、あるいはきつい労働をやらせて搾り取るやりかたです。もう一つの相対的な搾取のやり方は、もっとスマートなやり方ですが、それは資本の生産力を高めて労働力の価値そのものを引き下げて、剰余労働を増やすやり方なのです。歴史的には最初の絶対的な搾取のやり方は資本がまだ労働力を雇い入れてそのまま使用して剰余価値を得るやり方ですが、後者の方法は資本がもっと発展して生産様式そのものを資本の生産にあったものに変革するなかで、行われるものです。だから『資本論』の叙述でもそれはあとから考察されることになっています。マルクスはこれを労働の形態的包摂から実質的包摂への移行などと言っていますが、そうした難しいことはまたそのときに問題にすればよいでしょう。
その次に、問題にしなければならないは第5章の表題「労働過程と価値増殖過程」についてです。
資本の生産過程というのは、商品の生産過程であり、その商品の生産を通じて剰余価値の生産を行うわけです。そして商品はご存知のように、使用価値と交換価値(価値)との直接的な統一物です。だから資本の生産過程も使用価値の生産と価値(剰余価値)の生産との直接的に統一された過程として存在しているのです。だからそれらを対象とする第5章は使用価値の生産と剰余価値の生産とを対象にすることになるのです。すなわち現行版では「労働過程と価値増殖過程」という表題になり、「第1節 労働過程」、「第2節 価値増殖過程」となっています。しかし、フランス語版ではこれが「第7章 使用価値の生産と剰余価値の生産」となっていて、「第1節 使用価値の生産」と「第2節 剰余価値の生産」と内容に則した表題になっています。
そしてとりあえずは、分析的に一方の使用価値の生産、すなわち「第1節 労働過程」が私たちの分析の対象になります。
ところで、すでに指摘しましたように、現行版の「労働過程」はフランス語版では「使用価値の生産」となっています。しかしそもそも「労働過程」というのは、どういうことでしょうか。それは「労働」に「過程」が付いていますが、「過程」が付くことによって何が変わるというのでしょうか。
実は第1節の第3パラグラフのフランス語版には現行版にはない次のような注があります。本文と一緒に紹介しておきましょう。
〈労働過程①が分解される単純な要素は、次のとおりである。(1)人間の一身的な活動、すなわち、厳密な意味での労働、(2)労働活動の対象、(3)労働活動の手段。
① ドイツ語では労働過程(Arteits-Process)。「過程(procès)」という語は、発展の現実的諸条件の全体において考察される発展を表現しているが、この語は久しい以前から全ヨーロッパの科学用語に属している。フランスには、この語は当初processusというラテン語の形でおずおずと導入された。次いでこの語は、このペダンティックな仮装をはぎとられ、化学、生理学等の著書や形而上学の数々の著作のなかに忍びこんだ。それはついには、完全に自国語になるであろう。ついでながら注意しておくが、ドイツ人もフランス人と同じように、日常語では「訴訟(procès)」という語を法律的な意味で用いている。〉 (江夏・上杉訳168頁)
つまり「過程」というのは〈発展の現実的諸条件の全体において考察される発展を表現している〉のだそうです。だから労働過程というのは労働が発展していく現実的諸条件をその全体において考察されるという意味を表しているということのようです。
さて、商品の二要因である使用価値と価値とは対立したものであり、だから使用価値には価値は一切含まれず排除されています。また使用価値というのは、如何なる歴史的な社会形態とも無関係に歴史貫通的に存在しているものですから、だからこの労働過程も、とりあえずは資本関係が捨象された素材的な関係として私たちの前に現れます。それは如何なる社会関係にも関わりのない一般的な関係として取り扱われるのです。
それでは実際に「第1節 労働過程」の各パラグラフの文節ごとの解説に移ることにしましょう。
第1節 労働過程
◎第1パラグラフ(労働過程はまず第一にどんな特定の社会的形態にもかかわりなく考察されなければならない)
【1】〈(イ)労働力の使用は労働そのものである。(ロ)労働力の買い手は、労働力の売り手に労働をさせることによって、労働力を消費する。(ハ)このことによって労働力の売り手は、現実に、活動している労働力、労働者になるのであって、それ以前はただ潜勢的にそうだっただけである。(ニ)彼の労働を商品に表わすためには、彼はそれをなによりもまず使用価値に、なにかの種類の欲望を満足させるのに役だつ物に表わさなければならない。(ホ)だから、資本家が労働者につくらせるものは、ある特殊な使用価値、ある一定の品物である。(ヘ)使用価値または財貨の生産は、それが資本家のために資本家の監督のもとで行なわれることによっては、その一般的な性質を変えるものではない。(ト)それゆえ、労働過程はまず第一にどんな特定の社会的形態にもかかわりなく考察されなければならないのである。〉
(イ)(ロ) 労働力を使用するということは労働をするということです。労働力を買った人は、労働力を売った人に労働をさせることによって、その労働力を消費するわけです。
すでに紹介しましたが、第2篇第3節の一文をもう一度紹介しておきましょう。
〈いま、われわれは、労働力というこの独特な商品の所持者に貨幣所持者から支払われる価値の規定の仕方を知った。この価値と引き換えに貨幣所持者のほうが受け取る使用価値は、現実の使用で、すなわち労働力の消費過程で、はじめて現われる。この過程に必要なすべての物、原料その他を、貨幣所持者は商品市場で買い、それらに十分な価格を支払う。労働力の消費過程は同時に商品の生産過程であり、また剰余価値の生産過程である。〉
つまり資本家は労働者から彼の労働力を買い入れ、また労働力の使用に必要なすべての物、原料その他も市場で買い、いよいよ労働力の現実の使用に取りかかろうとするわけです。しかし労働力の使用というのは、労働そのもののことです。だから資本家は労働力を使用し消費するために、労働力の売り手である労働者に労働をさせなければなりません。こうして資本家は労働者のなかに潜在的にある力を発現させ、その可能性を現実化させるわけです。
(ハ) このことによって労働力を売った人は、現実にも、活動している労働力に、つまり労働者になるのです。それ以前はただ潜勢的に、可能性としてそうだっただけなのです。
こうして他方で、労働力を資本家に販売した人も、初めて労働者になるのです。すなわち現実に活動している労働力になるのです。だから彼らはそれまではただ潜勢的に労働者だったにすぎません。労働力を所持しているというだけでは労働者とは言えません。世の中には労働力を所持していながら、それを発揮していない人は一杯いますが、だから彼らを普通は労働者とは言いません(不労者とか寄食者とかいろいろと言い方はありますが)。その所持している労働力を現実に発揮している人こそが、労働者という資格があるわけです。
(ニ)(ホ) 労働者は彼の労働を商品として表わすためには、彼はそれをなによりもまずは使用価値として、つまり何らかの種類の欲望を満足させるのに役だつ物に表わさなければなりません。だから、資本家が労働者につくらせるものは、ある特殊な使用価値、ある一定の品物です。
労働者は彼の労働によって商品を生産するのですが、商品は使用価値と価値との直接的な統一物です。たがら商品を生産するためには、まずは価値の素材的担い手である何らかの使用価値を作らなければなりません。つまり何らかの社会的な欲望を満たすのに役立つものに自身の労働を表さなければならないのです。つまり資本家が労働者に作らせるものは、ある特定の使用価値をもつもの、ある一定の物品でなければならないのです。
(ヘ)(ト) 使用価値または財貨の生産は、それが資本家のために資本家の監督のもとで行なわれることによっては、その一般的な性質を変えるものではありません。だから、その使用価値の生産、すなわち労働過程はまず第一にどんな特定の社会的形態にもかかわりなく考察されなければならないのです。
何らかの使用価値あるいは何らかの財貨の生産というのは、いかなる社会形態にも関わらず存在しています。以前の第1章第2節「商品に表わされる労働の二重性」のなかでは次のように述べられていました。
〈それゆえ、労働は、使用価値の形成者としては、有用労働としては、人間の、すべての社会形態から独立した存在条件であり、人間と自然とのあいだの物質代謝を、したがって人間の生活を媒介するための、永遠の自然必然性である。〉 (全集第23a巻58頁)
だからそれが資本家にために資本家の監督のもとで行われるからといって、その使用価値を生産するという一般的な性質を変えるものではありません。だから労働過程そのものは、まず第一にどんな特定の社会的形態にも関わりのないものとして考察されなければならないのです。
『61-63草稿』から紹介しておきましょう。
〈貨幣所有者は、労働能力を買った--自分の貨幣を労働能力と交換した(支払いはあとでやっと行なわれるとしても、購買は相互の合意をもって完了している)--のちに、こんどはそれを使用価値として使用し、それを消費する。だが、労働能力の実現、それの現実の使用は、生きた労働そのものである。つまり、労働者が売るこの独自な商品の消費過程は労働過程と重なり合う、あるいはむしろ、それは労働過程そのものである。労働は労働者の活動そのもの、彼自身の労働能力の実現であるから、そこで彼は労働する人格として、労働者としてこの過程にはいるのであるが、しかし買い手にとっては、この過程のなかにある労働者は、自己を実証しつつある労働能力という定在以外の定在をもたない。したがって彼は、労働している一つの人格ではなくて、労働者として人格化された、活動している〔aktiv〕労働能力である。〉 (草稿集④83頁)
〈私が食べる小麦は、それを私が買ったのであろうと自分で生産したのであろうと、どちらの場合も同じく、その自然規定性に従って栄養過程で働きをする。同様に、私が私のために私自身の労働材料と労働手段とで労働しようと、あるいは私の労働能力を一時的に売った貨幣所有者のために労働するのであろうと、一般的形態における労働過程には、すなわち労働〔Arbeiten〕一般の概念的諸契機には、なんの変わりもない。この労働能力の消費、すなわちそれの、労働力〔Arbeitskrafte〕としての現実の実証、現実的労働--これは、それ自体としては〔an sich〕、ある活動が諸対象へのある種の諸関係にはいる、という過程である--は、依然として同じままであり、同じ一般的諸形態で運動する。いやそれどころか、労働過程あるいは現実の労働〔Arbeiten〕が前提〔unterstellen〕するのは、まさに次のこと、すなわち労働者は、彼の労働能力を売るまえには、彼がそのなかでのみ自分の労働能力を実証することすなわち労働することができるところの対象的諸条件から分離されていたが、この分離が止揚されるということ、彼はいまでは、彼の労働の対象的諸条件にたいする、労働者としての本性に即した関係〔Naturgemäße Beziehung〕に、労働過程にはいる、ということである。したがって、私がこの過程の一般的諸契機を考察するときには、私はただ、現実的労働一般の一般的諸契機だけを考察するのである。〉 (草稿集④101頁)
◎第2パラグラフ(労働の一般的規定。労働は、まず第一に人間と自然とのあいだの一過程である)
【2】〈(イ)労働は、まず第一に人間と自然とのあいだの一過程である。(ロ)この過程で人間は自分と自然との物質代謝を自分自身の行為によって媒介し、規制し、制御するのである。(ハ)人間は、自然素材にたいして彼自身一つの自然力として相対する。(ニ)彼は、自然素材を、彼自身の生活のために使用されうる形態で獲得するために、彼の肉体にそなわる自然力、腕や脚、頭や手を動かす。(ホ)人間は、この運動によって自分の外の自然に働きかけてそれを変化させ、そうすることによって同時に自分自身の自然〔天性〕を変化させる。(ヘ)彼は、彼自身の自然のうちに眠っている潜勢力を発現させ、その諸力の営みを彼自身の統御に従わせる。(ト)ここでは、労働の最初の動物的な本能的な諸形態は問題にしない。(チ)労働者が彼自身の労働力の売り手として商品市場に現われるという状態にたいしては、人間労働がまだその最初の本能的な形態から抜け出ていなかった状態は、太古的背景のなかに押しやられているのである。(リ)われわれは、ただ人間だけにそなわるものとしての形態にある労働を想定する。(ヌ)蜘蛛(クモ)は、織匠の作業にも似た作業をするし、蜜蜂はその蝋房の構造によって多くの人間の建築師を赤面させる。(ル)しかし、もともと、最悪の建築師でさえ最良の蜜蜂にまさっているというのは、建築師は蜜房を蝋で築く前にすでに頭のなかで築いているからである。(ヲ)労働過程の終わりには、その始めにすでに労働者の心豫のなかには存在していた、つまり観念的にはすでに存在していた結果が出てくるのである。(ワ)労働者は、自然的なものの形態変化をひき起こすだけではない。(カ)彼は、自然的なもののうちに、同時に彼の目的を実現するのである。(ヨ)その目的は、彼が知っているものであり、法則として彼の行動の仕方を規定するものであって、彼は自分の意志をこれに従わせなければならないのである。(タ)そして、これに従わせるということは、ただそれだけの孤立した行為ではない。(レ)労働する諸器官の緊張のほかに、注意力として現われる合目的的な意志が労働の継続期間全体にわたって必要である。(ソ)しかも、それは、労働がそれ自身の内容とその実行の仕方とによって労働者を魅することが少なければ少ないほど、したがって労働者が労働を彼自身の肉体的および精神的諸力の自由な営みとして享楽することが少なければ少ないほど、ますます必要になるのである。〉
(イ)(ロ)(ハ)(ニ) 労働というのは、第一に人間と自然とのあいだの一つの過程です。この過程で人間は自分と自然との物質代謝を自分自身の行為によって媒介し、規制し、制御するのです。人間は、自然素材にたいして彼自身一つの自然力として相対します。彼は、自然素材を、彼自身の生活のために使用されうる形態で獲得するために、彼の肉体にそなわっている自然力、腕や脚、頭や手を動かします。
私たちは労働過程をどんな特定の社会的な形態ともかかわりなく考察しようとしているのですが、というより、如何なる社会的形態のなかにも普遍的に存在しているその一般的な形態で考察しようとしているのですが、その場合にまず最初に問題になるのは、そもそも「労働」というのは何なのか? ということです。
労働というのは人間のなかに潜在的に備わっている労働力を発揮することです。しかしそのためには人間がその労働によって働きかける対象がなければなりません。その対象というのは本源的には自然そのものです。だから労働を一般的に見るなら、それは第一には人間と自然とのあいだの一つの過程だということです。
人間は自然と労働によってかかわるなかで、人間が生きていくのに必要なものを自然から獲得・摂取し、不要なものを排泄しています。つまり人間は自身と自然との間の物質代謝を労働によってコントロールしているのです。
このコントロールのなかでは、人間は自然に対して自身も一つの自然力として相対します。そして自然素材を自分の生活に必要なものに変化させ、それを獲得するために、自分自身の自然力として備わっている腕や足、あるいは頭と手を動かすのです。
(ホ)(ヘ) 人間は、この運動によって自分の外の自然に働きかけてそれを変化させ、そうすることによって同時に自分自身の自然〔天性〕を変化させます。彼は、彼自身の自然のうちに眠っている潜勢力を発現させ、その諸力の営みを彼自身の統御に従わせるのです。
このように人間は自身と自然との間の物質代謝をコントロールするなかで、人間は自然に変化をもたらすだけではなく、実は人間自身が自身に備わっている自然の力そのものを変化させ、発展させていくのです。彼は、彼自身のうちに眠っている潜勢力を発現させて、その諸力を自身の統御に従わせているのですが、その過程を通して自身の諸能力を発展させていくのです。
(チ)(リ) ここでは、労働の最初の動物的な本能的な諸形態は問題にしません。労働者が彼自身の労働力の売り手として商品市場に現われるという状態にたいしては、人間労働がまだその最初の本能的な形態から抜け出ていなかった状態は、すでに太古的背景のなかに押しやられているからです。
私たちは労働をその一般的な姿で考察するとしましたが、しかしあくまでも人間に固有のものとしてそれを考察するわけです。だから人間がまだ動物的な本能的な形で自然に働きかけていたような状態のものは問題にしません。少なくとも労働者が彼自身の労働力の売り手として商品市場に現れているという状態を前提しているのであって、それに比べれば人間労働がその本能的な形態から抜け出ていないような状態は、はるか太古の時代の物語として私たちの視野には入ってこないのです。
(ヌ)(ル)(ヲ) 蜘蛛(クモ)は、織匠の作業にも似た作業をするし、蜜蜂はその蝋房の構造によって多くの人間の建築師を赤面させます。しかし、もともと、最悪の建築師でさえ最良の蜜蜂にまさっているのは、建築師は蜜房を蝋で築く前にすでに頭のなかで築いているからです。だから労働過程の終わりには、その始めにすでに労働者の心豫のなかには存在していた、つまり観念的にはすでに存在していた結果が出てくるのです。
私たちの労働に似たことは動物のなかにも見ることができます。例えば蜘蛛は、緻密な巣をかけて、織物のようなものを作りますし、蜜蜂が蝋で作る巣は極めて精緻な構造になっていて、へたくそな大工を赤面させるのに十分な出来ばえです。
しかしこのような動物の作業と人間の労働との決定的な違いは、人間の場合にはその労働が始まる前に、その労働の結果が頭のなかに描かれているということです。動物の場合はただ本能によって行われている作業が、人間の場合に人間自身の意志によって行われているということです。労働過程の終わりには、その始めにすでに労働者の頭のなかにあった観念的なものが、現実に存在するものとして、労働過程の結果として現れてくるのです。
(ワ)(カ)(ヨ) 労働者は、自然的な物の形態変化をひき起こすだけではありません。彼は、自然的な物のうちに、同時に彼の目的を実現するのです。その目的は、彼が知っているものであり、法則として彼の行動の仕方を規定するものであって、彼は自分の意志をこれに従わせなければならないのです。
最初にこの部分のフランス語版を参照しておきましょう。
〈彼はたんに自然的素材の形態変化を行なうだけではない。彼はこのばあい同時に、自分自身の目的--この目的は、自分が意識するものであり、法則として自分の行動様式を規定するものであって、彼は自分の意志をこれに従わせなければならないのである--を実現する。〉 (江夏・上杉訳168頁)
だから労働者は、その労働によって自然の物のなかにその形態変化を引き起こすだけではありません。彼は自然の物のなかに、彼自身の目的を実現するのです。その目的というのは、彼がすでに彼の頭のなかに描いているものであり、そしてその目的を達成するために必要な自然のなかにある諸法則を認識し、それに彼の行動を従わせるために、自分の意志を働かせなければならないものです。
(タ)(レ)(ソ)(ツ) そして、これに従わせるということは、ただそれだけの孤立した行為ではありません。労働する諸器官の緊張のほかに、注意力として現われる合目的的な意志が労働の継続期間全体にわたって必要なのです。しかも、それは、労働がそれ自身の内容とその実行の仕方とによって労働者を魅了することが少なければ少ないほど、したがって労働者が労働を彼自身の肉体的および精神的諸力の自由な営みとして享楽することが少なければ少ないほど、ますます必要になるのです。
この部分もまずフランス語版を見てみましょう。
〈しかも、これに従わせるということは、一時的なものではない。仕事は、活動する諸器官の努力のほかに、それ自体が意志の不断の緊張からのみ生じうるような一貫して変わらない注意力を、仕事の全期間にわたって必要とする。労働がその対象とその遂行様式によって労働者の心をとらえることが少なければ少ないほど、労働が肉体的および知的諸力の自由な活動として労働者に感じられることが少なければ少ないほど、一言にして言えば、労働の魅力が少なければ少ないほど、仕事はますます上記の注意力を必要とする。〉 (江夏・上杉訳168頁)
そしてこうした自然力のもつ諸法則に自身の行動を従わせるために意志を働かせるということは、労働するために必要な肉体的な諸力能をそれに従わせて発揮するだけではなく、注意力として発揮される合目的的な意志が労働の継続期間全体にわたって発揮されるということでもあるのです。
だからこのような精神的な集中力は、その労働がそれ自身の内容やその実行の仕方によって労働者自身を魅了することが少なければ少ないほど、つまり労働者の労働が彼自身の肉体的・精神的な自由な営みとして、それ自体が喜びとなることが少なければ少ないほど、そうした合目的的な意志の強さは必要とされるのです。
(全体を9分割して掲載します。以下は(2)に続きます。)