| ラヂオアクティヴィティ[Ra.] 第二部・国境なき恐怖 165チェルノブイリ大惨事  チェルノブイリ大惨事と画面に文字が映る。 「おじいさん、始まりますよ。勇気も写るかもしれませんよ」 庭で鶏を遊ばせていたおじいさんは、鶏を鳥小屋に追い込んで、あわてて座敷に座る。 カメラのむこうの ソーシアは気力を振りしぼっていた。 「私が生まれたころは、ソ連という国がありました。その国には、特権階級の人たちがいました。政府の役人や党の役員はいい生活をしていました。党というのは共産党だけでした」 なぜ、こんなことから話しはじめたのだろう、と勉は考えた。そうか、秘密主義ということを説明したいのか……。 「アメリカでスリー・マイル島事故が起きたとき、ソ連の原子力関係者は、そんなことはソ連では絶対に起きないと説明していました」 おじいさんは、おばあさんに、 「どこかの国も、そんなこと公言しているわね……」 「どこの国かって、日本じゃないの……」 近くに原発があることをおじいさんは思い出した。 「原子力関係者は、事故が起こったとき、本当に責任があった人は、だれ一人、何の責任もとりませんでした。事故は起きないと教えていたくせに……」 おじさんは、煎餅をつまみ。 「それでも、やっぱり起こった……。まったく、学者とかいうのは、口ばっかりで責任もとらん! 昔、徳光アナウンサーは、ジャイアンツが負けて坊主にしたことがあった……。まったく、学者なんて……、熱心なジャイアンツ・ファンを見習うべきじゃ」 「全員がみな、嘘つきじゃないでしょうに……。おじいさん。そう興奮しないで……」 テレビ画面では、ソーシアが慎重に話す。 「これから、チェルノブイリ原発事故についての、VTRがあります。でも、ソ連は秘密主義でした。いいえ、それ以上でした。ソ連政府は意図的に事故を隠蔽したのです。KGBが、その隠蔽の主導権をとったのです。ソ連政府の発表では、物証や目撃者の証言と一致しないのです。まるで違った報告だったのです」 ソーシアのアップが映る。 「それでは、VTR、スタート!」 チェルノブイリ原発がうつる。 一九八六年四月二十六日零時・地震発生・震度四と字幕がでる。 男のアナウンサーの声。 「チェルノブイリは二つの断層の間に建てられました。原発では、その日の夜勤者は二十名でした。コンピューター・センターの責任者は青い閃光を見たのです。中央建屋は断層の真上にあり、その下には硬い変成岩がありました。雷のような音がして、天井からタイルが落ちてきました。床が波うち、電気が消え、非常灯がつきました。その三十秒後に耳をつんざく音がしました。七号機の近くで屋根が抜け落ち、機械室の電気が消えた。原子炉の停止が決断されました。アキーモフは緊急停止のAZ5のボタンを押した。何が起きてもこのボタンを押せば安全といわれていたものでした。あたり一面に粉塵が舞い、電気が消えました。電気がついたとき、屋根をつきぬける光をみました。壁、天井、床が揺れました。二度目の爆発は、小さなものでした。さしこんでくる光を通して破壊のようすが見え、光はいろんな色がまざりあったもので、地上百メートルの高さまで上昇しました」 チェルノブイリ原発はみごとに破壊された写真が画面に映っている。 女性アナウンサーの声。 「森の樹々や湖や川や小麦畑やそして果樹園や町の集落が、巨大な火柱の灼光にくっきり映えて浮かび上がっていました。黒煙はぐんぐんと上昇し、膨らみ、とどまることなく天空でなおも膨らみ続け、やがて、茸雲があらわれたのです。二人の若い技師は、原子炉を見に行き報告しました。「制御棒なんてありませんよ。外に出ました。中央ホールはもう影も形もありませんでした」と驚くべきことを話したのです」 女性の声は、しんみりと話しだす。 「また、ある職員は、非常呼び出しを受け、あわてて走っていきました。第四発電所の建物に近づくと、黒鉛が吹き飛んで、あたり一面にゴロゴロしていたのです。放射線レベルもすごく高くなっていたのです」 男性アナウンサーの低い声に替わる。 「消防隊に通報が入ります。第二消防隊第三小隊はただちに現場へ出動しました。とちゅう、隊長は無線を通じて、キエフ州全域の消防隊に緊急出動を要請する第三警報を発します。一時三十分、第三小隊は現場に到着したのです。広い屋上はあっという間に火と煙に包まれ、悪いことに屋根はアスファルトで覆われていたのです。高熱で溶け出し、泡立ったアスファルトが靴の下で燃え、衣服にも飛び散り、皮膚を焼きました。煙と熱と痛みで消耗しきった隊員たちに、放射能が最後の一撃を加えたのです。一時三十五分、プリピャチ市の市部の消防を担当している独立第六消防隊が現場に到着しました。彼らは原子炉区域の消火と第三ブロックの延焼防止を引き受けた。そこは放射線レベルが最も高く、とても危険な場所でした。第三小隊の中尉は機械室屋根の消火を隊員にまかせ、彼は第六消防隊の応援にかけつけました。消防隊で最初に殉職した六人は、すべてこの原子炉区で消火に当たった者たちでした」 また女性の声。 「一時四十六分、休暇中だった少佐が自宅からかけつけ、直接消火の指揮を取りました。かれは非常階段をのぼって屋上に出ました。爆発でパックリと口を開けた原子炉、そのすぐそばで火とたたかっている部下たちの姿を目撃した時、テリャトニコフは体中の血が凍る思いで、一瞬立ちすくんだといいます。二時十分、機械室の火災をおさえ、二時三十分、原子炉区の火災をおさえた。三時三十分から四時、消防隊の中から消火活動中に嘔吐、失神する者が続出したため、人員の交替を行なった」 画面では、消防士が活躍している様子を描いている。 「四時現在、事故現場には各地区から十五の消防隊が集結した。四時二十分、放射線が危険なレベルに達していることを考慮し、消防隊員と機材を現場から避難させた。五キロ離れた地点に撤退、予備隊を編成して待機させたのです。四時五十分、火災抑制。六時三十六分、鎮火。この夜、出動した消防車輛は総数八十一台、隊員は総数百八十六人だった。初期消火活動に当たった隊員たちは自分たちの負傷や体の不調を手当てする前に、事故現場から何人もの原発運転要員を救出した。その中の一人、第四発電ブロックの自動化システム調整係V・シャシェノークは、看護婦である妻に見守られながら間もなく絶命した」 ドイツ語の新聞が画面に出る。 「西ドイツでは、ベルギッシュ・グラッドバッハの日刊紙が、事故当日にモスクワからキエフに飛行機で向かった百人のドイツ人団体旅行客の一人の談話として、午後三時ごろ、「明るい青空に黒雲」が突然あるのを飛行機から見た話をのせた。それは、一万メートルの高度にあった、と聞きます」
 ありがとうございます。 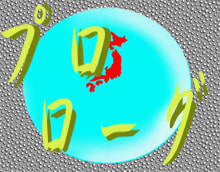   Index[Ra.] |
最新の画像[もっと見る]
-
 いい音ってなんだろう-あるピアノ調律師、出会いと体験の人生-
12年前
いい音ってなんだろう-あるピアノ調律師、出会いと体験の人生-
12年前
-
 音楽演奏の社会史-よみがえる過去の音楽-
12年前
音楽演奏の社会史-よみがえる過去の音楽-
12年前
-
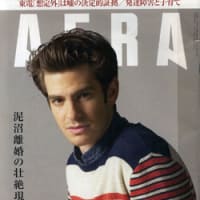 AERA ’12.7.16
12年前
AERA ’12.7.16
12年前
-
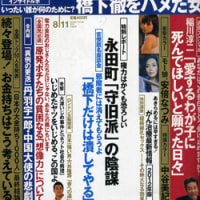 週刊現代 2012-8-11
13年前
週刊現代 2012-8-11
13年前
-
 AERA ’12.7.9
13年前
AERA ’12.7.9
13年前
-
 必ず来る!大震災を生き抜くための食事学-3・11東日本大震災あのとき、ほんとうに食べたかったもの-
13年前
必ず来る!大震災を生き抜くための食事学-3・11東日本大震災あのとき、ほんとうに食べたかったもの-
13年前
-
 僕のお父さんは東電の社員です-小中学生たちの白熱議論!3・11と働くことの意味-
13年前
僕のお父さんは東電の社員です-小中学生たちの白熱議論!3・11と働くことの意味-
13年前
-
 日本の原爆-その開発と挫折の道程-
13年前
日本の原爆-その開発と挫折の道程-
13年前
-
 エコノミスト-週刊エコノミスト- 2012-3/13
13年前
エコノミスト-週刊エコノミスト- 2012-3/13
13年前
-
 エコノミスト-週刊エコノミスト- 2012-3/6
13年前
エコノミスト-週刊エコノミスト- 2012-3/6
13年前









