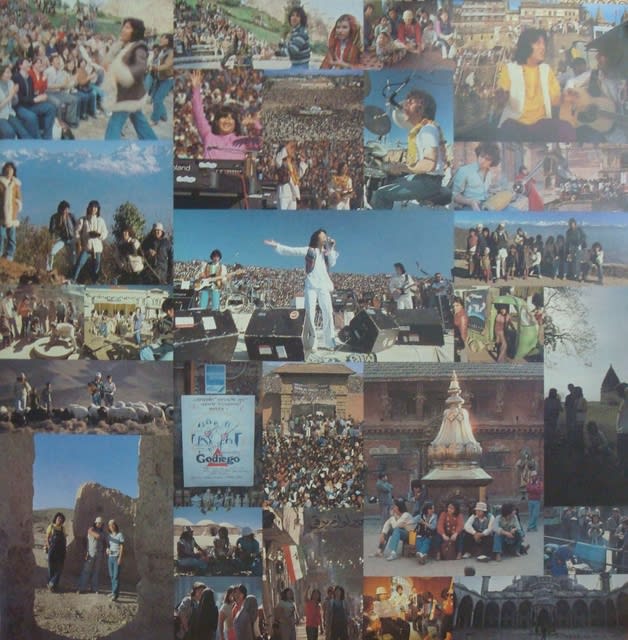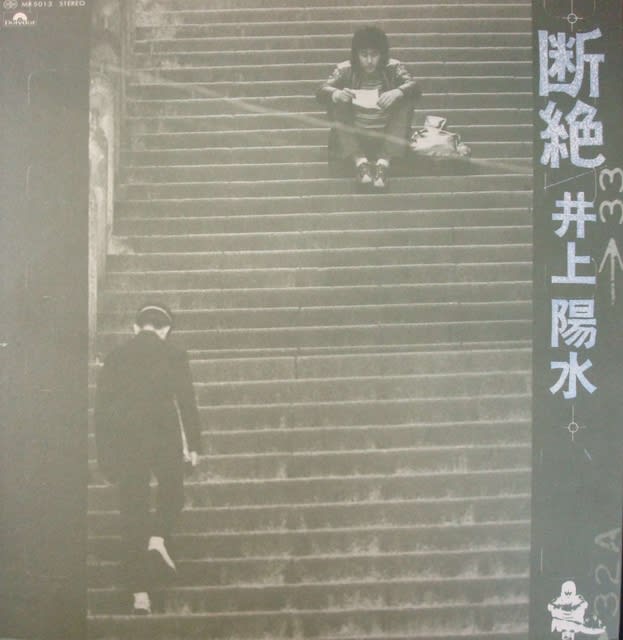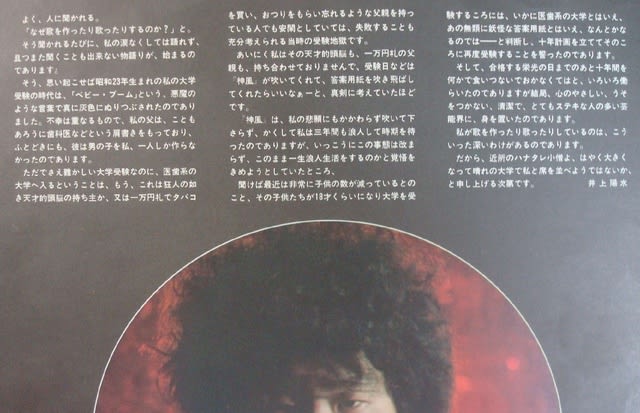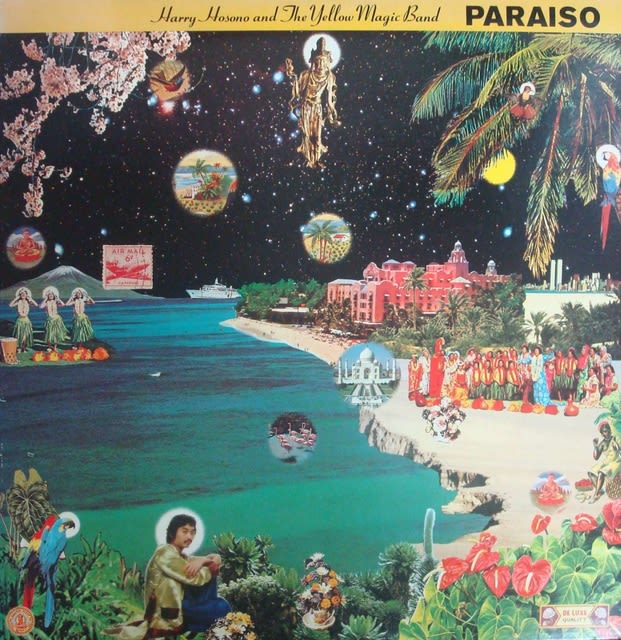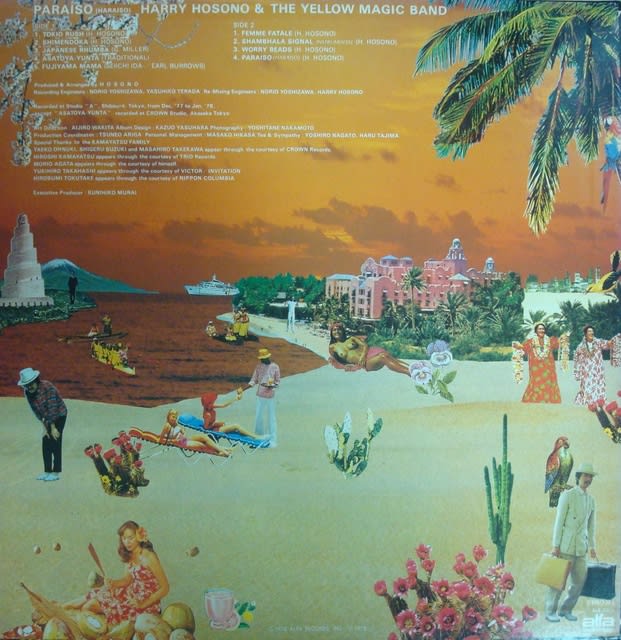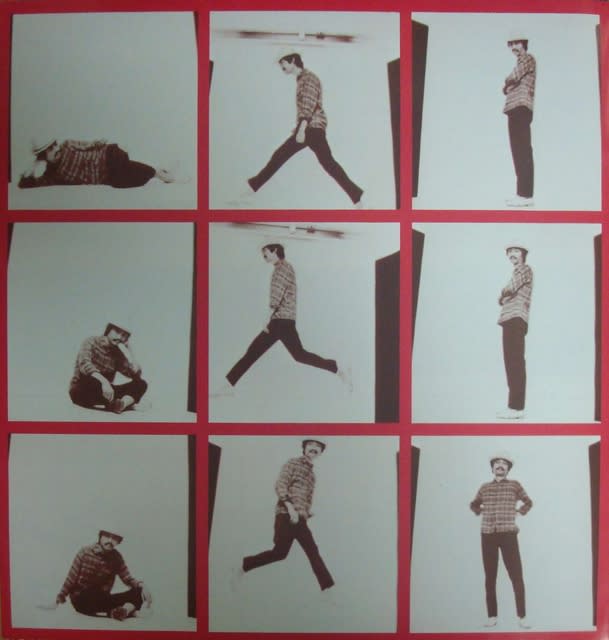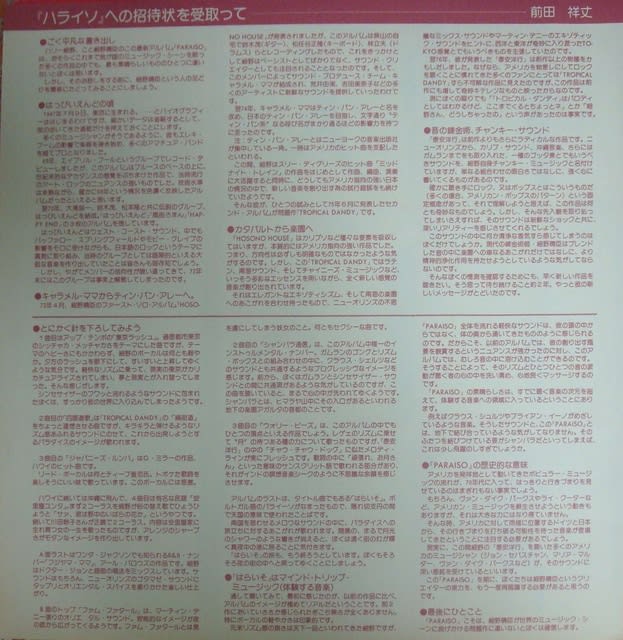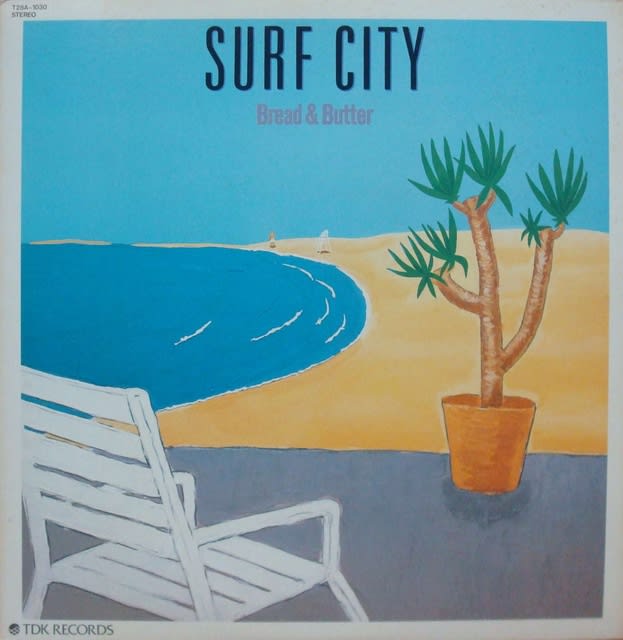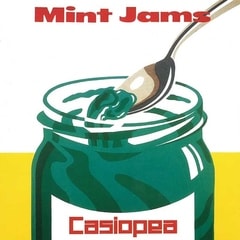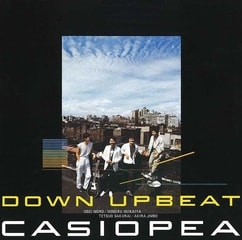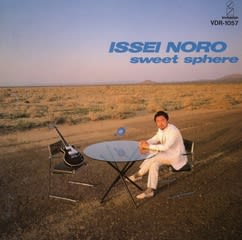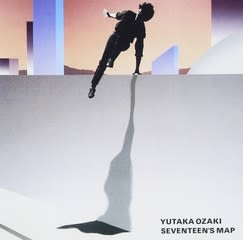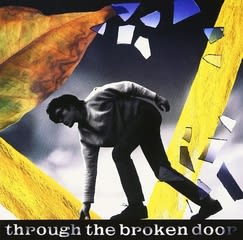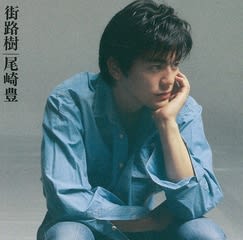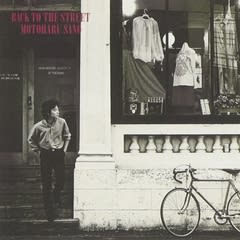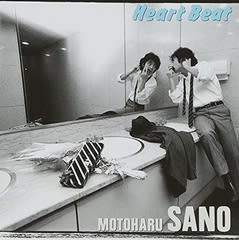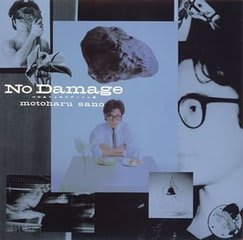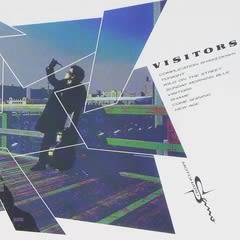助手:博士〜、たっ たっ たっ たっ 大変です!
博士:一体どうしたと言うのじゃ? 久々の登場に、かなり気合が入っているじゃないか。
助手:それがですね、今日古〜いシングル盤の収納ボックス整理していたら、こんなの見つけました。
博士:オォ〜、これは中村晃子が年に出したシングル盤、“なげきの真珠”ではないか! 少し前にオークションで買った洋楽シングル盤セットに間違って紛れ込んでいたのかのう〜

オォ〜、キレイなお方じゃ。
助手:レコードなしのEPのペラ・ジャケで、しかも当時これ買った人は多分彼女の大ファンでピンナップとして壁にでも張っていたと思われる画鋲の突き刺した跡がジャケの四隅に見受けられる中々気合いの入ったものですね〜。
でっ、これどうします?
歌謡曲なので、当研究所にはちょっと場違いな気がしないでもないので、廃棄処分にしましょうか?
博士:バッカモーン! 中村晃子といえば1967年に“虹色の湖”を大ヒットさせ、翌年1978年に出たシングル、“砂の十字架”も連続ヒットさせたのじゃ!
この“なげきの真珠”は同じ作詞作曲家のチームによる第3シングルにあたる。
助手:なるほど。単なる歌謡曲じゃなく、バックの演奏にエレキのビート・バンドを従えた、女性版一人GSってやつですね。
博士:GS(グループ・サウンズもしくはグループ・サウンド)って言葉は、ロックンロールに変わる新しい名称として、60年代の中頃登場した和製エレキ・ビート・バンドに対する総称じゃよ。
だから、彼女は女性版一人GSのパイオニアの一人と言ってもいい存在じゃよ。
助手:わかりました。取り敢えずこのペラ・ジャケは保管しておきましょう。
ところで、博士はこの歌聴いたことあるのですか?
博士:不覚にも聴いたことはない。メロディーを覚えているのは“虹色の湖”と “砂の十字架”だけじゃのう〜
Wikiによると1971年にボーリングのスポ根連続ドラマ、美しきチャレンジャーの主題歌も歌っていたとなっておるが、ドラマの主人公の新藤恵美に心が奪われてしまったのでこれまた全く覚えておらん。
ちなみに嘆きといえば、月亭可朝の“嘆きのボイン”はよく覚えておるのじゃが….
助手:それじゃ“なげきの真珠”じゃなくて全く覚えのなかった “なげきのシングル”ってことですかね?

恋に死んでしまった 真珠は、そっとひとりだけ(シングル)に なりたい〜♪
博士:一体どうしたと言うのじゃ? 久々の登場に、かなり気合が入っているじゃないか。
助手:それがですね、今日古〜いシングル盤の収納ボックス整理していたら、こんなの見つけました。
博士:オォ〜、これは中村晃子が年に出したシングル盤、“なげきの真珠”ではないか! 少し前にオークションで買った洋楽シングル盤セットに間違って紛れ込んでいたのかのう〜

オォ〜、キレイなお方じゃ。
助手:レコードなしのEPのペラ・ジャケで、しかも当時これ買った人は多分彼女の大ファンでピンナップとして壁にでも張っていたと思われる画鋲の突き刺した跡がジャケの四隅に見受けられる中々気合いの入ったものですね〜。
でっ、これどうします?
歌謡曲なので、当研究所にはちょっと場違いな気がしないでもないので、廃棄処分にしましょうか?
博士:バッカモーン! 中村晃子といえば1967年に“虹色の湖”を大ヒットさせ、翌年1978年に出たシングル、“砂の十字架”も連続ヒットさせたのじゃ!
この“なげきの真珠”は同じ作詞作曲家のチームによる第3シングルにあたる。
助手:なるほど。単なる歌謡曲じゃなく、バックの演奏にエレキのビート・バンドを従えた、女性版一人GSってやつですね。
博士:GS(グループ・サウンズもしくはグループ・サウンド)って言葉は、ロックンロールに変わる新しい名称として、60年代の中頃登場した和製エレキ・ビート・バンドに対する総称じゃよ。
だから、彼女は女性版一人GSのパイオニアの一人と言ってもいい存在じゃよ。
助手:わかりました。取り敢えずこのペラ・ジャケは保管しておきましょう。
ところで、博士はこの歌聴いたことあるのですか?
博士:不覚にも聴いたことはない。メロディーを覚えているのは“虹色の湖”と “砂の十字架”だけじゃのう〜
Wikiによると1971年にボーリングのスポ根連続ドラマ、美しきチャレンジャーの主題歌も歌っていたとなっておるが、ドラマの主人公の新藤恵美に心が奪われてしまったのでこれまた全く覚えておらん。
ちなみに嘆きといえば、月亭可朝の“嘆きのボイン”はよく覚えておるのじゃが….
助手:それじゃ“なげきの真珠”じゃなくて全く覚えのなかった “なげきのシングル”ってことですかね?

恋に死んでしまった 真珠は、そっとひとりだけ(シングル)に なりたい〜♪