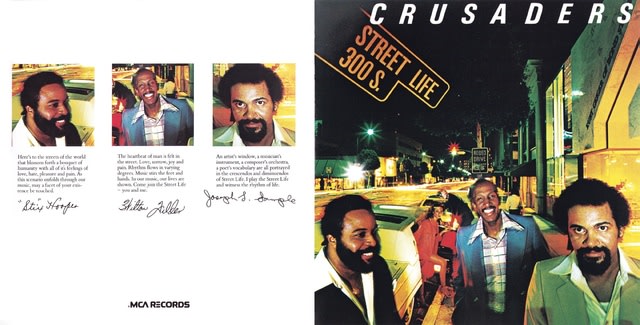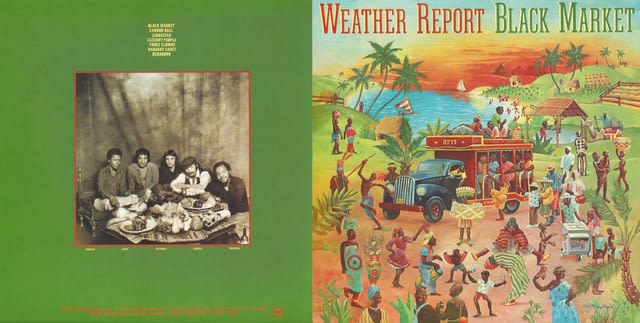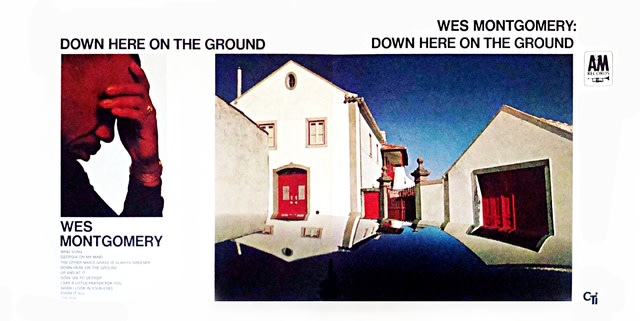最近は数多くの日本のバンドが海外進出し、必ずしも流暢な英語で歌われなくともインパクト1発でそこそこ受けている。
いや~、時代は変わったと感慨深い。
その昔、数多くのミュージシャンが海外に挑戦したが、局地的にインパクトを残したのはインスト系。ただアメリカではやっぱりラジオ・フレンドリーな歌物が強い。
ジャズやフュージョン系ではどうしてもマーケットが小さくて大成功を収めるには苦労する。ジャズ・ギタリストのジョージ・ベンソンが大成功を収めたのは、歌も上手く歌えたからだと思う。
日本を代表するインスト・バンド、カシオペアも80年代なんとかアメリカのマーケットで成功しようとプロデューサーにデヴィッド・ボウイーのバンドのギタリストだったカルロス・アロマーをプロデューサーに起用し、インスト系ポップ路線プラス歌物数曲を加えアメリカ仕様で挑んだのだがその壁は厚かったみたい。
そんなカシオペアも1987年、それまでのアルファ・レーベルから海外進出をより効率的に目指すためだったのか、メジャーのポリドール系の新しく設立したオーラ・レーベルに移籍。
スタジオ・アルバムを2枚出した後、原点に戻ったインスト・サウンドで海外ツアーに出る。
その音源が1988年に出たWorld Live ‘88だ。日本、オーストラリア、メキシコ、ブラジルそしてアメリカでの公演からオーラ・レーベル時代の曲を中心に選曲されている。


(EU盤の初回CD)
やっぱりコレだね、カシオペアは。ちなみに再発盤には東京でのライブ音源が2曲がボートラと追加され、それらにはホーン・セクションが導入され更にパワー・アップ。
ただ残念な事に70年代末頃から10年ほど活動してきたものの、それぞれの思い描くバンド活動に関してのギャップが広がってきたのか、ベースの桜井哲夫とドラムスの神保彰がバンドから脱退。その後カシオペアはメンバーを入れ替えて活動を継続する。
やっぱりこの4人がベストでしたかね。