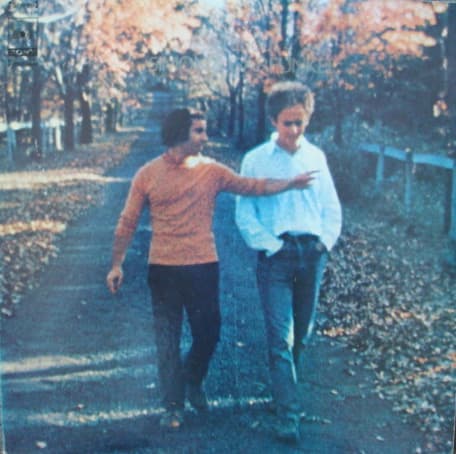海外で働いていると“日本人はいつも日本の方を向いている”なんて良く言われます。
お客さんを訪問した際、急いでいるのですぐに注文を出したいのだが、価格をこの額にあわせてくれって言われたとき悩みます。
その商品の仕入れ価格がインプットされているので、ある程度の値引であれば仕入れ価格から逆算して利益が出るのであれば、その場でオーケーって言えるのですが…
そう言った場合、大概提示される先方の価格が、利益が出るか出ないかの微妙~なレベルなんですね。そうなると、出先の人間の一存では判断できないのです。
となると、決まり文句は、“日本サイドに確認を取ってから、返事をします。”
これが週の初めならば、翌日に日本から確認を取った上で返事が出来るのですが、金曜日の午後にそのような事態になると、返事は次の週ってことになり、お客さんから上述のように皮肉られるわけです。
私も苦い経験があり、すぐに決断してくれって言われたので、過去の販売実績の価格を照らし合わせて、受注すれば何とかギリギリで利益が出ると言う判断で、注文を飲み込んでしまいました。
すぐに結論を出さねば、他社に注文を持っていかれると言う状況を説明し、受注した旨日本に連絡すると、価格が改定されその価格では安すぎて受け入れられないと返事が来て大変な事となりました。
その後、お客さんに状況を説明し、受注価格を少し上げてもらったのと同時に日本サイドもメーカー側から何とか特別に値引きする事が出来、事なきを得ました
もちろん、後日社長さんにはこっぴどくしかられた記憶があります。
今のように、携帯端末やインターネットが使えればその場で日本と連絡がとれるのですが、何しろ二昔以上前の頃の話なので、当時の通信手段は、事務所まで戻ってテレックスか固定電話を使用する以外ありませんでした。
だから、重要なお客さんから、今すぐ結論を出せと言われれば、腹をくくってエイ、ヤーの気合と共に返事するしかなかったのです。
そして今でも、“あんたはいつも日本の方を向いている”なんて言われそうです。
何故なら当ブログの記事は日本に向けて発信されているからです。
日本にいた時はそうでもなかったのに、いざ外に出ると、毎朝インターネットで他愛のない日本のニュースを拾い読みしたり、プロ野球の結果を見て”また負けてる“なんて、東京都民でもないのに都知事選に妙に関心を持ったり、ホント!結構気になりますね。
若かった頃は、海外に出れば何でも見てやろうとか体験してやろうって、日本のことは忘れて結構前向きだったのに、歳をとるとそうでも無くなるって言うか…
やっぱり生まれ育ったところ一番なのかも。
生まれた街で
荒井由実
いつものあいさつなら どうぞしないで
言葉にしたくないよ 今朝の天気は
街角に立ち止まり
風を見送ったとき
季節が わかったよ
生まれた街の匂いやっと気づいた
もう遠いところへと ひかれはしない
小さなバイクを止め
風を見送ったとき
季節が わかったよ
街角に立ち止まり
風を見送ったとき
季節が わかったよ
お客さんを訪問した際、急いでいるのですぐに注文を出したいのだが、価格をこの額にあわせてくれって言われたとき悩みます。
その商品の仕入れ価格がインプットされているので、ある程度の値引であれば仕入れ価格から逆算して利益が出るのであれば、その場でオーケーって言えるのですが…
そう言った場合、大概提示される先方の価格が、利益が出るか出ないかの微妙~なレベルなんですね。そうなると、出先の人間の一存では判断できないのです。
となると、決まり文句は、“日本サイドに確認を取ってから、返事をします。”
これが週の初めならば、翌日に日本から確認を取った上で返事が出来るのですが、金曜日の午後にそのような事態になると、返事は次の週ってことになり、お客さんから上述のように皮肉られるわけです。
私も苦い経験があり、すぐに決断してくれって言われたので、過去の販売実績の価格を照らし合わせて、受注すれば何とかギリギリで利益が出ると言う判断で、注文を飲み込んでしまいました。
すぐに結論を出さねば、他社に注文を持っていかれると言う状況を説明し、受注した旨日本に連絡すると、価格が改定されその価格では安すぎて受け入れられないと返事が来て大変な事となりました。
その後、お客さんに状況を説明し、受注価格を少し上げてもらったのと同時に日本サイドもメーカー側から何とか特別に値引きする事が出来、事なきを得ました
もちろん、後日社長さんにはこっぴどくしかられた記憶があります。
今のように、携帯端末やインターネットが使えればその場で日本と連絡がとれるのですが、何しろ二昔以上前の頃の話なので、当時の通信手段は、事務所まで戻ってテレックスか固定電話を使用する以外ありませんでした。
だから、重要なお客さんから、今すぐ結論を出せと言われれば、腹をくくってエイ、ヤーの気合と共に返事するしかなかったのです。
そして今でも、“あんたはいつも日本の方を向いている”なんて言われそうです。
何故なら当ブログの記事は日本に向けて発信されているからです。
日本にいた時はそうでもなかったのに、いざ外に出ると、毎朝インターネットで他愛のない日本のニュースを拾い読みしたり、プロ野球の結果を見て”また負けてる“なんて、東京都民でもないのに都知事選に妙に関心を持ったり、ホント!結構気になりますね。
若かった頃は、海外に出れば何でも見てやろうとか体験してやろうって、日本のことは忘れて結構前向きだったのに、歳をとるとそうでも無くなるって言うか…
やっぱり生まれ育ったところ一番なのかも。
生まれた街で
荒井由実
いつものあいさつなら どうぞしないで
言葉にしたくないよ 今朝の天気は
街角に立ち止まり
風を見送ったとき
季節が わかったよ
生まれた街の匂いやっと気づいた
もう遠いところへと ひかれはしない
小さなバイクを止め
風を見送ったとき
季節が わかったよ
街角に立ち止まり
風を見送ったとき
季節が わかったよ