人は、己れをつづまやかにし、奢りを退けて、財を持たず、世を貪らざらんぞ、いみじかるべき。昔より、賢き人の富めるは稀なり。
唐土に許由といひける人は、さらに、身にしたがへる貯へもなくて、水をも手して捧げて飲みけるを見て、なりひさこといふ物を人の得させたりければ、ある時、木の枝に懸けたりけるが、風に吹かれて鳴りけるを、かしかましとて捨てつ。また、手に掬びてぞ水も飲みける。いかばかり、心のうち涼しかりけん。孫晨は、冬の月に衾なくて、藁一束ありけるを、夕べにはこれに臥し、朝には収めけり。
唐土の人は、これをいみじと思へばこそ、記し止めて世にも伝へけめ、これらの人は、語りも伝ふべからず。
<口語訳>
人は、己れを約やかにし、奢りを退けて、財を持たず、世を貪らないのが、すごいはず。昔より、賢き人の富むは稀である。
唐土に許由といった人は、さらに、身にしたがえる貯えもなくて、水をも手して捧げて飲んだのを見て、なりひさこという物を人が得させたりしたらば、ある時、木の枝に懸けたりしたが、風に吹かれて鳴ったのを、やかましいと言って捨てた。また、手にむすんでだ 水も飲んだ。いかばかり、心のうち涼しかったろう。孫晨は、冬の月に衾なくて、藁一束あったを、夕べはこれに臥し、朝には収めた。
唐土の人は、これをすごいと思えばこそ、記し止めて世にも伝えたろう、こちらの人は、語りも伝えるはずもない。
<意訳>
人は、我が身を慎み、贅沢を避け、財産を持たない。
世を貪らずに生きるのがすごいはずだ。昔より、賢者が金持ちな事は稀である。
唐の許由って人は、さらにその上を行く。
許由は、身ひとつでなにも持っていない。
水すら手ですくって飲んでいるのを見た人が、ひょうたんで作ったヒシャクをくれたのだが、ある時、ひょうたんを木の枝にかけておいたら風に吹かれて鳴るので、やかましいと捨ててしまい、また手で水をすくって飲みはじめた。
やかましいひょうたんを捨て、手ですくって飲む水はいかに爽快だったろうか。
また、唐の孫晨は、寒い冬の時期に布団もなくワラが一束だけあったので、夜はワラにくるまり、朝にそれを片付けた。
唐の人は、こういうことをすごいと思ったから、書きとめて世に伝える。
大和の人は、語りも伝えもしない。
<感想>
旅に行きたい。山寺にこもりたい。
などという願望と同じく、これも出家する前の兼好が抱いた願望のひとつだろうと思う。兼好は、清貧に憧れていたんだろう、清く正しく美しい貧乏に。
もちろん、この段を書いたのが、出家する前の兼好であるという断定はまったくできないし、何の根拠もない。
だが、『徒然草』の読み方のひとつとして理解していただくなら、初期の数十段は「兼好が出家する前の気持ち」を書いているのではないかと俺は読む。
出家以前、あるいは出家後、兼好が実際にいつ書いたのかなんてのは問題ではない。それに、執筆時期を特定できる材料を俺はもたない。
いつ書いたにしろ、兼好は『徒然草」の初期の段で、出家する前の気持ちを書いた。俺はそう読んだよという話だ。
初期の『徒然草』の文章が、出家する前の兼好の気持ちを書いた文章だとして、その後の出家した兼好法師は、ちゃんと旅もしたし山寺にもこもった。
兼好は、憧れをちゃんと実践した。
でも、清貧はどこまで実践できたかわからない。手で水をすくって飲んだり、布団もないほどの清貧生活なんて実行できたかのだろうか。
もしかしたら、死ぬ直前にできたかもしれない。
実は、兼好法師はいつ死んだのか現代では不明になっている。
いつどのように死んだのかが現代に全く伝わっていない。
兼好の最晩年は、室町幕府の武士達とのコネを生活の糧としていたそうだ。
だが、時代は乱世である。そんなコネなんていつどうなるか分からない。コネもなくなり、とくに収入もない兼好は、なに一つなくのたれ死んでしまったかもしれない。
まぁ、なんにしろ、なんにも物がない生活ってのには少しあこがれる。
<ところで>
この段で、『徒然草』は一段落する。
序段から続いた文章の、とりあえずのまとめが、この第18段であろう。
序段で兼好は、自分が「つれづれ」な日常の日々を送っていると告白した。
次に、第1段冒頭で、「いでや、この世に生れては、願はしかるべき事こそ多かめれ」と書き出し、望みの数々を書き連ねたうえに、そんな欲望は全て打破すべきかもと語る。
何故だろう、世間にしがみつき出世しても、兼好の身分じゃたいしたことがないのが分かっちゃったからだ。兼好には自分の人生の先が見えちゃったのだろう。そんな先の見える人生なんかとは違う生き方を兼好は望んだ。
その答えが出家なのだが、出家する事に対して怖れもある。世間との関係を断ち切り、酒も女も諦めねばならない。(酒は飲んでいたようだが)
貴族社会での出世を諦めて、世間との関係を断ち切り出家する前に、兼好は改めて自分の欲望を再検討してみることにした。
そして、自分が何を望んでいるのかを書き続ける。書いているうちに、このくらいの欲望なら、性欲以外はなんとかなるかもという状態に達した。
すると、今度は新たな欲望がすでに兼好の心には浮かんでいる事に気がついた。「出家への憧れ」である。
兼好の心は、すでに世俗を捨てて出家する事にとりあえず納得した。
兼好はこの段で、余計な財産も、ガツガツした生き方もいらないと中国の賢人を例にあげて語る。
余計な人間関係や、余計な持ち物もいらない。
清く正しく美しい清貧シンプル・ライフこそが、自分の望みである。
そう宣言したので、序段からの区切りがついた。
『徒然草』は、次段からやや趣きが変わる。
<いらぬ解説>
『つづまやか』
「約まやか」と書く。倹約するさま。
『いみじ』
形容詞。忌み避けねばならぬほどに程度や様子がはなはだしいという意味で用いられる。望ましい事にも、望ましくない事にも使用される。兼好法師が使うときは、望ましい事として使用する事が多い。「とてもすぐれている」「とても立派だ」などの意味で使う事が多い。
『世を貪らざらんぞ』
「世をむさぼる」は、欲ぶかく立身出世や金を求めて生きる様子。現代人はあまり使わないが、感じがよく出てる。
『唐土』
唐の地、昔の中国のこと。
『なりひさこ』
「ひさこ」はひょうたんの事。あるいは水などをすくう「ひしゃく」を指す言葉。
この場合、「ひょうたん」に間違いないのだろうが、「なりひさこといふ物」なんて自信なさげな書き方をされるとなんだか俺まで自信がなくなる。
当時は、ひょうたんを縦に二つに割ってヒシャクとして使っていたらしい。たぶん、そうしたものをこの段では言っているのだろう。
兼好は、この段の故事を中国の本を参考にして書いたらしく、『徒然草』のテキストには参考にしたと思われる部分の書き抜きもある。それによると、「なりひさこ」は「一瓢(いっぺい)」とあるが、一瓢となりひさこが同じものであるかどうかは良く分からない。
『手に掬びてぞ水も飲みける』
「掬ぶ」は「むすぶ」。「両手をあわせて水をすくって飲んだ」という意味。
『衾(ふすま)』
かけぶとんのこと。
『これらの人』
唐土(中国)のひとに対して、こちら(我が国)の人はという意味。










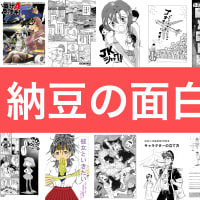

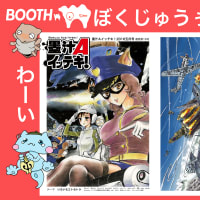
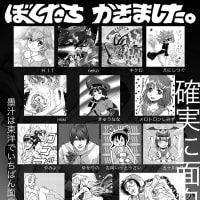


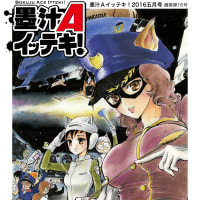



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます