『徒然草』を書いた兼好には、吉田兼好(よしだ けんこう)の他に、兼好法師(けんこう ほうし)という呼び方もある。
さて、この二つの呼び方は、どちらがより正しい呼び方なのか?
だいたい同一人物になんでいくつも名前があるのだろう?
「吉田兼好」という呼び方は、兼好が吉田神社の社務職を代々つとめた一族の出身であることから後の時代の人が勝手につけた「呼び名」であるという事は、前に説明した。
それでは、「兼好法師」とはなんなのだろう?
どうして、「兼好法師」なんだ?
だいたい、「法師」ってなんなのだ?
法師は、『西遊記』の「三蔵法師」が有名。
他には『耳なし芳一』の「琵琶法師」なんかも有名。
ようするにお坊さんに対する「尊称」が「法師」だ。
兼好は、お坊さんだったから「兼好法師」と呼ばれた。
「法師」は、仏教のお坊さんに対する尊称である。
だが、お坊さんそのものを指し示す場合にも使われた。
現代で言うなら、「なんとか法師」は、「なんとか先生」という呼び方に似ている。
学校の先生の正式な職業名は「教員」である。「先生」は職業名ではない。
例えば、あなたの担任の先生がレンタルビデオ屋の会員になる時に、職業欄へ自分の職業を記入しなきゃならない場合、「学校の先生」なんてふつうなら書かないだろう。「教員」とか記入するはず。
「先生」はあくまで「尊称」だ。
「尊称」は、自分でない他人が、誰かを尊敬する時に用いる言葉だ。
木村って教師がいたら、生徒であるあなたは、その人を全く尊敬していなくても、とりあえず「木村先生」と呼んでおく。
尊敬しているフリぐらいはしとかないといけない、内申書もこわいしね。
だけど、「教員共」をカンタンに指し示す場合にも「先生」は使われる。
だから、期末試験終了後の昼休みに、職員室でストーブにあたりながらボンヤリ弁当を食っている「教員共」は、まとめて「先生たち」と呼ばれる。
そんなで「法師」と「先生」の使われ方は良く似ている。
どちらもそもそも「尊称」である。
だが、その職業につく人達をカンタンに指し示す言葉として使われる場合もある。
学校の「先生」と違って、「法師」の正式な職業名は特定できない。
法師は、坊主の尊称であるが、だいたい、坊主って職業なのかと聞かれたら、う~んどうなんだろう? となる。
ただ、坊主の正式な呼び方と言うのなら、「僧」か「仏僧」あたりが適当ではないだろうか。
昔の僧には、座りが悪いけど正式な個人名なんかなかった。
僧なんて、かって生きてた仏教の教祖である「釈迦」の弟子の誰それとしか言えない連中なのである。
僧は、釈迦の弟子になる時に俗社会を捨てる。
その時に、俗社会と一緒に名前も捨てる。
そんな連中の本名なんて、問題にするも馬鹿らしい。
だから、『徒然草』の作者でありつつ、僧であった兼好に、本当の本名なんか本来ない。
「兼好法師」という呼び方も、あくまで尊称にすぎない。
後の時代の人が勝手につけた通称の「吉田兼好」と同じで、他人からの「呼び名」でしかないのだ。
戸籍が存在する現代と違い、自称と呼び名しかない。
それが昔の僧だった。
そうだったのだ!
例えばだ。
『西遊記』の三蔵法師が、シルクロードを通って天竺を目指す途中に道に迷って、現代の東京都の立川市に迷い込んじゃったとする。
その三蔵が、立川駅前の南口「アレアレア」にある『TSUTAYA』で、レンタルビデオを借りようと思うなら、僧名である「玄奘三蔵」を名のるべきで、尊称の「三蔵法師」を名のるなら、自分で自分は「俺は三蔵先生だ!」と言っているのに等しい。
マトモな僧なら自分で自分を「法師」とは言わないはずだが、調査不足で確証はない。
じゃあ、『徒然草』の著者を現代の我々はなんと呼べば良いのか?
好きに呼べばいい。「吉田兼好」でも「兼好法師」でもマルだ。
ただ、それじゃあまりに乱暴なので、正解らしい事を言うなら、鎌倉時代末期の京都で「兼好(けんこう)」と名のっていた僧が、『徒然草』を書いた人だ。
じゃあ、『徒然草』の作者を、現代の俺たちは「兼好」と呼べば良いのか?
そうだとも言い切れない。
何故なら、書いた本人が自分をなんて呼んでもらいたかったのかが、現代ではすっかり抜け落ちているからだ。
もはや、この世には『徒然草』の原本(オリジナル)はない。あるのは写し(コピー)ばかりだ。
現代には、なぜか兼好直筆の『徒然草』は伝わっていない。
後の世の人による「写本」しか、『徒然草』は現代に残されていない。
本人の署名のない著作物の写しでは、書いた本人をなんて呼べば良いのか分からない。
もはや、好きに呼ぶしかない。
それが正解だ。










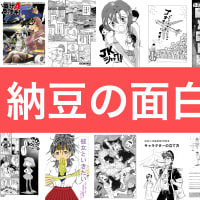

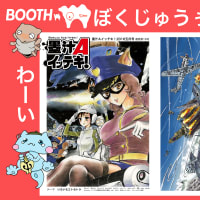
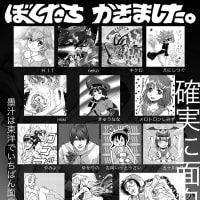


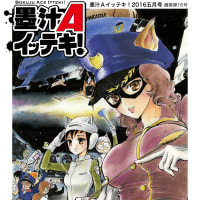



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます