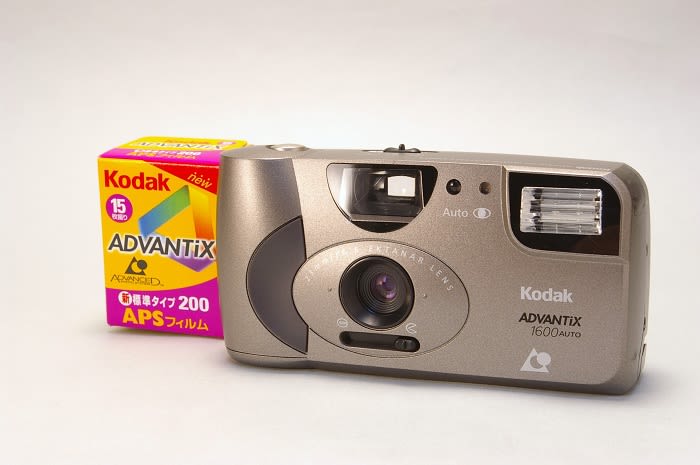[印刷]の今とこれからを考える
「印刷図書館クラブ」月例会報告(平成28年1月度会合より)
●文化財の保護はデジタル印刷システムで
デジタル写真技術とデジタル印刷システムを活用した文化財保護活動が盛んになり、幾つかのプロジェクトが全国各地で展開されている。デジタルカメラで絵柄を忠実に撮影し、デジタル印刷で微妙な色彩を表現する――そうした技術的な強みを駆使することで、古い文化財を現代に甦らせようというのだ。デジタル印刷の多くはインクジェット方式を用いるが、そうしたなかでトナー方式によって伝統的な文書を複製・復元する試みが、システム機器を開発・販売する専門メーカーの手でおこなわれている。文字を中心とする古文書の場合、トナーの方がシャープに再現できるという利点があるという。そのプロジェクトの目的は、古い文献を誰もが簡単に手にとって見られるようにすることにある。文化の伝承に貢献するのはもちろん、開示されていない貴重な古文書を公開可能にする社会的な意義もある。専門メーカーが一定の予算を確保して無料で実施することは、企業による文化保護活動の一つのあり方として注目されている。
●作成当時の状況や時代背景を考慮しながら
このメーカーによると、①現在の姿をそのまま忠実に再現する現状再製、②作品がつくられた当時の状態を推測しながら再現する復元再製――の二通りがある。とくに後者の場合、歴史的背景や関連書物から得られる情報などを根拠に、依頼者(所有者)との協働で画法、顔料、素材、装丁方法などを選んでいくところに特徴がある。長い歴史のなかで失ってしまった文字、図柄、製本などを納得いくかたちで復元しよういうのである。原本を傷めることなく電子化するためにデジタルカメラを使用するが、雲母(きらら)刷りや金箔、金絵具による描画など、鮮やかな光沢感、繊細で優美な質感を忠実に表現すべく、ライティングには細心の注意を払う。また、素材である和紙の最適な選択にも気を遣い、巻物の巻き皺まで忠実に復元するそうだ。撮影して得られた電子データは、できるだけ原本に近づけるよう画像処理し、カラーマッチング技術、多彩なトナーの使用で忠実な色再現を期しているのはいうまでもない。
●学術研究、教育、産業育成にも効果あり……
博物館や資料館、図書館などに所蔵されている古文書を、実際に手に取ることはなかなかできない。電子化による複製は、そうした貴重な本を身近に目にすることのできる機会を与えてくれる。伝統文化に対する人びとの関心を高めるだけでなく、所有者からの積極的な情報発信、有識者への研究資料の提供、若い世代向けの教育効果といったさまざまなメリットがある。文化伝承の“バリアフリー化”ともいえる優れた保護活動となっている。電子化できない部分は手描きによる表現でカバーするようにすれば、自然に伝統技術の継承にもつながる。逆にデジタル機能を高めて古い文書の現代文化、多言語化をはかれば、時代を超え国境を越えて一気に広がる。和紙や絹織物を使った巻物類をつくれば、抄紙産業、織物産業の発展にも寄与することができる。地震、火山噴火、大火といった災害の研究に際しても、古文書の有効利用で過去の情報がより簡単に得られることだろう。文化を継承、伝承していくことで、新しいビジネスチャンスが生まれてくるに違いない。
●印刷産業の業態変革は理解されているか?
大手印刷会社が事業構造の転換を急いでいると、産業分野の専門紙に報じられた。転換先とされたのは、デジタルメディアへの展開や事務処理業務の受託などだが、よく考えてみれば、大手に限らず印刷会社が業態変革、事業領域の変更を模索しているのは今に始まったことではない。大手印刷会社がどう生きていこうとしているのか興味をもたれ、それを産業界に伝えようとしたのだろうが、情報としては決して目新しいものとはいえない。それより気になったのは、印刷産業のビジネス基盤はこうだという固定観念(先入観) ?をもって記事が書かれたことではないだろうか。印刷産業からのPRが足りない部分も確かにあるが、新聞記者の“勉強不足”もあるのでは? 事務処理業務の受託はすでに当たり前の話になっている。「処理」に力点を置いていくと、印刷産業が課題としている受注産業からの脱却は叶わない。ここはやはり「プロセス」を提供するなかで、付加価値を取得する方向をめざす必要がある。企業の中核事業となるコアコンピタンスに集中して、それ以外はアウトソーシングしていくという考え方は、どの産業においても共通している。だが、そうすることによって新しいビジネス価値を創出できなくては意味がない。付加価値獲得競争が激しくなるなかで、印刷産業としても、印刷出力を“代行”するだけは通用しない。顧客のビジネスを支援できるコミュニケーションメディアを提供しなければならない。そんなことを感じた新聞記事だった。
●印刷会社は「コミュニケーション」に強くなろう
このところ急速に発展しているIT産業は、どのような事業ビジョンと経営方針をもってビジネスをおこなっているのか――印刷会社はもっともっと関心を寄せなければいけない。そういう印刷会社自身が独自の特長とは何かを強く意識して、事業に取り組む必要がある。本来の強み=文字に関する強みを活かして、ICT(情報コミュニケーション技術)企業をめざすべきだろう。印刷会社はITを外側から遠目で語る前に、中に飛び込んで強みを発揮できる分野を模索し、そこで新たな業態を構築しなければならない。ごく身近な例として、出版社から依頼されて書物の製作を引き受けるという関係から脱して、自ら出版企画を立て逆に出版業界に売るようにしたい。大地に足を着けて長年実績を重ねきた「出版印刷」というビジネス基盤があるはず。情報を扱える(処理/加工できる)という強みをもっているはず。それを武器に、出版社がやっている仕事を印刷会社が率先して手掛けるべきなのである。「コミュニケーション」をかたちにできる余地は、この出版印刷の例に限らずたくさんあるに違いない。
●文化性、人間性の観点を組み込んだ技術発展を
デジタル化が進展するなかで、そこには、ITの実情をみるまでもなく「文化性」が見受けられない。抜け落ちているような気がする。クラウドコンピューティングやビッグデータ分析の効用を否定するわけではないが、ハードの進歩に私たちは引きずられ過ぎているのではないか。ビジネスや生活の向上に役立つさまざまなソフトが開発されてはいるが、それでも個々の人間サイドからの視点が欠けている。コミュニケーション分析との付き合わせもみられない。科学技術と感性とは、相互に行き来しながら進歩していくものだと思いたい。データの変更を求められる一品生産型のプリメディア/プリプレス工程と、その後の複製生産型の印刷工程の関係を考えると、印刷メディアの製作には「設計」が重要であることがわかる。データの意味解釈、適切な処理と選択を可能にしてくれる人工頭脳(AI)を使って、両者をどう一貫化するのかという問題がいずれ出てくるだろう。そのとき、人間のもつ技能と感性をいかに組み込んでいくのかも課題となるだろう。文化性、人間性の観点はどうしても欠かせないのである。
●今まで縛られてきた“柵”から抜け出してほしい
《12月度記事参照》 今では、ITの活用で読者ニーズに即した情報を素早く提供できるビジネス環境が確立されているのに、出版社も印刷会社も、大量につくらないと儲からないという思いに未だ翻弄されている。読者が無意識に抱いている潜在ニーズをいかに顕在化するか――ニーズを気づかせる仕掛けによって購読を勝ち取るというマーケティング力に欠けている。読者に一番近い立場の書店もエリアマーケティング的な努力をしていない。そうした“柵”から抜け出し、じっくり考えることができるなら、新しい需要、新たな市場を見つけられるはずである。印刷メディアがもつ本来の利用価値を核とするマーケティングが可能になるだろう。
「印刷図書館クラブ」月例会報告(平成28年1月度会合より)
●文化財の保護はデジタル印刷システムで
デジタル写真技術とデジタル印刷システムを活用した文化財保護活動が盛んになり、幾つかのプロジェクトが全国各地で展開されている。デジタルカメラで絵柄を忠実に撮影し、デジタル印刷で微妙な色彩を表現する――そうした技術的な強みを駆使することで、古い文化財を現代に甦らせようというのだ。デジタル印刷の多くはインクジェット方式を用いるが、そうしたなかでトナー方式によって伝統的な文書を複製・復元する試みが、システム機器を開発・販売する専門メーカーの手でおこなわれている。文字を中心とする古文書の場合、トナーの方がシャープに再現できるという利点があるという。そのプロジェクトの目的は、古い文献を誰もが簡単に手にとって見られるようにすることにある。文化の伝承に貢献するのはもちろん、開示されていない貴重な古文書を公開可能にする社会的な意義もある。専門メーカーが一定の予算を確保して無料で実施することは、企業による文化保護活動の一つのあり方として注目されている。
●作成当時の状況や時代背景を考慮しながら
このメーカーによると、①現在の姿をそのまま忠実に再現する現状再製、②作品がつくられた当時の状態を推測しながら再現する復元再製――の二通りがある。とくに後者の場合、歴史的背景や関連書物から得られる情報などを根拠に、依頼者(所有者)との協働で画法、顔料、素材、装丁方法などを選んでいくところに特徴がある。長い歴史のなかで失ってしまった文字、図柄、製本などを納得いくかたちで復元しよういうのである。原本を傷めることなく電子化するためにデジタルカメラを使用するが、雲母(きらら)刷りや金箔、金絵具による描画など、鮮やかな光沢感、繊細で優美な質感を忠実に表現すべく、ライティングには細心の注意を払う。また、素材である和紙の最適な選択にも気を遣い、巻物の巻き皺まで忠実に復元するそうだ。撮影して得られた電子データは、できるだけ原本に近づけるよう画像処理し、カラーマッチング技術、多彩なトナーの使用で忠実な色再現を期しているのはいうまでもない。
●学術研究、教育、産業育成にも効果あり……
博物館や資料館、図書館などに所蔵されている古文書を、実際に手に取ることはなかなかできない。電子化による複製は、そうした貴重な本を身近に目にすることのできる機会を与えてくれる。伝統文化に対する人びとの関心を高めるだけでなく、所有者からの積極的な情報発信、有識者への研究資料の提供、若い世代向けの教育効果といったさまざまなメリットがある。文化伝承の“バリアフリー化”ともいえる優れた保護活動となっている。電子化できない部分は手描きによる表現でカバーするようにすれば、自然に伝統技術の継承にもつながる。逆にデジタル機能を高めて古い文書の現代文化、多言語化をはかれば、時代を超え国境を越えて一気に広がる。和紙や絹織物を使った巻物類をつくれば、抄紙産業、織物産業の発展にも寄与することができる。地震、火山噴火、大火といった災害の研究に際しても、古文書の有効利用で過去の情報がより簡単に得られることだろう。文化を継承、伝承していくことで、新しいビジネスチャンスが生まれてくるに違いない。
●印刷産業の業態変革は理解されているか?
大手印刷会社が事業構造の転換を急いでいると、産業分野の専門紙に報じられた。転換先とされたのは、デジタルメディアへの展開や事務処理業務の受託などだが、よく考えてみれば、大手に限らず印刷会社が業態変革、事業領域の変更を模索しているのは今に始まったことではない。大手印刷会社がどう生きていこうとしているのか興味をもたれ、それを産業界に伝えようとしたのだろうが、情報としては決して目新しいものとはいえない。それより気になったのは、印刷産業のビジネス基盤はこうだという固定観念(先入観) ?をもって記事が書かれたことではないだろうか。印刷産業からのPRが足りない部分も確かにあるが、新聞記者の“勉強不足”もあるのでは? 事務処理業務の受託はすでに当たり前の話になっている。「処理」に力点を置いていくと、印刷産業が課題としている受注産業からの脱却は叶わない。ここはやはり「プロセス」を提供するなかで、付加価値を取得する方向をめざす必要がある。企業の中核事業となるコアコンピタンスに集中して、それ以外はアウトソーシングしていくという考え方は、どの産業においても共通している。だが、そうすることによって新しいビジネス価値を創出できなくては意味がない。付加価値獲得競争が激しくなるなかで、印刷産業としても、印刷出力を“代行”するだけは通用しない。顧客のビジネスを支援できるコミュニケーションメディアを提供しなければならない。そんなことを感じた新聞記事だった。
●印刷会社は「コミュニケーション」に強くなろう
このところ急速に発展しているIT産業は、どのような事業ビジョンと経営方針をもってビジネスをおこなっているのか――印刷会社はもっともっと関心を寄せなければいけない。そういう印刷会社自身が独自の特長とは何かを強く意識して、事業に取り組む必要がある。本来の強み=文字に関する強みを活かして、ICT(情報コミュニケーション技術)企業をめざすべきだろう。印刷会社はITを外側から遠目で語る前に、中に飛び込んで強みを発揮できる分野を模索し、そこで新たな業態を構築しなければならない。ごく身近な例として、出版社から依頼されて書物の製作を引き受けるという関係から脱して、自ら出版企画を立て逆に出版業界に売るようにしたい。大地に足を着けて長年実績を重ねきた「出版印刷」というビジネス基盤があるはず。情報を扱える(処理/加工できる)という強みをもっているはず。それを武器に、出版社がやっている仕事を印刷会社が率先して手掛けるべきなのである。「コミュニケーション」をかたちにできる余地は、この出版印刷の例に限らずたくさんあるに違いない。
●文化性、人間性の観点を組み込んだ技術発展を
デジタル化が進展するなかで、そこには、ITの実情をみるまでもなく「文化性」が見受けられない。抜け落ちているような気がする。クラウドコンピューティングやビッグデータ分析の効用を否定するわけではないが、ハードの進歩に私たちは引きずられ過ぎているのではないか。ビジネスや生活の向上に役立つさまざまなソフトが開発されてはいるが、それでも個々の人間サイドからの視点が欠けている。コミュニケーション分析との付き合わせもみられない。科学技術と感性とは、相互に行き来しながら進歩していくものだと思いたい。データの変更を求められる一品生産型のプリメディア/プリプレス工程と、その後の複製生産型の印刷工程の関係を考えると、印刷メディアの製作には「設計」が重要であることがわかる。データの意味解釈、適切な処理と選択を可能にしてくれる人工頭脳(AI)を使って、両者をどう一貫化するのかという問題がいずれ出てくるだろう。そのとき、人間のもつ技能と感性をいかに組み込んでいくのかも課題となるだろう。文化性、人間性の観点はどうしても欠かせないのである。
●今まで縛られてきた“柵”から抜け出してほしい
《12月度記事参照》 今では、ITの活用で読者ニーズに即した情報を素早く提供できるビジネス環境が確立されているのに、出版社も印刷会社も、大量につくらないと儲からないという思いに未だ翻弄されている。読者が無意識に抱いている潜在ニーズをいかに顕在化するか――ニーズを気づかせる仕掛けによって購読を勝ち取るというマーケティング力に欠けている。読者に一番近い立場の書店もエリアマーケティング的な努力をしていない。そうした“柵”から抜け出し、じっくり考えることができるなら、新しい需要、新たな市場を見つけられるはずである。印刷メディアがもつ本来の利用価値を核とするマーケティングが可能になるだろう。