印刷図書館クラブ
印刷人のフィルム・フィルムカメラ史探訪 VOL-29
印刷コンサルタント 尾崎 章
1963年5月に東京光学機械㈱(現:㈱トプコン)が世界初のTTL測光方式の一眼レフ「トプコンREスーパー」を発売して世界の注目を集めた。
「トプコンREスーパー」は、装着レンズの開放絞りで測光出来る開放測光方式にも対応、1964年に発売されたTTL測光の二番手・旭光学「ペンタックスSP」が絞り込み測光にとどまり、更にキャノンのTTL開放測光対応が1971年であった事、等々より東京光学の先進技術が世界に実証された「歴史的名機」となっている。
東京光学 トプコンREスーパー

トプコンREスーパーのミラー測光技術
東京光学は、当時の親会社である㈱東芝の技術協力を得て世界初のミラーメーターを開発、「トプコンREスーパー」に搭載している。
ミラーメーターは、一眼レフのミラーをスリット状のハーフミラーとする高度の真空蒸着技術加工を施してファインダー視野を妨げずにミラーを透過した透過光を測光して適性露光を求める方式である。
トプコンREスーパーのミラーメーター

更に東京光学は、装着レンズの開放絞りでの測光及びフォーカシングを可能とする開放測光技術を世界に先駆けて開発、開放測光に不可欠な装着交換レンズの開放絞り情報を連動ピンでカメラボディに伝える連動ピン方式も同時に新開発している。
このレンズ情報をボディに伝える連動ピン方式は、業界標準として定着した事は周知の事項である。
東京光学は、当該TTL測光方式を1960年に「撮影レンズの透過光を測定する方式の露出計を組み込んだ自動プリセット式一眼レフ」として特許出願(1967年・特許公告)、キャノン、ニコン、ミノルタ等のカメラ各社がパテント料を支払ってTTL一眼レフの製品化を行っている。
東京光学は、ドイツ・ケルン市で開催される世界最大の写真機材展「フォトキナ1963展」
に「トプコンREスーパー」を出展、世界のフォトジャーナリストから「カメラ史の1ページを記す偉大な発明」として絶賛を博している。
トプコンREスーパーの開放測光・連動ピン

システムカメラとしても高い完成度を有したトプコンREスーパー
「トプコンREスーパー」が競合他社に与えたインパクトはTTL測光にとどまらず、システムカメラとしての充実度も挙げることが出来る。
当時は、日本光学「ニコンF」がシステムカメラとしての頂点にあったが、システムカメラとしての高い充実度を伴った「トプコンREスーパー」が一気に形勢逆転を図っている。
システムカメラとして注目された特長は次の通りである。
①調整無でカメラに装着できるモータードライブ機能(世界初、3コマ/秒)
②250枚撮り長尺フィルムマガジン
③ミラーアップ無で装着可能な25mmレトロフォーカス型広角レンズ(世界初)
④ペンタブリズム交換式、各種ファインダー対応
⑤眼底カメラ、手術用顕微鏡等のメディカル対応。
アメリカ海軍は、「トプコンREスーパー」の性能及び豊富な多用途対応性を評価して従前の「ニコンF」から「トプコンREスーパー」へ海軍正式規格カメラの変更を実施している。この海軍正式規格カメラの変更に伴い空母、空母艦載機、潜水艦、各種艦艇に「トプコンREスーパー」が搭載される展開に至っている。
TTL測光のコンセプト発表は、旭光学が先行
1960年開催の「フォトキナ」展で旭光学工業㈱(当時)は「ペンタックス・スポットマチック」の試作機を展示して注目を集めている。「ペンタックス・スポットマチック」は直径3mmのcds受光部を取り付けた腕木バーをフォーカシングスクリーンの中央部に繰り出して測光する方式で、標準レンズの約1/15の狭角度で受光することより「スポットマチック」のネーミングでスポット測光をアピールしている。
しかしながら、当該機能の実用化が難しく、ファインダー接眼窓の両側に小型cds受光部を配した平均測光の「ペッタックスSP」を「トプコンREスーパー」の一年遅れで発売する展開に至っている。
旭光学 ペンタックスSP

当該機は絞り込み測光等の仕様面で「トプコンREスーパー」よりも劣ったものの「ペンタックスSV」等で普及型一眼レフ市場をリードしていたことより「ペンタックスSP」も普及型TTL一眼レフとして11年のロングセラーを記録するヒット商品になっている。
TTLの語源論争
1963年に東京光学が「トプコンREスーパー」を発売して際には、「TTL測光」の用語は無く、東京光学では「ミラーメーター方式」という表現を行っていた。
東京光学の社史「東京光学50年史」には、海外向け説明書作成時に翻訳を担当した速川賢一氏が考案した造語で「Through The Lens」の頭文字を採った造語であることが記載されている。
この「Through The Lens」に対して国内外より異論が唱えられ「TTL論争」が生じた懐かしい経緯がある。
その論点は次の通りである。
①露出計の受光部には集光レンズが一般的に取付けられており、外付け露出計でも「Through The Lens」になる。
②撮影レンズの透過光を測定することより「Through the Taking Lens」の頭文字が正論である。
③撮影レンズの後面で測光する為に「Behind Taking Lens」、BTL測光の表記が正論である。
「Through the Taking Lens」論は、東京写真大学・加藤春男助教授(当時)等の学識経験者が正当性を主張、「BTL」は米国・ベルハウエル社等が主張したが、TTL測光のパイオニアである東京光学が「Through The Lens」説を採用したこともあり、略語論争は自然に消滅する展開に至っている。
1964年に旭光学が発売した「アサヒペンタックスSP」を「アサヒカメラ」(1964年10月号)がニューフェイス診断で取り上げた際には、「TTL・スルーザレンズ」の記述が各所に見られ、これ以降「TTL=スルーザレンズ」表現・記述が固定化することになった。
トプコンREスーパー発売当初のカメラ雑誌広告、TTL表記は無い

世界初のTTLレンズシャッター一眼レフ・トプコンユニを発売

印刷材料・CTPは
1993年9月に米国・シカゴで開催された印刷展示会・Graph Expo展でイーストマン・コダック社が「KODAK Direct Image Thermal Plate830」のプロトタイプを展示、注目を集めた。
続いてコダックは、1995年開催のDRUPA1995展で当該プレートのライブデモを実施、サーマルCTP時代の先駆けとなるプレートメイキングシステムの商品化に成功している。
一方、富士写真フィルム(当時)もDRUPA1995展で高感度フォトポリマープレートLPAを発表してコダックに対抗している。
「CTP」は周知の如く「Computer To Plate」の頭文字を採ったもので、黎明期には製版フィルム無で直接プレートメーキングが可能となる事より、「ダイレクトプレート」の名称・呼称が使用された時期もある。
しかしながら、1970年代に電子写真方式及び銀塩写真方式による版下から直接プレートを作成するダイレクトプレート、カメラプレートと称される軽印刷向けの高感度プレートが商品化されており、830nmの赤外レーザー光源を使用するサーマルプレート、フォトポリマープレートは「CTP」「Computer To Plate」の呼称が一般化する展開に至っている。
サーマルCTPプレート「プレートの二重表記」
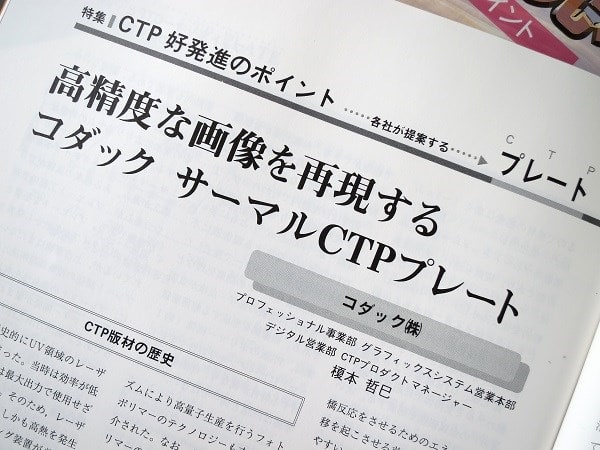
「CTP」の呼称は、2000年代初頭には完全に定着したが、デジタル印刷機による「Computer To Press」との混同も生じやすく、「CTPプレート」の重複表示がカタログ等々で使用されるケースが一般化している。Computer To Plateシステム用プレートと解釈すれば不自然な「プレート重複表示」問題も解決できる。
以上









